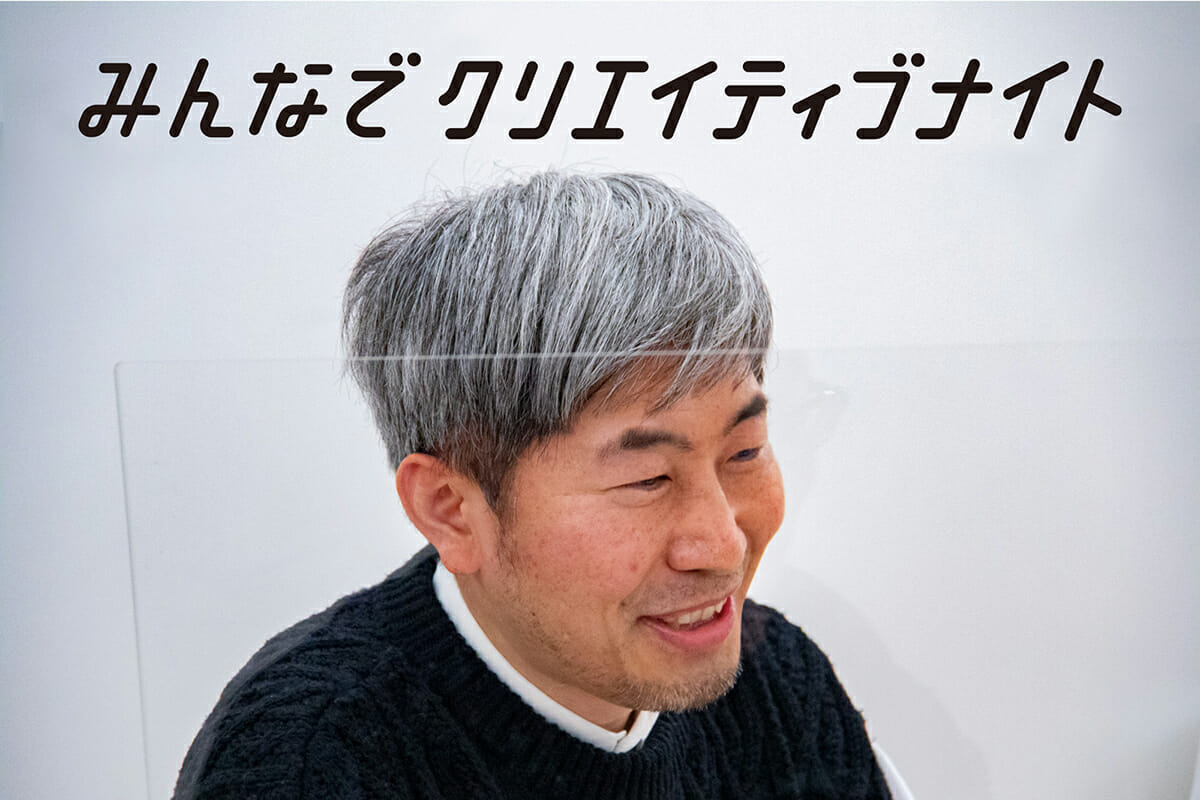NHK「理想的本箱 君だけのブックガイド」はEテレの本の紹介番組である。
【番組紹介】
静かな森の中にある、プライベート・ライブラリー「理想的本箱」。 あなたの漠然とした不安や悩み、好奇心に答えてくれる一冊を、この世に存在する数えきれない本の中から見つけてくれる、小さな図書館です。 これから長い人生を生きていくあなたに素敵なヒントを与えてくれる本を、あなたの心に寄り添って一緒に見つけてゆきます。※上記公式サイトより引用
各回毎にテーマが設定されており、
「理想的本箱」主宰・吉岡里帆
「理想的本箱」司書・太田緑ロランス
「理想的本箱」選書家・幅允孝
の三人によって毎回3冊の本が紹介される30分番組である。
昨年の放送を観て、今年の各月の最初の記事は、この番組の各回を順に取り上げることにした。
番組の詳細については、過去の記事を参照されたい。
選書家となっている幅允孝(はばよしたか)さんは、主に書店や図書館のプロデュースを手掛けるBACHという会社の代表をしている人で、詳細は下記のリンクを参照されたい。
さて、これまで放送された8回のテーマは以下の通りである。
2021年:第1回 もう死にたいと思った時に読む本
2021年:第2回 同性を好きになった時に読む本
2021年:第3回 将来が見えない時に読む本
2022年:第1回 もっとお金が欲しいと思った時に読む本
2022年:第2回 ひどい失恋をした時に読む本
2022年:第3回 母親が嫌いになった時に読む本
2022年:第4回 父親が嫌いになった時に読む本
2022年:第5回 人にやさしくなりたい時に読む本
※初回放送順
前回は、2021年放送分の第1回「もう死にたいと思った時に読む本」の深沢七郎「人間滅亡的人生案内」を取り上げて終わってしまったので、今回は、残りの二冊の話をしたいと思う。
NHK「理想的本箱 君だけのブックガイド」選定書
・もう死にたいと思った時に読む本(初回放送日:2021年12月9日)
深沢七郎「人間滅亡的人生案内」河出文庫(2016)
村田沙耶香「しろいろの街の、その骨の体温の」朝日文庫(2015)
若松英輔「悲しみの秘儀」文春文庫(2019)
村田沙耶香「しろいろの街の、その骨の体温の」朝日文庫(2015)
一冊目の深沢七郎「人間滅亡的人生案内」の次に紹介されたのはこの本だった。
新興住宅地に住む女子中学生が主人公の学園物である。
【内容】
クラスでは目立たない存在である小4の結佳。
女の子同士の複雑な友達関係をやり過ごしながら、
習字教室が一緒の伊吹雄太と仲良くなるが、
次第に伊吹を「おもちゃ」にしたいという気持ちが強まり、
ある日、結佳は伊吹にキスをする。
恋愛とも支配ともつかない関係を続けながら
彼らは中学生へと進級するが――
野間文芸新人賞受賞、
少女の「性」や「欲望」を描くことで評価の高い作家が描く、
女の子が少女に変化する時間を切り取り丹念に描いた、
静かな衝撃作。
【著者について】
1979年、千葉県生まれ。玉川大学文学部芸術文化学科卒。2003年、『授乳』で群像新人文学賞(小説部門・優秀作)を受賞しデビュー。2009年、『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、2013年、『しろいろの街の、その骨の体温の』で三島賞、2016年、『コンビニ人間』で芥川賞受賞。同作は累計発行部数100万部を突破した。その他の著書に『マウス』『星が吸う水』『タダイマトビラ』『地球星人』『殺人出産』『消滅世界』『生命式』などがある。
※上記バナーの Amazon 商品サイトより引用
まず思ったのは、「もう死にたいと思った時に読む本」というテーマに対して、なぜこの本なのかということであった。
選者の幅さんによると、教室の中の価値観に縛られて自由に動けない主人公・結佳を通して、自分の価値は自分が作ることができるということを教えてくれる一冊であるという。
ここでの教室の中の価値観とは、「スクールカースト」と呼ばれる学校のクラスで生徒間に形成される序列であるという説明であった。
なるほどねぇ。
前回の記事では、「人間滅亡的人生案内」のような人生相談本で悩みが解体されても、問題そのものが解決される訳ではないという点を指摘した。
そしてこの点について、悩みの解体をきっかけとして自分自身で問題の再設定を行えば、問題はより意味のある具体的なものになり、解決のために行動していくことで状況は変わっていくという私の考えを書いた。
幅さんのこの本の選定は、やはり悩みは解体されても問題は解決しないということを意識したものだろう。
大人であれ子どもであれ問題を解決しようと思えば、多かれ少なかれ自分自身と自分の置かれている現実とに向き合っていく必要がある。
この小説の中心は、小学四年の時の仲良し三人が、中学二年になって同じクラスになってからの物語であるが、映像化による内容紹介は主に中学二年時点の状況説明であった。
まずは、スクールカーストと呼ばれるクラス内のグループの序列の説明である。
このクラスの女子は5つのグループに分かれており、主人公・結佳は下から二番目のおとなしい女子のグループである。
このグループは主人公・結佳自身から「真面目で安全な私達は男子と話すことは滅多にないがそれなりに教室での居場所を確保している。」と説明される。
かつての仲良しの一人・若葉はスカートを上げたり透明なマニキュアをしたりと少しだけ悪いことをしながら着飾っている一番上のグループに入っている。
この下の二つのグループは、これよりも少しこどもっぽくて賑やか子たちである。
一番下のグループは行き場のない子たちが寄り添っているような感じで、もう一人のかつての仲良しである信子はこのグループだった。
このグループの序列の中にあって、主人公・結佳が信子について語るセリフはこうである。
「二年のクラス替えの後、信子ちゃんが私を見て嬉しそうな顔をした時、私はしまったと思った。小学校の頃と変わらない無邪気な笑顔が、それぞれに値札が付けられた今では、扱いに困る代物だった。」
若者にとって生活の中心は学校であり、そこでの居場所は非常に重要である。
主人公である結佳が自分自身の状況説明で、「教室での居場所を確保している」と言っているのはこの居場所の重要性を意味していると思われた。
この点では、この作品は学校という居場所の生きづらさをリアルに描いている作品なのだろう。
そして、このようなグループの序列の持つ意味合いを伝えるセリフとして、主人公・結佳が信子について語るセリフは実に上手い所を引っ張ってきているように思う。
私自身の中学生時代が思い出されたが、グループとその序列というのは確かにあった。
実際の雰囲気が昔とどう違うかは、気になるところではある。
さて、映像化された内容紹介は、状況説明が中心となっておりその後の物語には触れられていなかったので、再び幅さんのコメントが入る。
教室という小さな世界に縛られていると感じている主人公・結佳にとって、この小さな世界の外に平気でジャンプできる男の子・伊吹との関わりが、結佳自身が教室という小さな世界を飛び出す大きなヒントになるという。
そして、物語が進む中で信子は涙と鼻水を垂らしてあがきもがきながらこの教室の状況を壊していくという。
やがて、主人公・結佳はかつては「扱いに困る代物」として敬遠していた信子を、美しいと思うようになる。
これが、自分がどう思うのかということに基づいて自分の価値を自分で作ったということであり、幅さんはここに注目するのがこの小説を主人公・由香の成長物語とする読み方であると言っている。
さて、そもそものテーマである「もう死にたいと思った時」にこの本を読むという前提に立ち返ってみよう。
この本が自分の価値は自分がつくることができるということを教えてくれる一冊であるとして、この自分の価値を自分で作るということは、もう死にたいと思う現状を打開する助けになるだろうか。
「もう死にたいと思った時」にこの本を読むという前提において、自分の価値を自分で作るということの意味の核心は、自分の価値を自分で作るということそのものではなく、教室での価値基準に対して自分の価値を自分で作る自由があることに気づくことであると思う。
この自由についての気づきがあれば、この本はもう死にたいと思う現状を打開する助けになると私は思う。
そして、この自由についての気づきに至る道筋はやはり、悩みの解体をきっかけとして本当の問題は何だろうかと問うた時の、自分自身と向き合うという分岐であると思う。
学校生活がスクールカーストに縛られているものであるのはわかった。
これが息苦しさや生きづらさの原因であることもわかった。
深沢七郎さんの「人間滅亡的人生案内」では、学校とはそういうものだという形で悩みは解体されたが、問題は解決していない。
この悩みの解体をきっかけとして、本当の問題は何かと自問した時、教室の中の価値基準に縛られている自分であると自答すれば、自分自身と対峙することになる。
この過程を、小説であるとはいえ追体験できるということであれば、この選定はなかなか悪くない。
とは言え、この本で自分自身と対峙する過程を追体験しても、悩みは一時解体されるだけかもしれない。
大人の現実で考えてみよう。
既存の価値観から脱するシンプルな方法は反抗である。
鬱憤を抱えた大人が社会に対する誰かの反抗を見て溜飲を下げるが、自分は同じ現実に居続けるというのはよくあることだ。
自分にはそんなことはできないという訳である。
しかし、実際に反抗するかどうかは問題ではないと私は思う。
小説の主人公・結佳は変われたけれども、自分は変われないということであれば悩みは一時解体されるだけかもしれない。
しかし同様に、実際に自分の価値を自分で作るかどうかは問題ではないと私は思う。
なぜなら、いきなり自分の価値を自分で作るなんてことは大抵は出来ないからだ。
これに対して、自分の価値を自分で作る自由があることに気づくことは出来る。
気づきは、いつも突然だから。
そして、気づきはいつも突然だけれども、理由がない訳ではない。
「もう死にたいと思った時」にこの本を読んだから気づいたというのは、立派な理由であると思う。
心の自由に気づいて自分にはまだできるかもしれないことがあるということを感じること、これが「死にたいと思う心」を救うと思うのだ。
ここで、この小説のタイトルが改めて気になった。
気になったのは「しろいろの街の、その骨の体温の」というタイトルの、「骨の体温」という表現の奇妙さである。
体温は骨に付いている肉がもたらすものである。
肉の中心に付いている骨の体温、肉の核心にある白い塊りの熱とは何ぞや。
ここには、作品を象徴するような意味合いが込められている筈である。
肉を支えている骨が人生を支える価値観であるならば、この体温とは、普段はひっそりと肉の中心にある骨としての価値観が自分らしい生き方を求める青春の熱なのではないか。
本当のところはわからないが、こう考えてみると若者向けの選書として、やはりこの選定はなかなか悪くないのではないかと思われた。
さて最後にもう一点、気がかりなことがある。
それは、この本は男子中学生向きなのだろうかということである。
とは言え、何をどう書くかは作者の自由であるから、この小説が男子中学生向きではなくても止むを得ないところだろう。
ということで、この手の男子中学生向きの本をこのブログで取り上げた中から選んでみることにした。
筆頭はミヒャエル・エンデの「はてしない物語」かと思ったが、ファンタジー物であることと人生全般がテーマになっている点で、「もう死にたいと思った時」に読むという前提にはややアンマッチな気がした。
「もう死にたいと思った時」に読むという前提では、パトリック・ネスの「怪物はささやく」の方が好適だろう。
この二冊を挙げてみたがどちらも海外の作品であったので、日本人の作品を新たに挙げておく。
▼なだいなだ「おっちょこちょ医」集英社文庫1979
【内容】
医者のいなかったヘーワ町にやってきたディストレ先生は、無類のあわて者。病名を間違えたり、劇薬を与えたり、単純ミスの大安売り…。純朴な人びとが巻き起こすユカイな物語。
※上記バナーの Amazon 商品サイトより引用
【著者略歴】
1929年、東京生まれ。作家。精神科医。著書は『パパのおくりもの』『人間、この非人間的なもの』ほか。
※なだいなだ「おっちょこちょ医」筑摩書房(1974)より引用
作家で精神科医でもある著者は、20年以上前に岩波ジュニア新書から「いじめ」についての本も出版している。
▼なだいなだ「いじめを考える」岩波ジュニア新書1996
ここで「おっちょこちょ医」を取り上げたのは、一つには内容紹介に「純朴な人びとが巻き起こすユカイな物語」とある通り、ユーモアがあるからである。
もう一つは、それでいながら「わかい読者たちへ」と題されたあとがきに書いてあるように、骨太なテーマが設定されているからである。
「ためらうなよ。人をすくって罪になるなら、罪をおかせよ」
先生は、こういってドースルに、ニセ医者になれ、という。ぼくは、それが、けっしてまちがったことではないと思う。きみたちにはそれがわかるだろう。
しかし、ぼくは、こんなことをおとなのお話の中では書けないだろう。おとなには、この真実がわからないだろうと思うからだ。できることなら、ぼくは、きみたちがおとなになったときに、この真実がわかるようなおとになっていてもらいたいものだと思う。
※なだいなだ「おっちょこちょ医」筑摩書房(1974)p253-254 より引用
ここでの先生とは主人公のディストレ先生であり、ドースルは先生の助手となった若者である。
なださんの言っていることが正しいかどうかはさておき、私にとってこの本は心の自由に気づく理由となった本の一冊である。
生きづらさを感じる若者に、こうした本で気づきがあるように願う。
骨が熱を帯びればもっといい。
実のところ、自分の価値を自分で作るというのは人生で繰り返される課題であるから、大人もまだまだ考えていきたいと思う。
またまた長くなったので、もう死にたいと思った時に読む本(3)の記事へ続く。