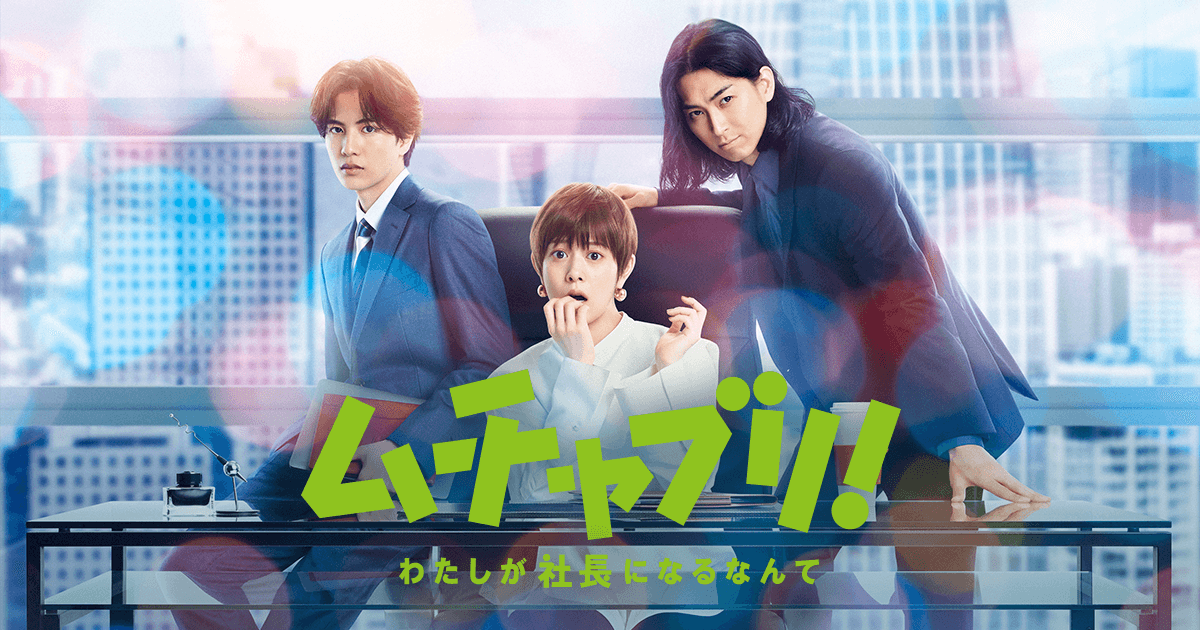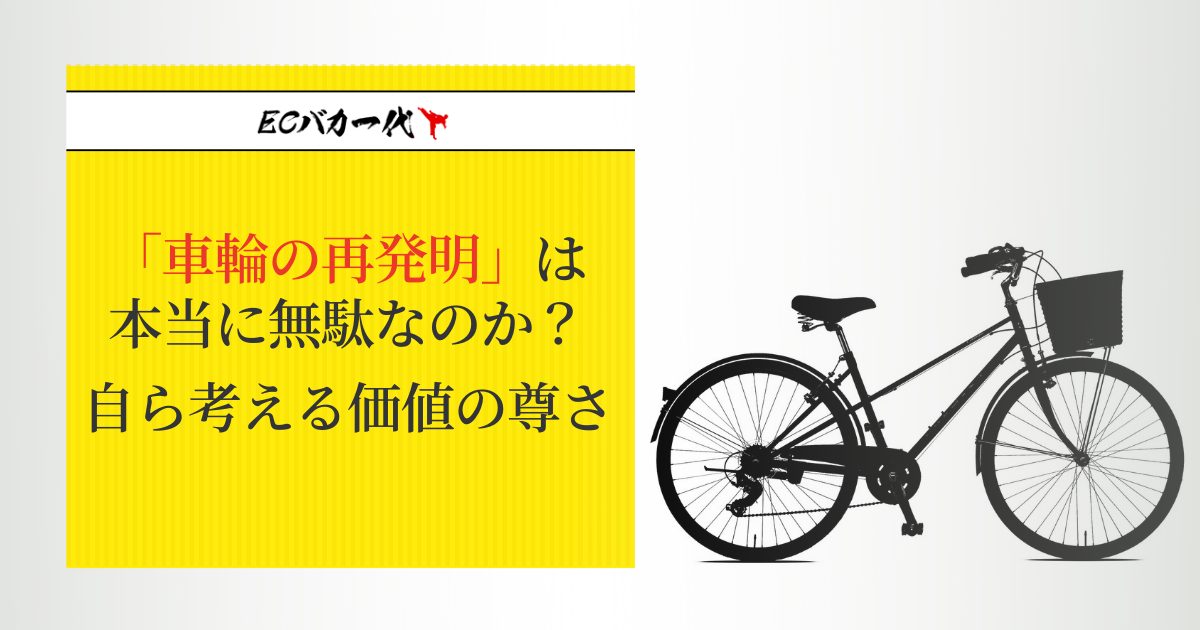今年の新しい冬ドラマとして、以前の記事で黒木華さん主演の「ゴシップ #彼女が知りたい本当の〇〇」(フジテレビ)を取り上げたが、実はもう一つ観ていたドラマがあった。
高畑充希さん主演の「ムチャブリ!わたしが社長になるなんて」である。
▼ドラマ「ムチャブリ!わたしが社長になるなんて」公式サイト
※見逃し配信の情報もあり
公式サイトの紹介文はこうである。
30歳OL、イマドキ世代、出世欲ナシ!、帰ったらビール。
そんなイチ社員だった彼女を襲った悲劇は――
「私が社長に!?」
いきなり子会社の社長に大抜擢!
従業員との衝突、売上不振、ライバル社との闘い。
「どうしてわたしがこんな目に……!?」
こうなったら……そのムチャプリ、チャンスにさせていただきます!
さらに、全くタイプの違うオトコたちに板挟み!?
ナマイキ部下 VS カリスマ上司
どっちも難アリ!!
果たして恋には発展するのか!?
雛子の明日はどっちだ?
一歩ずつだけど着実に前に進む、
さとり?ゆとり?そんな言葉では縛られない!
等身大ヒロイン登場!
人生は夢中になるから面白くなる!
仕事も恋も無理難題の嵐を突き進め!
爽快!お仕事エンターテインメント!!
お仕事エンターテインメント物として普通に面白そうである。
ストーリーは基本的には平社員が突然に責任あるポジションに抜擢されて頑張るという内容で、これには目新しさはないものの、高畑充希さんが無茶振られるたびに、
「なぁ~にぃ~」
というのは観ているだけでも面白い。(笑)
まぁ、高畑充希さんはコメディ作品ではいつも面白いので、最初はまだ普通に面白いお仕事エンターテインメントドラマとして普通に観ていただけだった。
基本的には社長も楽じゃないという話を、高畑充希のキャラクターを活かしながら面白く描いていたし、デキる社長とデキない社長をあからさまに対比しているのもわかりやすくて良かった。
話自体が面白くなってきたのは第3話ぐらいからである。
この手の話の場合、抜擢された平社員は実は能力があるのに埋もれていた場合と、父親の急死で家族経営の会社の社長に突然なるといった理由で能力はないけれども突然なってしまう場合がある。
この作品は、抜擢した社長は潜在的な何かを見ての判断のようだが、実態としては能力のない方のケースである。
この場合はピンチの乗り越え方が、ドラマの持つメッセージと強く関係してくる。
この点についても総評的に書くと、「できないことだらけでも前向きに頑張ることによって、周りの助けが得られてチームとして成功していける」というようなメッセージを持った内容であると思われる。
これにも目新しさはないのだが、このできないことだらけでも前向きに頑張るところの描き方を見ていて思い出した本があった。
それが、橋本治さんの「「わからない」という方法」(集英社新書2001)である。
この本のタイトルはヘンだ、と思ったあなたへーー著者初のビジネス書!?
「わからない」ことが「恥」だった二十世紀は過ぎ去った!小説から編み物の本、古典の現代語訳から劇作・演出まで、ありとあらゆるジャンルで活躍する著者が、「なぜあなたはそんなにもいろんなことに手をだすのか?」という問いに対し、ついに答えた、「だってわからないから」。─かくして思考のダイナモは超高速で回転を始める。「自分は、どう、わからないか」「わかる、とは、どういうことなのか」……。そしてここに、「わからない」をあえて方法にする、目のくらむような知的冒険クルーズの本が成立したのである!
[著者情報]
橋本 治 (はしもと おさむ)
一九四八年、東京生まれ。作家。東京大学文学部国文科卒。在学中の六八年に描いた駒場祭ポスターでイラストレーターとして注目される。七七年『桃尻娘』で講談社小説現代新人賞佳作受賞。以降、小説・評論・戯曲・古典の現代語訳・エッセイ・芝居の演出等で精力的に活躍。主な著作に『桃尻語訳枕草子』『江戸にフランス革命を!』『'89』『窯変源氏物語』『ひらがな日本美術史』『二十世紀』等。『宗教なんか怖くない!』で第九回新潮学芸賞受賞。
※Amazon の上記バナーサイトより引用
正直なところ、紹介文にあるような「目のくらむような知的冒険クルーズの本」ではなかったとは思ったが、タイトルのヘンさに見合うだけのものはあった。
この本で橋本さんが言っている「「わからない」という方法」とは、私なりの表現で簡潔に言ってしまうと、「手っ取り早く答えを得るのは楽だけれども、どうしてそうなのか本当のところはわからないから、答えに至る過程を自分なりにわかるまで確認していくという方法」である。
ビジネスで「車輪の再発明」と言うと、知られている解決方法があるのに一から解決方法を考えしまう無駄を批判する場合が多いが、近年では下記の記事のように自己成長の観点で敢えて自分で考えてみることのポジティブな意味も指摘されてきている。
ここには、なぜビジネス書を読んでもできるようにはならないかということの一つの答えがあるように思う。
つまり、わかった人がわかった結果を書いているから、わからない人が読んでも頭でわかっただけで出来るようにはならないということである。
橋本さんがこの本を書いてから既に20年以上が経っているが、検索サイトで調べればとりあえず何か答えらしきものが得られてしまうのが当たり前になった今こそ、「「わからない」という方法」を再認識する意味は大きなものになっていると思われる。
とは言え、橋本さんも書いているようにこの方法は実に泥臭く手間と時間がかかる方法なのである。
そして、他人が「「わからない」という方法」を実践している過程を見る機会はほぼないのである。
その理由は、実践している人が少なく、その過程の記録が少なく、更にその少ない記録を見聞きする機会が少ないからである。
この意味では、橋本さんのこの本はなかなか貴重であるし、このドラマも主人公の「わからなさ」を全面に出して描いている珍しい作品なのである。
▼2月9日放送の第5話の見逃し配信は下記(2月16日まで)
▼第5話までのあらすじ、脚本については下記を参照