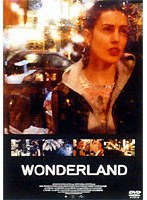静かな
とても静かな映画ですね
これほどまでに日常に接近した映画って近年無かったような気がします。
日常に接近しているということは、人の心の機微をうまく捉えて、描いているということ。
この物語は、
亡き母の墓をたてることになり、兄のもとに
弟が久しぶりにたずねてくるところから始まります。
兄は内向的で職人気質。
判で押したように同じ毎日をたんたんとすごしている
弟は陽気で明るい男。
数々の事業を手がけている。
兄の工場で働く中年女性マルタは、
いつも就業時間前のきまった時間にシャッターの前で
兄がくるのをじっと待っている女性。
彼女もまた同じ毎日をたんたんと歩んでいる。
兄は、弟が来る前に、マルタに
自分の妻のふりをしてくれないかと頼む。
快く引き受けるマルタ。
マルタの心の動き。
たんたんとした日常を送り、日常に埋没しているマルタの心には
このちょっとしたうそをきっかけに久しぶりに感じるであろう、高揚感が
浮かんでくる。
でも兄はそれに気づかない。
マルタがベッドをくっつけても、すぐ話してしまうし
ほとんど語りかけもしない。
自分の人生にあきらめを感じているんだろうな。
弟は陽気な、よく話す男。
マルタにも気さくに話しかける。
マルタの気持ちはだんだんと移ろっていく。
余談ですが、人の心根を映像でもうまく見せてくれる映画でした。
特に、マルタがホテルの弟の部屋を訪ねるシーンは秀逸。
端にある兄のから、さらに端っこの弟の部屋に向かうマルタの後姿を
カメラは、静かにうつしだしています。
その後姿からは、彼女の心の移ろいがとてもよく伝わってきます。
兄はどうか。
彼はホテルの最終日で偶然手にした幸運を目の当たりにして
やっと自分の人生を前向きに生きること、その意味に気づいたんだと思います。
でもそれは遅かった。
もうマルタは工場にもどってこない。
本当にしずかでしずかで
ゆったりと時間が流れていきます。
でもそんな中でも人の心はゆっくりと移ろい
時にはがらりと様相を変えることもある。
ちょっぴりどきっとする映画でした。
大切な人の心を離さないように・・