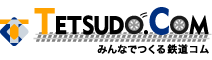世論が鉄道による存続を選択すると言うことで、行政も重い腰を上げたわけですが、和歌山市がやはり一番そういった点では存続には消極的であったことは間違いありません。
この頃の南海は消極的施策を打って出ており、あまり話題にも上りませんでしたが2005年(平成17年)11月27日には、久保町駅、築地橋駅、築港町の各駅を廃止しています。
さて、ここで行政が決めたスキームを今一度確認しておきましょう。
ただ、この時点で言えたことは、この枠組みにより少なくとも10年間の運営は保証されたと言うことでした。
参考 県・市・町による貴志川線支援の枠組み
(出所)2005年2月7日付わかやま県政ニュースを参考に作成。
和歌山県
和歌山市・貴志川町の鉄道用地取得費を補助金で全額負担(貴志川線は上下分離方式のため)
将来の大規模修繕費として累計2.4億円を上限に支出
ただし、次の条件付き
・県は鉄道運営の主体として参加しない
・両市町が10年以上の運行を担保する
和歌山市・貴志川町
・土地は市と町が保有する。
・運行事業者への赤字補填については市が65%、町が35%の割合で8億2000万円 を上限に10年間負担する。民間事業者を公募する。
・可能な限り民間事業者の協力を得て、利用促進に努める。
和歌山電鉄、たま電車
たま電車は、いちご電車、おもちゃ電車に次ぐ第3弾で一番内装等にも力が入れられた車両ですが、結果的に毎日の通勤には使いにくい電車になってしまっています。
ということで、行政としても一定の整理ができたことから、公募・選考にと入っていったのですが、南海電車側も廃止に際しては一定の理解を示し、車両等施設の無償譲渡の条件で協力してくれたことも大きかったことは記憶に残しておきたいことだと言えます。
現在の和歌山電鉄に関しては、電車の費用は実質0円で導入したわけですが、今後電車を導入すり場合現行のスキームでは他社から中古車の譲渡を受けるか(この場合も南海から譲渡を受けるとしても無償とはいかないのでその辺でまたぞろ存続に関する問題が出て来そうです。
今回は、引き続き補助金を出すと言う形で結論が出ましたが沿線人口の減少などを考えれば沿線地域への産業の創出、もしくは新たな観光施設、もしくは三社参りに敷設された路線ということで沿線の神社とタイアップした施策などを検討すると言うことも必要になってくると思われます。
「たま」頼みの集客も良いですが、何時までもそのブームが続くとは思えません。
「にたま」がたま同様に人気を博すかというとこれまた未知数であり、そうした人気頼みの危うい方策ではなく地に足が着いた施策をしていく必要があると思うのですが、どうも和歌山電鉄は「たま」の人気だけに頼り過ぎている傾向が感じられてなりません。
たま、社葬の際のスナップ
すみません、話が大きく横道に外れてしまったので、本題に戻りたいと思います。
自治体による事業者の選考自体は秘密裏に行われ、WCANなどの市民運動側にも情報は漏れてくることはありませんでしたが、当時の世間一般の意識は、「岡山電気軌道(両備グループ)」だろうというのが大方の予想でした。
実際に、運営ノウハウがあることなどを考慮すれば、消去法的にそこしか残らないのですから。
2005年4月28日、行政は運営事業者を岡山電気軌道とすることを正式に発表しました。
また、同年5月7日には和歌山東高校・貴志川高校の生徒らが中心になって、「貴線祭」が開催されました、場所は貴志川諸井橋河川敷で行われ、当日は曇り空でしたが、露天・コンサートなどが行われ、祭りを盛り上げようという高校生たちの熱気が伝わってきました。
2010年頃までは開催されていたようなのですがその後はどうなったのでしょうか?
ご存じの方が居ましたら教えてください。
http://where.ikora.tv/e384275.html
こうして、事業者が決まったことは大きな成果でした、しかし問題がないわけではありませんでした、補助金の期間は10年間という期限があります、それ以後も赤字が続けば同じようば問題が発生しないとも言えないのです。
新たな利用者の増加などが見込めなければ衰退してしまうわけでWCANのメンバーもほっとすると共に、引き続き地元でファンドを作り運営基金にする必要性について勉強会が行われました。
引き続き10年を限度とする補助金は決まりましたが、当初両備グループが黒字にしますと言う約束は果たされないままであり、予断は許さないものと思っています。
現在も未来をつくる会が中心になって運動を行っていますので今後も継続して和歌山電鉄について見守っていこうと思いますし、さらなる発展としてLRT化なども視野に居れた運動をしていきたいと思っております。
続く
鉄道の情報は下記でもたくさんございます。
クリックをお願いします。
にほんブログ村