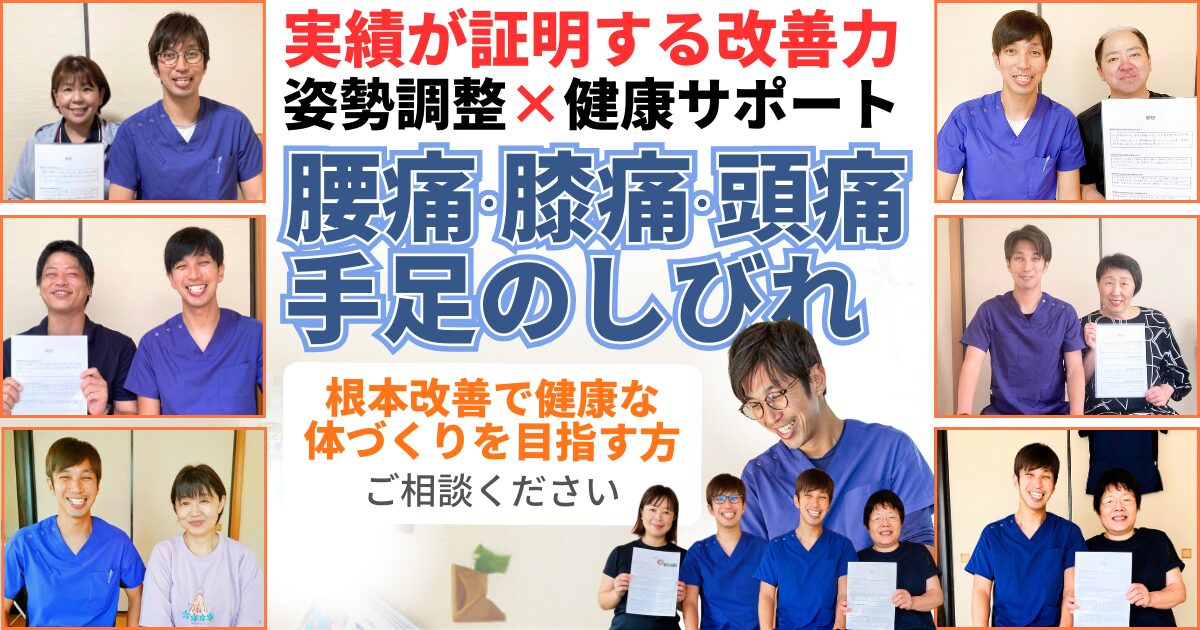最近「なんとなく体がだるい」「頭痛や肩こりがひどくなった」「寝ても疲れが取れない」と感じることはありませんか?
この時期は「三寒四温」といって、寒い日と暖かい日が交互にやってくることで気温差が大きくなり、自律神経が乱れやすくなります。自律神経のバランスが崩れると、体のあちこちに不調が現れやすくなるため注意が必要です。
そこで今回は、三寒四温の時期に起こりやすい不調と、その対処法について詳しく解説していきます!
三寒四温とは?この時期に体調を崩しやすい理由
三寒四温とは?
「三寒四温(さんかんしおん)」とは、寒い日が3日ほど続いたあとに、暖かい日が4日ほど続くという気候の変化を指す言葉です。本来は冬の終わりから春先にかけて使われる言葉ですが、最近では秋から冬、冬から春にかけても使われるようになっています。
この時期は、朝晩の寒暖差が大きく、日によって10℃以上の気温差があることも珍しくありません。そのため、体がこの変化についていけず、自律神経の乱れを引き起こしやすくなります。
自律神経が乱れるとどうなる?
自律神経とは、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)のバランスを保ち、体温調整や内臓の働きをコントロールする重要な役割を持っています。しかし、気温差が大きいと、このバランスが崩れ、以下のような不調が現れます。
- 肩こり・首こりの悪化(筋肉が緊張しやすくなる)
- 頭痛やめまい(血流の乱れによる影響)
- 倦怠感や疲れが取れない(自律神経の乱れによる影響)
- 寝つきが悪い・眠りが浅い(交感神経が優位になりやすい)
- 関節痛や神経痛の悪化(気温差による血管収縮)
では、これらの不調を予防・改善するためにはどうすればよいのでしょうか?
三寒四温の時期におすすめの対処法
① 朝晩の寒暖差対策をする
気温の変化が激しい時期は、**「1枚脱ぎ着できる服装」**を意識しましょう。特に朝晩は冷え込みやすいので、以下のポイントを押さえてください。
- 首元・手首・足首を冷やさない(「三首」を温めると血流がよくなる)
- 薄手のインナーを重ね着し、調整しやすくする
- カイロやレッグウォーマーを活用する
また、室内ではエアコンや加湿器を使い、室温と湿度を適度に保つことも重要です。
② 生活リズムを整えて自律神経を安定させる
自律神経を安定させるには、規則正しい生活習慣が欠かせません。
- 毎日同じ時間に起きる・寝る(睡眠リズムを崩さない)
- 朝日を浴びる(体内時計を整える)
- 夜はスマホやPCの使用を控える(ブルーライトは自律神経を乱す)
特に、朝起きたらコップ1杯の水を飲み、軽いストレッチをするだけでも自律神経が整いやすくなります。
③ ぬるめのお風呂でリラックスする
交感神経が優位になりやすいこの時期は、副交感神経を活性化させるために「ぬるめのお風呂」に入るのが効果的です。
- 38~40℃のぬるめのお湯に15~20分浸かる
- 入浴中に深呼吸をしてリラックスする
- 入浴後はストレッチやマッサージで血流を促す
湯船に浸かることで血行が良くなり、肩こりや関節痛の予防にもなります。
④ 軽い運動で血流を促す
寒暖差による血行不良を改善するためには、適度な運動が効果的です。
- ウォーキング(20~30分程度)
- ストレッチやヨガ(朝・寝る前におすすめ)
- 軽い筋トレ(スクワットやラジオ体操など)
運動不足になるとさらに自律神経が乱れやすくなるため、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。
⑤ 食事で自律神経を整える
食事の内容も、自律神経の安定に大きく影響します。
- 温かい食事を意識する(スープ・鍋料理・生姜湯など)
- ビタミンB群(豚肉・納豆・卵)を摂取する(自律神経の働きをサポート)
- 腸内環境を整える(発酵食品・食物繊維を摂る)
特に、**発酵食品(ヨーグルト・納豆・キムチ)**は腸内環境を整え、自律神経の乱れを防ぐのに役立ちます。
まとめ
三寒四温の時期は、寒暖差が大きいため、自律神経が乱れやすくなります。すると、肩こりや頭痛、倦怠感などの不調が現れやすくなるので、日常生活の中でできる対策をしっかりと取り入れることが大切です。
✅ 朝晩の寒暖差対策をする(重ね着・温活)
✅ 生活リズムを整え、自律神経を安定させる
✅ ぬるめのお風呂でリラックスする
✅ 適度な運動で血流を促す
✅ バランスの取れた食事で体を整える
この時期を快適に過ごすために、ぜひ今日からできることを実践してみてください!
別府市の別府おひさま整体では姿勢改善+健康サポートを行い
痛みがない、再発させないお体へと変わらせて
整体に通わなくて良くなる『整体通いから卒業させる』整体院です
まずは痛み改善の第一歩のご連絡をお待ちしております。