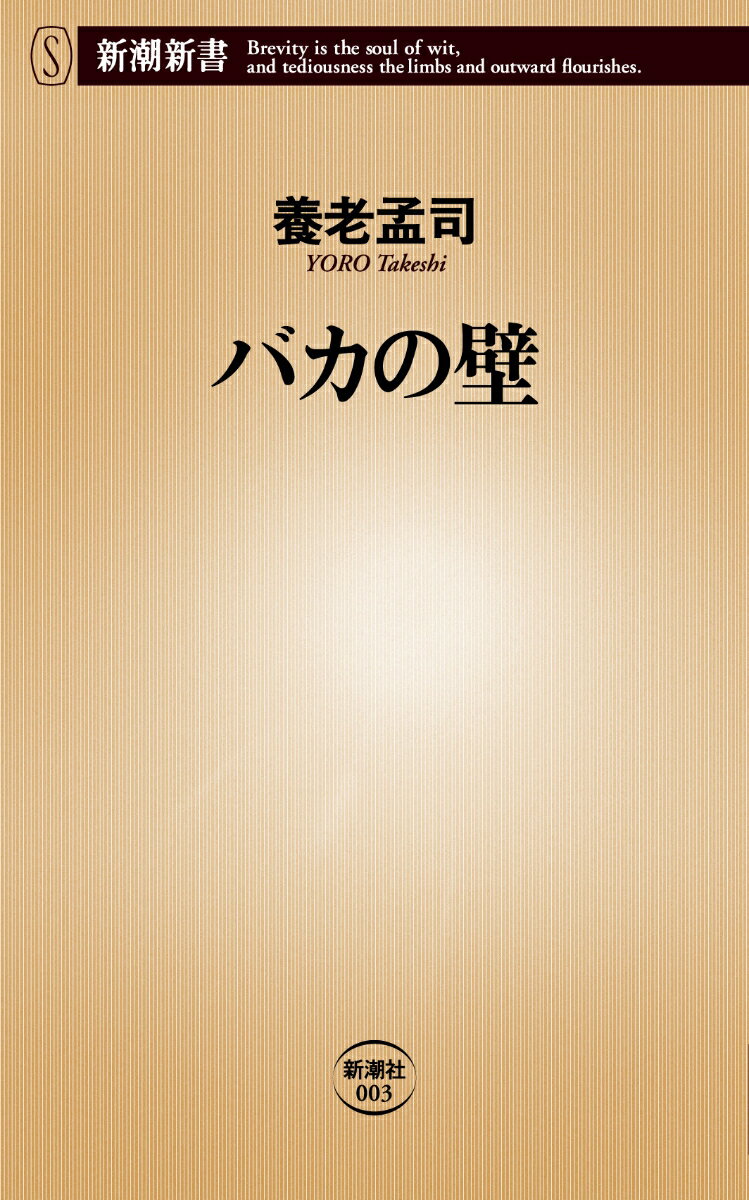英語は全く分からないのだが、aとtheの使い分けは、aがそこにひとつしかないもので、theはそれしかないものだと漠然と認識していた。
改めて調べてみるとそのことはあながち間違いでもなく、日本語に無理やり当て嵌めるとすると、aはたくさんある中のひとつ、つまり"とあるペン"で、theは"そのペン"というニュアンスだそうだ。
今更ながら、バカの壁を買って読んでいる。
その初めの話の中で、変わらないのは情報であり、変わるのは自分であるとしている。その例としての話の中にaとtheの違いの話が出てくる。
内容とは逸れるが、このaとtheの違いについての話が個人的にとても面白かった。
aとtheをそれぞれ、不定冠詞と定冠詞と英語では呼ぶ。
私も最初に習ったときは、名詞にいちいちそれを付ける意味がわからなかったし、なんなら今もわからない。
どうやらこれは、概念の話らしい。
ものすごくざっくり言えば、"りんご"という言葉がある。an appleは、頭の中に浮かぶりんごで、the appleは、この手に持っているこれしかないりんごのことだ。
an appleは、プラトンの言う"イデア"である。
りんごは実際、色も形も大きさも違っているけれど、人の意識の中で認識しているりんごというものがある。
しかしthe appleは、自分の意識の外に差し出されたたったひとつのりんごだ。
それをソシュールは、「言葉が意味しているもの(シニフィアン)」、「言葉によって意味されるもの(シニフィエ)」と説明しているという。
シニフィアンは、頭の中のりんごで、シニフィエは自分の目の前にあるりんごだ。
しかし日本語に定冠詞と不定冠詞のように使い分ける言葉がないかと言えばそれは違うと養老さんはおっしゃる。
「昔昔、おじいさんとおばあさんが、いました。おじいさんは、山へ芝刈りに…」の中の"が"と"は"の使い分けがそれだ。
はじめに「おじいさんとおばあさん"が"」の部分で読み手に、頭の中でおじいさんとおばあさんをイメージさせる。それから、そのあとの「おじいさん"は"」で、特定のおじいさんが物語の中を動き出すというのだ。
しかし"が"が、不定冠詞的な役割で、"は"が定冠詞的な役割を持つとは断言できないだろう。
それはこの文の中ではそうであるというだけで、前後の文脈によっては、役割が変わる場合もあるかもしれない。
「 昔昔、おじいさんとおばあさんはいました。おじいさんが山へ芝刈りに…」でも、おかしくはない気がする。
通常なら、「昔昔、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯していると…」であるが、"が"と"は"を反対にするとその後の話は変わるだろうか。と、ふと不思議になった。
「昔昔、おじいさんとおばあさんは、いました。おじいさんが山へ芝刈りに、おばあさんが川へ洗濯に行きました。」
続きはおばあさんの方にデカい桃が流れてくるというイベントが発生するのだが、この場合だとおじいさんの方にもイベントを発生させたくなってしまうという困った事態が起こる。
よくよく考えたら、昔昔おじいさんとおばあさんは…にすると、そのあとに"どこに"いたのかを入れたくなってしまうということにも気付いた。
なんで"が"と"は"を使い分けるのかの意味もわかっていないのに、自然と使い分けてしまうのか。
例えば、職場にゴミが溜まっていて、それを「私"が片付けます!」と言われるのと、「私"は"、片付けます!」と言われるのでは、後者の方に同調圧力を感じる。が、の方ではあんたがやってくれるんだね。と思うが、は、の方では、あんたもやるなら私もやらなきゃいけないような…と罪悪感を感じるのである。
ほぼ同じことを言っていても、たった一文字で、言っている方も言われた方も、別の意味で意図したり、解釈するのが変わってしまうのだ。
ならば、「ワタシ、カタヅケマス。」とカタコトで話した方が、誤解が少ないのかもしれない。
どっちも意図せず、その行為以上の解釈もされない。
なるほど。カタコトの外国人がなんだか好ましいのは、その意味の共通しない場所で"勘ぐる"という作業を必要としないからかもしれない。
無意識に共有する部分が多ければ効率的で便利だが、その分知りたくない本音まで伝わってきてしまう。
誰もの心の中に善意と悪意が同じように存在するのならば(少なくとも私はそう思っている).それを見ない。という選択が人との関係を良好にする場合がある。
善意と悪意があるのは人の心の真実だ。
しかし、自分がそこから善意だけを掬い取ろうとすることも可能だった。
それが、"信頼"なのだろうと思う。
the 悪意ではなく、a 悪意。
a 善意ではなく、the善意。を意識したいものだ。
…はて。何の話であったか。