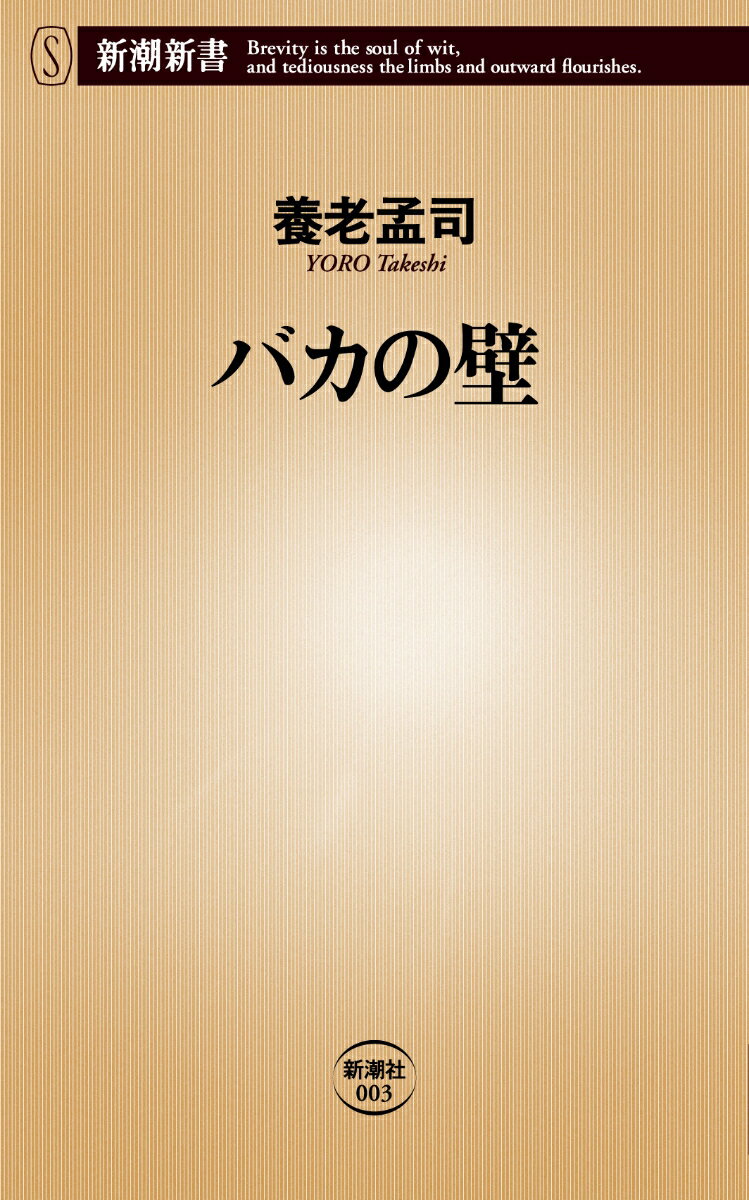ピカソの名言にこんなものがあるという。
ー10代でルネサンスの巨匠ラファエロのような絵は描けたが、子どものように絵を描くには生涯かかった。ー
ただでさえ、絵というものがわからないのに、ピカソの絵がなんなのかなんてまるで理解できなかった。
しかし養老さんの話とこの名言を読むと、なるほど。と腑に落ちる。
晩年のピカソの絵のキュビスムが様々な角度から見た物の形をひとつに収める手法だと言われても、なんのことだかわからない。
しかし世界は基本、カオスである。
私の目が物質を構成する最小単位である素粒子を見ることができたら、その目で見るこの世界は何の形も持たないものだと認識するのだろう。
りんごはりんごではなくなる。
しかしそこから視力を悪くしていくと、あら不思議!素粒子の振動、振る舞いなどの違いで、私はりんごを認識することができる。さらにりんごは、りんごという言葉によって、私の中でより確かな存在になるのであった。
私たちは見たいもの見、聞いたいものを聞く、とよく言われる。
例えば本一冊読むにしても、同じ文章を確かに読んでいるにも関わらず、その人の心、あるいは思考に響くものはまるで違うのだ。
バカの壁とはなんだろう。
私たちが見ているもの、知っているものは、誰もに共通しているものではない。と自覚することなのかもしれない。
だからこそ、養老さんは個性よりも人との間に共通するものを探せ、みたいなことを言っている(違ったらごめん笑)。
個性なんて発揮しなくても元々みんな違っている。そんなことよりも、人の気持ちがわかる。ということの方が大事だ、と。
ものすごく当たり前なことなんだけど、でもそれは同時にとても難しいともやっぱり感じる。
本気で相手の気持ちを自分に当てはめらば、とても苦しいからだ。
だから人は、こうしろ、ああしろ。と言う。
自分の考えを押し付けたくなる。
けれども共感は、相手の痛みを自分の痛みとして想像することだ。
自分がそうなれば、私もあなたのように痛い。
苦しい人にそれ以上の言葉をかけることが出来るだろうか。
しかしその共感はときに言葉以上の意味を発揮するように思う。
思いを背負ってもらえている。と思うだけで、自分の苦しみが軽くなるように思えるときがある。
例えそれが自分の勝手な思い込みでも。いえ。思い込みかもしれないと疑いつつも、そう思い込める
場所に誰にも犯すことのできない自分の自由があるのだ。
アートは時に人の心を傷付ける。と宮台さんはおっしゃる。
社会はクソだ。大勢のために個を犠牲にする。
秩序を保とうとすれば、力を失う。
法外の世界で、彼らはどこまでも自由だ。
大人たちが持つバカの壁を吹き飛ばす力を持っている。
ーこの感動的なラストシーンでは<足萎えのオイディプス>の周りに無数の「女達」が群れ集います。そこで例の二項図式が再確認されます。男/女、草原/森、輪郭あり/輪郭なし、屹立/癒合、離散体/連続体、光/闇。<足萎えのオイディプス>は恐らく、クソ社会の中で犠牲になった者達を背負いながら、これからを生きていくことだろう……観客にそう予想させた処で映画が終ります。
<足萎えのオイディプス>として<社会>を生きてゆけ、治らない傷を隠して「なりすまし」ながら<社会>を生きていけ、という推奨でもあります。ー