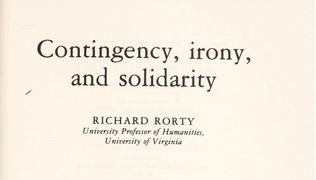○NHK Eテレ「100分de名著」
リチャード・ローティ
『偶然性・アイロニー・連帯』
この本のナビゲーターは、プラグマティズム言語哲学とその思想研究をベースとする哲学者の朱喜哲(ちゅ・ひちょる)さん。
◇前回記事
なんかちょうどいいタイミングでその朱さんが書いた文章を見かけたので、ちょっくらそこから引かせてもらいましょう。月刊誌『群像』への寄稿エッセイから。
◇月刊『群像』2024年3月号
◇随筆:朱喜哲
「酒場の〈公正(フェアネス)〉」
(p.480~481)より抜粋
2023年夏に『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす ー 正義の反対は別の正義か』(太郎次郎社エディタス)という本を出した。この本では、「公共的な言葉づかい」と「私的な言葉づかい」とを区別して、そのどちらも手放さず、両者を使い分けながら、なんとか会話を続けていくことの重要性を説いている。
そのバランスをとるための手がかりが、表題の「フェア(である)」という感覚だ。私たちは、この感覚をさまざまな場面で問われ、ときに失敗する。決定的な破局、もはや会話は打ち切られ、なんらかの力に訴えるほかなくなるような局面をできる限り避けながら、一触即発の危険に満ちたこの社会を、それでもいっしょに営んでいる。
おおげさな話に聞こえるだろうか。そんなことはない。それは、たとえば街の酒場で、あなたがふだんやっていることだ。
もちろん、別に酒場でなくてもよい。そこが、さまざまな人が訪れうる社交の場で、ゆえに誰が何を気にしているのか完全にはわからない、それでもその場にいる誰かをあえて傷つけようとは思っていない、そんな場所であるならば。
(~中略~)
とりとめのない話をする。そこに共通の目的はない。あえて言えば、会話を続けることそれ自体が目的で、避けるべきは相手を不意に傷つけたり、激昂させたりすることである。
そのための注意点は、もちろん言葉づかいであるとか、宗教や思想、容姿の話は避けるとか、さまざまである。あえてまとめれば、同じ場に居合わせているのは自分とは異なる人で、重要な点において意見を異にしており、自分が当たり前だと思っていることが当たり前ではない人かもしれない、というごく当然の警戒心をいだくことだろう。
(引用終わり)
◇『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす ー 正義の反対は別の正義か』朱喜哲 太郎次郎社エディタス 2023年
おや?『群像』3月号の朱喜哲さんの文章があるページの更に20頁ほど先、奇遇にも朱さんが「100分de名著」と『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす』で取り上げた哲学者ローティの主張と似たようなことを言っている人が。
永井玲衣(ながいれい)さん、哲学研究者・哲学対話仲人がその連載の中で。パレスチナ・ガザの凄惨な報道が連日届く “「普通じゃない」世界 ” に、打ちのめされながらも悶え模索する「今、何を書くか」。
今回の大規模破壊・大殺戮に際して配信されている現地の声、及び日本で緊急出版された岡真理さん『ガザとは何か ー パレスチナを知るための緊急講義』を引きながら、遠くで起こっている「普通じゃない」事をいかにして自分たちの話として引き付けていくか、を「言葉」の事象から手探りしている。
先に文章中の『ガザとは何か』の引用部分を。
◇永井の文章中から、岡真理『ガザとは何か』引用部分を孫引き
(同書 p.142、145)
ガザは実験場です。
2007年当時で150万人以上の人間を狭い場所に閉じ込めて、経済基盤を破壊して、ライフラインは最低限しか供給せず、命を繋ぐのがやっとという状況にとどめおいて、何年かに一度大規模に殺戮し、社会インフラを破壊し、そういうことを16年間続けた時、世界はこれに対してどうするのかという実験です。
そして、分かったこと・・・世界は何もしない。
(~中略~)
ハマースと名付けた者たちを非人間化する言葉が氾濫する中で、パレスチナ人が人間であるということを私たちが理解するために、私たちは文学を、文学の言葉を必要としています。文学は、人間にヒューマニティを取り戻させます。
誤解しないでください。文学によって人間性を取り戻すのはパレスチナ人ではありません。私たちです。
パレスチナ人が私たちと同じ人間である、それは当たり前のことです。[・・・]そのことを私たちが理解することによって、私たち自身が人間になります。
(孫引き終わり)
◇『ガザとは何か ー パレスチナを知るための緊急講義』岡真理 大和書房 2023年
◇朝日新聞デジタル 記事
岡真理「沈黙は虐殺の共犯」
*有料記事なので途中までしか読めない。いや、途中までは読める!
◇永井玲衣 『群像』連載
「世界の適切な保存 ㉑手渡す」(p.500~504)より抜粋
(岡『ガザとは何か』引用部分を受けて)
岡真理さんは、これを「恥知らずの忘却」とあらわす。こうして忘却を繰り返すことによって、今回のガザでのジェノサイドを整えてきたと。
(~中略~)
他者の言葉を食べるように読み、パレスチナ人の詩を目にうつし、わたしたちが人間になろうとする。
(~中略~)
言葉とはつねに他者に向けて手渡されるものだ。その意味で、言葉を手放してはいけない。言葉を失ったとしても、言葉をあきらめないことをつづけなければならない。普通じゃない、普通じゃない、これは普通じゃない。普通とは何か? という、問いではなく集中力を霧散させてしまうような誘惑と闘って、この感情を適切に保存しながら、手渡していくことをあきらめない。
そして同時に、わたしが人間であろうとするために、適切に保存されなければならないことがある。それは、私たちの忘却である。無邪気な残虐さである。
(~中略~)
見ようとしてこなかった無邪気さや、「めんどいな」としか思わなかった貧しさ、その無機質で、かわいていて、つるつるした心のかたむきを、保存する。そのような心があり、これからもあり、まだあることもまた、保存する。これは言葉にされ、手渡される。情けなくうなだれ、居心地の悪さを感じながら、手渡される。
(引用終わり)
そして呻吟しながらの永井のこの思索は、リチャード・ローティの説論に還ってくる。
◇『偶然性・アイロニー・連帯』
内容紹介サイト
岩波書店版(2000年)の「序論」より
「私のいうユートピアにおいては、人間の連帯は『偏見』を拭い去ったり、これまで隠されていた深みにまで潜り込んだりして認識されるべき事実ではなく、むしろ、達成されるべき一つの目標だ、とみなされることになる。
この目標は探究によってではなく想像力によって、つまり見知らぬ人びとを苦しみに悩む仲間だとみなすことを可能にする想像力によって、達成されるべきなのである。
連帯は反省によって発見されるのではなく、創造されるのだ。私たちが、僻遠の他者の苦痛や屈辱に対して、その詳細な細部にまで自らの感性を拡張することによって、連帯は創造される。」
(引用終わり)
○も、もう我慢できないッ!
リチャード・ローティの思想はパレスチナの人々の為だけでなく、日本国内や世界中で起こっている「分断・断絶」「差別・蔑視」「虐待・殺戮」「無視・無関心」の病理を見据え応急措置を施す処方箋となり得るか。
ウクライナ戦争も、いや戦闘状態だけでなく、日本においても外国人労働者の労働実態、入国管理制度問題、ジェンダー多様性の展開、言論空間に広がるヘイトスピーチなど、見えない境界線が隔てる人と人との乖離がいよいよ実害として顕在化している現在。
応急措置じゃダメなんじゃないか、伝統的にも宗教信仰的にも歴史的にも地政学的にも社会福祉的にも、誰もが納得できる明快で根本的な解決法を探るべきではないか、という理想は掲げてもいいんだと思うけれど。
しかし急性的に進行する悲劇を即刻に食い止めるためには、絶対的唯一の解決法を追い求めるよりもまず、現状をわずかでも改善し得る妥協点に向けての「会話・対話」を細々とでも繋いでいくことが大切なのではないか?
我々と彼らが今このようであるのは “偶然性” の産物、“アイロニー” で見るならば全てのアイデンティティと境界線に必然性などない。ならば現在の不変に見える区別や人々の悲しみ憎しみもまぜこぜにして、“連帯” をこれから創造していくことも可能なのではないか?
その道を探るローティの思想はいよいよ切実に現代世界が求める希望であると思う。
またローティは現代アメリカのプラグマティズムに拠る哲学者ということで、字義通り「プラグマティズム(実践主義)」の立ち位置から伝統に依存する近代哲学の道を棄却した。
そこで古代ギリシャから続く「真理の探究」との西洋哲学の究極目標を惜しげもなく捨て去り、今人々が必要とする “連帯” を産み出すために独自のルートを開拓する姿は痛快でもある。
だから一般的な西洋哲学の論理展開を見慣れてる人がローティの言説に触れると、すごく珍妙な感覚を味わえると思う。これまで一番大切にされてきた考え方の枠組みを、まったく意に介さずにそこからずずいっと外れていこうとするから。
でも伝統的な枠組みから大きく外れていっても不思議と破綻していないような、とても説得力と整合性があるような奇異な感じも抱く。面白いんですよ、ローティの考え方の筋道。
ああっ、そんなこと言ってたら、もっともっとローティ哲学を喧伝したくなってきちゃった! もう我慢できない、やっちゃえっ!
◇「100分de名著」NHKテキスト
『偶然性・アイロニー・連帯』より
(p.6)
ローティの思想を一言で言うなら、「哲学とは『人類の会話』が途絶えることのないよう守るための学問である」というものになります。これは、ローティが自身初の単著『哲学と自然の鏡』(1979年) で述べていることをテーゼ化したものですが、これがローティの哲学全体を貫くテーゼにもなっています。
(p.27~28)
哲学者たちはことばづかいに序列を付けようとする。しかし実際の私たちは、より本当らしいものに近づくためにことばを使っているわけではなく、むしろことばを使うことによって自己を創造しているのだとローティは述べています。
ことばというものは、単に特定の目的のために使いこなされる道具であるというよりは、それを使うことによって目的自体を設定し、使い手の在り方を表現し、乗っていると思ったら乗っ取られてしまう、そんな極めて特殊な「道具」です。そして、それこそがことばの力だとローティは考えているのです。
(p.28~29)
ここに、ボキャブラリーをめぐる偶然性のプロジェクトの中心的なモチーフが出てきます。私たちは、ボキャブラリーを媒介にして真理(必然)に近づくのではない。ボキャブラリーを駆使し、ただ単に、それゆえ自由に、自分を「再記述」する。これが「言語の偶然性」におけるローティの議論の要点です。
みなさんもよく、少々わかりづらい話を聞いたとき、「それは、こういうことですよね?」と別のことばで言い換えて確認することがあると思います。それがローティの言う「再記述」です。
再記述は、抽象度を上げて真理に近づくというよりは、並列的な言い換えによって理解の “襞(ひだ)” を増やしていくことだと言えます。このように、ことばを「減らす」方向ではなく、「増やしていく」方向に価値を見出すことが、ことばの偶然性を認めるということなのです。
(p.32~33)
私たちの社会は、全員が同じ目標を共有しているわけではありません。それぞれの信念、欲求、価値観において対立する人々が、それでも何とか一緒に生活しようとしています。これは厳然たる事実です。
他方、偶然の産物としての私たちの道徳というものもたしかにあります。偶然とはいえ私たちが大切にしてきた言語、ことばづかい、価値観、それらに基づく道徳です。しかしながら、それはあくまで偶然の産物であり、その正しさを保障してくれるものは何もありません。ですからひとえに、互いを保護する(傷つけない)という最小限の目的をお互いにすり合わせながらやっていくほかない。そういうものが私たちの社会のありさまであると、ローティは考えているのです。
目的はバラバラで、「同調を避け」ているけれど、お互いを保護するという意味では協力することができる。そんな者たちがそれでも何とかやっていく。それがローティの言う「リベラルなユートピア」という社会の描像です。
そんなリベラルなユートピアの市民に必要なのが、「自己の偶然性」の認識です。一緒にやっていく人同士のあいだでは、自分が相手に影響されたり、相手が自分に影響されたりする可能性があると認識する。つまり、それぞれが変わりうる存在であり、必然に固執するのではなく偶然に開かれていることを確認する。そうやってお互いを改訂されることに対して開きながら、どうにかしてときには手を携える。そこに、連帯の可能性や必要性が出てくるのだとローティは言います。
つまり、「必然的な本質を共有しているわれわれだから、わかるはずだ」ではなく、むしろ本質など持たない、互いに偶然的な存在であるからこそ、何かしら一緒にやっていくことができるという可能性が出てくる。ここが、偶然性から連帯の契機が出てくるという、このあとの議論につながる部分です。
(p37~38)
しかしながら、その前の引用に戻れば、自分たちが最終的にはそれにすがるしかないような終極の語彙(ファイナル・ヴォキャブラリー)でさえも、アイロニストは「たえず疑問に思っている」とローティは言っています。自分にとっては「ファイナル」と思えるボキャブラリーさえも、よりよくなる可能性に開かれたものだと考えることが、まさにアイロニーだということになります。
ローティは、アイロニストは自分の終極の語彙が絶対のものだとは思っていない、なぜなら事実、他人の終極の語彙に感銘を受けることがあるからだと言っています。たとえば小説を読み、自分とはまったく境遇が違う人の話に触れる。自分がキリスト教徒だとして、仏教徒がどれほど真剣な信仰を抱いているかについて学ぶ。
そうしたことを通じて、自分とは異なる終極の語彙を持つ人が存在することを知る。そしてややもすれば、自分もそちらの終極の語彙に近づくことさえできると知る。これが、自分を疑うことができるという意味でのアイロニカルな態度です。
こうしたアイロニストは、「自分の終極の語彙だけは人間でない何か(合理性、神、真理など)に触れている」と考えることはない、とローティは述べています。
(p.42~43)
ローティがここで用いる「リベラル」は、東欧ラトビアで生まれ北米で活躍したユダヤ系の政治哲学者ジュディス・シュクラーからその定義を借りています。
シュクラーは、リベラリズムの思想とは「何が善であるか」の一致ではなく、「何が悪であるか」の一致に端を発しているとし、「恐怖に対峙するリベラリズム」の重要性を論じました。彼女はリベラルを、「残酷さこそが私たちがなしうる最悪のことだと考え、それを避けることを求める思想」と定義しています。ここで言う残酷さには、暴力など物理的な残酷さだけでなく、人を辱めたり貶めたりする心理的な残酷さも含まれています。
一方、アイロニストの定義はさきほど見たように、自分にとって最も重要な信念や欲求が、偶然の産物だということを認められる人物です。
このシュクラー的なリベラルと、ローティが定義するアイロニストは、公共的なリベラリストと私的なアイロニストとして、一人の人間のなかに同時に存在しうる、というのがローティの主張の重要なポイントです。リベラル・アイロニストは偶然性を認める人ですから、自らの信念は何らかの本質や必然に結びついているとは考えない、つまり基礎づけえないとわかっている。
しかし、そうは思いながらも、人が受ける苦しみや、人類がなしうる残酷さというものが減少していくことを望む。それは両立しうるのであり、そのやり方がリベラル・アイロニストという人物像を通して体現されるとローティは言います。
(p.59)
公私を統合しようとすることは、いずれかのボキャブラリーを黙らせることだ。その統合の要求を放棄すれば、私たちは公的にも私的にも会話を続けることができる。会話を続けるなかで、私たちは他者の語彙に触れ、心を動かされたり、疑問を感じたりしながら、自己を拡張し、自己の終極の語彙を改訂に開いていく。改訂の余地があるからこそ、私たちはそこに、他者とのつながりや重なりという希望を見出すことができる。つまり私たちは、リベラル・アイロニストであるからこそ、連帯の希望を抱くことができるのです。
(p.68)
(伊藤計劃の思考実験的SF小説『虐殺器官』を紹介して)
しかし、現実の歴史に目を向けてみると、ことばの言い換えやその使い方の浸透が、虐殺に至るまでの過程において決定的な役割を果たしたと言える例が実際にあります。
それを研究したのが、ローティの孫弟子にあたる米国コネティカット大学のリン・ティレルです。彼女は2012年の論文「虐殺の言語ゲーム」において、1994年のルワンダ内戦で起きた大量虐殺を取り上げ、言語共同体におけることばづかいが変わることがジェノサイドにまで行き着いたことを具体的に分析・検討しています。
(p.76)
人間に本質というものがあるとすれば、それを持っていない相手は人間ではないということになり、「われわれ」と「やつら」のあいだに線引きがされてしまいます。人権主義者が言うように「人間には本質的に人権が付与されている」と考えるのならば、翻って「人間でないものには人権がない」ということにつながるのです。
人権はたしかに大事な概念です。それは帰結において大事だといえます。「人には人権がある、だからそんなことはやってはいけない」という話のために使ってこそ人権ということばは活きる。しかし人権が本質だという話になると、そもそも相手が私たちと同じ人間だという感覚がない場合には、それは前提において機能しないことになってしまいます。
(p.78~81)
そして、私の私的な目標はあなたの苦しみに何の関わりも持たないかもしれないが、「私の終極の語彙のなかでも公共の活動に重要な関わりをもつ部分は、私の行為が影響を及ぼすかもしれない他の人間存在を辱めうるさまざまな事態すべてを自覚することを自らに要求する」と述べます。
つまり、人権という「本質」を基盤にするのではなく、残酷さを減らすというリベラルの、したがって「公共的な目標」のために、紐帯を結ぶ。これがリベラル・アイロニストのあり方だとローティは説くのです。
「こうして、リベラルなアイロニストは、別様の終極の語彙についての可能なかぎり多くの、想像力を介した交際・知識(イマジナテイブ・アクウエインタンス)を必要とする」。ここからローティは、リベラル・アイロニストにとって重要なのは、実は哲学ではなく、文学やジャーナリズムなのだ、というあっと驚くような主張を展開します。
(~中略~)
ローティは、本質主義を採ることはもはやできないからこそ、小説やエスノグラフィが、他者の苦痛に対する感性を高めるという公共的な目標のために役立つというのです。
【 連帯は、誰が聞いても認めうる原言語の形態をとってすでに待っていることが発見されるものなのではなく、小さき断片を手がかりに構築されなくてはならない。】
「誰が聞いても認めうる原言語の形態」とは、改めて確認するなら、本質を探究すればわれわれはみな同じ人間だとわかるということです。ローティは、連帯とはそのようなものとして「発見される」のではないという。
そうではなく、連帯は「小さき断片」を手がかりに「構築され」るとローティは言っています。小さな共感や、一人ひとり個別の人間に対しての同情やシンパシーといったものを手がかりにしてつくっていかざるをえないということです。真理の探究や知識の基礎づけによっていつかその原理が発見されるのではない。それはつくるしかないものなのだ。これが、ローティの「連帯」についての考え方です。
(p.83)
では、本質という話を抜きにして、どうやって連帯の可能性を探っていくのか。最後に残る課題はそれです。言い換えれば、どうすれば私たちは「残酷さ」に対する感性を磨くことができるのか。共感を育むことができるのか。
前回の最後に見たように、ローティはその手がかりをフィクションやエスノグラフィ、ジャーナリズムに求めます。とりわけフィクションには、「正しくなさ」を内側から描きうるという意味で、そこに可能性を見出しているのです。
(p.86~87)
われわれを拡張せよ。これがまさに、ローティが考える希望としての感情教育です。これがなければ残酷さの回避というものは機能しはじめない。その意味で、感情教育はリベラリズムにとって非常に重要で不可欠な要素です。端的には、被害をありありと描くジャーナリズム、ルポルタージュ、そしてフィクションが、まず役割を果たすことになるでしょう。
私たちはそうした分野の作品を通じて、被害者が置かれた悲惨さ、残酷さ、そしてそれが偶然のものでしかない・・・つまり私たちにも起こりうる・・・ことを想像することが可能になります。
(~中略~)
「私たちは、小説家のおかげで、残酷な行為が起きているのはまさにそれが気づかれていない領域でなのだという事実ばかりにではなく、残酷さは私たち自身のうちに源があることにも注意を向けることができるようになる」と述べています。私たちのなかにありうる「残酷さの芽」というものに対して意識を向けさせてくれる。これもまた、フィクションの役割だというのです。
(p.99~100)
再び『偶然性・アイロニー・連帯』第3部第九章から引用しましょう。
【 私が提起する見方は、道徳的な進歩と称される事柄があること、しかもその進歩が現実により広範な人間の連帯へと向かっていることを肯定するものである。しかし、その連帯は、あらゆる人間存在のうちにある自己の核心、人間の本質を承認することではない。
むしろ、連帯とは、伝統的な差異(種族、宗教、人種、習慣、その他の違い)を、苦痛や辱めという点での類似性と比較するならばさほど重要ではないとしだいに考えてゆく能力、私たちとはかなり違った人びとを「われわれ」の範囲のなかに包含されるものと考えてゆく能力である。】
文化の違いや宗教の違いは、一見すると大変大きな違いに思えます。しかしそれがどれだけ違っていようとも、そこに苦痛を受けている人が存在する、辱めが存在する、そこに対して残酷さを行使するようなわれわれの加害行為がありうる、こうしたことに思いを馳せることによって、「われわれ」という範疇を少しでも広げることが可能になるのではないか。ローティはこのような考えを示しています。
それは、文字通り一歩一歩進むしかない、慎重な歩みとなるでしょう。しかし、伝統的な哲学が自明視した本質主義を棄却した以上、人々の連帯は、まさにいまここにある小さな断片を手がかりにつくるしかないのです。
(p.105~106)
ローティにとって、社会という単位で目指すべき希望も、そしてそのためにむしろ直視しなければならない暗黒面も、どちらも避けては通れないものでした。それは決して「わかりやすい」哲学ではありません。というのも、ひとつの正しい立場、正しい主張へと読者を説得するものではなく、むしろそうした「正しさ」を解体し、自身にとって重要な「終極の語彙」を改訂へと開くことに促す点にこそ、ローティ哲学の最重要ポイントがあるからです。
これで引用を終わります。っていうか、朱喜哲さん執筆のNHKテキストは一冊まるごとかけての起承転結で論旨展開しているので、つまみ食いだけではその魅力の十分の一もお伝えできませんでな。全文を読みたければお購い求め下され、今月中だったらほとんどの書店で取り扱いがあると思います。
さてここまで見てきたローティ哲学、いかがだったでしょうか?
なんかほんのりと、仏教思想のかすかな香りが感じられるのは気のせいか?
「われわれはたまたま人間に生まれてきた」「この世は仮の宿り、この身は借り物の器」「だから生まれ育ちや今のステータスなんてものも、偶然のわずかな差分でしかない」
「無無、一切皆空!(本質なんて無いよ)」「不易流行、生々流転(すべては移り変わりゆく)」
「それでも今世での多生の縁がある、どうにかこうにか仲良くやっていきましょうよ」
ローティが活動した現代アメリカでは、近代に鈴木大拙らによって紹介された仏教思想が時を経て多彩に芽吹いていた。ヒッピー文化やオリエンタリズムへの傾倒、アジア圏への憧れや「禅 ZEN」カルチャーの浸透。これら東洋哲学の派生波にローティも少なからず浴していたのではないかと考える。
それで伝統的な西洋近代哲学と相容れない部分が出てきた、とか? 想像ですけどね。
ただ一箇所、テキストで紹介されているローティ思想に納得できない所があります。
「【残酷さに対峙するための共感】(p.84~85)」の章で述べられている「残酷さのさなかにある人は、何もことばを発することができない」という主張は、苦しみの渦中にある当事者の声を過小評価する流れにつながりうる点で批判されるべきかと思う。
ガイド役の朱さんもこの点については留意していて補足説明をしているが、やや物足りない弁護にも感じられる。
しかしローティ(1931~2007年)の思弁活動は既に10数年前に途絶えており、この批判を受けて論考を改訂することは本人にはできない。それはむしろ今日を生きるローティの後進や賛同者の役目、ローティ思想に物足りないものを感じたならば自分たちで修正・補強し、実践する道を見出していくべきなのだろう。
そしてその補強、いや補強にとどまらず、論理と両輪をなす現場の実践に資する観点は、日本で立岩真也ら社会学者・社会運動家や福祉従事者らが鍛え上げ続けている。
方法論や活動フィールドは異なれど今、多くの人々が同じヴィジョンを重ね、遠くに居る他者の痛み苦しみが少しでも減ることを求めて動いている。