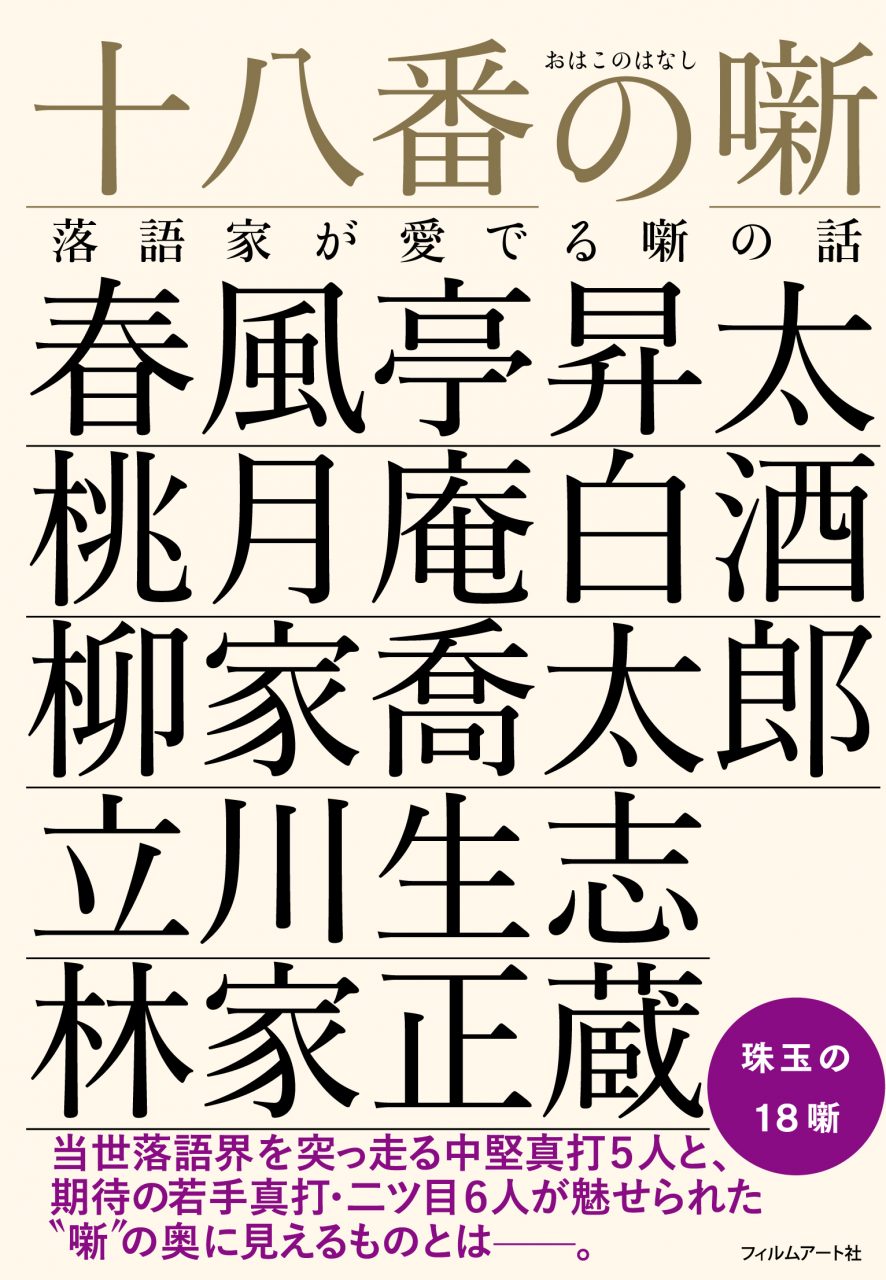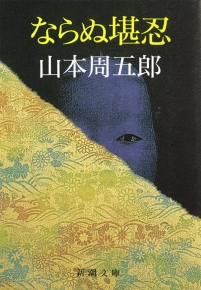○古臭いくせにいつまでも新しい、それが落語の人情噺(にんじょうばなし)
◇日経新聞 2023.10.22(日)朝刊
1面コラム欄「春秋」より
女優の寺島しのぶさん出演という話題にひかれ、10月の歌舞伎座に足を運んだ。演目は世話物「文七元結(ぶんしちもっとい)物語」である。もとは名作落語。こちらは五代目古今亭志ん生の語りを暗記するほど聞いた。山田洋次監督が脚本・演出を手がけた舞台の仕上がりも楽しみだった。
▼腕はよいが博打で身を崩した左官の長兵衛。女房のお兼とは喧嘩ばかり。見かねた娘お久は金を作るため遊郭に駆け込む。孝行に感じ入った女将のはからいで「約束」と引き換えに50両を手にした長兵衛だが、帰り道、お店の金をなくして思い詰めた手代文七に出会ってしまう。
▼ただでさえ泣ける話なのに、輪をかけて山田流の演出が泣かせる。劇場を出て雑踏を歩きながら、しみじみ思った。この物語に出てくる人物はみな、自分よりも他人を先に思いやる。人のことなど心配している場合ではないくらい、暮らしに窮しているにもかかわらず。その心根の優しさに触れて、ひととき胸がぬくもる。
▼「人間は信じるに足るものだ、という思いを感じて、お客様が席を立てる作品になれば」と監督は会見で語っていた。遠く、だが同じ空の下でまた、人々が憎みあい争っている。人間は信じるに足る。その言葉は彼の地では空虚にしか響かないのか。「人の命ってのはそんなもんじゃねえ」。志ん生の長兵衛が言っている。
◇『キネマ旬報』2024年1月号
連載コラム「立川志らくのシネマ徒然草」No.619「山田洋次監督の歌舞伎を見る の巻」
久しぶりに歌舞伎座に足を運んだ。山田洋次監督が演出をするからである。
(~中略~)
そして落語に精通している(『文七元結』は落語のネタ)山田洋次監督は、歌舞伎なのに敢えて役者の動きよりも台詞に重きをおく演出をした。あの広い歌舞伎で台詞中心の芝居にするのは相当の賭けだったと思う。
でも一流の落語家ならば、千人二千人の観客を物語のドリームに誘うことはそんな難しいことではない。その台詞の中心となったのが女郎屋のおかみを演じた片岡孝太郎と主人公の長兵衛の女房を演じた寺島しのぶ。そしてコミカルな動きを長兵衛を演じた中村獅童に任せた。確かに目の前に繰り広げられている世界は歌舞伎なのだが、現代喜劇のようでもあり、立体落語のようにも見えた。
ラストは、芝居的なほのぼのとした感じで幕となったのだが、そこは落語のようにズバッと暗転に、いや実は落語の『文七元結』も落ちがない。『芝浜』並みの落ちがついたらいいのにと、談志も格闘したが無理だった。山田監督も無理ならば、おっと志らくの出番か! いやはや。
(引用終わり)
○『文七元結』と『碁盤斬り』
『文七元結』は人情噺の傑作の一つで、明治の不世出の名人・三遊亭圓朝の作と伝わる。昭和の名人・五代目古今亭志ん生も得意とした演目で、すったもんだの挙げ句に万事丸く収まる筋が特徴。
娘のお久が父長兵衛の金の工面のために吉原に我が身を売る展開はあれど、長兵衛と手代文七とのやり取りの末に結局は大団円で幕を閉じる。
◇『落語の名作 あらすじ100』
著:青木伸広/監修:十一代目金原亭馬生(きんげんていばしょう)
日本文芸社 2017年
「第四章 ほろりと泣ける人情噺」
▼『文七元結』 より結末を引用
翌朝になり近江屋の使いの者が吉原へ。文七と主人は長兵衛の長屋へ赴き、五十両の金を返して、親戚づきあいの契りを交わす。祝いの酒に、肴として用意したのは一丁の駕籠(かご)。中から出てきたのは近江屋に身請けされたお久だった。
このお久と文七が夫婦となり、後に麹町に元結(もっとい=髪のもとどりを束ねるヒモや糸)屋を開いて、ご維新の頃まで繁盛したという「文七元結」の一席。
(引用終わり)
うう、よかったねぇ・・・。
お久は吉原に入ってすぐに身請けされて実家に帰ってきたんで、そこら辺の設定もハッピーエンドの雰囲気に一役買っている。これがお久が帰って来れなかったとか、吉原で何年も過ごしたとかいう話になると、だいぶ印象が変わってくる。
しかし同じ人情噺でも、似たような筋を辿ってしかも同じく我が身を売り遊郭に入った娘が、ついに帰って来ないままエンディングを迎えるという演目がある。それが『柳田格之進(やなぎだかくのしん)』、またの名を『碁盤斬り(ごばんぎり)』。
前掲参考書からこの噺の粗筋を引用しよう。
あ、ちなみに、以下の引用文中でちょいちょい登場人物名の細部が変わることがありますが、出典の記述を尊重してそのまま記載してます。
古典落語では流派や演者によって作中の固有名詞が変更されることも多く、また題名そのものも複数ある場合があります。
映画タイトルは『碁盤斬り』、これも演目名ではあれど、落語では主人公の名を取り『柳田格之進(やなぎだかくのしん)』の方が通るかも。他にも『柳田の堪忍袋』『碁盤割り』など内容にまつわる別名が。
あと人名も、主人公は「柳田格之進/角之進」、娘は「お絹」はまぁ定番。柳田が懇意にする商家は「万屋/萬屋(よろずや)」、その主人は「源兵衛/万兵衛」、番頭は「徳次郎/徳兵衛」など。どちらかというとこの万屋の主従の名前にバリエーションがあるかも。
では『柳田格之進』あらすじを。
◇同『落語の名作 あらすじ100』「第四章 ほろりと泣ける人情噺」より
▼『柳田角之進』(p.104~105)
〖 濡れ衣を着せられた武士の意地と誇り 〗
事件の発端は八月十五日の晩。浪人・柳田角之進がいつものように碁敵(ごがたき)の万屋万兵衛に招かれ碁を打っていった後で、五十両という金の行方が分からなくなった。この金は、二人が碁を打っているところへ万屋の番頭が届けにきた売掛金。さては柳田が・・と疑う番頭だが、主人の万兵衛は、曲がったことの嫌いな柳田様がそんなことをなさるはずがないと一向に取り合わない。
どうしても柳田への疑念を振り払えない番頭は、翌日になって主人に無断で柳田を訪ね、五十両の一件について問いただした。すると柳田は、「金を盗ったおぼえはないが、このようなことが上に届いては家名を汚す。その場に居たのが不運と思い、五十両用意いたそう」
そう言って翌日また訪ねるよう言いつけ番頭を帰した。実は柳田、金のことで疑われたのを恥辱と考え、切腹して身の潔白を示そうとしたのだった。
ところが、そうした父の腹づもりを察した娘が、自ら吉原に身を沈めることで五十両を用意し、結局は切腹を思い止まらせた。
翌日、金を取りにきた番頭、「もし後で金が出てくるようなら、私の首と主人の首をさしあげます」としたり顔で言い残して帰っていった。
店に戻った番頭から話を聞いた万兵衛、褒めるどころかその勝手な振る舞いを厳しく叱り付け、急いで柳田を訪ねるのだが、家はすでにもぬけの空。柳田はどこかへ消えて行方知れずになっていた。
季節は流れ、暮れの煤(すす)払いの日。万兵衛の居間から五十両の包みが見つかる。やはり柳田は盗んでいなかったのだ。さあ万屋は大騒ぎ。どうにかして柳田を探し出そうと、店を挙げての捜索が始まった。
年が明けて、正月の二日。湯島切通しの坂で番頭と鉢合わせをしたのが、なんと柳田角之進。事情を聞いた柳田、「首を洗って待っておれ」と言い残して去っていった。
翌日、万兵衛と番頭は揃って柳田の前へ。ところがいざ斬られるという段になると、万兵衛は番頭をかばい、番頭は主人をかばって自分ひとりだけ斬って欲しいと申し出る。憎い相手であるとはいえ、互いを思いやる主従の姿に感じた柳田は、床の間に置いてある碁盤を真っ二つに切り落とし、両名の首の代わりとする。
ならぬ堪忍、するが堪忍。のちにこの堪忍が両家に明るい春をもたらす「柳田の堪忍袋」という一席。
(引用終わり)
む、娘さん・・ッ!
高潔な武士・柳田格之進の忍耐より、互いにかばい合う主従の絆より何より、娘さんの扱いヒドくない!? 吉原に入ったっきり戻りませんが。
そう、ここが『文七元結』と『柳田格之進/碁盤斬り』の大きな違いの一つ。厄介な性分を持つ父親の窮地を救うために娘が同じ道を辿りながら、彼女らのその後の扱いに大きな隔たりがあるのだ。
『文七元結』長兵衛の甲斐性なしを贖うために吉原に向かった娘お久の覚悟、『碁盤斬り』柳田格之進の不運不遇を支えるために遊郭に入った娘お絹の覚悟。それが両話の重要な軸となりながら、彼女らの視点に立ち物語を追うと、随分な境遇の差が浮き彫りになる。
アレ? これ現代フェミニズムの観点に立つと、どっちもアウトなんじゃない?
『文七元結』もギリギリだと思います、お久が数日とはいえ吉原に入ったのは確かだから。ただこちらは、その吉原の見世の女将が長兵衛お久の父娘とも旧知の仲で、お久から事情を聞いた上で娘の身を預かる、という説明が為される。
客は取らせず長兵衛が真面目に働いて借金を返せば何事もなく家に帰そう、との約定が交わされるので、まだ救いがある。まぁ、その大事な金を、身投げしようとしてた見ず知らずの若者にひょいと渡しちゃうんだから話がややこしくなる訳ですが。
この長兵衛の、困ってる人を放っておけずに自分の大損を顧みず手を差し伸べてしまう心意気が、この人情噺の真骨頂でもあります。だからって娘の身の無事がかかった大事な金を、さして逡巡もせずにその場の勢いでやっちゃうってのは如何なものか?
◇『十八番の噺 落語家が愛でる噺の話』フィルムアート社 2017年
▼柳家喬太郎(やなぎやきょうたろう)の『文七元結』(p.106~107)
古典落語の文七元結にも、そういった(ときどき、噺の中で、まったく思ってもみなかった台詞を言っちゃったりする)ことがありました。
橋の上で長兵衛が、金をなくして身投げしようとしている商家の奉公人の文七に金をやるじゃないですか。金は、娘のお久が吉原に身を沈めてこしらえてくれたんだと説明する長兵衛に文七が、そんな大事な金はなおさらいただけない、と拒絶の姿勢を見せる。
そこで長兵衛が、「ここにお久がいたら、『おとっつあん、私はいいから、その人にやっておくれ』って、うちの娘だったらそう言うんだよ。だからてめえにやるんだい」って、ふと口をついたことがあるんです。
まったく思ってもいなかった台詞です。僕じゃなくて、僕の中の長兵衛が言ったんです。江戸っ子っぽくはないかもしれない。江戸っ子っていうのは、意地でお金をやっちゃうみたいなところがあるから。けど、「お久が言うに決まってる」っていうのは、江戸っ子の了見と多少違っても、僕の『文七元結』はこれでいいと、そう思いました。
女性の落語ファンの方に、『文七元結』がいい噺なのはわかる。だけどお金をあげる場面は引っかかっていた。江戸っ子だからって頭では理解できるけど、本当にあげるの? とどうも共感できなかった。
ところが僕のを聴いて、「あの一言ですとんと腑に落ちた」と言ってくれた人がいました。よかったなと思いましたね。
(引用終わり)
むむぅ、難しい・・!
離れていても互いを想い合い心ばえを慮る父娘の情、だけどそこでお金をポンッとやっちゃうのはどうなのよ、お父っつぁん?
しかし筋立てとその後の展開にお久にとっても救済があり、結局はすぐに家に戻ってこれた。両家の縁も付き、最後はまぁハッピーエンド。
一方、『柳田格之進』はどうか?
◇「PRESIDENT Online」記事
〖「今の時代には合わない」と嫌っていた・・落語家・立川談志が「柳田格之進」を死ぬまで口演しなかった理由/そんな噺を「草彅剛主演の映画」にするためにやったこと:③ 〗(寄稿:立川談慶)
談志は、あの言動からは信じられませんが、フェミニストでした。
(~中略~)
もしかしたら、「武士の気概に対する美学というよりも、父のメンツのために吉原で働かないといけなかった娘の絹の不憫さ」を感じていたのかもしれません。
(~中略~)
娘を売るほどの値打ちが「武士の気概」にあるのか。当時の名人たちが平然とやっていた「柳田格之進」に違和感を覚え、口演しないことでひそやかに反旗を翻していたのかもというのは考えすぎでしょうか。
(引用終わり)
かの天衣無縫の落語家・立川談志にしてからが、『柳田格之進』の筋には疑問を呈していた。時期的にも数十年前、前世紀中のことだろうが、フェミニズムがまだあまり根付いていない時代にあっても、この筋はさすがにむごいと感じていたのかも。
そんな上掲記事を寄稿した、談志門立川流真打の落語家・立川談慶(たてかわだんけい)さん。映画『碁盤斬り』公開に合わせた投稿で、その映画に本人が出演しているとのこと。
(* あ、ちなみにサイト記事の後半で映画のネタバレが少しあるのでご注意を。と、本稿でネタバレしまくってる拙者が言ってみる。)
そして映画『碁盤斬り』で件の娘・絹を演じるのが、清原果耶さん。真面目で凛とした芯の強さのあるお絹に相応しい配役であるが、なおさら彼女の辿る運命が気になってくる。
そう、主演・柳田格之進=草彅剛の役者としての円熟ぶり、監督・白石和彌の手腕にも大いに注目が集まりますが。この格之進の娘・絹の存在、扱い方描き方こそが、映画『碁盤斬り』の中で一・二を争う重大な核心であると考えているのですが。
お絹の境涯を物語の添え物程度の扱いにすることは、現代の感覚が許さない。格之進に武士の気概が、また他の登場人物にもそれぞれの譲れない意地があるように、年若い娘である絹にも貫き通したい矜持があるのだ。
このお絹が弱ければ物語はただ悲哀のものに、また父格之進の心理と行動にも強度が失われてしまうように思える。存在が薄ければ、身勝手な男たちがただただ無軌道に動き回るだけの映像になってしまうかも。
ゆえに絹=清原果耶の物語全体を引き締める責任は重い・・。っていうかもう公開直前で、撮影自体も1年くらい前に既に終わってるんだろうけれど。それでも他の熟練の出演者陣に勝るとも劣らぬ、強固な演技と存在感を発揮せねばならないだろう。
ちょっとお絹ちゃんの声出し応援とかしたいんですけどー、劇場で。頑張れー、お絹ちゃーんッ!
○お絹ちゃん、自害ルート!?
こちらもご参照↓。
◇『ぴあ エンタメ情報』連載
「 山本益博の ずばり、この落語!
:お気に入りの落語、その十七『柳田格之進』」
「 しかし、お絹と徳兵衛が夫婦になることが理不尽に思える落語家が、ほかの筋立てを考えだした。」
あっ、やっぱりみんなお絹ちゃんの扱いに納得いってなかったんだ。では具体的にどうするのか?
前掲『十八番の噺』にて、立川談慶さんと同じ談志門立川流真打の立川生志(たてかわしょうし)さんが選んだ自身の十八番噺の一つが『柳田格之進』。
現在ではしっかり骨格が出来上がっている古典落語でも、演者によって細部が異なっていたり解釈に幅が出たりして、人により違った味わいが出るのが寄席に通って現代落語家の口演をきく醍醐味の一つ。
時には筋立てを大きく変え、全く違ったストーリーにしてしまうこともあるという。
◇同『十八番の噺』より
▼立川生志の『柳田格之進』(p.137~147)
(主な登場人物)
浪人・柳田格之進、大店の主・萬屋万兵衛、番頭・徳兵衛、格之進の娘・お琴
(あらすじ)
碁をきっかけに厚い友情を結ぶこととなった浪人の柳田格之進と大店の主人・萬屋万兵衛。ある日、格之進が帰った後、萬屋の店で五十両が紛失していることが発覚し、番頭から、格之進が犯人ではないかと疑われ・・・。
▽三つのテーマがある
この噺、ほとんど笑うところがないんです。でも、どこか心を打たれます。
古今亭志ん生師匠、先代金原亭馬生師匠、志ん朝師匠の音源を聴いて、また一門の志の輔や談四楼の生の高座を勉強させてもらいながら、つくづくそう思いました。
しかし、自分でこの噺を演ろうと思うまでは随分と時がかかりました。なぜかというと、噺自体は素晴らしいのですが、何かが引っかかって、まるで自分の腑に落ちて来なかったんです。『紺屋高尾(こうやたかお)』のように藍色に染まった職人の手に花魁が気づかぬはずはないという現象的な腑に落ちなさではなく、もっと精神論的なところで納得がいかなかったのです。
噺の根幹に関わるところの腑に落ちなさでしたので、もし演るとしても、この噺は誰からも稽古をつけてもらわないのが逆に礼儀だなと思いました。いままでのカタチで教えてもらっても、どうせ変えてしまうのだから稽古をつけてくれた師匠に失礼になってしまう。
だから、すべて自分で作り直しました。『柳田格之進』というもともとのストーリーをいったんバラバラにして、一から組み立て直しです。
生志版『柳田格之進』に辿り着くまで試行錯誤し続けました。
先ず、柳田の娘さんの名前を先輩方とは変え、“お琴” としています。彼女の生き方そして死に方を自分自身で作ったからです。
そして、この噺のテーマを次のように考えました。
この人情噺は、武士と商人の噺です。主旋律は武士の生き方。さらにこの二つの身分の違いからくる三つのテーマが応酬しあいます。
一、柳田格之進と娘お琴の親子の情
二、柳田と萬屋万兵衛の男の友情
三、万兵衛と番頭徳兵衛の主従の情
人情噺というからには、この三つの情が描けなくてはなりません。
噺の世界に分け入りながら、一人ひとりの登場人物の立場になって、この時この人は何を悩み、何を救いとし、何を考え、どう行動したのかを想像してみました。この自問自答には、長い時間を要しました。
すると、自分にとって、いままで何が腑に落ちなかったのかが見えてきたんです。
それは、柳田格之進の娘の描かれ方でした。
主人公柳田格之進は人づきあいの不器用な武士ですが清廉潔白を貫く存在。しかし、常に彼は正しくはないということもストーリーからよくわかる。
お琴は、武士の娘として、父の正義の為に自ら犠牲となり、いわば、父の武士道の合わせ鏡のような存在。従来の『柳田格之進』では、この描き方が弱いと思っていました。
なぜかというと、商家の番頭に侮られるほどの父の不完全さを、娘が補っているんですものね。彼女こそ完璧な武士道実践者かもしれません。
『柳田格之進』の資料をいろいろ調べてみると、過去に娘が自害してしまう演り方があったことを知り、やっぱりな、と思いました。しかし、どの先人がどんなふうに演ったのかはわからない。ま、一から作り直そうとしているわけですから、わからないほうが良かったのですが。
浪人から脱しようとする父柳田格之進を助けるために、花魁になり苦界に身を沈める娘。そして、そこまでした祈りが叶い、父が帰参して藩士として再び生きていくとなったその時に、武家の教育と躾で育った娘が吉原で辱しめを受けている必要はない。
そんなお琴の気持ちを、柳田のこの台詞に込めてみました。
クライマックスである碁盤斬りの前、「私の首を」「いや、私の首を」と、萬屋主従がかばい合っているのを、「黙れ黙れ黙れ!」と喝を入れ、涙ながらに語る柳田。
「・・・運命(さだめ)とは非情なものよ。わしの帰参があと十日早ければ娘は吉原などへは行くことはなかった。帰参が叶い直ぐに金の支度をし吉原へ迎えに行ったが娘は逢うてくれんのじゃ。いったん離縁したものは・・・、父でも娘でもないと、父親のわしに逢うてくれんのじゃ。あくる朝、夜が明けぬ前に再び吉原へと行ったが、その時には娘は自害をしておった。
“ 柳田格之進様、ご帰参おめでとうございます ” と文を残してのぉ」
娘は、父親の帰参を確認するまでは生きていたことにしたんです。無事に帰参することをずっと祈っていたわけですから。願いが叶ったことを確認して、喉を突き自害をさせました。
これが僕の描き方です。お琴という武士の娘の生き方を考え、残酷ですがこうしました。
お琴には武家育ちの凛とした美しい娘でいてほしかったという僕の願いもありました。
自死を賛美するつもりは毛頭ありませんし、こういった武士道が正しいかどうかさえ疑問です。ただ、この噺は安易にハッピーエンドに終わるよりも、悲劇を伴いながらストーリーを完結することも大事だなと思っています。
▽ “柳田格之進” の人物像とは?
ここで、父、柳田格之進の立場に移ります。なぜ彼は、お琴の自死の後すぐに萬屋に仇を取りに行かなかったのか? いかに男尊女卑の時代だからといっても、最愛の娘が番頭の猜疑心の犠牲になったのですから。
きっと、清廉潔白な彼は自分の落ち度、自分の弱さを知っていたんでしょう。そして、首を取るべきか、許すか、迷いに迷っていたのでしょう。しかし、娘の悲しい自死がなければ、自分の過ぎ越してきた生き方、落ちぶれて浪人になった理由、あらぬ疑いをかけられた経緯などを深く顧みることもなかったかもしれません。商人に対しても、仇を取る気持ちのままで、許す気持ちにまでなれなかったかもしれません。
この娘の死は、柳田格之進はじめ登場人物すべてに、とても多くの意味を与えてくれているのです。登場人物のみならず、落語をしゃべっている僕にも、聴き手の皆様にも。
▽現在につながるテーマ
なぜなら、僕らが生きている今の時代も、殺意は介在しなくても、他人の過失や自然災害で罪なき人々がお亡くなりになることがままあるからです。
そんな時、過失や自然災害を憎いと思うし、もし人災ならば罪を償うべきとも思いますが、同時に、許すという心も持って生きなければ辛さが増すばかり、とも思うからです。
実は、この噺を作り直そうと思ったのが、2011年3月11日の東日本大震災の後だったのです。
多くの方が犠牲になられ、死について考えざるを得ませんでした。しかし、災害のショックで、この噺を高座にかけることは出来ませんでした。
そして翌年、偶然にも3月11日が横浜にぎわい座での立川生志独演会「ひとりブタじゃん」の公演。
土曜日でマチネだったので、地震発生時刻午後2時46分の一分前を仲入り時刻にしました。お客様はそれぞれのやり方で祈りを捧げていましたし、僕も楽屋でテレビの追悼番組を見ながら黙祷しました。その仲入りが終わり、後半の高座に、僕は意を決して生志版『柳田格之進』をかけたのです。
災害でお亡くなりになったおひとりおひとりにもそれぞれの人生があって、その人生がそこで終わってしまった。その無念さ。落語家の僕にはどうしてもお琴の死と重なり合ってしまいます。
死の持つ意味を自分なりに真面目に考えました。
柳田格之進は僕でもあり、この世の誰にでもあてはまります。同じように、お琴は我々の愛おしい家族、大切な友人、恋人、罪なき多くの人々でもある、と思いました。
▽相応しいオチを模索して
落語を再構築する上で重要なのは最後です。笑いのない噺だけに、落語らしく落としたい。この噺に相応しいオチ(サゲ)を探しました。
そして、このオチに、二つ目のテーマ “柳田と萬屋万兵衛の男の友情” を置いてみようと試みました。
で、思い至ったのが「待ったはなし」という囲碁の言葉。
まず前半、仲睦まじい囲碁の場面。柳田から提案で「これからは待ったはなしにしよう」「はい、そういたしましょう」、萬屋から提案で「これからは屋号ではなく万兵衛とお呼びください」「万兵衛殿で良いのか」と、この二人の友情がぐっと強くなるところを置いておく。
その前半の “万兵衛” に対しての終盤。娘の無念を晴らす為に柳田がこの商家に再訪してからサゲの台詞に至るまでずっと屋号の “萬屋殿” と呼ばせる演出にしています。娘が死んで、柳田は心の中に葛藤があり、なかなか萬屋に行けなかった。しかし、娘の仇、番頭に湯島で出会って濡れ衣が明白となり、約束通りに萬屋宅へ来たわけです。だから、決して “万兵衛殿” と親しくは呼べないわけです。
ここから、僕の作った台詞で説明します。
最後、二人の首ではなく碁盤を斬り、許す! とした後の柳田は、
「(浪々の身であった頃、)その方に出逢うて救われた。身分でなく立場でなく、生涯の良き友を得られたことが何より嬉しかった。萬屋殿、達者でお暮しくだされ」
と言い、去ろうとする。
「お待ちください」と萬屋が引き留める。
「万兵衛殿・・・」
ここで、初めて、仲が良かった時の呼び名で応える。
「万兵衛殿、忘れたか・・・待ったはなしじゃ」。
友情は断ち切れていない。そして、人生は一度きり、過ぎてしまった過ちは許そう、振り返ってばかりいても、時は容赦なく待ったなしで進んでいくものなんだから、そういう気持ちも含めての台詞です。
暗い噺ですが、せめてここで一瞬の光が射し、お客様が救われる気持ちになっていただければと工夫しました。
▽ “番頭” がキーマン
そして、三つ目のテーマ “万兵衛と徳兵衛の主従の情” も重要です。
先日、この商家の主従関係について、僕の狙いをズバリ見抜いてくださった紳士が現れたんです。
直木賞作家の安部龍太郎さんでした。時代小説の達人がいらっしゃるというので、その公演は、『柳田格之進』と決めていたんです。
客席で聴いてくださった先生に褒めていただきました。それだけで光栄でしたが、すぐに素敵なお手紙が届きました。おおよそ要約します。
「生志さん、一つだけ気になるところがあるので書きます。志の輔師匠の『柳田』も聴いたのですが、この噺は、番頭がカギだと思っています。
要は、この番頭が柳田の家へ行くのを、男の嫉妬ということを理由としていましたよね。けれど、もうひとつ訳がありそうです。番頭はひょっとしたら、主人も柳田が盗んだと疑っているのでは、と気づいたのでしょう。けれど、主人はそれを言えないでいる。ならば自分が悪者になって、柳田のところへ行ってお金を取り返そうとした。嫉妬ばかりではなく、主人を思う気持ちの表れではないか」と。
慧眼です。番頭は主人の為に自分を犠牲にできる男だったのです。
「主従の義、厚き事。娘ならわかってくれようぞ」という柳田の台詞を裏付ける読み解きでもありました。
(引用終わり)
か、果耶しゃんっ! なんてむごい最期を・・・。
いやいやこれは立川生志版の『柳田格之進』だから、映画版で清原果耶さん演じるお絹がどうなるかはまだ分かりませんが。少なくとも大筋として、金の工面のために自らを遊郭に身売りすることは確かでしょう。
か、果耶しゃんっ! なんでそんな自ら、イバラの道を歩もうとするんじゃ・・!(←物語に入り込み過ぎた観客)
そう、清原果耶には透き通った凛々しい役や華やいだ可憐な役と等しく、過酷な試練を正面から受けとめ足掻こうとする高潔な魂の役も良く似合う。しかし同時に、放っておくとどこまでもシリアスな方へシリアスな方へと爆進していく稀有な逸材(←諸説あります)。これは危ないッ!
映画の清原お絹ちゃんはたぶん死ぬこたぁないとは思うけれど、それに等しい辛い目には遇うかもしれない。やはりこの娘役の処遇境涯こそが『柳田格之進』中で引っ掛かる最大の難局であり、それゆえ物語の鍵になりうる。
○お絹ちゃんアナザールート
映画でどこまで描かれるかは分からないけれど、一応、落語には付け足しというか格之進一家の後日談があるんですね。
◇『古典・新作 落語事典』
瀧口雅仁 丸善出版 2016年
▼『柳田格之進』の項
二人を許した柳田は五十両の金を用意するのに、きぬが身を売ったことを話したので、早速源兵衛がきぬを身請けしきぬに詫びると、父のためならと許す。
柳田と源兵衛は再び深い付き合いをするようになり、番頭の徳兵衛ときぬは夫婦となり、万屋の夫婦養子となって男の子をもうけた。そしてその男の子を柳田が引き取り、家名を継がせたという。
(引用終わり)
ラストに碁盤をズバッと叩ッ斬るのが『碁盤斬り』の終局、柳田が口上を述べてたいていはそこで幕となります。前出の柳田「待ったはなしじゃ・・」のオチも、演者によって入れたり入れなかったり。
そのそもこの演目『柳田格之進』、人情噺の中でも特に笑いの要素が少ない変わった一品だそうで。かなり真面目に憂き世の義理人情を語り描こうとするものなんですね。
そこで上の後日談、これも付け足しと見なされていて、これを足すかどうかも演者の考慮次第。一応ハッピーエンドっぽい雰囲気を漂わせてはいますが、これもどうなんでしょうかね?
『文七元結』と違って融通がきく遊郭の女将が居なければやっぱり絹は見世に出ることになるし、そも自分がそんな境遇に陥った直接の原因たる万屋の奉公人を夫に迎えて、やれ目出度し目出度しとは到底言えないんじゃない?
いやぁ男女の縁は奇なもの味なもの、実は奉公人は誠実な男で二人は幸せに暮らしました、とか言われても。
( 映画では萬屋の奉公人は2人出てくる、もしかしたら中川大志さん演じる手代の弥吉ともう一人の番頭とで役割分担するかも?)
このハッピーエンドの構図は主に男性視点、武士の気概を通した柳田格之進、互いにかばい合う万屋主従の都合に合わせたもので、そこに女性の側、お絹の心情が欠けているように思われる。
後日談の筋は『文七元結』と似ていても、両者には娘の立ち位置を巡って決定的なズレがあるようだ。
男達の意地と面子をめぐるイザコザに巻き込まれ、自らの決断とはいえ遊郭にその身を売り、身請けされ戻ってきて場当たり的に彼らを許すことになった娘。
身勝手な男達を本当に許すことができるのか、この仕打ちに堪え忍ぶことができるのか?
いや、父である柳田格之進とて例外ではない。自身の不遇、朋友との訣別、娘の苦窮、それに加え映画版では諸悪の原因となる相手への復讐も描かれるとか。
しかし落語『柳田格之進』の筋はその復讐、憤怒と殺意の実現をギリギリの所で踏み止どまることにこそ主眼がある。自分の不甲斐なさと呪わしい運命から不遇をかこち、娘は吉原に向かい、碁友とは絶交した。その境涯の起点となった事柄が眼前に立ち現れた時、一体自分はどうなってしまうのか、ドス黒い激情を抑えることができるのか?
落語『柳田格之進』最後の一幕、締めくくりに用意されるのは「ならぬ堪忍、するが堪忍。」という格言。幸せな(?)後日談の存在を匂わせて、「のちにこの堪忍が両家に明るい春をもたらす『柳田の堪忍袋』という一席」と落ちる。
堪忍(かんにん)とは「堪え忍ぶ(たえしのぶ)」「相手の罪を許す」の意。今でも「堪忍袋の緒が切れた!」とか「すまん、堪忍してぇな!」とかの台詞で耳にすることがありますね。(ちょっと古いか。)
およそ耐えがたい苦しみに耐え、許しがたい仇敵と己の運命を心から赦すことができるのか?
この「堪忍」こそが落語『柳田格之進』、引いては映画『碁盤斬り』のメインテーマでありましょう。
○「ならぬ堪忍、するが堪忍」
これは慣用句の一節。手元の小辞典によると、「どうにも我慢できない苦しさを耐え抜くのが、真の堪忍である」の意。
ほんとはもうちょっと長い、というか元々ある「ならぬ堪忍、するが堪忍」の言い回しを使って後から歌仕立てにしたのかもしれないけれど。
「堪忍の、なる堪忍は誰もする。ならぬ堪忍、するが堪忍」
(=簡単に我慢できるちょっとした堪忍なら、誰でもできるものだ。とても許容できない、どうにも我慢できそうにない事をよくよく堪え忍んでこそ、まことの堪忍と言える。)
五七五七七の和歌形式になっている。これは中近世に詠まれた「道歌(どうか)」という、教訓的な内容を織り込んだ定型の教導歌である。日本人によく馴染んだ和歌のリズムを借り、信仰心や徳目を庶民に伝わるよう平易に説いたもの。
上の「ならぬ堪忍」の道歌を作り世に広めたとされるのが、心学者の中沢道二(なかざわどうに)。石田梅岩(いしだばいがん)が開いた心学(しんがく)は庶民に人倫を易しく分かりやすく教えるもので、その流れを汲む中沢道二も市中に立って人々に教えを説いた。
中沢は石川島の人足寄場にも通って無宿人や軽犯罪者ら寄る辺ない者たちに語りかけ、彼らが自らの道を見つけられるよう親身になって教諭したという。
道歌の方は正確には中沢道二の作とも確証できないのだが。「ならぬ堪忍、するが堪忍」と忍耐の大切さを説く内容は、生活実用の学を目指した心学者のものと考えるのはあながち外れているとも言えないか。
我慢てったって良い意味の我慢でしょうけれど。理不尽な仕打ちにただ黙って耐えることは堪忍ではなく。どうにもならない天運ならどうにか耐えてやり過ごし、人間関係の問題なら自分ができることはとりあえずやってみて、結果が出るまでちょっと辛抱。
日々の努力と忍耐を大切に、堪(こら)えられる事は堪え、それでもどうしても駄目ならもうしょうがないよ。
非人間的教条的な辛い我慢ではなく、あくまで人間性を高め、人と人とが許し合うための徳行としての「堪忍」である。ここ肝心。
抗いがたい逆境の中にあっても、その「堪忍」する対象は本人が決めること、当人だけが決められること。そして人の命と生の尊厳に重きを置くこと。この根幹が抜けては片手落ちだろう。
映画のラスト、柳田格之進はどんな堪忍をし、お絹はどう堪忍し、それは心の底から納得のいく選択であるだろうか?
* あ、説教臭い心学の先生を小馬鹿にした『中沢道二』ってぇ落語の小噺がある。あと人情話の名手・山本周五郎の短編表題にもなってますな。
◇『ならぬ堪忍〔新装版〕』
山本周五郎 新潮文庫 2012年
○志ん生のお家芸
さてそんな映画の原作、落語『柳田格之進』。本稿冒頭の新聞記事にもあったように昭和の名人・五代目古今亭志ん生が得意とした十八番の噺だったそう。志ん生から息子の十代目金原亭馬生・古今亭志ん朝にも継承され、まさにお家芸となったと。
昭和の爆笑王とも呼ばれた志ん生(1890~1973)、没後半世紀以上経った今でもリマスター作品が出るほど人気が高い。現存作品は晩年の録音がほとんどだから、ちょいとフガフガ喋ってんですがね。それが志ん生の人柄や生き様なんかと合わさって、なんとも言えない味わいになるというこれぞ名人芸。
その話しぶりも融通無碍、だいぶ不謹慎に思える際どいネタでも、志ん生が語ると不思議に危うく思えない。いや『黄金餅(こがねもち)』とか、長屋に死人が出て葬儀を出すまでをかなり巫山戯てドタバタ劇化してるんですがね、不謹慎なんだけどもついつい笑っちゃう。
人生の悲喜劇を茶化して面白おかしく聴衆に届けるその話芸の根底には、人間存在に対するある種の諦めと赦しがあるように思う。人間なんて所詮みんな不完全なもの、誰でも多かれ少なかれ欠陥を抱えているもんだ。
汗水垂らしてお金を稼いだって、ある日ふとしたはずみで西を向いちゃうこともある。じゃあ楽に気ままに遊んで暮らそうってやってると、お金が無くなって貧乏する人もいる。思うようには行きませんな。
そんな悲惨で滑稽で不可思議な人間の生を、愚かしくも愛おしいものとして紡ぎ出したのが志ん生の落語。みんなみんな不完全なんだよ、不完全に生まれて不完全に生きて、死んでも不完全なのが人間ってもんだ。
だからその日その日を滑稽でも大切に懸命に生きてみよう、たとえ辛くて悲惨でも、人と人同士で時に争い時に助け合いながら、共に暮らしていこう。
ああ、人の一生の不完全さを、そこで生まれる腐れ縁をこそ、心から信頼してたんだなぁ。
と、感動する前に志ん生落語を一度でも聴いてみて下さい。あまりに不謹慎すぎてドン引きするくらいのネタが大半です。
いや落語にはそういう歯に衣着せない、身も蓋もない赤裸々でプリミティブな価値観が未だ息づいていますから。今日的な倫理観だけで見ると大半がアウト、でもそのアウトの中にこそ人間の本性の一面が表れているとも言えて。線引きが難しいんですがね。
ところで志ん生、オハコの一つであった『柳田格之進』を高座にかけるに当たり、最後のサゲを工夫しました。前出『古典・新作 落語事典』に曰く、
「親が囲碁の争いをしたから、娘が娼妓(しょうぎ≒将棋)になった」
。
ヒデェ、言うに事欠いて・・。
○再び、「この世も捨てたもんじゃない、この人生は生きるに値する」
映画版はまだ分からないけど、落語『柳田格之進』の結末は因縁を吹っ切った潔い堪忍で締め括られる。
柳田格之進は怒りを込めた一刀を人ではなく碁盤に振り下ろし、盤の血溜まり梔子を形代に復讐の剣を納めた。ならぬ堪忍、するが堪忍。果たしてこの昔語りの忍耐を、現代人は心に宿すことができるだろうか?
今、日本となく海外となく、世界中のあらゆる土地で不寛容が広がっている。
怒りで振り上げた拳を、排除するために振り投げる言葉を、虐げるために振りかざした刃を、殺し尽くすために振り向ける銃口を砲塔を、決然と下ろし鞘に納めることができるだろうか?
◇『AERA』2024.5.20号
〖 対談 草彅剛 × 清原果耶 〗より
清原:
私は草彅さんが主演をされた映画「ミッドナイトスワン」が大好きで。まさか草彅さんの娘役として現場でご一緒できるとは想像もしていなかったので、毎日緊張していました。(草彅さんが)現場に入られると「父上がいらした、今日も頑張ろう」と。役柄のうえでも「父上のためなら腹を括ろう」と思っていました。
草彅:
清原さんはエネルギーを持っている方で、内側から湧き出る娘としての思いが伝わってきた。僕にとっても、格之進という人間にとっても、こんなに可愛い娘がいるから奮闘できた、というのもあると思う。格之進にとって大切なシーンでも、やはり清原さんの顔を思い出しながら演じていたから。
(引用終わり)
柳田格之進は、おそらく一人ではこの結末に辿り着けなかった。娘お絹の叱咤激励の支えがあり、不遇ながらも碁友に巡り会えた平穏な時期があり、そして武士の矜持と怨嗟と義理人情との間で悩みもがく葛藤の中に、思い出されたそれら人々との縁、温かい触れ合いの記憶があった。
憎しみの激情に駆られた者の心を踏みとどまらせるのは、人としての思いやりと仲間や家族との大切な思い出。
世界中に遍在する憎しみに染まった柳田格之進たちの傍らに、その良心となり得るお絹や碁友は居るだろうか? もし居ないなら、代わりに手を差し伸べ援助と和解を与えるような、底抜けにお節介な長兵衛となれないだろうか、世界中の人々が?
『文七元結』に出てくる人物はみな、自分よりも他人を先に思いやる。人のことなど心配している場合ではないくらい、暮らしに窮しているにもかかわらず。
山田洋次は言った、「人間は信じるに足るものだ、という思いを感じて」。志ん生の長兵衛が言う、「人の命ってのはそんなもんじゃねえ」。