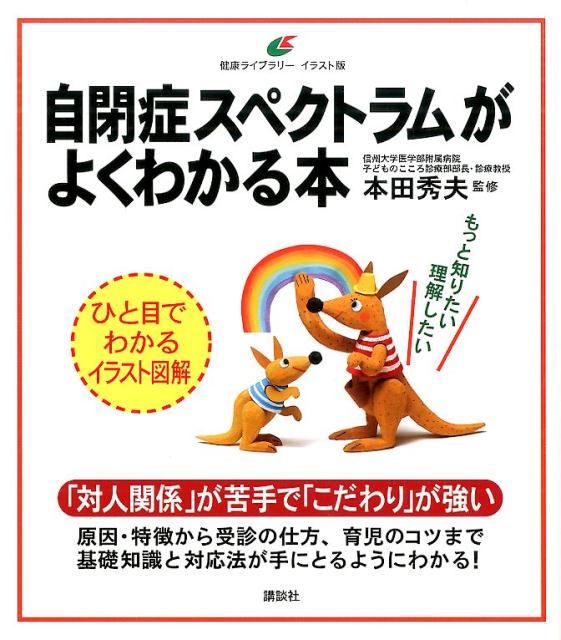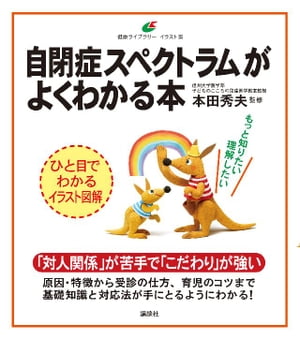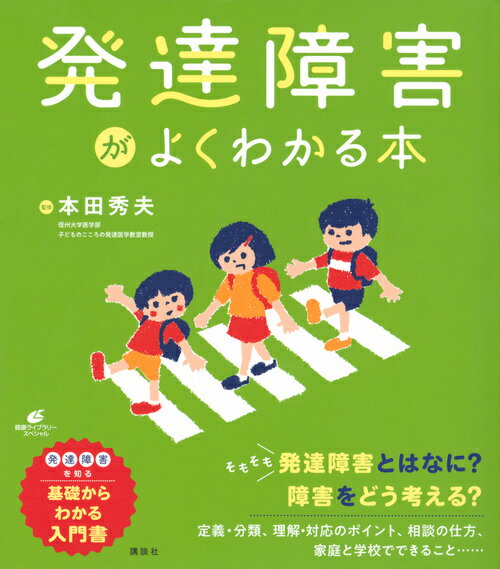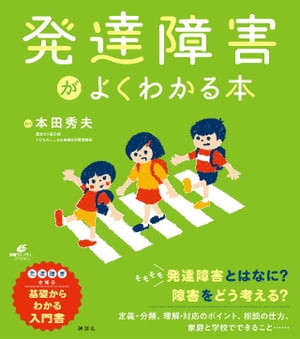「自閉症スペクトラムがよくわかる本」
(本田秀夫 監修)
監修者バックグラウンド
医学
先週紹介した
「発達障害がよくわかる本」と同じ
本田秀夫監修の本![]()
自閉症スペクトラムは
〝スペクトラム〟なので
発達障害と同様
ざっくりとした概念![]()
こちらも
はじめて調べようとするときに
まず広く満遍なく
正しい知識を得るるための1冊![]()
一般的に
専門家は自身の手法に
こだわりがちですが
この本は
「療育法は役に立つものならなんでもとり入れる」(p66)
とあるように
バランスの良い説明が
してあります![]()
この本の次には
それぞれの特性に基づいて
ASD、ADHD、LDなど
各論に進んだり
具体的な療育の手法を
調べるようにすると
良いと思います![]()
先週も説明した通り
まずは
医師が著しているものを
チョイスするのがおすすめです![]()
↓
↓
「自閉症スペクトラムがよくわかる本」(本田秀夫 監修)
もくじ
【まえがき】
【自閉症スペクトラムとは】 なぜ自閉症に「スペクトラム」がつくようになったのか
1 自閉症スペクトラムとはなにか
●ストーリー1 三歳児健診で息子が「発達が気になる」と言われた
【自閉症スペクトラムとは】一〇%の人にみられる特徴
【自閉症スペクトラムとは】特有の「発達スタイル」として考える
【自閉症スペクトラムとは】 アスペルガー症候群とはどう違うのか
【原因と経過】自閉症スペクトラムの原因はなにか
【原因と経過】 ストレスから、二次的な問題が起こりやすい
▼コラム「個性」と「障害」はどう違うのか
2「対人関係」と「こだわり」が二大特徴
●ストーリー2 以前から、愛情が伝わりにくい気がしていた
【特徴】対人関係を柔軟につくっていくことが難しい
▼「専門用語」解説コラム 折れ線現象、 エコラリア、 社会的参照、 共同注意
【特徴】自分のやり方やペースを本能的に優先する
▼「専門用語」解説コラム こだわり、常同行動、一番病
【特徴】視覚や聴覚、触覚などの機能に異常がある
【特徴】過去を覚えるのは得意、未来を想像するのは苦手
【特徴】育ち方によって、特性の現れ方は変化する
◆コラム 「社会的コミュニケーション障害」とは
3 気づいてから、診断を受けるまで
●ストーリー3 発達相談の窓口で、息子の様子をみてもらった
【受診】 早ければ一歳半健診で気づかれる
【受診】 子どもは小児科・児童精神科、大人は精神科へ
【診断】行動観察や面接、心理検査などを受ける
【診断】ほかの発達障害や睡眠の異常が併存しやすい
【診断】 うつや不安などの二次的な問題も確認する
◆コラム 保護者は子どもにいつ診断名を告知するか
4 各種機関で「支援」を受ける
●ストーリー4 支援を受けると、息子が変わってきた
【支援の基本】サポートを得て、二次的な問題を防ぐ
【支援の基本】支援で変わること、変わらないことがある
【支援1】医師や支援者に、発達の見通しを聞く
【支援2】 生活習慣や環境を調整し、暮らしやすくする
【支援3】 療育法は役に立つものならなんでもとり入れる
【支援4】 学校や職場、地域で支援制度を利用する
▼コラム 困ったときに利用できる相談機関・支援機関
5 生活面では二つのスキルを身につけたい
●ストーリー5 息子は困ったとき、人に相談できるようになった
【二つのスキル】 二つのスキルで得意を伸ばし、不得意を補う・
【二つのスキル】できることを着実におこなう 「自律スキル」
【二つのスキル】相談し、社会のルールを守る「ソーシャルスキル」
【スキルを身につける】 トップダウン式育児で、できることを優先
【スキルを身につける】 練習すること・休むことのバランスをとる
【幼少期のポイント1】 幼少期は保護的な環境で自信をつける
【幼少期のポイント2】 こだわりを「役立つこだわり」として残す
【幼少期のポイント3】 幼い頃から「合意」のとり方を練習する
▼「専門用語」解説コラム 構造化
【幼少期のポイント4】 人に報告・相談する習慣をつける
【思春期のポイント1】思春期以降は本人主体でチャレンジする
【思春期のポイント2】 進路はやや楽な道を選ぶのがベスト
【成人期のポイント】 学校と会社の違いを早くから意識する
◆コラム 当事者の活動拠点をつくる「ネスト・ジャパン」

![]() よろしくお願いします
よろしくお願いします![]()