さすがにこの方ほどともなると、
どれか一つを代表曲として
選んで紹介することが
難しいなとつくづく思った。
なんといっても歴代で最高の
売り上げを誇っている
女性アーティストなのである。
昨今のメディアの趨勢を鑑みれば、
この先その地位を
そう簡単に譲ることも
どうやらなさそうでもあるし。
ウルトラ・マドンナ~グレイテスト・ヒッツ(紙ジャケット仕様)/マドンナ
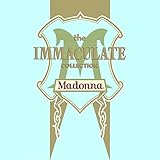
¥2,500
Amazon.co.jp
それでもなんだかんだいって、
この一枚がやはり
一番お手頃であろうことは
たぶん間違いはない。
デビューから数えて
7年目に発表された
キャリア初のベスト盤で、
全17曲も収録されているのに、
全米トップ10ヒットが数曲
選から漏れてしまっているという
実に途轍もない代物である。
この一点だけとってみても、
このマドンナという人が
あの当時いかに怪物みたいに
流行っていたかが
察せられるというものだろう。
結局いろいろと迷った末、
ピックアップは
このCrazy for Youに
させていただくことにした。
もちろん当然のように
全米トップに輝いているし、
やはりあの時代が産んだ
名バラードの一つだと思う。
なお同曲は、85年の映画、
『ヴィジョン・クエスト』への
提供曲だったという経緯から、
オリジナル・アルバムには
残念ながら収録されていない。
それもあって今回は
ベスト盤のジャケ写を掲げた次第。
ちなみにこの曲と
最後まで選を争ったのは
もちろん僕の中での
話でしかない訳だけれど、
まずは83年のデビュー・アルバム
MADONNA所収のBorderlineと
それから86年の
4thアルバムの
タイトル・トラックとなっていた
Like a Prayerだった。
本当はどちらも捨てがたい。
とりわけLike a Prayerは
おそらくある意味で、
このマドンナという人の
核となるような思想が
見事にポップ・チューンとして
昇華されている
重要なトラックだと思っている。
人生はミステリー
誰もが一人で
立ち向かわなければならない――
こんな真っ当で衒いのない
少し気恥ずかしいくらいの歌詞を、
下は十代やさらにその下から、
上は僕と同じかその上まで、
一緒に口ずさんでいる、
なんてようなことが
彼女のステージや他の場所では、
たぶんしばしば
起きてしまっている訳だから、
なんというか、ただすごい。
こういうのがだから、
ポップ・ミュージックの
力なんだろうと思うし、
やはりマドンナは今や
押しも押されぬ世界最高の
ポップ・スターの一人に
名前を連ねているのだと思う。
まあこのLike a Prayerについては
機会を改めて取り上げようとは
思ってこそいるのだけれど、
正直実は最近結構本編に
手こずることがしばしばで、
エクストラまではなかなか
手が回っていないのが現状である。
まあでも、いずれ必ず。
そして、さらにその次の
次点といっていいのか、
VogueとHolidayの二曲も
本当はかなり捨てがたかった。
あるいはマドンナの
ベスト・トラックは
やっぱりHolidayなのかとも
思うこともしばしばある。
聴けばやっぱりほぼ必ず、
今日も頑張ろうかなといった
気持ちにさせてもらえるし、
実際全編隙がない
完成度だなとも思っている。
だからまあ
この辺りのチョイスに
もし大きく
頷いていただける方ならば、
たぶん名古屋か、あるいは
京都辺りまでなら、
一緒に新幹線乗れそうな気がする。
いや、このネタしつこくて
そろそろ申し訳ないかなとも、
ちょっとだけ
思わないでもないのだけれど、
でも少ししたら、
後一回だけ蒸し返す予定でいる。
まあそれはどうでもいいのだが。
さて、このマドンナの
最初の大ヒットとなったのは
実は上に名前を出した
いずれのトラックでもなく、
デビュー・アルバムの
オープニングを飾っていた
Lucky Starなる一曲だった。
当時とにかく
それこそものすごい勢いで
同曲のビデオ・クリップを
目にしていた記憶がある。
もちろんネットはおろか
携帯電話もない時代で、
DVDやブルーレイなど
影も形も
存在しなかった頃である。
それでも週に三枠か四枠、
洋楽のビデオ・クリップを
流してくれる番組があって、
そのオン・エアでしか
目にすることが
なかったはずなのに、
なんだか飽きるほど目にした。
ほとんど白バックみたいな
セットもなければ
ロケをした訳でもないだろう
背景の前で、
男性ダンサー二人を従えて、
あのマドンナ・ルックとでも
いうべき黒の上下の衣装で、
延々と踊り続ける
マドンナの映像が
本当に繰り返し
流されていたのである。
だけどもうすでにその当時から
やっぱり本当は
Holidayがいいんだよね、とか
いや、Borderlineの方が
名曲だろうとか、
そんな話をすでに
していたようにも記憶している。
もっともそれもそのはずで、
このLucky Starは実は
そのデビュー・アルバムからの
なんと五枚目に当たる
シングル・カットだったのである。
そんな順番だったのに、
彼女にとって初の
全米トップ3入りを果たす
大ヒットとなったのだから、
掛け値なしの
ブレイク・スルーだったと
いっていいだろう。
今となってはむしろ
当時のワーナーのスタッフが
よくぞこれだけ粘り強く
このアルバムを
プロモーションしたものだと思う。
実際新人のデビュー作から
五枚のシングルを切るというのは
結構勇気というか、
相応の覚悟が必要な
作戦だったはずである。
まあ確かにこの時期、
次回予定の
シンディー・ローパーなる
シンガーもまた、
デビュー・アルバムから
同じく五枚の
シングル・ヒットを出すという
快挙を成し遂げてこそいるのだが、
彼女の場合は
リード・オフ・シングルが
とにかく売れに売れたという
実績がすでにあった。
翻ってマドンナには
そこまでの背景はなかったのに、
シングルを切る、つまり
プロモーションを
仕掛け続けられたということは、
会社の側に、このレコード、
あるいはこのアーティストは
どんなことをしてでも
絶対に売るんだといった
強固なコンセンサスがなければ
できなかったはずだと思う。
そしてその根拠というか、
原動力みたいなものは、
もちろん想像でしかないのだが、
これはたぶんマドンナ自身の
売れよう、ビッグになろうという
そういう野心では
なかったろうかと思うのである。
つけ加えておくならば、
このLucky Starみたいな
つまりはアルバムの冒頭に
持ってこられるような
強力なトラックを、
五枚目まで取っておけたという
その戦略が
相当すごいといえるだろう。
やはり同じ年のアルバム、
スプリングスティーンの
BORN IN THE U.S.A.を
ちょっとだけ思い出さないでもない。
この作品も当初は、
どうしてあのタイトル曲を
シングルにしないのか、
不思議に思いながら
眺めていたりもしたものである。
さて、話をマドンナに戻すと、
実際デビュー・シングルの
Everybodyの段階から
すでにマドンナは、
ダンス・チャートでの注目を
集めていたことは確かだった。
非常に覚えやすい名前だったことも
幸いしていたのかもしれない。
これが本名だというところが、
またなんとも
唖然としてしまう部分なのだが、
そしてさらに、
上でも触れたHolidayや
Borderlineといった佳曲が続いて、
人気と知名度とを
じわじわと上げていった。
普通はこの辺りでもう、
セカンド・アルバムを
発売してしまっても
たぶんおかしくはなかったと思う。
ところが最後の最後になって
このLucky Starが
ついにポップ・チャートでの
ブレイクを
果たしてしまったことにより、
あのナイル・ロジャーズの
プロデュースによるセカンド
LIKE A VIRGINが、
発売直後からすでに
手のつけられないような
大ヒットとなって、
瞬く間にこのマドンナは
スターダムを
上り詰めてしまったのである。
最初にあのアルバムを
聴いた時はやや複雑だった。
正直今でも作品としては、
ファーストの方が上だったと
そう思っていなくも
ないくらいである。
何よりも、リリクスというか
曲ごとのモチーフを
ここまで下世話にしてしまう
必要はないだろうと思った。
そもそもがタイトルからして
あからさまに扇情的である。
なかなかこの
Virginという単語は
ポップ・ソングでは
使いにくいとも思うのだが、
まあそれをあえてやるのが、
この時のマドンナ自身なり、
スタッフなりの戦略の
眼目だったのだろう。
しかもさらに続いて
シングルで登場したのは、
またずいぶんと
キャラクターの作り込まれた
Material Girlなる曲だった。
唯物主義礼賛とでも
いえばいいのか。
小金を貯めてる男の子たちが
あたしの大変な時を
助けてくれるものなのよって
そんなことをいっている訳だから
いわゆるラブ・ソングとは
まったく対局の位置にある
アプローチである。
それでもこの一枚が
あれほどまでに受けたのは、
やはりどこかで、
あの時代に潜んでいた
伏流水みたいな何かの傾向と、
絶妙にシンクロしていたから
なんだろうなあと
まあ今になってみれば
ついそんなふうにも考えて
しまったりもするのである。
とにかくこんな具合に
マドンナは以後も一貫して
何をするにも
ギリギリのところを突いてきた。
十代の妊娠問題に、それから、
のぞき部屋にしか
思えない場所を舞台にしたビデオ。
ステージでキリストさながらに
十字架にかけられて登場し
物議を醸し出したこともある。
こういう考察はもう
すっかり後出しの
謗りを免れ得ないなのだけれど、
でもたぶん、
売れようとか話題になろうとか、
そういうレベルの意図も
確かに皆無では
なかったのだろうが、
それ以上にたぶんこの人は
そういうものを
自分が表現しなければならない
そんな感じの切迫感に
どこかで常に
追い立てられ続けていたの
かもしれないなあ、と
そういうスタンスだからこそ、
これだけの長い時間
シーンに君臨することが
できていたのかなあ、と
なんだか近頃
そんなふうに感じてしまっている。
今回本テキストを起こすに当たり、
初めてちゃんと、あの
『イン・ベッド・ウィズ・マドンナ』と
それから06年の
『テル・ユー・ア・シークレット』を
両方見てみた。
どちらもいわば、
ツアー・ドキュメンタリーといった
ジャンルに入る種類の映像で、
もちろん演出も
多少入っているのだろうけれど、
本人そのものも
やっぱり根っこのところでは、
あのパブリック・イメージに
だいぶ近い感じの
キャラクターの持ち主
なのだろうなあ、とは感じた。
もう死語かもしれないけれど
はすっぱという言葉が、
本当に似つかわしい感じ。
品があるとはとてもいえない。
FuckとかMasturbateとか
カメラの前でも平気でいうし、
それどころかランチの席でも
周囲にノせられれば、
ドリンクの瓶を加えて、
とんでもない真似までしてみせる。
まあこういう人だろうとは
思っていなくもなかったのだが。
ところが意外だったというか、
ほとんど感心くらいまで
思わずしてしまったのは、
このマドンナ、今も昔も
ステージが始まる前に、
ダンサーと
バック・ミュージシャンとを
一同に集め、
ショウの成功を
神に祈っているのである。
ちょうど食前の祈りのように
全員がアーメンと和して終わる。
まさにあんな感じである。
――ちょっと不思議な気分になった。
敬虔という言葉は
まったく似合わないのに、
むしろ信念に近いような
信仰みたいなものを
感じざるを得なかったのである。
まあだからこそああいう
磔刑と茨の冠の再現という、
パフォーマンスにも
繋がっていったのかな、と
ちょっとだけそんなことも
考えてしまわなくもなかった。
こういうことを文字にして
書いてしまうと
どこからか怒られて
しまいそうではあるけれど、
レノンのキリスト発言もそうだが、
この時のマドンナの
バチカンとのトラブルも
それを神への冒涜だと、
判断を下しているのは実は
教会の僧侶、つまりは
人でしかないことは
たぶん間違いはないはずである。
僕なんかはだからむしろ、
本当に神様がいるのなら、
こういった程度のことで
冒涜されたとか腹を立てるような
そういう狭量な存在では
絶対にあってほしくないと思う。
だからつまり
こういった事例が暴き出して
しまっているのは実は、
その神なる存在の心情を
自分たちは忖度できるのだと、
どこかで信じている
人の側のある種の
傲慢なのではないかと思うのである。
そしてむしろそういう態度こそが
本当は糾弾されて然るべき
ものなのではないのか。
僕はだから、レノンやあるいは
このマドンナみたいな人の方が
ひょっとするとよほど
神という存在との距離が近い
そういう場所に
手が届いているのかも
しれないなと、時に本気で
考えてしまったりもするのである。
そしてマドンナは
実は一貫して
人というものが本質的には
否応もなく猥雑に
作られてしまっていることを
彼女なりのやり方で世に暴く、
そういう役目を自認して、
それを貫いてきたのかな、と
まあそんなことを
とりわけ今回は
つらつらと考えてしまった。
いや、まあそんな
大したことを
いいたい訳ではないんだけれどね。
僕自身、このマドンナの
レコードを聴きながら、
こんなことに
思いを巡らせる日が来ようとは、
あの頃はちっとも
思ってなどいなかった。
なんか本当にすごい人に
なっちゃったのかもしれない。
カバラに惹かれてイスラエルまで
行っちゃう人なんて、
たぶんなかなかいないだろうしね。
さて、振り返れば今回は
とりわけ後半になって
当初予定していた内容より
ずいぶんと堅苦しい話に
なってしまいもしたのだけれど、
だから僕自身としては
この方に関してはもう
ことの善し悪しや
賛否などはすっかり通り越し、
自分の時代の巨大なアイコンとして
なくてはならない存在だというのが、
たぶん今の認識である。
新譜が出たり、あるいは
ニュースなりが入ってくれば
必ず注意を向けると思うし、
同い年のMJとプリンスとが、
なんだか立て続けに
この世を去ってしまった
今となっては
せめて彼女だけにはずっと
シーンに君臨し続けて
いてほしいな、と
やっぱりどこかで思っている。
ダンス・パフォーマンスが
もう難しくなったのなら、
それこそ今回のCrazy for Youや
Borderline、あるいは
This Used Be My Playground
辺りのバラードだけで、
セット・リストを組んだ、
アンプラグドみたいな編成での
ステージで全然かまわないと思うし、
それで皆十分に
盛り上がると思うんだけど、
いかがでしょう。
では最後に締めのトリビア。
でも今回は本編の続き
みたいなものかもしれない。
03年だからもうすでに
十三年も昔の出来事に
なってしまう訳なのだが、
American Lifeという曲の
ビデオがまた
いかにもこのマドンナらしく
全米各局で放送禁止の
憂き目に遭っていたりする。
それこそレノンのImagineが
放送禁止になっていた時期である。
僕もこれ、今回初めて
ネットで探してちゃんと見てみた。
――いや、これはすごいわ。
もちろん設定の上での
話でしかないのだけれど、
このクリップの舞台は
いわば本物の軍人たちによる
ミリタリー・ルックの
ファッション・ショウである。
そこへマドンナが
脱走兵みたいな感じで、
四人のバック・ダンサーを従え、
車で乱入してくるというのが、
大体の大まかな構成である。
実際の戦闘機による爆撃や、
あるいは例のキノコ雲の映像が、
随所でコラージュされていたり、
あるいは明らかに
アラブ系とわかる子供たちが
ほとんど襤褸のような衣装で、
軍人たちと同じ
ステージに上がったりと、
とにかくやりたい放題なのだが、
何が嫌かって、
最初はなんだかシラケた感じで
ステージを眺めていた
プレスを中心とした観客たちが、
マドンナらの登場によって、
一気に戦場の様相を
呈してしまった壇上の光景に、
あからさまに
興奮していくところなのである。
実際爆発で、兵士の手足が
吹っ飛んでしまったりし始めると、
観衆はほとんど熱狂してしまう。
いや本当、これは確かに
いろんな意味で
流せなかったんだろうなあ。
正直この映像を見て
僕自身もまた
毎日のように目にしている
雑多なニュース映像に対し、
はたしてこういう気持ちを
微塵も抱いていないかどうか、
ついつい自問してしまった。
しかもこのビデオ、
オリジナルのヴァージョンでは、
最後の最後に
マドンナが投げた手榴弾が
もちろんそっくりさんな訳だが
当時のブッシュ大統領の手に
すぽりと収まって、
するとそれが実はライターで、
この偽ブッシュが
悠然と煙草に火をつけるという
ご丁寧なオチまで
つけられているのである。
同クリップの公開の
ほぼ直後に
あの湾岸戦争が事実開戦して、
この映像はかくのごとき次第で、
ほぼお蔵入りとなっている模様。
さすがにマドンナ自身も
まさか実際の開戦までは
予期していなかったらしく、
このビデオのアイディアや撮影に、
今まで相当の時間を使ったのに、と
いった内容のコメントを
どこかで発してもいるようである。
ちなみにこの曲に関しては
マドンナが歌っているだけの
シンプルなビデオが
新たに作りなおされたそうなのだが、
しかしながらこの映像は
どのヴァージョンも今に至るまで
商品化まではされていない。
それもやむなしだよなとは思う。
でもそういうものまで、
今の時代は今回の僕のように
見ようと思えば簡単に
見ることができてしまう訳なのだが、
その是非はともかくとして
いずれにせよだから
結局何がいいたいかというと、
こういったいわば、
日常の陰に身を潜め、
僕らが普段は目を逸らし、
やり過ごしているような違和感を
五分程度の時間で
暴いてしまえるという
その事実そのものに改めて、
なんというかこの人の
ポップ・スターの領域すら
たぶん超えてしまった存在感を
今さらながらまざまざと
感じさせられてしまうのである。
いやでも、なんか今回は
テキスト全体が
なんとなく支離滅裂になって
大変すいませんでした。
前半と後半で分裂してるし、
このマドンナという人を
上手く紹介できた気が
正直まるでしておりません。
いずれこの方については
やはり機会を改めて
取り上げることにしようと思います。