アメリカン・ニュー・ウェイヴの
押しも押されぬ代表格だろうと
まあ僕が個人的に
勝手に見做しているバンドを
二つばかり続ける予定である。
しかしもう今となっては
30年以上も前の
「ニュー」な訳だから、
その辺りは適当に
眉に唾つけながら
お読みいただければと思います。
とにかくまずはこちらから。
カーズなるバンドである。
ハートビート・シティ/カーズ
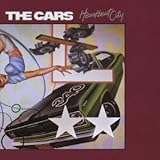
¥1,419
Amazon.co.jp
しかし改めてあの
80年代の前半から
中盤にかけての一時期には
なんと素敵な
力の入ったアルバムたちが
続々とシーンに
登場してきていたことだろう。
やはりある意味でそれは
LPのA面B面という
一つの確固とした、
しかも同時に一時代を
演出してきたフォーマットの、
ある種のスワン・ソングの
ようなものだったの
かもしれないなあと、
もちろん今だからこそ
いえることではあるのだけれど、
この企画を延々とやりながら、
ついそんなことを
我知らず考えてしまって
いるような場面が増えている。
もちろん僕自身が
当時ハイ・ティーンという
まあこういういい方は
正直あまり好きではないが、
いわば感受性なるものが
最も鋭敏だったといえる、
そういった時期に、
しかもリアル・タイムで
これらの作品群を
通過してきたという事実に、
大きくどころではなく、
印象を左右されていることも
また間違いなく本当だろう。
三つ子の魂
なんとやらではないけれど、
十代の中盤から後半にかけて
出会ってきた諸々というのは
生涯にわたって思いの外
深く影響を残すものらしい。
だからひょっとすると自分は、
還暦なんて過ぎてもなお、
DDやらヴァン・ヘイレンやらを
部屋の中でずっと
流しているのだろうなあ、と
時々どころではなく考える。
たぶんきっと
このままなんだろうなあ。
十年なんて実は結構
あっという間に過ぎて行くし、
嗜好が変わる気配も
さらさらないから、
たぶん2026年辺りになっても
こんな具合に
当時の音楽を聴きながら
延々とタイプを
打っているんだと思う。
むしろそうできれば
きっと満足なのだろうし。
さて、どうやらそろそろ
筆も十分暖まってきたようで。
そういう訳でカーズのこの
HEATBEAT CITYなる一枚もまた
そういう輝きに
満ちあふれていた一枚だった。
このカーズなるバンドは、
リック・オケイセックと、
ベンジャミン・オールという
二人のヴォーカリストを
バンド内に擁し、
曲のタイプによって、
リード・シンガーを
使い分けるという、
どこかビートルズを
思わせないでもない
ある種変則的な
スタイルを採用していた。
もっともビートルズと
はっきりと異なっているのは、
ソングライティングを
主に手がけた方が
その曲を歌っていたと
いうようなことは全然なくて
曲を書く方はもっぱら、
このオケイセックなる方が
ほぼ一人で
受け持っていた模様である。
でもこのヴォーカルの
役割分担も
カタログを聴いていると納得がいく。
というのも、この
オケイセックという人の唱法が、
相当どころではなく
独特なのである。
コミカルぎりぎりといっていい。
ラップという訳では
全然ないのに
歌っているという感じが
あまりしてこない。
似ているタイプの
すぐには浮かんで来ない
シンガーだといってよい。
無理矢理にでも挙げるとすれば
エコバニ(♯43他)の
イアン・マッカロク辺りが
一番近いかもしれない。
あそこまでの壊れ方を
装うことはほぼないのだが、
歌い上げるという感じには
どうしてもなってこない。
どこか喋りの延長にあるような
スタイルなのである。
実際オケイセック自身
本当にいい声が必要な曲は、
オールに任せていたという主旨の
発言をしてもいるようでもある。
さて、彼らのデビューは
78年にまで遡る。
結成はボストンで、
五人がそれぞれ過去に
レコーディングの経験もあり、
さらには
メンバーのうちの二人が
あのバークリー音楽院の
出身者だという、
実は存外にしっかりとした
バック・グラウンドを有して、
シーンに登場してきている。
もっともオールと
オケイセックの二人は、
それよりもよほど以前からの
知己だった模様で、
故郷オハイオで
たぶんまだ十代のうちに
出会っていた彼らは、
意気投合して
まずはデュオのような形で
音楽を始めていたらしいから、
これをカーズの原型とみるのが、
たぶん正しいのだと思う。
そして音楽を続けていくために
二人は一緒にはるばると
ボストンまで出てきて、
そこでライヴハウスへの出演や、
前述のように複数のバンドでの
レコーディングの経験などを
重ねて行くうち、
のちにこのカーズの
不動のラインナップとなる
ほかの三人と徐々に
繋がっていったのだそうである。
時代は70年代後半、
まさにパンク・ブームの
真っ盛りの時期だった。
スクィーズ(♯69)の時にも
似たような愚痴を少しだけ
こぼしてはいるのだけれど、
なんだかこの時期、
目新しいものは全部、
パンクという言葉で
くくられていたような感じもあって、
このカーズもだから、
たぶんそういった脈絡から、
イギリスやドイツでの
プロモーションなども
比較的早い時期に
経験している模様である。
こと音楽に関していえば
何故だか斬新なものには
欧州とりわけ英国のリスナーが、
まず反応してくるような気がする。
ちなみにこのカーズの
デビューに関しては、
是非とも紹介しておきたい、
興味深い逸話があったりする。
五人での最初のデモ・テープを
数曲作成し終えた後、
オケイセックは当時の知人で、
ボストンのラジオ局の
ディレクターだった女性に
このコピーを一部
渡したのだそうである。
そしてこの彼女が、
自分の担当する番組で
彼らの曲を流したところ、
局にリクエストが殺到し、
ついにはこの時の一曲、
Just What I Neededが
同局のプレイリストの上位に
ランクされるまでに
なったのだということである。
この実績があったが故に
カーズはエレクトラとの契約を
比較的スムーズに
獲得できたということらしい。
なんだかちょっと
懐かしいというか、
羨ましくなるくらいの、
古き良きラジオ・デイズと
でもいった感じで、
僕はこのエピソードが
すごく好きだったりする。
いずれにせよ、彼らは実際、
デビュー作からしてもう
かなり突出していたと
いっていいのではないかと思う。
少なくともこれより以前に
アメリカから登場してきた
種類の音とは
まるで違っていたことは
たぶん間違いがないだろう。
初期のカタログは後追いでしか
聴いていない僕でさえ
そんなふうに思うのだから、
当時の衝撃は
相当なものだったと思う。
実際独特なサウンドなのである。
オケイセックの
奇妙なヴォーカルと
競うようにして
前面に出てきているのは、
明らかなシンセサイザーの
結構派手な音色だし、
ドラムにも多少の加工が
施してあることは
たぶん間違いがないのだが、
テクノポップという言葉は
ちっとも似合って響かない。
かといってロックやあるいは
パンクという用語で
形容してしまうことは
多少どころでなく憚られる。
基本はポップなのだとしか
たぶん表現しようがない。
そのうえ、最初から彼らは
実にいろんなことを試みている。
ハンドクラップを
イントロに大きく導入した
トラックがあるかと思えば、
思いもよらないような場所に
大胆な変拍子が使われていたりする。
ギターはギターで、
ロカビリーのニュアンスを
どこかにとどめていたりして、
なんともだから、
ジャンル分けなるものを
それこそ真っ向から
拒んでくる種類の音楽を
一貫して作り出しているのである。
ちょっと無理矢理にいってしまえば、
アメリカから登場したサウンドで
一番80年代っぽかったのだと思う。
しかもだから、ブリティッシュ・
インヴェイジョンという括りの中で
アメリカのシーンに
当時続々と紹介されてきた
あちらのバンド群と
唯一拮抗できた、
国産のバンドが
このカーズだったのでは
なかったろうかと思うのである。
音数が多くて、
適度にポップで
似ているものがあまりない。
だから僕は今でも
Tonight She Comesや
You are the Girlなどの
彼らの後期の
ポップ・チューンを聴くたびに、
結局こういう手触りは
カーズからしか
出てこなかったよなあと、
そんな思いをまあ逐一
新たにしているという次第である。
さて、ではそろそろアルバム
HERTBEAT CITYの話に行こう。
84年発表の同作は
彼らの五枚目のアルバムで、
僕が最初にリアル・タイムで
このカーズ・サウンドを
経験することになった一枚である。
ただただもう、圧倒的だった。
わかる人にはわかるであろう
あのハエのビデオで有名な
You Might Thinkを筆頭に、
オケイセックが
キリストさながらに
水の上を歩いて見せる映像を、
タイトル通りに
実現してしまったMagic、
さらにはあの、
アンディ・ウォーホルが
何故だか登場してきた
Hello Againと、
まるでMTV時代の
到来を祝う凱歌のような
様々なアイディアに富んだ
ビデオ・クリップたちとともに
カットされたシングルは、
次々と大ヒットとなっていた。
やはりある種、
エポック・メイキングな
一枚だったといっていい。
このアルバムに限らず、
カーズの場合、
五人のコーラス・ワークが
時に曲に不似合いなほど美しい。
聞けばそれもそのはずで
この前作まで彼らの
プロデュースを手がけていた
R.T.ベイカーなる方は、
あのクィーン(♯33)の
Bohemian Rhapsodyを
手がけたまさに
その人だったのだそうで。
いや、まったく納得がいった。
実は本作からは
プロデューサーが
交代してもいるのだが、
それでもやはりコーラスは
かなりの時間をかけて
録っていたのだそうで、
この特徴は上でちらりと
曲名だけ出しておいた
Tonight She Comesや
You are the Girlといった、
本作以降のトラックでも
十分過ぎるほど健在である。
そしてそんな名盤の白眉が
今回表題にした
Driveだったといっていい。
個人的には、来月には
ここにも登場させる予定でいる
シンディ・ローパーの
Time After Timeと双璧を為す、
80年代アメリカが生んだ、
珠玉のバラード・トラックだろう
くらいにまで考えている。
この曲、どうして出てきたのか
不思議なくらいの出来である。
カーズっぽい
ある種の素っ頓狂さが
すっかり抜けていて、
テンポもひどくゆっくりで
しみじみ心にしみてくる。
もちろんヴォーカルは、
オールの方が取っている。
それでも
白玉のシンセサイザーと
溶け合うようなコーラスが、
やはりカーズならではの
サウンドになっているのである。
ちなみに同曲は85年に
最高位二位を記録し、
バンド最大のヒットとなっている。
Driveのリリクスのボディは基本
次々と繰り出される
疑問文のみで構成されている。
オールのいつもよりどこか
淡々としたヴォーカルが、
もう手遅れなんだと
いずれ君に伝えるのは
いったい誰なんだろう、とか、
君が叫ぶ時、その傍らで
耳を塞いでいるのは誰だろう、とか、
とにかくそういう
同じ構文のセンテンスだけを、
執拗なまでに繰り返していくのである
ちなみにタイトルのDriveは
今夜君を家まで送るのは
いったい誰なんだろうという、
キモの一節から
採用されている。
だからこの歌には、
別れてしまった恋人への
断ち切れない思いが
綴られているのだと思う。
そしてただ一カ所、
メロディーラインが
変わってくるところにだけ、
このストーリーの話者が
ほんの少しだけ顔を出す。
間違っていることなんて何もない
そう思いながら
進み続けていくことなんて
たぶんできないのさ――
正直この一節が
胸に突き刺さってくる場面は
この年になってもしばしばある。
しかもさらにこのビデオが実は、
You Might Thinkにも増して、
傑作だったりするのである。
ヴォーカルがオールなので、
最初は彼のシーンから
始まってこそいるのだけれど、
この映像には、
曲の内容そのままに
ヒロインが設定されている。
この彼女の演技がすごいのである。
オーヴァーラップを駆使しながら
同じ場所で表情を変えていく
つまり笑っているうちに泣き出したり、
あるいは呆然としてしまったりする
この方のそういう、
いわば音声のない演技が、
最初に目にした時から
強烈に印象に残ったものである。
――なんだったんだろうなあ、
シンプルな故の強力さみたいな
手応えを感じていたのかもしれない。
ちなみにバンドのメンバーが、
最後の方で、
マネキンになって登場してくるのも、
気が利いていて
しかも不思議に、
曲の雰囲気と調和していて、
やはりいまだに鮮明に
記憶に残っている
映像の一つとなっている。
なお、この時のモデルは、
やがて数年後に、
リックの奥さんとなったのだそうで。
経緯は複雑なので割愛するけれど、
いや、それだけの魅力は
なるほどあったような気がする。
さて、しかしながらカーズは
88年にDOOR TO DOORなる
6枚目のアルバムを発表した後、
惜しくも解散してしまう。
もうバンドが最早
機能していないことが
ただ報告されただけの、
淋しいというか、
カーズらしい解散ぶりだった。
それから12年後の00年には
ベンジャミン・オールが、
膵臓癌によって
52歳の若さで世を去ってしまう。
彼が自分の口で解散について
何らかのコメントを残すことは
ついになかったようである。
一方のリックの方は
この出来事を経てもなお
再結成には否定的だった。
05年にはキーボードのエリオットと、
ギターのグレッグを中心にして、
ニュー・カーズという形で
ある種の再結成が
実は為されてもいるのだが、
リックはやはり
ここにも参加してはいない。
だからこの時ヴォーカルとして
ラインナップに迎えられたのは、
たぶん名前を知っている方も
少なくないとは思われるけれど、
なんとあの
トッド・ラングレンその人
だったりするのである。
嘘のようだが本当の話である。
結局このニュー・カーズは
幾つかの新曲を含む
ライヴ作品一枚だけで
解消してしまったらしいのだが、
この一枚、実は結構貴重かもしれない。
なんといっても
トッドのヴォーカルで
それこそ今回のDriveや
You Might Thinkのみならず、
カーズの代表曲の
ほとんどが聴けるし、
一方で、カーズ・サウンドの
バッキングによる
名曲I Saw the Lightも
収録されていたりするのである。
しかも不思議というかなんといおうか、
オールがヴォーカルだった曲でも
あるいはオケイセックのそれでも
このトッド・ラングレン、
オリジナルに比べても、
さほどの違和感なく
歌いこなしているのである。
いや、これは素直に敬服しました。
さて、その後さらに年月が過ぎ、
ようやく去る12年になって、
オールを除いたオリジナルの
ラインナップでの再結成が
ついに実現してはいる。
同年には実に
24年ぶりとなるアルバム
MOVE LIKE THISなる一枚が
発表されてもいるのである。
このちらについては
現在のところ、
未聴のままでいるのだけれど、
そのうち入手して
ちゃんと聴こうと思っている。
最後に念のためだが
ベンジャミンの
ファミリー・ネームである
Orrのカナ表記は、
現在はオアの方が
どうやら通りがよさそうなのだが、
昔から慣れ親しんでいた
せいもあったものだから、
本稿ではあえて
オールのままにしたことを
蛇足ながら付記しておく。
では締めの小ネタ。
オールの死後、オケイセックは
08年のソロ・アルバムで、
彼への追悼のため、
Silverなる曲を発表している。
トラックの手触りそのものは
だいぶ違っているのだが、
リリクスの構成が少しだけ、
今回のこのDriveを
思い起こさせるような
構造になっている模様である。