まずは一番南のデンマークから。
アクアというバンドである。
カートゥーン・ヒーローズ~ベスト・オブ・AQUA/AQUA
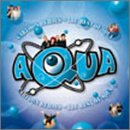
¥2,621
Amazon.co.jp
男女のツイン・ヴォーカルを擁した
ポップ・バンドというスタイル。
二人の掛け合いめいた形を活かす
ソングライティングが特徴的で、
バブルガム・ポップなどとも
形容される場面もあるようである。
この呼称、でもたぶん、
ほどよく彼らの音楽を表している。
重々しさとは一切無縁というか、
ある種おちゃらけた、
華やかで浮き足立ってて
同時に吹けば簡単に飛ぶというか、
膨らんだかと思うと
一気にはじけて
後にはほとんど何も残らない。
いってみればそんな感じである。
ただただその場が
楽しければそれでいい。
もちろんそうはいっても、
自暴自棄みたいな感じとは
まるで違っているのだけれど。
これ一応、誉めているつもりです。
さて、で、この手のパイオニアは
結局はアメリカのB-52’sだったと、
僕は勝手に決め込んでいるのだが、
このアクアはもっと
なんというか、全体を
カリカチュアライズして
登場してきた模様である。
本家B-52’s以上に、
コミックバンドみたいに見える。
同バンドについては、
アメリカ行ったら割と早めに、
取り上げるつもりではあるのだが、
このB-52’sもやはり、
男性ヴォーカルは、
終始どことなく
コミカルな唱法に徹底して、
一方で女性のヴォーカリストの方は、
キレるギリギリみたいな感じの、
ある種、戸川純的とでもいおうか、
あるいは川本真琴のような、
自ずと甲高さが
強調されてくる種類の声の持ち主で、
この一見相反するよう見えながら、
実は根底で同じものを
有している両者が、
一つのトラックの中で
巧妙に絡み合ってくるところが、
一番の魅力だと
昔からそんな具合に
思っているのだけれど、
このアクアは、だから、
まったくその延長線上にあって、
しかもそれを、他の追随を
許さないような場所まで
突き詰めてしまったところが、
一番の特徴であり、
魅力なのではないかと思っている。
そういうのがやはり、
耳に入った途端に引っかかってきて、
90年代デビューのバンドながら
手を伸ばしていたりする訳である。
とりわけこの男性のパート、
ギリギリどころでなく
徹底してコミカルである。
歌い方もそうだが、
歌詞そのものもほとんどアウト。
たとえば彼らの出世作に
Barbie Girlというトラックがある。
もちろんこれ、
あのバービー人形のことである。
歌の冒頭から、主人公は、
あたかも現実のように
バービーと会話し、
彼女をデートへと誘う。
だからまあ、あえて堅苦しくいえば、
トラック全体が、
虚構とのある種の係わり方を、
揶揄しようとしているようにも
聴こえてくるという訳である。
たとえば曲の途中で、
女声の方のパートが
こんな感じに切り込んでくる。
You can brush my hair,
Undress me everywhere――
敢えて訳出はしないが、
ここまではっきりといってしまえば
もう大したものであろう。
しかもビデオでは、
レネの左腕結局とれちゃうし。
さらに最後のトドメは
Life is your creationの一節である。
なんだろうなあ、この、
メタフィクショナルなアプローチ。
まあこういうのは
正直好みでもあるし、
ほとんど感心して
しまうくらいな気分になる。
本当、素材の選び方からして、
アイディア勝ちだと思う。
しかもこの曲のラスト、
僕らはこれから始まるんだよ、
みたいなラインで終わっていて、
なんだろう、
どこにも救いの見つからない
ある種のループ落ちみたいな
手応えを残して終わるのである。
だからまあ、たぶんこの男の子
(というには声がやや野太すぎるが)
ずっと自分の作り出して
夢の中に居続けて、
でもそれで幸せなんだろうなあ、
なんてことを
ついつい考えてしまうのである。
本当不思議だなあ、と
思うのだけれど、この人たち、
自分たちがなんというか、
音楽をやっているのみならず、
ある種虚構内存在みたいなものとして
存在しているという部分に関し、
はなから覚悟ができているというか
すっかりひらきなおっていて、
そういう演出を徹底してくる。
でも改めて考えてみれば、
エンターティナーというのは
あるいはそのくらいで
あるべきなのかもしれないと
思ったりもしてしまう。
ところでちなみにこのBarbie Girl、
一時バービー人形のメーカーから、
訴訟を起こされもしたそうで。
で、所属会社のMCA側も
負けじとこのマテルなる会社を
逆に訴えたりもしたらしいのだが、
最終的には裁判所から、
両社とも頭を冷やすべきでしょう、
くらいなことをいわれて、
結局すべての訴えが
取り下げられたそうである。
いや、今となれば
微笑ましい逸話だなとでも
いうしかないかとも思うけれど。
さて、そういういわば、
音楽に巧みに乗りながら
虚実の境目みたいな場所を
やじろべえのように
危うく渡っていくとでもいうような
このバンドのアプローチが
極限の場所まで行き着いたのが、
このCartoon Heroesという
トラックなのではないかと
個人的にはそんなふうに
捕らえていたりする。
もちろんCartoonというのは
ある種包括的な位置にもある
単語だとも思うし、
最初に引っかかったのが
この曲だという理由もあるが。
いやしかしこの曲、
いつ聴いても
本当に不思議な手触りである。
ハッピーなサウンドであることは
もちろん間違いはないのだけれど、
僕はこの曲を聴くたびに
なんだかちょっとだけ
切ないような気分に
なってしまったりするのである。
その手応えの正体は
正直よくわからないのだが、
まるでフィクションの内側にいる、
そこにしかいられない存在が上げる、
明るい悲鳴みたいなものを
真っ向からぶつけられている、
そんな気がして
しまうことがあるのである。
まあ僕自身、そういう存在を
作り上げる側だといえばそうなので、
ある種のそういった
負い目に似た感情が、
共振してしまうのかもしれないが。
いや、でもたぶんこの曲は、
そういう難しいことを
考えて聴いてはいけない。
よくやるなあ、と
ビデオを見ながら笑うのが
一番ただしい聴き方であろう。
ちなみにCartoon Heroesの映像は、
ファンタスティック・フォーの
パロディになっている。
それから僕自身も子供の頃
トムとジェリーや
ハンナ・バーバラの作品群は
よく見ていたクチなので
この曲で繰り返し登場してくる
ロードランナーの
ブレーキ音みたいなSEは
ものすごく大好きである。
さらについでに挙げておくと、
Dr. Jonesはだから、
インディ・ジョーンズを
下敷きにして作っているし、
Bumble Beesのビデオでは、
全編ではないけれど、
メンバーがバグズ・ライフみたいな
3Dアニメのキャラになって
登場していたりする。
まったく、実に徹底している。
ぼか、Good Morning Sunshineと
Turn Back the Time辺りも
結構好きだったりする。
さて、そういえば一時期ほど
名前も聞かないようだけれど
最近はどうしているのかな、と
思って調べてみたら、
数年前にBack to the 80’sなる
新曲を発表しているのだそうで、
早速探してチェックしてみた。
いや、これも本当にひどいわ。
無論いい意味でなんだけどさ。
だっていきなり
ロナルド・レーガンの時代に戻ろうよ、
みたいなラインから始まって、
アイアン・メイデンとか
バナナラマとか
マイアミ・ヴァイスとか並べて、
ヒューイ・ルイスが
本当にニューズだった頃、
マイケル・ジャクソンの
肌がまだ黒かった頃、
なんてことを、
平気で歌ってる訳ですよ。
もうこれだけで十分なのに、
極めつけはこちら。
トゥイステッド・シスターが
MTVに映ってた頃、だってさ。
しかも相当大事なことらしく、
二回どころでなく
かなり繰り返して歌ってるいるし。
いや、トゥイステッド・シスターを
知らない人には
さっぱりだろうとは思いはするけど。
とにかく僕は、夜中に一人で
相当大ウケしてしまいました。
確かに今、あの人たち
テレビに映すのは
怖いかもしれないよなあ、
もうここまでやってくれると
ただただ清々しいばかりです。
なんかでも、
バンドがバンドだけに、
今回はネタが次々と見つかってくる。
で、本当にこの曲、
大丈夫だったのかななどと、
思ってさらに調べてみると、
案の定、上で引いた
マイケル・ジャクソンの部分は、
この通りになっているのは
本国デンマークと、
フランス盤のシングルだけだそうで。
それというのも、
同曲のリリースの直後
マイケル急死の一報が
飛び込んできたらしく、
メンバーの強い意向で、
間に合うものでは、
ここを変更したということらしい。
いや、本当綱渡りだなあ、この人たち。
それでもこういう姿勢には
やっぱり敬意を表したくなる。
それにしても、まあ本当、
80’sというのは
たぶんいい時代だったんですよ。
もちろん個人的な感慨ではありますが。
さて、では締めのトリビアは
このBack to the 80’sに登場した
トゥイステッド・シスターなる
バンドのナンバーから。
We’re not Gonna Take itというのが、
同バンドの
最大のヒット曲なのだけれど、
12年のアメリカ映画、
『ロック・オブ・ザ・エイジズ』で、
キャサリン・ゼタ=ジョーンズと
それからほかのキャストとが
同曲を歌っているのを聴くことができる。
もっとも、作劇の展開上、
スターシップの87年のヒット曲、
We Built This Cityとの
変則的なメドレーではあるのだが。
ちなみにこの
『ロック・オブ・ザ・エイジズ』は、
そもそもはデフ・レパードの
アルバム・タイトルで、
ブロードウェイでかかっていた
いわゆる
ジューク・ボックス・
ミュージカルだったものを、
映画化した作品で、
デフ・レパードのほか、
ボン・ジョヴィやフォリナーなど
いかにもあの頃の
アメリカン・ロックといった趣の曲が、
次から次へと登場してくる。
いや、デフ・レパードは
イギリスなんだけれどもね。
ティファニーなんかも
使われていた気がする。
ちなみに
デフ・レパードのトラックは
トム・クルーズの歌唱で
披露されていたりもするので、
あの辺りの時代の
好きな方には楽しめると思う。
いや、もう本当に
今回は前回とうって変わって
小ネタがどんどん続く。
さてこのWe’re not Gonna~の
トゥイステッド・シスターによるビデオ、
内容に一部、某所から
クレームがついたことは
どうやら間違いないようである。
実際放送禁止みたいな
憂き目にまで
遭っているのかどうかまでは、
さすがにウラが取れなかったが。
いや、確かにヴォーカリストの
見た目は異様だけれど、
ビデオの筋書き自体は
そんなに目くじらを立てるほど
大したものではないと思う。
でも、なるほどさすがアクア、
ちゃんと突くべきところ
突いてきている訳である。
まだ終わらない。
しかも、しかもなのだが、
いろいろ眺めてみたところ、
今現在この曲、
あのドナルド・トランプ氏が
選挙運動の
キャンペーン・ソングとして、
使用しているらしい。
――いや、確かにそれっぽいけど。
それにしてもまあ、よもやまさか
トゥイステッド・シスターの曲で、
選挙戦を戦う
大統領候補が出てこようとは。
でもあの人は、個人的には
大統領としては
さすがに受け入れ難いと思うけど。
まあでも、ここまでくると、
彼のいっている一連、実のところは、
選挙戦略のための
ポーズかもしれないなあ、とも
ちょっとだけ穿ってしまいます。
いや、だって、
トゥイステッド・シスターだよ。
どんなギャグ?って突っ込みたいけど。
いやもちろん、
同バンドには
何の恨みもないのだが。
でも少なくとも、
もしこのまま当選しちゃったら、
国家元首のテーマ曲が
これってことになる訳でしょ?
ジョークとしては
ものすごくよくできているとは
ついつい思ってしまいもしますが、
まあ、そういうレベルの
組み合わせというか、
チョイスだと思うんだけどなあ。
いや、バンド知らない人には
全然わからなくて
今回は大変申し訳ないのだけれど、
でも画像どこかで見つけてもらえれば
いいたいことも
十分納得してもらえるかと思います。
今回はさらについでに、
もう一つだけ
リサーチの中で拾ってしまった
余計なネタも
最後に披露しておくことにする。
やっぱりWe’re not Gonna~
がらみなのだが、
同曲を書いた同バンドの
リード・シンガー、
D.シュナイダーによれば、
このWe’re not Gonna Take it、
実はそもそもの着想の段階で
讃美歌第111番、
通称『神の御子は今宵しも』を、
参照しているのだそうである。
クリスマスによくかかるやつ。
かみーの みこーは
こよぉいしもぉってやつですね。
なるほどいわれてみれば、
サビのラインの頭は、
ほんのちょっとだけだけれど、
確かに似ていなくもない。
――うーん。
でも正直、これもまたどうにも
受け容れ難い気もするが。
それにしても、なるほど、
今回のトランプが
あれほどアメリカの白人層の
心をつかむ訳である。
当然皆、根っこのところでは
クリスチャンなのだろうから、
理由こそはっきりと
わからないままに、
どこかであの気分を思い出して、
いつかなんとなく
信じてみたいような気分に
なってしまうのかもしれないなあ。