スウィートボックスという。
グレイテスト・ヒッツ/スウィートボックス
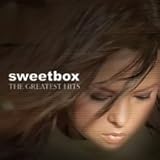
¥2,621
Amazon.co.jp
これは、ユニットと
表現するのが正しいのかな?
いや、この人たちは、
まだ動いているとこは
きちんと見たことがないもので。
昨今なら、探せばすぐ
どこかから簡単に
出て来るんだろうけれども。
とにかくでも、
この方たちのアプローチ、
なるほど極めて独特である。
ある種、アイディア勝ち
みたいなものだよなあ、とも
思わないでもないのだが、
でもまあ、面白いし、
ちゃんと随所に気が配られて、
極めて心地好く仕上がっている
個性的なサウンドであることは
間違いがないので
取り上げることにした次第。
さて、何が特徴的かといって
この方たちの作品、基本的に、
ダンス・チューンに、
クラシックの有名な
モチーフをフィーチャーして、
いわばトラックを
立たせてくるという手法を
採用しているのである。
まあ、そうではない曲も
もちろんあるにはあるのだが、
そういう場合も、
弦や管を、機械ではなく
生の楽器で録音したりすることで、
どこかにそういう空気を
きちんと留めることに
概ね成功しているといっていい。
まあ、カタログの全部を
聴いてみた訳でもないのだが、
オリジナル作品だと
クレジットされている
楽曲群の中にも、
古典的といおうか、
ある種の格調を
十分に感じさせてくる場合が多い。
いかにも不思議な手触りである。
ちなみにこのスウィートボックス、
我が国においては一時期、
ウェディング・パーティーの
BGMとして、
非常にもてはやされたそうで、
なるほどなあ、と頷きもした次第。
さて、彼らのデビューは
95年のことになる。
Booyahという最初のシングルが、
いきなりイタリアと、それから
シンガポールのチャートとで
一位を獲得したのだそうである。
いや、繰り返すけれどこれ、
ドイツのグループなのである。
まあずいぶんと奇妙な
組み合わせともいうべき場所から、
最初の反応が返ってきたものである。
もっとも、イタリアでの
人気に関していえば、
確かに随所で、ユーロビート系の
アプローチに通じるような、
リズムの刻み方は
しているかもしれない。
そんなところが、
支持を獲得したのかな、とも思う。
それに、トップには行かずとも
各国でそれなりに
ヒットしていたのかもしれないし。
いずれにせよ僕自身、
このBooyahという
デビュー曲は現段階では未聴なので、
確かなことはいえないのだが。
さて、そしていよいよ、
同曲に続いて発表されたのが
今回のピックアップである、この
Everything’s Gonna Be Alrightなる
ある種のキラー・チューン
だったという次第。
少なくとも同曲が、彼らにとって
大きな転機となったことは
九分九厘間違いはない。
すなわち、このトラックで、
まず今回の記事の冒頭で紹介した、
クラシックと
ダンス/ヒップ・ホップの
融合という手法が
初めて採用され、そして同時に
彼らのいわば個性として
確立されたのである。
なるほどずいぶんと遠い昔に、
スターズ・オンみたいな企画で、
フックト・オン・クラシックという
名前を冠したシリーズが、
クラシックをダンス・ビートに
載せるということを
たぶん最初にやっていたのだけれど、
あれともまた、少なからず
アプローチの種類が違っている。
むしろ、EL&P(♯100)の
方法論に近いのかなあ。
いや、やっぱり
それともちょっと違うなあ。
ちなみに上の
スターズ・オンというのは、
オランダの企画ユニットの名前で、
ビートルズやアバやらの
代表曲をメドレーにして繋いで、
シングル・ヒットを飛ばしていた。
あれはたぶん、70年代の
終わり頃だったのではないかと
思うのだけれど、
もう少し後だったかもしれない。
いや、本当この手の企画、
あの頃はよく、深夜のラジオで
耳にしたものなのである。
今になって振り返ってみれば、
このスターズ・オンのヴァージョンで
僕自身、初めて耳にした、
ビートルズの楽曲というのが、
少なからずあっただろうことは、
否定できないかとも思われる。
まあ、メドレーなので、
サビだけだったりする訳だが。
いや、また話がずいぶんと
横道に逸れてきたので、
そそくさと今回の
スウィートボックスの話題へと
戻ることにしようと思う。
やはり彼らのサウンドの
組み立て方の語法というのは、
ヒップ・ホップの方法論に
極めて近いのだとは思う。
だが決して、サンプリングを基本に、
バック・トラックを
仕上げている訳ではないところが、
彼らのユニークなところであろう。
加えて、基本借り物のモチーフで、
バッキングの全体を
仕上げてきていたとしても、
そこに載っかってくるのは、
ラップではなく、
カウンター・ラインとして
十分に機能する
新しい別種の旋律である。
それがやはり、彼らのトラックを、
斬新なものにすることに
成功しているのだと思う。
さて、今回のピックアップの
このEverything’s~なる曲が
下敷きとしたのは、
御存知の方には
いわずもがなだとうとも思うのだが、
あのバッハの
『G線上のアリア』である。
この曲は、
相当どころではなく強力である。
一気に衆目を集めたのも
十分に頷けるといっていい。
ちなみに映画版の『エヴァ』と
それからブラピと
モーガン・フリーマンとが共演した
デヴィッド・フィンチャー監督による
95年のアメリカ映画、
『セヴン』が確か、
作中で同曲を使用していたはずである。
たぶん探せばもっといっぱい
使われているのでは
なかろうかとも思われるのだが、
すぐには浮かんでこなかった。
いや、とにかくだから、
昔からこの曲ばかりは、
本当に不思議な音楽だなあと
個人的に思っていたりするのである。
――ただ、極めて美しい。
それはまず間違いがない。
でも、その美しさの正体が、
僕にはいまだに
よくわからないままなのである。
少なくとも、華やかさとか、
はしゃぐ感じとはまるで違う。
それでも、表現されているのが
悲しみや、それに準ずる種類の
感情であるとも到底思えない。
宗教的な荘厳さ、あるいは
敬虔さみたいなものならば、
感じなくもないのだけれど、
やはりそれとも微妙にぶれている。
この『アリア』のメロディーや
全体の展開の届いてくる、
あるいは訴えかけてくる場所は実は、
たぶんもっと
個人的な部分なのだと思う。
静謐という言葉が
本当によく似合う旋律である。
それが本当にそっとそっと、
信仰とかそういうものさえ、
すっかり縫うようにして通り越し、
善悪の境目みたいな場所を、
柔らかく刺激してきている。
そんな感じの錯覚が起きる。
まあこんな具合に、
この曲を聴くたびに僕は
これ、いったいなんなのだろうなあ、と
首を傾げてしまっているのである。
まったく、これだけ書いても、
全然上手く表現できた気がしない。
だから、こういうのが本当に
言葉なんてものの
決して届かない場所にいる、
そういう種類の美なのだと思う。
だいぶ大袈裟になってしまったとは
我ながら思わないでもないけれど、
でも、だからこそ、
この『G線上のアリア』は
古今ほとんど類を見ない
名曲の域に達しているのだと思う。
だけどこういう場合、つまり
「名曲」のさらにその上に君臨する、
みたいなことをいいたい時は、
いったいどうやって
表現すればいいんだろうね。
やっぱ超名曲しかないのか?
でも、あんまりそぐわないよなあ。
まあとにかくである。
このメロディー、間違いなく、
人類が生み出した、
五本の指に入るレヴェルの
宝物であることは断言していい。
もちろんこういうのは所詮、
個人的な感想であるので念のため。
そういう訳で、僕としては、
それほどの旋律を
武器にして攻めてこられてしまえば、
耳に止まるし、
やっぱり、いいな、と
思ってしまう訳である。
実際僕自身、95年デビューの
アーティストなんて、ほかは
ほとんど知らないといっていいのに、
ベスト盤とはいえ、
アルバムをちゃんと持ってた訳だし。
でも、なんで買う気になったのか、
全然覚えていないんだよねえ。
だからまあ、
実のところをいってしまえば、
この『アリア』のメロディーは
全然Alrightな感じは、
しないんだけどなあ、
でも外れてる訳でも決してないし、
なんてことをつらつら思いつつ、
時々聴きたくなって、
この一枚、今もしばしば
プレイヤーに載せているという訳である。
ほか、今回のベスト盤の収録曲では
パッヘルベルの『カノン』や
ジョバンニ・バッティスタ・
ペルゴレージなる作曲家の
『スターバト・マーテル』、
それから『アリア』と同じ
J.S.バッハの『アヴェ・マリア』なんかを、
また、もう一枚持っている、
09年の作品の方では、
ビバルディーの『四季』から『春』、
やはりバッハの『トッカータとフーガ』、
さらにはベートーヴェンから
『歓喜の歌』こと第九なんかを、
下敷きにしたチューンが聴ける。
ちと狙い過ぎの感は
否定できない場合もあるけどね。
また、上でジャケ写を掲げた
ベスト盤収録の
彼らのオリジナルの作品の中では
Cinderellaと
それからWaterfallなる曲が
個人的に結構気に入っている。
とりわけこの
Cinderellaの歌詞が
なかなかに
可愛いらしかったりするのである。
ずいぶんとカエルに
キスしてきたけど、
まだ王子様に出会ってないわ、とか、
ちょっとだけツボだったり
しないでもない。
いや、なんか似たような場面を
昔書いてしまったような
気もしないでもないのだが。
もっともあの時は
カエルではなくセイウチだったか。
いや、まあこれもだから
いつもの余談でありました。
ちなみに、このユニット、
フロントシンガーが
幾度か交代しているのだけれど、
なんだかそのたびに、
このEverything’s~は
リメイクしているようである。
さらに、歴代のヴォーカリストの
ほとんどは英語圏出身の方が、
努めてきた模様でもあるのだが、
しかしながらレコーディングとかは、
ドイツ本国で行われていたようなので、
だからこの彼女たちはみんな、
当時はドイツに移住して、
活動をしていたのだそうである。
アルバム制作は、
まずクラシックの音源を
聴きまくることから始まったなんて、
コメントをしている方もいるようである。
さらにちなみに現在は、
本邦のゴスペル・シンガー
福原美穂さんが、
ここに参加されているらしく、
しかも活動の拠点もついに
ロスへと移しているらしいです。
さて、では恒例のトリビアは
今回は『G線上のアリア』から。
この曲、ヴァイオリンの、
四本の弦のうちの一本、
G線だけで全部弾けるので、
この通称になっていることは、
たぶん皆さん普通に
ご存知なのではないかとも
思われるのだが、
でも、別にバッハが最初から
そういう意図を持って
書いた訳では決してない。
そもそもはこの曲、
管弦楽組曲の一部で、
その第二曲『アリア』が、
後年アウグスト・ウィルヘルミなる
ヴァイオリン奏者によって、
同楽器の独奏曲として、
編曲された際、転調されて、
G線上のみで、演奏することが
可能になったのだそうである。
それ以来『G線上のアリア』という
呼称が定着しているという経緯である。
で、このウィルヘルミは
19世紀の人なので、
だからまあ、バロック時代、
すなわち17世紀の人物であるバッハは、
自分の作ったこのメロディーが、
『G線上のアリア』と
呼ばれていることなど、
実はまったく知らなかったりするのである。
なんかこの逸話だけで、
まさしく芸術って感じである。