ノーランズである。
シングル・コレクション/ノーランズ
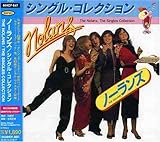
¥1,944
Amazon.co.jp
いや、だから、イギリス編で
彼女たちをついつい、
取りこぼしてしまったのですよ。
名前を出すことさえしなかった。
でも理由があります。
実はすっかり忘れていた訳では
まったくもってないのです。
洋楽聴いてて、この曲が、
頭から抜けるはずもありません。
もちろん僕の世代でって、
ことになるとは思いますが。
むしろ、早くやりたいな、
くらいに思ってました。
――でもねえ。
ひょっとして頷いてくれる方も
中にはいらっしゃるかも
しれないとも思うけれど、
実は頭の中で、アラベスクと
ごっちゃになっちゃってたんです。
『ダンシング・シスター』
まだやってないよなあ、
ああ、でもドイツに行くまで我慢我慢。
みたいな感じ。
いずれにせよ、
お恥ずかしい限りではあります。
そういう訳でついこの前の
ダニエル・ビダル(→♯102)で
石野真子さんに触れた時に、
ちょっとウィキなど覗いてみたら、
そうだよ、ノーランズは
全然ドイツじゃないよ、
そんなの当たり前じゃないか、
何やってんだ、俺、的な?
――すっげえ悔しいかも。
以上、どう足掻いてもいい訳でした。
それでまあ、どうしようかなあ、と考えて、
でも大晦日にこの曲に触れるのも、
そんなに悪くはないかもしれないよなあ、
などとも最初は思ったのですけれど。
なんていうか、いわば無条件に
ハッピーなトラックだし。
――ところがどっこい。
ちょっとリサーチをかけてみて、
少なからず戸惑いました。
その理由については、
後で触れることと致しますが。
そういう訳で今回の記事、
後半はやや、
新年には似つかわしくない方向へと、
重くなります。
どうぞ御了承の上お読み下さい。
だけど本当にこの曲は、
あの頃、相当どころではなく
流行ったのである。
どれくらいすごかったかというと、
オリコンのシングル・チャートで
並み居る邦楽曲を押しのけて
トップ・ワン獲得を果たしている、
そういう史上数少ない
シングルのうちの一つなのである。
折角なので、この際全部挙げてみる。
万が一抜けがあったら、
是非御指摘ください。
まずはオリコン・チャートの
集計が始まった68年に、
ビージーズの
Massachusettsが
一週だけだがトップを記録し、
同じ年、サイモン&ガーファンクルの
The Sound of Silenceが、
こちらは二週にわたって
同じポジションをキープする。
翌年、メリー・ホプキンなる
イギリスの女性シンガーが
Those Were the Days(『悲しき天使』)で
やはり一週だけだが、トップに君臨する。
ちなみにこちらは、
P.マッカートニーの
プロデュース作品だったりするらしい。
たぶん森山良子さんによる
日本語盤の方が、
通りがいいかとも思うけれど。
そして70年には
ジェリー・ウォレスなる
こちらはアメリカの
カントリー・シンガーが
『男の世界』という
マンダムのCMソングで首位を記録する。
同じ年に発表された
ショッキング・ブルーのVenusや
ビートルズのCome Together,
Let it Beでも手の届かなかった、
トップ・ワンのポジションを
こちらは実に、三週にわたって
キープしていたりするもするのである。
そして76年、洋楽では今なお
史上最大の売り上げ枚数を誇る
ダニエル・ブーン(英国)の
Beautiful Sundayが登場し、
今回のノーランズによる
『ダンシング・シスター』を挟んで、
80年代に入った83年、
アイリーン・キャラが
Flashdance...What a Feelingで、
さらに次には12年という長い間を開け、
95年にセリーヌ・ディオンが
To Love You Moreというトラックで
それぞれ一位を記録する。
そして97年、
あのダイアナ妃の事故死を受け
リイシューされた、
エルトン・ジョンの
Candle in the Windが
頂点まで昇り詰めたのを最後に、
欧米のアーティストによる
トップワン・ヒットは
現在に至るまで
すっかり途絶えてしまっている。
ひょっとして
テイラー・スィフト辺りが
握手券でもつければ、
今ならなんとかなるのかもしれないが。
まあ、日本のマーケットのために
そこまでしてくれることは
九分九厘九毛九糸ないだろう。
なお、これらのほかに
イスラエル出身の
ヘドバとダビデというデュオの
『ナオミの夢』という曲が
71年に一位を記録しているのだけれど、
これは日本語詞がA面だったらしいので、
ちょっと違うのではないかと思う。
っていうか、
イスラエルのアーティストなんて
後にも先にもこの二人しか知らないや。
だから、この『ダンシング・シスター』は
ある意味ではこの国の洋楽史上、
十分十指に入るトラックなのである。
80年の秋、
松田聖子の『風は秋色』から
首位の座を奪い、
五輪真弓の『恋人よ』に抜かれるまで、
二週にわたって、
このポジションをキープしている。
しかし、この
『ダンシング・シスター』という
邦題が実に上手いと思う。
ノーランズは、五人姉妹による
ファミリー・グループである。
だからこのトラックの
Dancingというキーワードと、
いわばグループの構成というか、
キャラクターが一発でわかる、
シスターという語が組み合わされ、
それ以外には何もない。
すごいや、と思う。
もちろんジャクソンズという
先例があるから、
グループ名だけで、
ああ、きっと家族なのね、とは
なんとなくだがわかったけれど。
ちなみにノーラン家は、
実は六人姉妹である。
上から、アン、デニス、モリーン、
リンダ、バーニー、コリーンとなる。
当初は両親も一緒に、
ザ・シンギング・ノーランズという
名前で活動していたらしい。
もっともコリーンだけは、
幼すぎるという理由で、
この段階ではまだ
正式なメンバーではなかった模様。
やがて姉妹だけになり、
グループ名をノーランズと改め、
次女のデニスがグループを抜け、
代わりにコリーンが
正式にメンバーとして加えられる。
このいわば過渡期に
録音されていたのが、
I’m in the Mood for Dancing
だったということらしい。
もっとも日本に紹介された時には、
もうコリーンがメインの
形になっていたようにも思う。
重くなるのはここからである。
後年、長女のアンが
自伝を発表している。
その中で彼女は、16くらいの頃まで、
自身に父親からの
虐待があったことを
明らかにしているのである。
女の子へのアビューズといえば、
つまりはそういうことだろう。
末娘のコリーンも、
この父親が、アンと自分、
それから母親に対して
極めて暴力的だったことを
肯定している。
――いや。
ちょっとどころではなく
ショックだったかな。
なんていうか、そういう経験というか
トラウマを刻み込まれた女の子たちが、
Gotta Pull Myself Togetherなんて
歌っているのを聴きながら、
知らなかったとはいえ、
『恋のハッピー・デート』とか、
まあ中坊だった僕らは、
喜んでいた訳である。
もちろんこのGotta Pull~は、
普通に失恋の歌である。
彼は去ってしまったけれど、
あたしのせいだし、
何とかして立ちなおらなくちゃ
みたいな感じ。
だけど、Pull Myself Togetherである。
――どうにかして自分を繋ぎ止めないと。
予想もしなかった方向から
こういうのをぶつけられてしまうと、
正直どう反応していいか
まったくわからなくなってしまう。
否応なくマイケルのことを
思い出してしまったし、
ランナウェイズの
シェリー・カーリーなんかも、
ちょっと内容は違うけれど、
結構すさまじい人生を
送ってきているはずである。
こういったネグレクトというか、
チャイルド・アビューズを
テーマの一画に据えた作品を
僕もここまで一冊だけ書いている。
『オールド・フレンズ』と
いうのがそれである。
短編『向日葵の迷路』で試みた
同一作品内で同じ一つの出来事を
あえて二方向の視点から
記述してみるといった試みや、
あるいは
クロス・カッティングの
人称のすり替えによる
収束のさせ方など、
テクニカルなトライアルの出来には
自分でも十分満足しているし、
そういった部分を、
評論家の方に評価していただいても
いるのだけれど、
いかんせん、
モチーフがモチーフだし、
LGBTの問題にも踏み込んでいくので、
全体にひどく重苦しい。
それでも、ラストの
月がきれいですね、のネタは、
結構決まっているはずだと、
自分では思っていたりもするのだけれど。
挑んだという手応えはあるし、
連載という形をやりきったという
自信もくれた一冊なのだが、
さすがに楽しんで書いたとは、
声に出してはいいがたいことは否めない。
まあ、長いし、しかもそういう作品なので、
できれば体力気力のある時に、
手を伸ばしていただければ幸甚である。
それでも、僕らはやっぱり、
I’m in the Mood for Dancingや
Gotta Pull Myself Togetherを
ハッピーな気分で
聴くべきなのだろうと思う。
トラック自体や、彼女たちの
パフォーマンスが目指していたのは
そういった気持ちをオーディエンスに
届けることだったろうことは、
疑いを差し挟む余地もないし、
そしてそれが十分以上に
達成されていることは、
記録が証明しているのだから。
では今回のトリビア。
いや、でもこれは到底
トリビアとはいえないなあ。
いわば個人的な思い出である
実をいうと、中学の時に
クラスメートの一人が授業中に放った、
「脳が乱れてノーランズ」という
なんともしょうもないギャグが、
この年になっても
どうしても頭から離れてくれない。
だから僕は、今回のこの
I’m in the Mood for Dancingを
耳にするたび、
まあそいつのことやら、
中学時代のことなんかを、
ついつい思い出して
しまったりもするのである。
そして、あの教室に、
そういう見えない傷と
戦っていたティーンネイジャーが、
一人もいなかったことを
今となってはただ祈るだけである。
事実として確かめたいとは
もちろんほとんど思わないし、
そもそもそういう術もなければ、
知って何ができる訳でもない。
それは十分わかっているのだが。
それでも、そうであればいいなあと、
やはりそう思ってしまう。
さて、そういう訳で皆様には、
今年も一年、ここにおつきあい
どうもありがとうございました。
残念ながら年頭に掲げた目標は、
諸般の事情により、
お恥ずかしながら、
一つも実現していない訳ですが、
なんか、来年は何とかなりそうです。
まあひっくり返る可能性が
決して皆無ではないのがこの世界で、
そういうのも実は昨年、
図らずも経験してしまったのですが。
――でも。
諦めたら確かにそこで
試合終了なんですけれど、
諦めなければ、
たとえどんなに時間がかかっても
結構なんとかなるものですし、
もちろん僕自身、
全然何も諦めてませんから。
っていうか、
むしろ一番出したい本に
光明が差して来て、
多少はしゃいだりしてますから。
次の話、その次の話を、
どんどん考えようという
くらいな感じだったりします。
では皆様には、
どうぞよいお年をお迎えください。
来年も、いや来年こそ、
いろいろとよろしくお願い致します。
ちょっと高い本になりそうなんで、
少し早めに多少の予算を
キープしておいて戴けたりすると、
大変幸甚だったり
するかもしれません。