先週も多少御案内した通り
だからここからは、個人的には
さほど聴き込んだという
訳でもないのだけれど、
さすがに取りこぼしたくは
ないよなあ、といった感じの
アーティスト群になってくる。
まずはこちらから。
70年代初頭にシーンを席捲した
ボウイと並ぶ、
グラム・ロックの雄である。
グレイト・Aサイドヒッツ1972-1977/T.レックス
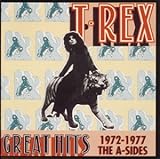
¥2,097
Amazon.co.jp
Tレックスという。もちろんこれ、
ティラノサウルス・レックスの意。
だがまあむしろ、
マーク・ボランというべきかもしれない。
無論このバンドのシンガーであり、
ギタリストであり、
そしてソングライターだったのが、
すでに伝説だといって
決して過言ではないであろう、
本名をマーク・フェルドという
このマーク・ボランと
いうお方なのである。
厳密にいっておくと、バンド名は
ティラノサウルス・レックスから
改名して正式にTレックスとなり、
最後には、そのものずばりというか、
マーク・ボラン&Tレックスという
表記へと変遷している。
後期になるほど、
メンバーは流動的になり、
実態はほとんどマークの
ソロ・プロジェクトのような
形となってしまってもいたらしい。
いずれにせよ、このバンドは
77年、ボランの死によって、
その活動に終止符を打っている。
さて、彼らのレコーディングの中では、
たぶん20th Century Boyなる曲が、
昨今とりわけ我が国では、
一番通りがいいのではないかと思う。
もちろん浦沢直樹さんの
あのコミックがあったからである。
同曲のあの、強烈にノイジーな
ギターの引用で開幕した物語が、
まさかあんな世界に
繋がっていこうとは、
正直思いもしなかった。
何よりも映画がきちんと、
オリジナルの音源を使っていたことは
傍目から見て相当嬉しかった。
ちなみに同曲の邦題は、
『20センチュリー・ボーイ』になる。
『20世紀少年』は、
だから訳語ということになるのか。
まあ大した違いはないとも思うけれど。
大体僕らが少年だった頃には、
21世紀なんて言葉は
ほとんど未来と同義語だったのである。
――まあとにかく。
この20th Centuries Boyは、
一にも二にも、やはりあの
冒頭のギターなのである。
ハンド・クラップだけをバックに鳴る、
二つの音階だけを行き来する
割った響きのシンプルなライン。
このフレーズ、
以前エクストラでも取り上げた、
ストーンズのSatisfaction(♭53)や
あるいはDパープルの
Smoke on the Waterにも比肩し得る
それこそ20世紀が、いや、
ロックンロールなる音楽が
この世界に産み落とした、
もっとも偉大なギター・リフの
一つであるといわれるような場面も
少なからずあったりする。
この点は、僕もまったく異存はない。
世界を変える力があると信じたという
あの形容も、
さほどの誇張ではないといっていい。
もっとも、僕自身がこの
Tレックスの音楽に入ったのは
まずはGet it onからだったりする。
もちろんあのパワー・ステーションが
カヴァーしていたからである。
僕がどれほどDDを偏愛しているかは、
ここを見て下さっている皆様には
おそらく既にお察しの通り。
そういう訳で、ジョンとアンディが
ピック・アップするアーティストとは、
いったいどんな音楽だろうというのが、
まずは興味の入り口だった。
ロバート・パーマー(♯74)の
ヴォーカルによる
些かヘヴィーな手触りに比べると、
オリジナルはずいぶんと明るく、
むしろ開けっぴろげに聴こえてきて、
最初は戸惑ったことを覚えている。
まあでも、つまるところ
この感じがTレックスであり、
マーク・ボランなのである。
Get it on, Bang a Gong, Get it on.
シンプルという言葉さえ、
最早すっかり通り越した
直球であるといっていい。
訳せといわれても困ってしまう。
なんというか、そしてこれ、
このサビの通りの曲なのである。
ほかTelegram Samとか
Solid Gold Easy Action辺りも
それなりに好きだった記憶があった。
もっとも正直なところを告白すると
CDを買いなおすことは
最近までなんだか
ついついしそびれてしまっていて、
今回本稿を起こすに当たり、
実に久し振りに
彼らのトラックを聴いてみた。
いや改めて、このボランの書く曲
よくも悪くも安定している。
終始ぶれるということがない。
クールな脳天気さとでもいうべきか、
基本すごく華やかで、
ともすれば70年代中盤以降の
ロックンロールが
そちらへと傾いてしまいがちな、
ある種の気難しさとは、
はっきりと距離を置いている。
むしろところどころで、
オールディーズや
ある種のフレンチ・ポップスみたいな
手触りに寄り添っている。
そう思えてしまうほどわかりやすい。
しかし、かといって、
ステレオタイプな訳では
全然ないところがすごいのだと思う。
この辺りがやはり、
時代や世代を超え
支持を集め続けていく
所以なのだろう。
その証拠に、彼らの楽曲のカヴァーや、
映画そのほかへの使用は、
今でも枚挙に暇がないのである。
いずれにせよ、このTレックス・サウンド、
随所でそれこそジギー期の
ボウイの作品群を想起させる音や
アイディアが聴こえてきたりして、
ああ、だからこれがきっと
グラム・ロックだったんだなあ、と
感慨を新たにさせられたりもしてしまう。
もっともこれにも
それなりにわかりやすい理由があって、
グラム期に至るまでのボウイと、
このTレックスの代表曲の多くは、
トニー・ヴィスコンティという
同じプロデューサーの
手によるものなのである。
今さらだが一応さらっと触れておくと、
このグラム・ロックのグラムとは、
豪勢とか魅惑的とかいうニュアンスの
Glomorousなる語に由来している。
Tレックスも多くの場合、
ちょっと軽薄なくらいの
女性コーラスと、
決して前面に出過ぎることのない
それでも印象的なストリングスを
随所にフィーチャーすることによって、
このいわば、賑々しいとでも
いったような手触りを
見事に作り上げてくれている。
この辺がどうやら
ヴィスコンティのスタイルらしい。
でもなんか、そうなると
実はグラムというシーンは、
つまるところ、この三人で
回していたのかもしれないなあ、
などともちょっとだけ思ってしまった。
さて、今回表題にしたMetal Guruは
72年の作品で、彼らの四曲目の
全英ナンバー1獲得曲である。
ぎりぎり下世話なんだけれど、
それが独特の味わいになっていくのが、
このマーク・ボランの作る楽曲の
一番の魅力なのではないかと、
個人的にはまあそんなふうに思っていて、
その特徴が最もよく出ているのが
実はこのトラックなのではないかと
なんとなく感じたりもしたので、
今回はこのチョイスとなった。
実際冒頭のコーラスのラインとか、
独特の猥雑さを抜きにしてしまえば、
本当どこにでも
ありそうな感じの旋律なのである。
それがそうでなくなってしまうのは、
実はこの人の、
ちょっとした言葉の選び方に、
起因しているのではないかと思う。
そもそもはまずこのGuruなる語だが、
あまり好ましくない方面から、
ある時いきなり有名になって、
今やわが国でも一般的に使われるように
なってしまっているけれど、
(主に宗教的な)指導者といった意味の、
音通りの、あのグルのことである。
――金属製の導師。
これだけでだから、
それこそ『20世紀少年』と同じくらい、
シンプルなのに奇妙な違和感が、
否応なく呼び起こされてきてしまう。
ほか、先に曲タイ出しちゃったけど、
『電報のサム』だったり、
こちらはアルバム・タイトルだが、
『電気の武者』の邦題で有名な
Electric Warriorだったり、
さらには最後のアルバムのタイトル曲は
『地下世界のダンディ』だったりと、
やっぱりちょっと、
発想のどこかが普通ではない。
しかも、そういったモチーフが
曲や作品の中に取り込まれた時に
あまりどころかまったく破綻を
見せることがなく、
むしろ、それしかないような
イメージに固定されていくところが、
やはり只者ではなかったのだと思う。
マーク・ボランは’77年9月16日、
自身の30歳の誕生日を目前にして
自動車事故で命を落としている。
あのエルヴィスの死の、
ちょうど一ヵ月後のことである。
ハンドルを握っていたのは、
当時彼の事実上の細君だった、
グロリア・ジョーンズという
黒人の女性シンガーだった。
彼らは生活をほぼ一緒にしており、
二人の間には
当時二つになる子供もいたのだが、
戸籍上、マークには別の配偶者がいた。
そもそもが、マークとこのグロリアとは
この本妻の紹介で
出会ったのだともいわれているらしい。
その彼らがロンドンで二人で食事を終えて
家へと帰るその途上、事故は起きた。
フェンスポストに接触した車が、
コントロールを失って、
道路沿いの一本の樹に衝突して止まった。
シートベルトをしていなかった二人は、
二人ともそれぞれ車外に放り出された。
グロリアは腕と顎を
したたかに骨折しこそしたのだが、
どうにか一命を取り留めた。
一方のマークはというと、
即死だったという記述もあれば、
十分に治療可能な傷だったが、
むしろ彼の体の方が、
長年にわたる薬物使用のせいで
相当にぼろぼろだったため、
手術を断念せざるを得なかったのだと
搬送先の医師が語ったというような
証言も見つかっている様子である。
さらに、生前マークは一度ならず、
自分は30歳まで生きられないだろうと、
自ら口にしていたとの話もあったりして、
だからまあ、この辺りが僕が、
最初にこの方を形容するのに、
伝説という言葉を使った理由なのである。
本当に、それこそ
駆け抜けた人生だったのだなあ、と思う。
なお、バンドのメンバーが
マークの死後、80年代以降も
時折Tレックスの名前で活動したりも
しているらしいのだが、
やはりこれは別ものであろう。
まあ、聴いたこともないのだけれど。
では締めのトリビアである。
上でも触れた通り、マークには
このグロリアとの間に、
ロランという名前の息子がいた。
しかしながら結局最後までこの二人は
そういったいわば、
合法ではない関係だったものだから、
グロリアとロランには、
法的な相続権は一切認められず、
経緯が経緯だけに
遺族側からも経済的な援助を
受けることができなかったらしい。
マークのこの最初の奥さんについては、
詳しいことはよくわからないのだが、
ある意味では、二度も同じ相手に
夫を奪われたことになる訳だから
一概に責めることも、
できないかなあとは思わないでもない。
いずれにせよ、この時、
このグロリアとロランの窮状に
手を差し伸べてくれた人物こそが、
あのボウイだったのだそうである。
さらにロランが語ったところに寄れば、
どんな場面だったかまでは
さすがにわからないのだけれど、
ボウイとマーク、それに先述の
トニー・ヴィスコンティの三人が、
それぞれにいつか息子が生まれたら、
ファミリー・ネームと韻を踏むように
名前をつけようか、みたいな話を
遠い昔に交わしていたりもしたらしくて、
そういった理由で、彼の名前は、
ロラン・ボランとなったのだそう。
ちなみにボウイの長子は、
ゾウイ・ボウイ、
ヴィスコンティの息子は、
モンティ・ヴィスコンティに
しようという話だったらしい。
ゾウイは本当にゾウイだけれど
さすがにヴィスコンティの息子までは、
今回ウラが取れませんでした。
さらにちなみにこの
ゾウイというのはミドル・ネームで
ダンカン・ジョーンズという名前の
映画監督さんが、
このゾウイその人であったりします。
ほら、ボウイは本名はジョーンズだから。
なお、上の一連のネタに関しては、
英デイリー・メール紙の
同内容の記事を
抄訳あるいは要訳された
幾つかのサイトを
参考にさせていただきましたことを、
ここに付記しておくことに致します。
さて、最後は例によって取りこぼしのメモ。
基本70年代以前は
さほど得意ではないのだけれど、
本当は、せめてキンクスくらいは
ちゃんとやろうかと思ってはいたのである。
でもやはり枠が
足りなくなってしまって見送った。
それから、ザ・フーと、
ダイア・ストレイツについても諦めた。
また、グラムに続いて起った
重要なムーヴメントである
パンクのシーンからは
クラッシュ、ダムド辺りくらいには
触れておこうかとも
思わないでもなかったのだが、
この辺はさらに不得手だったりするので
割と早い段階で断念している。
ちょっと違うかもしれないけれど、
スレイドやステイタス・クォーも、
ここで一回分のテキストを
もたせられるほどには知らない。
それから、サンデイズ(♯30)の時や
そのほかで幾度か名前を出している、
スミスについても
結局は手が回らなかった。
あと、ザ・キュアーにも。
そういやあソフト・セルなんてのも
確かイギリスのはずだったが。
フロック・オブ・シーガルズもそうだよな。
ビリー・ブラッグとアズテック・カメラも
ここで出しておいた方がいいのかな。
ジ・アラームなんてのもいた気がするが。
さらには、
ニュー・オーダー(♯17,♭13,♭37)を擁した
ファクトリー・レーベルを中心にして起った
いわゆるマッドチェスターの
ムーヴメントについても
ここでは扱わずじまいになる。
ハッピー・マンデーズとか
ストーン・ローゼズとかいたのだが。
この辺りの動きの中では、
ザ・ファームというバンドの
All Together Nowという曲が
結構よかったように記憶している。
いってみれば典型的な
カノン・コードのトラックなのだが、
シンセとギターの音色の選び方や、
ちょっとかったるいヴォーカルの加減が、
そこそこニュー・オーダーっぽかったりして、
それなりに好みに合っていた。
ええと、念のためだけれど、
このザ・ファームというのは
ツェッペリンのジミー・ペイジが、
ポール・ロジャーズと組んだ
バンドのことではありません。
あちらはTHE FIRMで、
こちらのスペルはFARMなのである。
ややこしいなあ、もう。