Night Birds/Shakatak
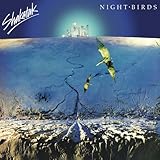
¥1,323
Amazon.co.jp
いやあ、流行った流行った。
しかもこのNight Birds、
82年の作品である。
この時期だと、僕自身はまだ、
本格的に洋楽にどっぷりとは
ハマっていなかったはずなのである。
それでも、その存在を知っていた。
少なくとも、後年例の
『男女七人~』で劇中に使用され、
もう一度脚光を浴びた時には、
なんだ、今さらかい、くらいに
斜にかまえて
眺めていたことは間違いがない。
いや、嫌な若僧ですみません。
そういう年頃だったもので。
まあ、とにかくだから、
それほどこの、
Night Birdsという曲の先鋭性と、
それからなんと形容するべきか、
ある意味で日本人には、
非常に親しみやすいともいえる、
この一風変わったバンド名とは、
絶大なインパクトをもって、
シーンに登場してきたのである。
ちなみにこのシャカタクなる
ちょっとどころではなく
不思議な名前の由来だけれど、
まず、もちろん造語である。
そしてこれ、
まだ彼らがアマチュアだった当時、
自分たちのレコードを支援してくれた、
Shack Recordsなる
リテイル・ショップに敬意を表し、
そこから拝借しているのだそう。
――ん? ちょっと待てよ。
ではそのShackなる店が応援した
彼らの初期のレコードとは、
どんな名前で出ていたのだろう。
ついついそんなことを
ふと疑問に思ってしまうのは、
はたして僕だけなのだろうか。
なんだかニワトリが先か卵が先か、
みたいな話になってきましたが。
さすがに調べた限りでは、
そこまでのことは
はっきりとはわかりませんでした。
一説には、そのShack Recordsに
これからAttackをかけるから
シャカタクなのだともいうのだそう。
なるほどこちらの方が
筋は普通に通りそうだが、
そうなると今度は、
語順にちょっと違和感があるかなあ。
いずれにせよ、本当のところは、
ビル・シャープ本人に
当たってみなければわからない。
それにしても、
このNight Birdsというトラック、
いろんな意味で
本当に斬新だったのだと思う。
前回の予告からすでに僕は
この言葉を使用してはいるのだが、
おおよその場合、
あの頃こういった音楽は
フュージョンという括りで
語られていた。
その起源は、もちろんジャズにある。
クロスオーヴァー・ジャズというのが
たぶんこのフュージョンなる用語と
ほぼ同義語だったといってよい。
二つの異なる世界/分野が
交錯するというのが
こちらのクロスオーヴァーなる語の
本義なのだが、
いわばジャズが、電子音楽や、
ロック/ソウル、あるいはラテンなど
とにかく様々なジャンルを、
自身のうちに取り込み始めた、
そういった流れを
当時このように呼んでいた。
そして、こちらもまた、
さほどはっきりと
覚えている訳でもないのだが、
たぶん大体同じ頃、我が国に
クロスオーバー・イレヴンという
ラジオの深夜番組があって、
その番組の選曲のテイストが、
なんとなくこちらの
ベクトルに寄り添っていた。
都会的、あるいは
ソフィスティケイテッド。
ムーディーというよりは、
もう少しだけ洗練されている。
いかにもな、しかも抽象的な
形容だなあとは
自分でも思うのだけれど、
まあだいたいはそんな感じで、
この番組、真夜中手前の、
あのなんともいえない空気を
巧妙に演出してくれていた。
小倉エージさんとか
大伴良則さんの選曲だったはず。
しかし改めて、この手の音楽の
いわばパイオニアは
いったい誰になるのだろう。
すぐに浮かんでくるのは、
ウェザー・リポートか、あるいは
チック・コリア辺りなんだけどなあ、
などと考えつつ、
つらつらとウラを取ってみたところ、
かのマイルス・デイヴィスに、
BITCHES BREWという
アルバムがあって、
これが、同ジャンルの
ある種メルクマール的な
一枚なのだそうである。
70年の作品だそう。
今度ちゃんと聴いてみないと。
で、このアルバムに参加していた、
ウェイン・ショーターと
ジョー・ザビヌルが組んだのが、
上に挙げたウェザー・リポートで、
チック・コリアもまた、
同作でピアノを弾いているらしいから、
どうやら大体理解としては、
間違ってはいないようである。
なるほどなあ、
やっぱりマイルスか。
改めてそんなことを思った次第。
さて、たぶんジャズという言葉が、
史上初めてコマーシャルな意味で、
用いられ始めた時、
それが指していたのはおおよそ、
デキシーランド・ジャズだったと
いってしまってかまわないだろう。
いつだったか、セカンドラインなんて
用語にちらりと触れた時、
たぶんここでも少し
書いたのではないかとも思うのだが、
このスタイルは。そもそもは、
アメリカ南部の
葬儀の慣習に由来している。
そんな背景もあるせいか、
基本このジャズというのは、
ロックやソウルよりも
むしろ一層強力に、
アメリカという国に
結びついている模様である。
そのせいなのか、このジャンルには、
なかなかイギリス出身の
著名といっていい
アーティストが見つかってこない。
不思議といえば不思議ではあるが、
当然といえば当然なのかもしれない。
まあ、僕が知らないだけ、という
可能性は否定できないのではあるが。
それでも、このシャカタクと、
それから次回取り上げる予定の
レヴェル42とが、
ようやく70年代も
ほとんど終わろうかという
時期になって初めて
シーンに登場してきて、
やがてアシッド・ジャズなる
ムーヴメントが生まれていく、
土壌の一つとなったのだとは
いえるのかもしれないなとも思う。
もっとも、前にまとめて紹介した
このアシッド・ジャズという述語は、
ジャズというよりはむしろ
ポピュラーの1ジャンルとでも
いった方がいい気がする。
ちなみに現在はこの手の音楽、
スムース・ジャズという
用語で括られているらしい。
わかりやすいジャズという意味では、
なるほどこのシャカタクなんかにも
極めて相応しい表現かもしれない。
さて、そろそろ本題である。
このシャカタクと、それから
次回紹介予定のレベル42の
やっていたことというのは
ある種モダン・ジャズからの
反動もあったのだろうとも
思われるのだけれど、
技術的には確固としたものを持ちつつも、
同時に、ある意味
極めてわかりやすい。
アドリブも皆無ではないが、
さほどアヴァンギャルドではなく、
むしろ印象的なモチーフの
きっちりとした反復が、
曲の全体を貫いて
展開されることが多く、
聴いていて安心で、心地好い。
そういう意味では、
かなり強力にポピュラーの方向へ
寄り添っていたともいえる。
次回予定のレベル42など
明確にヴォーカル主導へと
方向転換したことによってようやく、
市場的な成功を獲得している。
その辺りが、英米の聴衆の
性質の違いなのかなとも想像される。
このNight Birdsにも、
一応ヴォーカルは入ってくる。
Flying through the night
Floating on a wind――
しかし登場してくるのは
こんな感じの
本当に短いヴァースだけである。
ところが、これが非常に
効いているのである。
夜の鳥たちという、そもそもが
二律背反をはらんだ曲タイと、
洒脱なピアノの旋律とで開幕した
このトラックに、
中ほどになって不意に
この短い女声のコーラスが
登場してくることで
極めて効果的に
ある種のイメージが補強される。
街の灯りに誘われて、
ついつい眠ることも忘れ、
藍色の夜空を縦横に舞う鳥たち。
決して現実ではないその光景は
むしろ見事なファンタジーだと
いってしまっていいのだと思う。
そしてこのヴィジョンがまた、
サウンド自体の雰囲気と
見事に一致しているのである。
それでもやはり、この曲の主役が、
ピアノであることは決して揺るがない。
だからたぶん、この最小限の
ヴァースの導入によって、
時に抽象的であり過ぎるという、
まあいわば
インストゥルメンタル・トラックの
ほとんどが宿命的に抱え込んでしまう、
ある種の弱点を
巧妙に克服して見せたのが、
このシャカタクの
このNight Birdsだったのだと思う。
彼らの提示して見せた
この音楽の在り方が、
時期的にはやや前後するかもしれないが、
あの頃たぶん、高中正義さん辺りが
大きな注目を集めることにも一役買い、
やがてカシオペアや、
スクエア(後のT-スクエア)らの
登場を促し、
しかもあれほどの支持を集める
一つの背景になっていたのでは
ないだろうかとも思ったりもしないでもない。
実際高中さんのサウンドなど、
言葉など一切なくても夏だった。
上手くいえないけれど、
標題音楽的な考え方が、
ポピュラーへと移植されていく、
一つの形だったのではないかと思う。
まあ所詮個人的な感想ではあるのだが。
さてこのシャカタクと
似たような手触りの音楽が、
なかなか見つからないで
困っているんだけどな、という向きが、
もし今でもいらっしゃるようだったら、
ついでながらここで、
デヴィッド・ベノワなる
アメリカのジャズ・ピアニストの作品を
結構な自信を持って
おススメしておこうかと思う。
この方については、もちろん
アメリカに渡ったら
ちゃんとやるつもりではいるのだけれど、
ちょっと透明な爽やかさを維持しながら
個々のトラックの構成が
あまり変則的になり過ぎない辺りが、
このシャカタクの手触りと、
かなり共通しているはずだと思う。
それからたぶん、以前紹介した
ジャズマスターズ(♯60)の音楽にも、
ちょっとだけ通じるものがあるかと思う。
さて、ではここからは取りこぼし予定の
アーティストの幾つかに触れていく。
まず、このシャカタクと同時期に
イギリスから出てきた
インストゥルメンタルの
分野のアーティストに、
ペンギン・カフェ・オーケストラなる
グループがいる。
後年、グループ名を、
やや短くペンギン・カフェと
改めてもいるようだが、
僕が聴いたのは、
BROADCASTING FROM HOMEという
彼らの四作目に当たる一枚だった。
今回中身を確かめてみたところ、
なんだか一曲だけ、
あの坂本龍一さんが、
作曲に参加していたようでもある。
それで聴いたのかもしれないが、
お恥ずかしながら、
全然記憶に残っていない。
そういう訳で、この
ペンギン・カフェについてもやはり、
ここでのついでの御紹介のみ。
ちなみにこの名前を検索してみたら、
業平橋にあるという、
同名のカフェがまず最初に出てきました。
本当にペンギンがいるそうです。
しかも泳いでいるらしいです。
ちょっと行ってみたいかも。
それから、たぶん
この並びで名前を出して
大丈夫だろうとは思うのだが、
ジョー・ジャクソンなる
アーティストも
やはりきちんとは取り上げずに終わる。
この方もまた、今回のNight Birdsと
まさに同じ82年に、
Steppin’ Outという曲を、
ビルボードでトップ10に
送り込むヒットを放っていらっしゃる。
グローヴァー・ワシントンJr. 辺りと
近い音楽性のようにも思うのだけれど、
恐縮ながらやっぱりこちらも
Steppin’ Out一曲しか知らないので、
深入りは控えておくことにする。
それから、考えてみるとイギリスの
フィメール・ヴォーカルによる
トラックをここで扱うのが
実は今回が最後になるので、
些か苦しいことは、
百も承知なのだけれど、
その繋がりでさらに二組ほど
今回名前を出させておかせて
いただくことにしようと思う。
一つ目は、
スージー&ザ・バンシーズという。
いわゆるサイケデリックな、
パンク・バンドである。
昔ベスト盤一回聴いて
それきりになっていたのだが、
少し前(といっても相当だけれど)に、
ソフィア・コッポラが撮った
キルスティン・ダンストの
『マリー・アントワネット』で、
彼女たちの曲が使われていて、
いやあ、そういえば
この曲知ってるわ、と
なんだか一人で
盛り上がってしまった。
Hon Kong Gardenなるトラックで、
とりわけ前奏に
結構なインパクトがある曲である。
とはいえS.コッポラなので
画面と一緒に見ると、
全然それっぽいとはいえない。
むしろこの世界観に
なんでわざわざこの音楽
当てるかなあ、という感じ。
だってまあこの方、
18世紀フランスを舞台にした
この同じ映画に、
ニュー・オーダー選曲してますから。
だからまあ、そういう人なのである。
さらについでに触れておくと、この彼女、
『ロスト・イン・トランスレーション』
という作品で、
はっぴいえんどの
「風をあつめて」を取り上げて、
同曲に世界的な注目を集めさせた
張本人というか、仕掛け人である。
それからもう一組、昔聴いて、
扱おうかどうしようかと迷ったのは、
コクトー・ツインズなるバンドである。
やはりパンクの文脈から
登場してきたグループだったと
思うのだが、
むしろどんどんと、
アンビエント・ミュージックみたいな方向に
進んでいったのでは
なかったかと記憶している。
確かになかなかに、似ているものの
すぐには見つからない種類の
独特な音楽をやっていた。
ただ、長時間聴いていると
やや疲れてしまう種類の
サウンドだったようにも思うのだが。
そういう訳で、
CDを買いなおすまでには
結局至らなかったバンドである。
ええと、またずいぶん長くなったな。
では、今回のトリビアは、
上のはっぴいえんどの
くだりだったということで、
どうか御了承いただけますよう。
でもそういえば、
ソフィア・コッポラって、
最近はいったい
何を撮っているんだろう。
とんと名前を聞かなくなって
しまったような気もしますが。