季違いだけど、まあ仕方がないか。
Jazzmasters 1/Paul Hardcastle
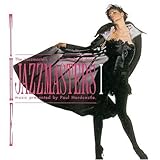
¥3,316
Amazon.co.jp
さて、アシッドあるいはスムース・ジャズと
呼ばれた一連のサウンド群の締めくくりは、
一応こちらの一枚である。91年の作品。
しかしながら厳密には、
このジャズマスターズの
サウンドについては、
アシッドという形容詞が冠されたことは
あまりなかったように記憶している。
少なくとも本国では、
例のG.ピーターソンを中心とした
当時の一連のクラブ・シーンの
ムーヴメントからは、
やや乖離した場所に
置かれたままだったはずである。
ただし、代表曲Blue Days辺りに
指示を集めた我が国の層というのは、
おそらくここまで数回にわたり扱ってきた
同系統のバンド/ユニット群と、
共通するエッセンスを、そのサウンドから
感じ取っていたのではないかとは思う。
さらにビルボードでは、
ワーキング・ウィークやTBNHと同様に、
このジャズマスターズも基本的には
ジャズ・チャートに分類されている。
その辺りのジャンル分けは、
結局のところ、根拠がよく
わからなかったりもするのだが、
いずれにせよ、
共通するテイストがあったことについては
たぶん間違ってはいないと思う。
さて、バンド名としてジャズマスターズと
名乗ってこそいるけれど、
このユニットの仕掛け人は、今となっては
知る人ぞ知るとなってしまった感もある、
ポール・ハードキャッスルなる人物である。
80年代を標榜したコンピレーションなどで、
19(nineteen)なる楽曲が収録されることがある。
85年の作品であり、これがおそらく
現在に至ってもなお、このハードキャッスルの
代表作の位置を占めるであろうトラックである。
シンセサイザーを駆使した
ある種無機的なバッキングに、
ヴォーカルではなく、
はたまた当時流行り始めたラップでもなく、
加工したニュース音声を載せるという
いわば破天荒なまでに
実験的だったこのトラックは、
発表直後から圧倒的に
市場の注目を集めることに成功する。
実際本国英国のシングル・チャートでは
なんと五週の長きにもわたって
トップ・ワンに君臨してもいるのである。
もっとも、内容が内容だけに、
アメリカでは20位に入るのが
やっとだったようではあるが。
それでもその席捲ぶりは
本当に大したもので、
チャート一位を獲得した国は
欧州を中心に計13にも昇る。
さらには我が国でも、
小林完吾さんの声による
日本語ヴァージョンが
制作されていたりもするのである。
じゅじゅじゅじゅ、
じゅうきゅう、じゅうきゅう。
真面目なアナウンスがダブで加工され、
こんな感じに聴こえてきたものである。
あ、なんか久し振りに
聴きたくなってきたな。
でもさすがにこれはカセットしかないなあ。
さてどこにしまってあることやら。
ちなみにこの小林完吾さんとは、
当時、日テレのいわばメインの
報道アナウンサーだった方である。
また、この19という数字、
ベトナム戦争に従軍した兵士の
平均年齢だったといわれているのだが、
その信憑性については、
多少の疑義がなくもないらしい。
しかしながら、その点に関する責めは、
作者のハードキャッスルではなく、
むしろ素材となったニュース番組を
作成した会社が負うべき種類のものであろう。
さて、しかしこれほどの
大ヒットに恵まれながらも、
このハードキャッスルは、
90年のSOUND SYNDICATEなる
アルバムを最後に
メジャーとの契約を
維持してもらうことが
できなくなってしまう。
もっとも85年以降は、そもそもが
自身のインディ・レーベルを立ち上げて、
ディストリビューションの契約だけを
結ぶという形を取っていた模様ではある。
いずれにせよ、そこで彼は、
国内外を問わず、
いわゆるメジャーとの契約獲得を
模索しなければならなくなってしまう。
そして、このJAZZMASTERSの前作に当たる
やはりKISS THE SKYという
ユニット名をそのまま冠した作品に、
まず手を上げた最初のメジャーが、
実は我が国の会社だったのである。
こちらのキス・ザ・スカイというのは、
ヴォーカリストにジャッキー・グラハムなる
黒人女性シンガーを起用したユニットで、
ジミ・ヘンドリックスの
Voodoo Chileのカヴァーなんかが
収録されていたりもして、
当時の日本のラジオのシーンで
目端の利くリスナーたちの
注目を集めることに
まずは十分な成功を収めた。
ちなみにこの作品は、後年アメリカでも
あのモータウンからリリースされている。
そして、この成果に喜んだハードキャッスルは、
次に考えていたこのジャズマスターズを、
同じ会社に預けることに決めるのである。
だから、このJAZZMASTERSという作品も
KISS THE SKYの場合と同様
アメリカでの発売に先行し、
日本でリリースされているのである。
そのため、日本盤の発売の時にはまだ
未発表だった曲が追加で収録されることとなり、
結果としてアメリカ盤の方が曲数が多いという、
当時としてはめずらしい事態となっている。
なお、こちらはモータウンではなかったが、
いずれにせよ、日本でのヒットを受け、
全米での発売が決まったような形であった。
しかも、さらにはこの作品が、
なんとビルボードのAORチャートで
一位を獲得するまでに至るのである。
たぶんAORで間違っていないはず。
ジャズだったかなあ、どっちだろう。
いずれにせよ、この頃はまだ、
スムース・ジャズなる分類の仕方は
ビルボードにはなかったと思う。
ちゃんとしたウラが取れなかったので、
曖昧になって大変申し訳ないのだけれど。
とにかく、以来このジャズマスターズは、
メンバーを入れ替えこそしながら、
昨14年までに、どうやら七枚の
オリジナル・アルバムを発表し、
存続し続けている模様である。
しかも08年にはビルボードで、その年の
ベスト・スムース・ジャズ・アーティストにも
選出されたりしているらしい。
さて、今回取り上げたこの
最初のアルバムの時点でのバンドの編成は、
ハードキャッスル本人以外に、
ヘレン・ロジャーズなる女性ヴォーカリストと
サックス/フルートを担当する
ゲイリー・バーナクルなるアーティストの
計三人となっていた。
このバーナクルのフルートが、
じわじわと効いてくるのである。
だから、彼がこの一枚で
ユニットを離れてしまったことは、
個人的にも非常に残念な事態だった。
Sound of Summerはこのデビュー盤の
オープニングを飾っていた、
つまりジャズマスターズの登場を
鮮明に刻印したトラックである。
独特の深みのあるサウンドを有した
シンセサイザーのパターンに、
まずフルートのラインが載っかってくる。
そして物憂げな歌が始まるのだけれど、
このヘレンというシンガーの声質が、
シャーデーを紹介した際にも確か、
そんなふうに形容したかもしれないが、
なんというか、
極めて木管楽器的なのである。
だからこそ、バーナクルのフルートと、
気持ちよいまでに絡み合ってくる。
プログラミングのドラムスのビートを、
バーナクルの生音がほどよく中和し、
(後半ではサックスも鳴らす)
さらにはヘレンのヴォーカルと相俟って、
なんともいえず気怠げな
夏の空気を醸し出してくれるのである。
いい曲であり、サウンドである。
ほか、前の方でまず触れたBlue Daysや、
三曲目のI Really Miss Your Love、
あるいはBody Heat辺りも佳曲。
バーナクルのソロをフィーチャーした
インストナンバー群も、アルバムに
ほどよい起伏をつけてくれている。
個人的にも、
大変オススメの一枚である。
今となっては、入手することも
なかなか難しいだろうなあとは
さすがに思いはするのだが、
もし万が一どこかで見つけたら、是非。
さて、ということでそろそろ
締めのトリビアのお時間なのだけれど、
実は今回のネタは
かつてここではこれ以上は
なかったくらいに
いわば自給自足である。
本記事では、いつもとちょっと違って
ライセンス契約の背景についてまで
やや踏み込んで記述している。
あるいはここまで、
多少首を捻られていた向きも
ひょっとするとあったかもしれない。
そもそもが、たぶんこんな経緯など、
公式にはどこを探しても
まずは出てこないはずなのである。
ジャミロクワイの八枚契約くらいになれば、
確かに記事になったりはするだろうが、
こちらは決して、さほど有名な話でもない。
では、何故そんなことまで書けるのか。
それはまあ、ある意味僕が、
当事者の一人だからである。
数字は書かないよう気をつけたから、
たぶん守秘義務みたいなものには、
抵触したりはしてはいないはず。
――では種明かしと行こう。
実は、このアルバムの日本盤、
僕がレコード会社時代に手がけた
数少ない仕事のうちの一枚なのである。
これをいってしまうと
会社が特定できてしまうから、
今まで公にしてはいなかったのだが、
まあ、もうだいたい知ってる人は
どうやらほぼわかっているらしいから。
そろそろいいかな、と思った次第。
でもだから、僕自身がある種公的に
これを認めるのは、
今回が初めてのことである。
洋楽と邦楽とでは
仕事のニュアンスが
かなり違いはするのだけれど、
一応担当ディレクターというやつでした。
だから、曲順やアルバム・タイトル、
ジャケットのディレクションなども
ほぼハードキャッスルから任せてもらって、
好きにやらせて頂いたものである。
つまり、上で起伏がどうとかいっている部分は、
ある意味ではこの上なく自画自賛なのである。
でも基本、音楽はハードキャッスルのものだから、
一概にはそうともいえないとも思うのだが。
どうだろう、だめだろうか。
まあ、という訳で、色々な場所に出ていく
各種のコピーなんかはもちろんのこと、
ロゴに使う英文も、辞書を引き引き
必死になって捻り出したものである。
結局は辞めてしまうくらいだから
この仕事も含め、やっぱり当時は
色々とあるにはあったのだけれど、
今となってはもうすべてが、
ただ懐かしいばかりである。
それどころか、こんな場面でちょっと
鼻を高くしながら話せるくらいの、
貴重な経験をさせて戴いたと思っている。
担当を離れることを電話で告げた際、
このポール・ハードキャッスルが、
自分が上司に掛け合ってやると
いってくれたことは今でも忘れない。
けれどそもそもが
異動は僕からの希望だったので、
もちろん説得して断ったのだけれど、
本当に残念がってくれたものである。
だから、彼がこのジャズマスターズを
今でも維持してくれていることについては
心底嬉しく感じている。
いつか挨拶したいなあ、とも思うしね。
そんな機会がはたしていつか、
この身に訪れてくれるのかどうかも
残念ながら僕にはまだ定かではないが。
ま、人にはそれぞれその人なりの
歴史があるのだということで。
それも、こと作家なんていう人種となれば
たぶんなおさらだろうと思います。
ちなみに先日この件を、
よくここで引き合いに出す、
別カドの編集長氏に
初めてカミング・アウトしたら、
まずは歩きながら一旦大きくのけぞって、
それからちょっと嬉しそうにしながら、
あれ、実はすげえ好きだったんですよ、と、
驚きつつとても喜んでくれました。
ちょっとどころか、
相当してやったりでした。
そういう訳で本作、個人的に
どうしたって比べられるものなど
今後も絶対に
有り得ないだろう一枚なのである。
あの縦長の外盤のパッケージも
外箱のまま、ちゃんと未開封で
大事にしまって取ってある。
今回だから、この原稿を書くために、
この作品をずっと聴いてたんですけどね。
やっぱりいろいろと複雑なもので
なかなかプレイヤーには
載せらずにいたんですよ、正直なところ。
でもやっぱり、いい一枚だと思います。
この音楽が好きだったから、
あの頃もちゃんと頑張れた。
だからこそ結果に繋がったんじゃないか。
まあ、そんなふうに思ってしまいます。
いや、思わず遠い目になってしまうな。
という訳で、とりわけまた、
そう簡単には使いどころの
見つかりそうには決してない、
無駄な豆知識でありました。
今回はさらにもうちょっとだけ、
脱線というか、
遊ばせて戴こうかと思います。
本記事の冒頭の二行目のいい回しで、
うっかりちょっとでも
にやりとしてしまった皆様には、
大変申し訳ないのですが、
諦めて本記事に
いいね、をおいていって下さいますよう
慎んでお願いいたします。
簡単です。
そこの右下の笑ってるとこのやつを
ちょいとクリックするだけです。
たぶんうちのA嬢には、
なんのことやら
さっぱりだったのではないかと思います。
でも元ネタのわかる方は
たぶんこの中には、ひょっとして、
少なくなくいらっしゃるかもしれません。
だから、数字がいつもより多かったら、
あ、やっぱり年齢層高いんだ、とか、
一人で受ける予定ですので、
僕の楽しみのために是非、よろしく。