今回から少しの間、あの頃おおまかに
アシッド・ジャズと呼ばれていた
ムーヴメントの中から紹介していく。
まずは、このワーキング・ウィークである。
紹介は89年発表のコンピレーション、
初期の三枚のアルバムからの
ピックアップによるベスト盤である。
Payday (Highlights Coll)/Working Week
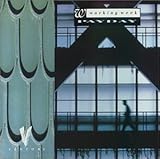
¥1,739
Amazon.co.jp
アシッドとは、酸化したといったような意味。
だからたぶん、ジャズが少し時代を経て
発酵するとどういうふうになるか、
みたいなニュアンスだったのだろうと思う。
もちろん、厳密には酸化と発酵とは
少なからず違うのだけれど。
そしておそらく、
このバンドの中心人物だった
ギタリストのサイモン・ブースが、
極めて早い時期に、この
アシッド・ジャズなる用語を
使い始めたうちの一人で
あることはほぼ間違いがないのである。
あるいは今では、この表現は、
あのジャミロクワイを見出した
レーベルの名称としての方が
むしろ一般的であるかもしれないけれど。
さて、当時このムーヴメントを
支えていたのは、
イギリスのクラブ・シーンである。
ヴォーカリストやギタリストではなく
DJという立ち位置の人物が、
ユニットの中心的存在として、
機能し始めるその萌芽は
おそらくこの時期にある。
たぶん一般的には、追って紹介する
ソウルⅡソウルの、ジャジーBが、
こういう在り方の認知度を
一気に高めたのではないかとも思う。
バンドはパーマネントなのだが、
トラックによって、その雰囲気に適した
異なるヴォーカリストを
採用していくというスタイルは、
ひょっとしてこの人たちが
最初だったのかもしれないな、とも思う。
もっともカウンシルのポール・ウェラーも、
実はアルバムCAFÉ BLEUにおいて
同じアプローチを試みているのだが、
時期的にどちらが早かったのかは微妙なところ。
しかも両グループとも、
ゲスト・ヴォーカリストとして起用したのが、
幾度かここで取り上げているEBTGの
トレイシー・ソーンだったりするのである。
まあしかし、それも実は当然のことで、
このワーキング・ウィークなるバンドの
いわば前身であるともいえる、
ウィークエンドというグループがあって、
これがある意味で、このジャンルの
パイオニアの一つだったのである。
ウィークエンドの活動期間は
82~83年だったから、
あるいはウェラーによるスタカンの発想も、
実は彼らの影響下にあったのかもしれない。
バグルズ以降の、テクノポップの隆盛に対する
一つの反動であったことは間違いがないだろう。
そのアプローチを極端に、
ジャズファンク/ラテンの方向へと寄せたのが、
このワーキング・ウィークというバンドだった。
しかし、バンド名が週の労働時間で、
ベスト盤につけたタイトルが給料日である。
この辺がだから、それこそウェラーや、
ブロモンのDr.ロバートの批判性を
否応なく思い出させてもくるのである。
音楽にも、ちょっとだけだが、
そんな小難しさが出ていないでもない。
さて、今回御紹介のWho’s Fooling Who?は
そんな彼らの作品の中でも、めずらしく
顕著にポップに寄り添ってくれている楽曲である。
どことなくハリウッド・ミュージカルにでも
出てきそうな印象もあるメロディー・ラインが
彼らのスタイルによって適度に昇華された
まるでビッグ・バンドみたいにスウィンギーな
アレンジの全体と、ほどよい調和を見せている。
初出はデビュー・アルバムだった。
個人的にはだからこれが、
彼らのベスト・トラックである。
ほか、ゴスペルを思い起こさせるような
旋律が非常に美しいDoctorなる曲や、
あるいは冒頭からムーディーなサックスが
響いてくるFriends(Touche Pas Mon Pote)
辺りが佳曲であるかと思われる。
いわば初期キャリアの総決算ともいうべき
この一枚の後に登場してきた、
FIRE IN THE MOUNTAINなる四枚目も
一応手元にはあるのだが、
残念ながらこちらは、あまり頻繁に
プレイヤーに載せることはない。
ヴォーカリストを変えながら、
バンドの個性を出そうというアプローチが
やや行き詰ってしまった感があるのである。
変化をつけようとこそしているのだけれど、
それがかえって一本調子になって、
しかもさらには、フックになるトラックが
どうにも聴こえてこないのである。
バンドはさらにもう一枚、
91年にBLACK AND GOLDなる
アルバムを発表しているらしいのだが、
この作品を最後に解散、
あるいは自然消滅してしまう。
その後、サイモン・ブースは、
クレジットを本名の
サイモン・エマーソンへと改めて
アフロ・ケルト・サウンド・システムなる
バンドに加わり、活動の軸足を
ワールド・ミュージックのジャンルへと
すっかり移してしまっている模様である。
このバンドは、あのピーター・ガブリエルの
リアル・レコードから
五枚ものアルバムをリリースしており、
うち一枚は、その狭いジャンルのうちでの
ことではあるけれど、一応はグラミーに
ノミネートされたりもしている様子だから、
どうやら彼も健在ではあるらしい。
僕自身はこのバンドの作品は未聴。
だが名前の通り、ケルト・ミュージックと
アフロ・ビートの融合を
目指しているのだそうである。
いやはや、本当に不思議な
フロンティアへの立ち方をする人である。
さて、では締めのトリビアである。
今回のPAY DAYにも収録されている
Vanceremos―We Will Winという曲が
たぶんまず最初に、このバンドに
シーンの注目を集めることに
成功したトラックである。
そしてここで聴こえているのが、
上で言及した
トレイシー・ソーンの声なのである。
実はあのSOSのコリーンも、
デビュー前に一度かあるいはほんの数回、
彼らとのセッションに参加しているらしいのだが
こちらの音源は残念ながら未聴。
ただ、彼女たちがその後展開した
音楽性を鑑みると、なんとなく
この組み合わせが十分に
頷けてくることもまた事実である。
なお、Vanceremosとはスペイン語で、
曲のサブタイトルにもある通り、
我々は打ち勝つ、といったような意味。
元々はチェ・ゲバラが戦場で叫んだ言葉で、
同国の左翼政治集団の名称にも
採用されていたそう。
ま、だからこの辺にも、
バンド名のチョイスと通じるニュアンスが
少なからずあったりするのである。