76年のアルバム、
NIGHT ON THE TOWNから。
Night on the Town/Rod Stewart
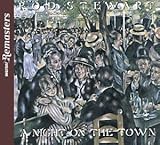
¥1,640
Amazon.co.jp
本編で取り上げた(ブログラジオ ♯41)
Maggie Mayのヒットの後、
さらに二枚のアルバムをマーキュリーから
リリースしたロッドは、
フェイセズからの正式な脱退(あるいは空中分解)
なんて事態をどうにか乗り越え、
年来の希望だったワーナーへの移籍を果たし、
同時に基本的な活動拠点をアメリカへと移す。
この経緯を経て発売された最初の作品が
名盤ATLANTIC CROSSING(’75)である。
大西洋を渡る。そのまんまである。
ジャケットも、巨人もかくやともいうべき
サイズのロッドが、今まさに片脚を
ニューヨークの地に踏み下ろそうかといった
イラストで飾られていたりする。
そして同アルバムには、
あのSailingが収録されているのである。
70年代にラジオを聴いていた方なら、
当時どれほど頻繁にこのトラックが
オン・エアされていたかについては、
甦ってくる記憶もあるのではないかと思う。
何せ、欧米での最初のリリース時に、
たぶんまだ10歳にもならなかった僕が
鮮明に覚えているくらいなのである。
まあひょっとすると、こと我が国では
同曲がTVCFに起用されるなどの
何がしかのきっかけがあって
幾度か繰り返し注目を集めていたりもするので、
その辺り、僕自身の記憶が
混乱している可能性もなくはないが。
で、アメリカに渡ったロッドがまず
やったことは何かというと、
マッスル・ショールズなるスタジオでの
レコーディングだったのである。
このマッスル・ショールズというのは
アメリカはアラバマ州にある都市の名で、
メンフィスと並ぶ、ソウル/R&Bの
聖地として知られている。
オーティス・レディングや
アレサ・フランクリン辺りが
この地で数多の作品を録音しているし、
ほか60~70年代にかけての数々のヒット曲が、
同地のスタジオから生まれているらしい。
ちなみにストーンズのBrown Sugarと
Wild Horsesも、この地にある二つの
著名なレコーディング・スタジオのうちの
一つで録音されたものである。
本年たぶんこっちのスタジオの来歴を描いた
映像作品が実は日本でも公開されている。
邦題を『黄金のメロディー
マッスル・ショールズ』という。
どうやらドキュメンタリー映画のようで
ミックやボノも登場してくるというから
是非観にいこうと思っていたのだけれど、
単館で、しかも上映回数も少なく、
どうしようかな、と思っているうち
気がつけば終わってしまっていた。
という訳で現在ソフト化待ちである。
で、どうしてこのスタジオの話を
長々としたかというと、
今回のThe First Cut is the Deepestもまた、
このスタジオで録音された音源なのである。
さて、アルバムNIGHT ON THE TOWNは
ATLANTIC CROSSINGの翌年の発表で、
全編は主にハリウッド近郊で制作されている。
だから、トラックの着手や完成の順序が
多少前後したのかもしれないとも想像できる。
いずれにせよ、たぶんこの二枚はある種
双子みたいな作品なのではないかと思っている。
ただ、アルバムの出来としては、
個人的にはこっちの方が好きである。
そもそもオープニングのTonight’s the Night
(Gonna be Alright)からして、
全米で七週だか八週だかトップ・ワンに
君臨し続けたという化け物みたいな曲である。
FAST HALFと名づけられた後半に登場する、
Big Bayouのブルーグラスっぽい
ヴァイオリンの導入など、
ロッドの声にまさにはまっている感じがするし、
クロージングのTrade Windもいい出来である。
だがとにかく何よりもこのアルバム、
Tonight’s ~から始まるA面
(クレジットに依ればSLOW HALF)収録の
全四曲が四曲とも、それこそ全編
クライマックスみたいなものなのである。
四曲目のKilling of Georgie(PARTⅠ&Ⅱ)なる
トラックの構成など、本当に唸る。
友人で、ゲイだったジョージイという名の若者が、
ニューヨークへ出て、そこで居場所を見つけ出し、
けれど喧嘩沙汰に巻き込まれて殺されてしまう。
ロッドはある意味では淡々と、
この彼の物語を、メロディーに載せて紡ぎ出す。
後半で、命まで取るつもりはなかったんだと、
加害者が弁明しているくだりにのみ、
かすかな怒りがにじみ出て聴こえてくる。
そのまま曲は終盤に入り、語り手はふと
生前のジョージイの言葉を思い出す。
待ったり躊躇ったりしてちゃだめなんだ。(中略)
だって目の前のチャンスがもう一度来るなんて
誰にもわからないんだからさ。
そしてこの一節を綴り終えた直後に、
曲そのものが一変するのである。
楽器やコーラスの編成こそ同じままだが、
リズムもテンポもアプローチも、
それまでとはまったく違うものへと姿を変える。
しかも、ここに至って初めて、
ロッドのヴォーカルは
語り手がジョージイの死を
途方もなく悲しんでいることを
ようやく明らかにするのである。
抑えてきたものがどうしようもなく
爆発してしまうこの感じ。
普通のポピュラーソングで表現できている
ほかの例を、僕は寡聞にして耳にしたことがない。
PARTⅡのこの箇所が、ビートルズ時代の
レノンの作品Don’t Let Me Downに
些か似過ぎてしまっているのは、
まあご愛嬌というものであろう。
ロッドのようなポジションの人が
同曲を知らなかったはずもないから、
わかってやったか、諦めたかのどちらかである。
まあ、曲作りのあまり得意でない
(とはいいながら、とりわけこの時期の
レコーディング作品は、共作も含め
自作曲の割合が多く、しかも佳曲が多い)
ロッドにしてみれば、
この感情の爆発を的確に表現するのに、
どうしてもこの旋律しか出てこなかったのだろう。
そう思うことにしている。
そういう名曲ぞろいの一枚ではあるのだけれど、
フェイヴァリットを選ぶとなると、僕としては
今回のThe First Cut ~になるのである。
むしろ、ロッドの全キャリアの中で、
Maggie Mayかこれか、どちらか迷う。
そういうレベルで好きである。
あとはTom Traubert’s Bluesが上位に
入ってくるかな、それに上のGeorgieも。
You Wear it Wellなんてのも、
結構好きだったりするなあ。
それに、最初の頃に取り上げた
In My Lifeもやっぱ忘れちゃいけないし。
あ、やっぱりキリがなくなってくるな。
だから本当、名曲が多いんです、この方。
さて、このThe First Cut is the Deepestは
残念ながらロッドのオリジナルではない。
英国のキャット・スティーヴンスなる
アーティストの作品である。
同曲は幾度かカヴァーされていて、
しかもそのうちロッドのものを含めた四曲が、
たとえばカナダのアーティストのヴァージョンが
本国でトップワンを獲得したりと、
どれも大ヒットを記録しているのである。
楽曲のすごさが自ずとうかがわれて
こようというものである。
なお、本邦ではロッドのヴァージョンにのみ
『さみしき丘』という邦題がつけられている。
これも実はなかなか好きである
もっとも、どこから丘が出てきたのかは、
イマイチよくわからないのだが。
ハープシコードの特徴的なイントロから、
アコースティック・ギターの
ストローク・プレイへ。
その上に載ったヴォーカルの後を
そっと追いかけるようにして、
いつのまにかベースが鳴っている。
こういう盛り上げ方が、
やはりセンスを感じさせる。
他の作者の手になる楽曲が、たちまち
彼独自のものとなってしまう所以であろう。
The First Cut is the Deepest。
――最初の傷が一番深いんだ。
タイトルだけでおおよそのところは
お察しいただけるだろうかと思うが、
初恋に裏切られることを綴った歌である。
ただし、ロッドあるいは話者は
実は傷つけた方の側である。
ちゃんと聴くと、あんまり格好のいい
ポジションにはいない。
どこか言い訳めいているし、未練がましい。
それがでも、全然みっともなく
聴こえてこないところが不思議なのである。
SheとYouがちょっとややこしいけれど、
三人称の方はおそらく、
一夜限りの相手のことだろう。
開きなおりでは決してないし、
むしろそれを悔いている。
だけどたぶん、もうどうすることもできない。
このサビのフレーズが、そして
トラック全体が閉じ込めようとしているのは、
たぶんそういう感情である。
だからこういうある種の、行き場のない
アンビヴァレンスみたいなものを
取り上げさせると、
このロッド・ステュワートという人は
本当にずば抜けて上手いのである。
いやしかし、同じアルバムの収録だからと
一度にまとめて扱ってみたんだけれど、
今回の二曲はきちんと二回に分け
別々に取り上げるべきだった。
自分でも重々そう思っております。
だから、本当はもうちょっとだけ
書くつもりのことがあったのだけれど、
また機会を改めることに致します。
こと今回は、皆様長文へのおつきあい、
まことにどうもありがとうございました。