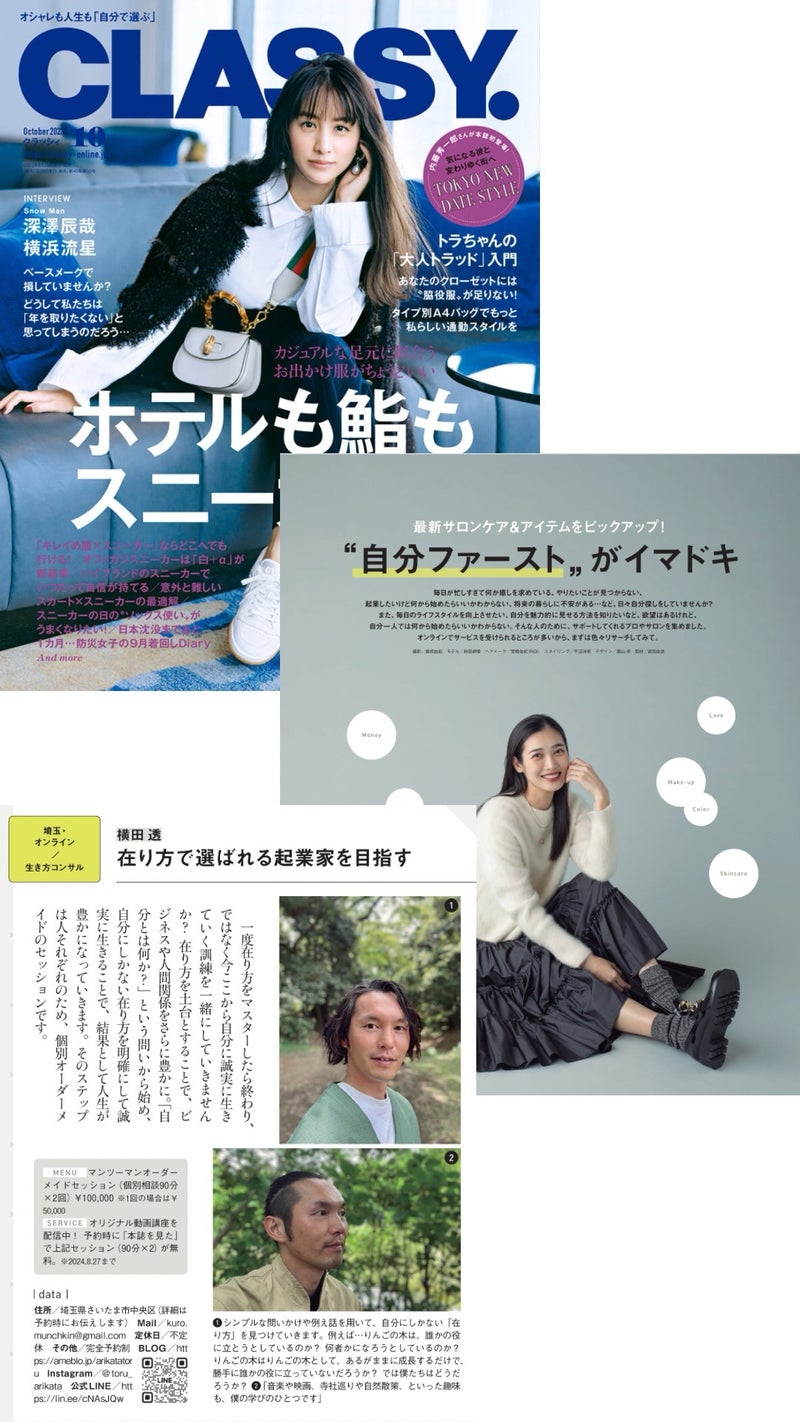はじめましての方は
こちらを読んで頂けると嬉しいです。
↓↓↓
横田透って誰ですか?
僕の個人的な人生ストーリーは
↓↓↓
【総集編】横田透の人生ストーリー
もっと詳しく知りたくなってきた方は
↓↓↓
多様性の時代をどう生きるか?
結論から言えば、、、
「答えのない問いかけを生きる。」
これからの時代、
大事なのはこれだ。
そして、
矛盾しているように聞こえるだろうが、
これは答えであって答えではない。
答えのない問いかけそのものに
意味はないからだ。
だから答えにはなり得ないが、
答えのない問いかけを通して
意見の違いを認めうことは
間違いなく求められてくる。
そういう話だ。
ちなみに、「自分らしさ」という言葉さえ
ただの「答え」でしかない。
だから、「自分らしさ」など不要だとさえ言える。
この考え方の基本には
「空思想」も含まれるが、
今日話していくのはそこじゃない。
多様性の時代、
「自分らしさ」という「答え」を
求めてしまうのはなぜなのか?
実はここに僕たちの闇が隠れている。
①質問恐怖症の大人たち
僕たち日本人ほど
人から質問されることを嫌う民族は
いないのではないか?
と僕は思うことがある。
あなたはどうだろうか?
僕は小さい頃から
疑問に思ったことは数知れず、
疑問に疑問を重ね今に至る。
今だとSNSを通して
人の発言にリプライをしにいく。
そこで質問をすることが
ほとんどなのだが、
多くの人が
「最初」から
僕の質問に答えることができない。
これはなぜなのか?
これは間違いなく
僕たちが受けてきた教育、
そして、
僕たちが住んでいる日本という国柄
これが関係してるのではないか?と僕は思う。
まず国柄について話していこう。
一体いつの時代からなのだろうか?
慮る(おもんばかる)というか
察するというか
思いやりや
おもてなしというか
こういった他者への気遣いや気配りというのが
美徳とされているのが
我が国日本なのではないだろうか?
日本の文化的にも
日本人の所作ひとつとってみても
そこには心が宿るようになっていたりする。
例えば
箸置き。
これは食事をいただく際に
食材への感謝と共に、
五感覚で味わうために
一度箸を置いて
よく味わうためのモノである。
食材に対しても
敬意というか
思いやりというか
そういう心を持てるのが僕たち日本人のはずだ。
他には
「間」への感覚。
特に、
誰がどこに座ったらいいか?などをはじめ
空間ひとつとっても
上座下座とあるように
どこがどうでと
事細かく心配りをするように
僕たちは教育されてきている。
客間とか
床の間
茶の間
空間に対してさえ
心を配るのが僕たち日本人なのだ。
これは他国では
なかなか見受け難い文化の一つではなかろうか?
しかしこの心配りが近年違った方向へと変化してきている。
どういうことかというと
心配りというよりは
「人の目を気にする」という言葉で表されるような
「他人からどうみられるか?」を
極端に気にしているということだ。
先ほどのような率先した心配りではなく、
後発的な、
それも危険を避けるかのように
他人の目を気にしてしまう。
自発的心配りから
他発的心配りとでも言おうか。
変化しているわけだ。
このことから何が起きているか?というと・・・・・
「忖度」
相手を推しはかるという言葉ではあるが、
どうも「他者からどう見られるか?」が先に来ている意味での
「忖度」とはなっていないだろうか?という話だ。
それこそ国会での答弁の席などがいい例だが
忖度を口実に
自分の意見を話さない大人たちが増えてきているのだ。
何を聞かれても
同じようにしか返答しない、
なんて光景はよく見られる話だ。
何もこれは国会の話だけではない。
会社や学校、
SNSにせよ
家族も含め
人が集まる場において
自分の意見を伝える大人たちがほとんどいない、
とお分かりだろうか?
何を聞かれたとしても
聞かれなかったとしても
当たり障りのない言葉でしか返答しない
そんな大人たちが増えているのだ。
心配りと忖度がごちゃ混ぜになっているにも関わらず
そのくせ
「これが自分らしさだ!」などといって
あたかも自由奔放かのように
自分勝手にことをやり過ごす大人たちが
圧倒的に増えているわけだが・・・・・・・
実はこれは仕方のないことでもあるのだ。
先ほど話したもう一つの観点。
僕たちが受けてきた教育についてここで話を深めていこう。
僕たち日本人が受けてきた教育が
いつ頃から今の形になったのか?
ここを考えることが大事な要素だ。
心配りと忖度がごちゃまぜになり
なぜここまで他人の目が気になるようになってしまったのか?
ここには日本の敗戦が大きく影響している。
というのも、
戦後教育そのものが大きく変化したからである。
この話については超重要な内容がたくさんあるので
また別の機会に話すが、
要点だけをまとめるとこうなる。
「日本人の大和魂を封じて
某国の犬になってもらうための
教育へ変化した」
とだけ言っておこう。
もちろん僕の個人的な意見ではあるが、
よく歴史を考えていくと
わかることはたくさんある。
他国からの目線で言えば、
「また日本が軍事力を身につけて
進軍されてもらっては困る。」
ということでもある。
そのためには
「犬の牙を抜いたらいい。」
こういうことだ。
でこれがどう転じたか?だが、
要は教育というものが
「自分たちの頭で考えて進めていくもの」
から
「言われたことに適応していくもの」
へと移り変わった、ということだ。
もっと嫌な表現をすれば、
「賢くなってもらっては困る」
(ここでいう賢さとは、
お勉強ができるという意味での賢さではなく、
世の理(ことわり)をはじめ
物事を見抜くような知恵を身につけてもらっては困るという話だ。)
「考えるな行動しろ」
「言われたことを言われた通りに行え」
「正解通りに行わなければならない」
とかく
国や社会、組織、集団が作り上げた「答え」通りに生きてもらわなければ困るという。
そういう教育になっていったわけである。
だから、戦後の日本では、デモも当然起こるようになるわけだ。
学生たちがデモ行ったのはなぜなのか?
ここにも日本の教育の闇がある。
別な面で見れば、
70年第80年代と
それこそ尾崎豊の歌にもあるような
ガラス窓を割るような学生たちが生まれたのも、
「学生」とはこうあるべきだ
という縛り付け
忖度から作られたと考えれば分かりやすい。
そして今、
尾崎世代の大人たちが親となり祖父母となり子育てをしているからこそ
人の目を気にしてしまうからこそ
「自己肯定感」という言葉が急速に広まったわけでもある。
他人の目から自分を防衛するための方法として、
同じ価値観同士で関わるという
そういった者たちも増えているのも頷けることかと思う。
だからこそ何が起きてしまうか?というと
何かを聞かれた時
何かを話す時でさえ
常に相手の顔色を窺う僕たちになっているのだ。
だから質問されれば即時
「答え」が自分の中に思い浮かび
「答え」に縛られる。
その答えというのもたくさんの答えとなるものがあるのだが
原則的に「自分を守る」必要があると感じやすい。
質問されるということは、
自分が間違っている、
不正解だから質問されるのだ、と
これまでの教育から脳にインプットされているからだ。
実際、
テレビやYoutubeなどを見たとしても
どんな番組でも正解が良いこと、不正解が悪いこと、として扱われるので、
質問に答えること自体に間違ってはいけないという思い込みが自動的に働いてしまうのだ。
実際、
心理学や脳科学、
起業家としてのマインドセットや
コーチング、カウンセリングをはじめ
何かしら人の心について学んだことがある人ほど、
驚くほどに質問に対して自分の意見で答えない。
当たり障りのない、どこかの誰かが言った言葉を、あたかも自分の答えのようにして話す。
本人たちは人の心について学んだつもりではあるが、
実は自分のことを何も知らないことさえ気づかない。
なぜなら
自分は学んできたという「答え」を
握りしめることで安心しきっているからだ。
だからこそ、質問された時に、
この安心を壊されるのが嫌だと、
勝手に思い込むのだ。
その結果、質問を攻撃と解釈する。
人の心がなんだと学び、
思考は現実化するとか、
目の前の現実は全て自分の潜在意識が作り出してるとか
自分軸だ自己肯定感だと
学んでいるにも関わらず、
質問が来た瞬間
相手を加害者として、
自分は被害者になる。
自分軸と言いながら
その瞬間に他人軸となるという
なんともおかしなことが起きてしまうのだ。
それくらいにまで
僕たちは他人の目を恐れ、
そして質問されることをも恐れているのだ。
その原因にあるのが・・・
②答えを握りしめる安心感
そう、答えを握りしめているという安心感だ。
先ほどから話している通り、
僕たちが受けてきた教育により
「答え」を最優先してしまうように
僕たちはプログラムされてしまっている。
例えば、
「6+6=12」と正解でなければならない、と
自動的に思い込んでしまっているのだ。
6+6=11ではなぜいけないのか?
誰もそんなことを考えないまま、
大人になっているのだ。
そんなふうにして大人になってしまった僕たちだからこそ
常に新しい答えはないか?と探し回る。
起業家話でよくあるのが
成功している人ほど新しいものをどんどん入れて
古いものを捨てている
というような話。
一見答えを手放していっているかのように見えるが、
答えを半永久的に追い求めているに過ぎない。
「答え依存症」というようなものだ。
答え依存症はどこから来るのか?
その一つが
「普通」
「みんな同じ」
という「錯覚」だ。
それこそ成功したいのなら成功者と同じことをしなさい、というのも
成功者と同じことが答えであり、
それが安心をもたらしてくれるからでしかない。
逆に言えば、
僕たちは
「違い」や
「異物」を
とことん嫌うようにさえなっている。
例えばの話だ。
自分の意見と違う人がいたとしよう。
自分の意見と違うことは
あなたの意見を
批判・否定・攻撃してることになるのか?
ここだ。
冷静に考えてみれば
そんなことはないとわかるはずだが、
これがSNSであったり
仕事、家族、子供相手だったらどうだろうか?
瞬間的に、
自動反応的に
批判・否定・攻撃と思ってしまうのではないだろうか?
ここが厄介なところだ。
なぜ意見が違うことを、
批判・否定・攻撃と思ってしまうのか?
それも瞬間的に自動的に。
ここで出て来るのが
僕たちの「答え」に対する「執着」だ。
別な表現で言うならば
答えにしがみついている
答えに対するこだわり
固定観念、思い込みなどだ。
僕たちはどうしても
これまでの人生経験から
答えを捨て去ることが難しい生き物になってしまった。
戦後数十年の時を経て
僕たちは祖父母の世代からして
「答え」を重んじて生きるように
プログラムされてしまっているからだ、
というのは先ほども話した。
それでも答えに執着してしまうのはなぜだろうか?
ここには
欲求を満たすことに対する自動反応がある。
僕たちが戦後受け続けた教育のべつな側面には
「人が人を欲求で支配する」という構図がある。
皮肉っていうならば
「ギブミーチョコレート」が
今や
「ギブミーいいね!」となっているに過ぎない。
というのも、
僕たちは豊かを感じる心を失ってしまったのだ。
いやいや、もう日本は戦後復興して豊かじゃないか?と思うだろうが、
今の僕たちが感じている豊かさに問題があるのだ。
僕たちが感じるであろう豊かさの定義とは何か?
先ほどの「ギブミーチョコレート」でいうなら「チョコ」が豊かさだ。
それにならうなら「いいね!」も豊かさである。
そう、僕たちがことごとく欲求の奴隷だと勘のいい人なら気づけるだろう。
承認欲求にせよ、
食欲、性欲、睡眠欲をはじめとした三代欲求も然り
マズローで言うところの承認欲求までを満たすことが豊かさだと
すっかり刷り込まれてしまっているのだ。
そして、残念なことに、
自己実現はやりたいことをやること、
理想の人生を生きること、
自分らしく生きることだという、
誤った考え方がコーチングによって広まったことで、
ほとんどの大人たちが自己実現を勘違いさえするようになった。
厳密によく観察すれば、
やりたいことをやること、
理想の人生を生きること、
自分らしく生きることは、
自分が自分を認める承認欲求でしかない、
と誰でもわかるはずなのだが・・・・・。
それも仕方ないのだ。
美味しい物を食べること。
欲しい物を手に入れること。
自分が幸せだと感じること。
誰かに認められること。
あげたらキリがないが、
豊かさを求めるのが自分の心の中ではなく
他者、モノへと向かうようになっているからだ。
「自分らしさ」というのも
厳密にみれば自分の中にはないことが、
自己理解を深めればよくわかる。
なんならブッダさんは自我はないとさえ教えてくれている。
それでも「自分」
そして「豊かさ」に
しがみついてしまうのはなぜか?
僕たちは自分が貧しいことを知っているからだ。
ここに問題が起こる。
分かりにくいかもしれないが、
豊かさを求め続けるということは、
今貧しいと自分で知っているということだ。
本当に心の底から豊かさを感じることができているのなら、
質問に対して恐怖する必要もないし、
自分らしく生きる必要もない、
答えさえ必要がないのだ。
安心もいらない、
何もいらない。
何もなかったとしても
豊かと感じる心が
本当に豊かであるということだ。
僕たちが思い描く豊かさが幻でしかないと
お分かりいただけるだろうか?
それでも豊かになりたいと欲にしがみつき執着してしまうのが僕たち人という生き物なのだ。
ここには「豊かになることが人生の幸せ」という「間違った」「答え」が僕たちに刷り込まれていることは、もういうまでもないだろう。
だからこそなのだ、質問することが大事になってくるのだ。
「これは本当なのか?」
「どうして?」
「なぜ?」
「どういうことなのか?」
にはじまる「問いかけ」だ。
③質問は対話のきっかけでしかない
「質問」
すなわち
「問いかけ」というのは
今ある自分の思考や感覚、心を
見出すためのきっかけでしかない。
ここまでの話を踏まえれば、
質問があなたを批判・否定・攻撃するモノではないことは
十分にお分かりいただけるかと思う。
僕たちがすっかり染まってしまってる
「今ある自分」「自分らしさ」
ここを問いかけていかなくては、
僕たちはずっと「欲求の奴隷」として「機械的」に生きていくこととなる。
もちろんそう生きてみてもいい。
質問、答えのない問いかけが目指すのは、
答えではないからだ。
今ここにおいてお互いに意見を交わし合い、
考えることに、答えのない問いかけの意義がある。
これがどういうことかを理解するためには
僕たちが日頃どのようにして人と話をしているのか?
知る必要がある。
今から話していくことは
人の話の聞き方の真実ではあるが、
この真実は頭で理解したところで意味はない。
実生活の中で、
あなたの会話を振り返り観察することで、
この話と一致しているのか?どうか?確かめて欲しい。
これを知識として、答えと知ったところで、人生における価値はゼロだ。
大事なのは、
このことを確かめた上で、
どう生きるか?という答えのない問いかけの先にある。
僕たちがどう話を聞いてるのか?と言うと、
近年よく言われる言葉で言うなら、「認知バイアス」を通して聞いている。
僕はこれを自分の都合のいいものの見方とも表現することはあるが、
この図のように膜というか、卵のようなものに包まれているといったん思ってもらおう。
この卵がなんでできてるかというと
僕たちの意識だ。
それこそ潜在意識的な話含め、思い込みや価値観といったもの。
シンプルに言えば、頭の働き全て。言語活動全般。
そして、僕たちの体に五感覚というものが備わっている。
さらに奥に心と呼ばれる領域があって、感情は心の代謝として起こる。
(補足しておくが、感情は基本的に心の代謝だが、頭で心を騙すことが可能だ。というか現代の僕たちはほとんどの場合、頭が心を騙して作り出した感情と、心の代謝からくる感情の区別がつかない。何言ってるのかわからないと思うが、感情に対していい悪いと思ってるとすればその働きは頭だ。僕たちは頭で生きることを教育され続けてきたため、心がどうあるか?を知らなさすぎる。僕たちは、自分の本当の感情を知らない、とあえて言おう。本当の感情を知るためには、頭が心を騙していることに気づかなくてはならない。これも知識ではダメだ。自分という生命をよく観察して初めて見えるかどうか?というレベルだ。本来の自己理解とはこういうものだが、頭で自分を理解したほうが楽だし、答えにして依存して安心できるから、そういう自己理解が今流行ってるが、その弊害で、誰も感情を理解できなくなっていると、お伝えしておこう)
この卵の中にあるものが全て自分だ。
誰かと話をする時、
相手にも同じく卵が存在する。
そして、
卵と卵が触れるか触れないかのぎりぎりのところに言葉が存在する。
本来こういう構図になっているはずなのだが。
僕たちは言葉と卵の区別ができないのだ。
相手が言った言葉に対して、
自分の卵の中にあることを
それが相手だとしてしまう。
これはこれまでの僕たちが受けてきた教育上、
仕方のないこと。
だって人の心について真摯に話す教育を受けてきてないのだから。
知識で人の心は理解できないと、誰もがわからなくなっているのは、
親からも、学校でも、社会でも、どこにいっても心の教育を受けていないからだ。
人の心を理解するためには、
人の構造を理解しなければならないのに、
人の欲求を理解することが
人を理解することだという
誤った答えが広まってしまっているのも、
僕たちがどれだけ欲に支配されているか?を象徴している。
今回散々挙げている例で言えば、
質問が来たということを攻撃と捉えるのはどこだろうか?
自分の卵だ。
でも、自分の卵の中で起きたことを、相手だと言ってしまうのもまた僕たちなのだ。
僕たちは普段、言葉を通して話をしているかのように錯覚するが、
厳密には自分の卵の話しかしてないのだ。
だからこそ質問していかなくては何も分かりようがないのに、
僕たちの中には質問に対する恐怖が埋め込まれている。
それでもやはり僕たちは
質問しあうべきなのだ。
お互いを理解し合うためには、
お互いの卵を含めて
お互いの意見を交わし合うことが求められるのだ。
④お互いの意見を交わす
お互いの卵を含めて意見を交わし合う。
これが「対話」だ。
これまで受けてきた僕たちの教育には
討論や議論、ディベートというものが驚くほどに少ない。
そのため、「対話」が何であるか?わからないことが多いかもしれない。
でも実は僕たちは日常茶飯事、対話をしている。
例えば食事の席。
これ美味しいね。
これいい香りがするね。
これ、味どう?なんか変な味しない?
などなど、だ。
食事の席で言うならば、
(もちろんくだらない世間話も大事だが、食事の席なら食事のことを話そう。)
食べてるものがどうなのか?
お互いの意見を交わし合うことがあるはずだ。
(もちろんこれがきっかけで喧嘩に至ることもあるだろう)
子育てともなれば、特に対話の重要性がわかるはずだ。
親側が勝手に子供のことをああだこうだと決めつけたところで、子供からは違った意見が来る。
泣いてる子供がなぜ泣いているのか?親の一方的な決めつけでは子供は泣き止まない。
それこそ子供の話をちゃんと話を聞いてあげなければ、子供がどう育つか?大いに想像がつくことだろうと思う。
対話が大事だと、容易にわかることだと思う。
それでもだ。
僕たちがこれまで受けてきた教育は
答えに当てまめて会話をしなければならなかった。
お互いの意見を交わすなど言語道断。
忖度が大事。
相手の目を気にしなければならない。
だからこそ、大人同士の会話となった時、
その会話が対話に発展することはほとんどない。
どこか他人の答えを探し当てるような、答え合わせの会話となりがちだ。
だからこそ、
人の欲求を理解して、
欲求に応えるというのは
会話としては非常にわかりやすい。
欲でお互いを支配することが簡単である理由はここにもある。
自分の意見を交わし合うよりも、
お互いの欲を満たしあっていたほうが
無害で無傷だと錯覚できるからだ。
でも実際はその会話の中には何も産まれない。
一時的に満たされたとしても
自分の欠乏感は拭いきれないのだ。
それでも欲という答えでお互いを騙しあっていた方が
自分の意見を述べるよりははるかにマシだと思ってしまうのもまた
現代を生きる僕たちだ。
自分の意見をいざ話そうにも、
自分の卵に囚われ
他人の答えに合わせなければと思うがあまり
他人の目を気にしてしまうのだ。
最近では
「人の目が気にならなくなりました!」などど
SNS上で発信する人もいるが、
その発言自体が
人の目を気にしているからこそであり、
人の目を気にしないことがあたかも「答え」のように感じているという、
人の目からきていると、
案外誰も気づかないものだ。
学べば学ぶほど、
経験すればするほど、
僕たちはどんどん「答え」に「執着」してしまう生き物でもあるのだ。
だからこそ、
そんな「答え」に「執着」している
そういった自分の「卵」含めて
他者と意見を分かち合うことが
大事だ。
ネガティブをポジティブにと、
卵の中をいくら見栄えよくしたところで何も変わらない。
自分の卵の中にある
汚さも美しさも
どちらも自己開示する勇気が大事だ。
そんな対話はほんの少しの勇気でいい。
自分の中にある小さなきっかけさえ
誰かに話そうとすれば
そこを糸口に
あなたの卵と
あなた自身が向き合うことができる。
答えのない問いかけさえ
自分の中に持てば、の話だが。
★「起業家のための哲学教室〜入門編〜」無料動画講座をプレゼント🤲
・なぜ今の時代、
起業家に哲学が必要なのか?
・起業家の仕事とは何か?
・今の時代はどうなっているのか?
・哲学とはなんなのか?
僕の意見も交えながら、
一緒に考えていきましょう!
僕と対話することで、
人間としての生き方・在り方を
一緒に見つめていきましょう。
ご登録はこちらから
★まずは僕とお話ししてみませんか?😌
答えのない問いかけ、
哲学、
対話・・・。
これらを体験していただくには、
僕と話すのが1番早いです。
公式ラインから
お問い合わせいただけたら、
あなたのための特別な時間を
ご提供させていただきます。
いつでもあなたのことを心からお待ちしています。