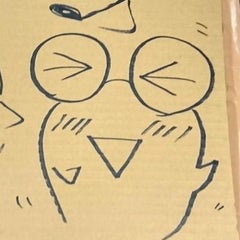久しぶりの更新
いろいろと仕事をしたり、文化財めぐりをしたりしているうちになかなか更新できず…、久しぶりの投稿になります。
今回は、以下のツイートから、石碑の文字を読みやすくする方法をご紹介します。
処理して単純に出力しただけだけど、結構読める。
— 半兵衛歳三 (@Hanbei1582) January 25, 2021
ただ、もっと読みやすくなる処理があるらしいんだけど、どうしたら良いんだろう? pic.twitter.com/eBjLKFucq5
ただ、私もまだ勉強中で、他にも方法はあると思いますので、あくまで一例としてご紹介します。
PLYで出力からCloudCompareで読み込み
さて、MetashapeやReality Captureなどで既にモデリングが済んでいることを前提に話を進めていきます。
モデリングの方法がわからない方は、このブログの他の記事をご参照ください。
今回例として使用する石碑はSketchfabにアップロードしてありますので、モデルデータをダウンロードしておいてください。
では、Metashapeで石碑のモデルを作ったとして、PLY形式で出力(エクスポート)します。
ファイル→エクスポート→モデルをエクスポート→.plyを選択、名前を入力して保存
これで.ply形式で出力できます。
他にもよく使われる形式で、.objや.stlなどの形式がありますが、色付きのメッシュで見たい場合が多いと思いますので、ここでは.ply形式を使用します。
続いて、CloudCompareでplyデータを開きます。
すると表示が出てくるので、applyかapply allを押します。
CloudCompareで向きを調整する
今回は、すでに向きがそろっていますが、手動で向きをそろえる方法をご紹介しておきます。
まず、①のメッシュデータをクリックすると、
メッシュが選択され、アクティブな状態になります。
この状態で、②をクリックすると、
選択したメッシュ(あるいは点群)の回転・移動が可能になります。
③をクリックすると、あらかじめ決められたいくつかの視点に変更されます。
真上から見たとき、真正面から見たとき、など図面をとる際にはとても便利です。
では、モデルを動かしてみましょう。
左クリックで回転、右クリックで移動ができます。
右上には下の図のような表示が出ますが、
Rotationでは回転する際にxyz軸のどれを固定するかを選べます。
その下のチェックボックスは、移動する際にどの面を移動できるかを選べます。
いろいろと試してみると感覚的に理解できます。
上段にもいろいろな機能があります。
左から1番目は一時停止です。作業を一時的にストップできます。
左から2番目はリセットです。移動や回転がすべてリセットされます。
左から3番目は完了です。移動や回転が反映されます。
左から4番目は中止です。編集がキャンセルされ、元に戻ります。
③を使いながら、正面から見たとき、横から見たとき、まっすぐになるよう調節する、
といった具合です。
今回の場合はそのままで構いません。
段彩をかける
それでは、モデルに色を付けていきます。
今回は文字を見やすくするため、凹凸に合わせてグラデーションにします。
モデルを選択した状態で、
編集→色→段彩→初期設定→OKを押します。
このとき、Customにすると、お好みのグラデーションに変更できます。
また、directionをxやyにすると、グラデーションの軸を変更できます。
段彩の結果がこれです。このままでも読めなくはないのですが、
もっとはっきり読めるようにします。
モデルをでっかくする!
今回の例では、肉眼でも見えるくらいまだ文字が残っていますが、
実際の石碑ではカッスカスでよく見えないものもあります。が、
「そんなに凹凸がないなら、倍増させればいいじゃない」
ということでモデルを大きくしてみます。
こんなことができるのもデジタルのいいところですね。
その前に、後で比較したいのでモデルを複製しておきましょう。
(メインの作業には必要ありません)
モデルを選択した状態で、虹色の羊マーク(クローン)をクリックすると
すぐに複製できます。
これで2つのモデルができましたので、
どちらかを選択して、大きくしていきます。
モデルの片方を選択して、
編集→乗算/スケールをクリックします。
(蛇足ですが、モデルを10倍にしてみます)
次に、下の画像のような表示が出てきます。
ここでは、xyz軸それぞれの方向に何倍にするかを決めることができます。
モデル全体を10倍にしたいなら、「Same scale…」にチェックをいれ、
Scale(x)に10を入力します。
Same scale…にチェックを入れておくと、xyz軸がそれぞれ同じように
乗算されるため、全体を大きくすることができます。
これで大きくなりました。
しかし、全体が大きくなっただけなので、
文字の見え方は変わりません。
文字をよりはっきり見えるようにするためには
凹凸をより際立たせる必要があります。
したがって、次は凹凸を強調するため、
z軸方向のみを10倍にしてみます。
Same scale…のチェックを外し、Scale(z)に10を入力します。
すると、このように、凹凸が強調されました。
フィルターを使う
続いて、フィルターでさらに強調します。
画面右上にフィルターが2つあるので、それをクリックします。
比較のため、乗算処理していないものと並べてみました。
乗算処理をしたことでかなり見やすくなっています。
照明を使う
続いて、照明を使い、影を作ることで、より判読しやすくします。
照明の効果を得るためには、先に「法線ベクトル」の計算を行い、
光に対して、どのように反映するかを計算しておく必要があります。
モデルを選択した状態で、
編集→法線→演算→Per-vertexをクリックしていきます。
これで下準備は完了です。
これですでに影が出ています。
続いて、F6とF7を使っていきます。
F6は太陽光の移動 on/off
F7はカスタム光の移動 on/off
ができます。
太陽光は移動できず、カスタム光は移動できます。
それぞれ、on/offを切り替えてみて効果を確認してみてください。
カスタム光をonにした状態では、どこかに黄色の十字が現れます。
これが光源の位置を表しています。
この黄色十字はctrlを押しながら右クリックで動かすことができます。
光源を動かすことで印象も変わり、文字の判読に役立つほか、
石の実測などで稜線を見るのにも役立ちます。
PCV処理
上記の処理について投稿したところ、なんと、CloudCompare公式さんから、アドバイスをいただいたので、さっそく試してみました。
Have you tested the PCV plugin as well? (Ambient occlusion)https://t.co/OiuKjzvitY)
— ☁ 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲 (@CloudCompareGPL) January 26, 2021
こちらのPCVというプラグインを使った処理方法のようです。
まずは、モデルを選択した状態で、
プラグイン→PCV/ShadeVisをクリックします。
出てきたダイアログでOKをクリックすると、細かな凹凸が消えたような状態になります。
結果、以下のようになりました。
さらに、モデルを選択すると左下にプロパティが出てきますが、その中の「法線」にチェックをつけたものも並べてみました。
これで手軽に見やすくなりました。
公式さんありがとう。
まとめ
以上のようにCloudCompareは無料ながら、
さまざまな機能をもっており、
これらを組み合わせることで埋蔵文化財調査においても
十分な活躍が期待できます。
ちなみに今回のモデルはスマートフォンの写真数枚から作成されており、
より手軽にモデリング~判読ができるようになっています。