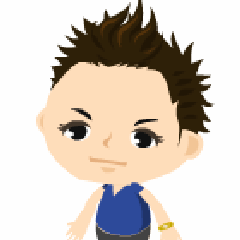まず初めに、下の写真を見てください。
黄身の色が違う卵がありますが、どちらが美味しいと思いますか?
(ネットで拾った写真なので、著作権にかかるようでしたら削除します)
恐らく多くの方は、黄身が黄色い左を選ぶのではないでしょうか? 更に言えば、黄色同士で比べた場合はオレンジや赤っぽい方が選ばれるのではないでしょうか?
しかし、各所で指摘されている通り、黄身の色は与えたエサの種類で変わるもので、栄養素や味が大きく変わることはないとのことです。なぜこんな質問をしたのかというと、指摘したいのは個人レベルの味の好みのことではなく、「なんとなくの印象」が生産や販売に影響を与えているということを指摘したかったからです。
生産者としては同じコストをかけるなら売れるものを作るのが当然で、卵の例を使うなら黄身が黄色い卵を生産します。黄身を黄色くするためには餌はトウモロコシがメインとなり、更に赤みを付けたいならパプリカやマリーゴールドなどを混ぜると言われています。これらの飼料の多くは輸入に頼っていることから、生産コストが上がって生産者の利益を圧迫しています。
データを示すと、配合飼料の原料の約5割はトウモロコシです。2022年のトウモロコシ輸入量の約6割はアメリカなので、肥料の時のような貿易相手としての不安感はありませんが、トウモロコシの国際価格はウクライナ侵攻等の影響により、2023年1月時点で前年同月比で20%上昇していることから、飼料価格の上昇は避けられません。
ここで前回紹介した「食料安全保障強化政策大綱」を思い出していただくと、「飼料作物の生産面積32%拡大」という項目がありました。また、輸入原材料の国産転換として「2030年までに2021年比で小麦+9%、大豆+16%、飼料作物+32%
米粉用米+188%などの生産面積拡大」という目標も立てています。ここから小麦と大豆の生産拡大目標よりも米粉用米が遥かに野心的な目標を掲げているのが分かります。これには仕方がない面があって、そもそも小麦や大豆は「冷涼乾燥」な環境を好む植物であり、稲は「温暖湿潤」な環境に向いた植物であるので、普通に考えれば日本で栽培するには稲が向いているという結果なります。もちろん、国内でも地域ごとに気候条件は違うし、品種改良の成果もあるので一概には言えないわけですが、国の政策という規模感と主食用米の消費量低下という現状を鑑みれば、やはり「飼料用米の増産」という結果に行きつきます。
そこで最初の質問に戻ります。「飼料原料の国産化」=「飼料用米の増産」に向かう以上、これからはだんだん卵の黄身が白くなっていきます。そうなったとき、消費者側の「黄身の色は黄色が濃い方が美味しい」という思い込みが捨てられるかどうかに、生産者(養鶏業者だけでなく米農家も含めて)の生存がかかっています。おいしさの指標は人それぞれですが、何時どこで誰が広めたかも分からない「なんとなくの印象」をどうやって払拭するかが、飼料原料の輸入超過の現状を改善するカギとなります。
さてここまで、食料自給率の問題だけではなく、そもそも食料を生産するための肥料の確保が厳しい現状であること、国も対策を取ろうとしていますが時間的に間に合わない可能性があるということ、そして消費者側も価格上昇に備えるだけではなく、意識改革も必要であるということを述べてきました。
その上で最後に言いたいことは、ここに肥料の使用を大幅に抑えられる「アクアポニックス」という農法がありますよ、ということです。アクアポニックスなら少なくとも窒素(尿素)は不要です。食用を考慮しなければ、魚には何を食べさせてもかまわないので、特別にエサを輸入する必要もないでしょう。そう考えると、今後の情勢においてはアクアポニックスの存在価値は高いと言えます。ただ、問題は国の政策に乗っかれるかどうか。有機栽培面積の拡大方針の中で、アクアポニックスが農法として認められるかなのですが…