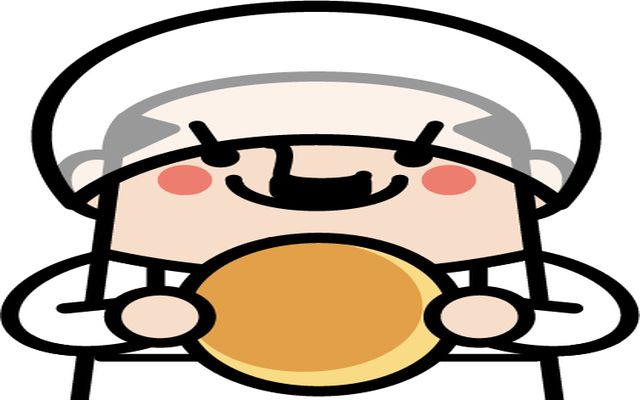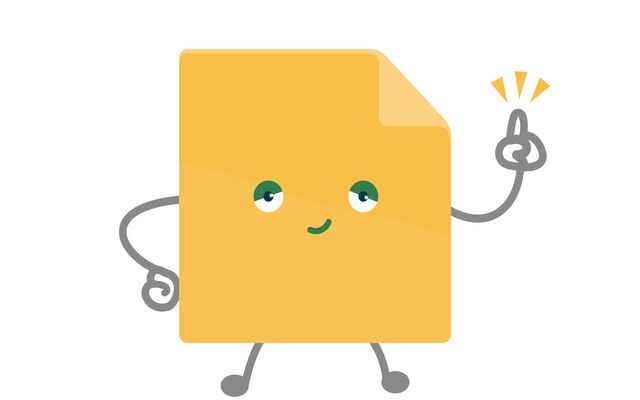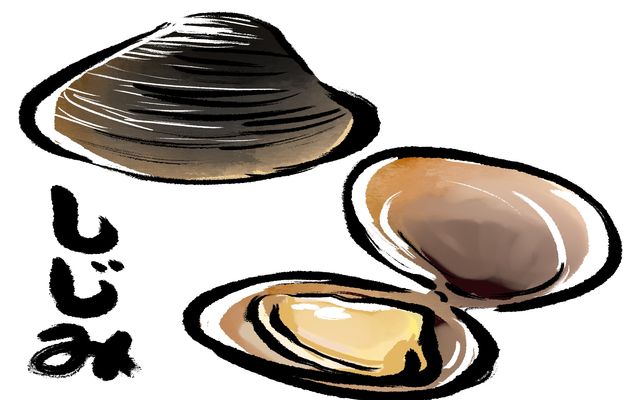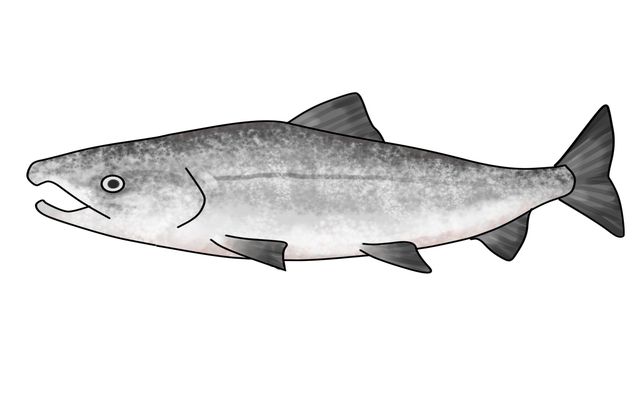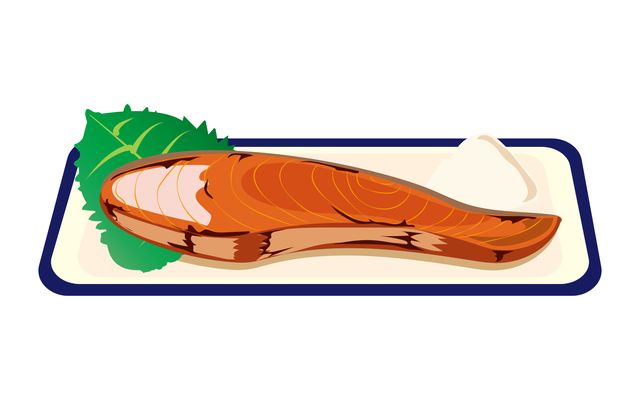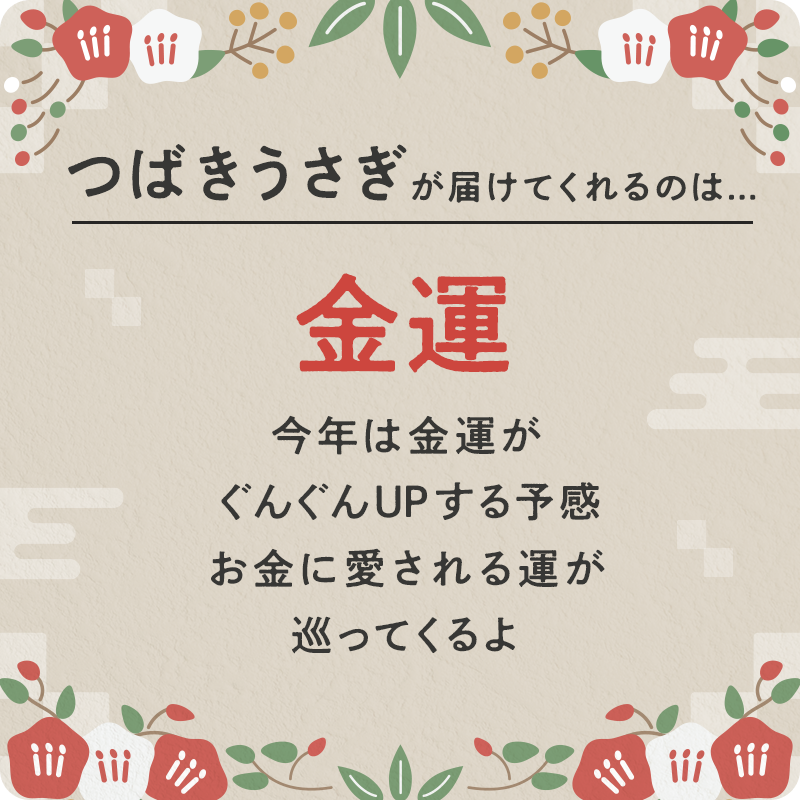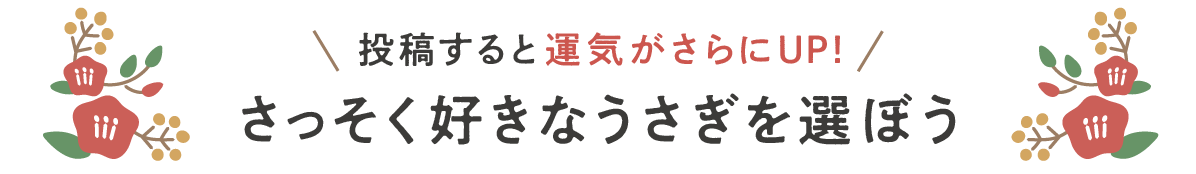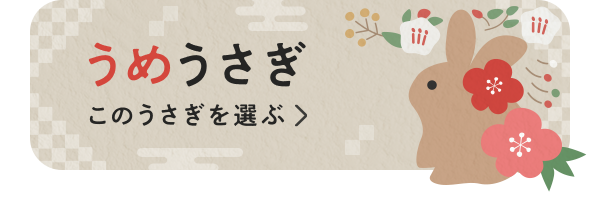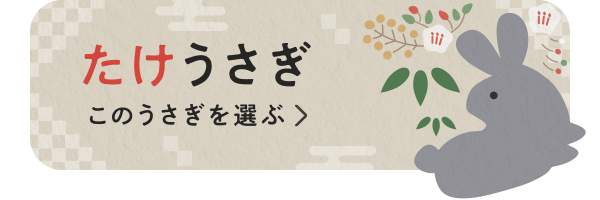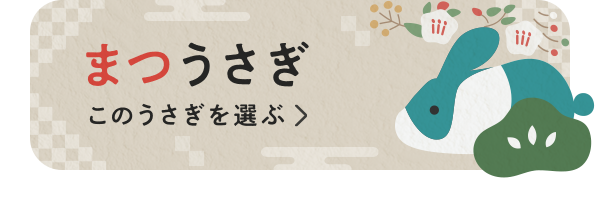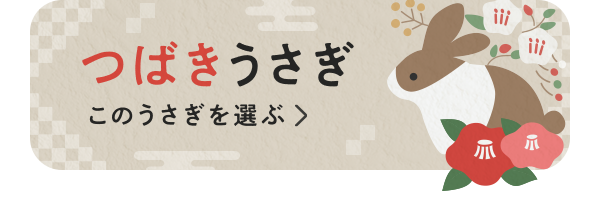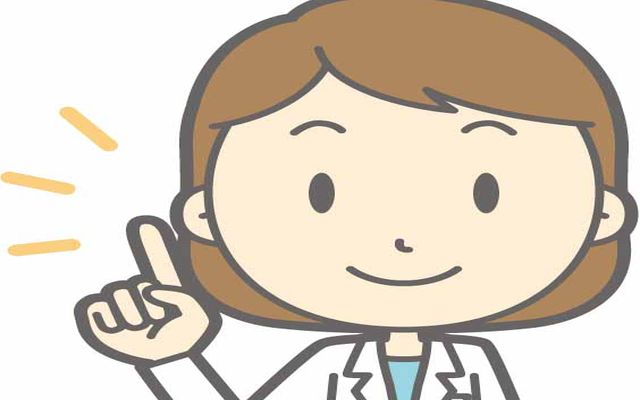ヨーグルトは手軽に食べられて、美味しく、しかも体に良い。
値段も手頃の商品も多く、毎日でも食べられる人気の食べ物だと思います。
そこで今回のブログでは、取り入れやすい食品だからこそ気をつけたい、安心して食べられるヨーグルトの選び方やヨーグルトによく使われている添加物の5選と通販やスーパーでも購入できるおすすめの無添加ヨーグルト6選を取り上げていきます。
安心して食べられるヨーグルトとはどのようなものでしょうか?
安心?
そもそもヨーグルトって体に良いと言われてんじゃないの?
そう思うかも知れませんが、ヨーグルトには様々な種類や味があります。
しかしその中には食べやすくするために、食品添加物が使用されているものがあります。
ヨーグルトに使われている危険な添加物5選

ヨーグルトによく使用されている添加物の中には実は危険なものもあるのです。
まずはヨーグルトによく使用されている添加物について五つご紹介します。
ヨーグルトに使われている危険な添加物1・スクラロース
危険な添加物まず一つ目はスクラロースです
スクラロースは砂糖の分子構造を変化させた人工甘味料で砂糖の600倍の甘さを持ちながら何とカロリーがゼロという特徴を持っています。
カロリー0で、砂糖を控えられるなら最高と思いませんか?
なのでスクラロースは、ヨーグルトの酸味を和らげるために添加されることが多いです。
ただしそんなスクラロースには、下痢や頭痛、薬の効果を阻害するといったデメリットがあり、さらにはアレルギーを引き起こしたり発がん性があるという研究結果もあるんですよ。
確かに安全性を保障してる物なので、すぐにアレルギーやがんにはならないでしょうが危険性のあるある物を健康に良いからと食べ続けることに疑問は感じませんか。
ヨーグルトに使われている危険な添加物2・アセスルファムk
二つ目はアセスルファムk です。
こちらも人工甘味料で砂糖の200倍の甘みを持つと言われています。
スクラロースと同じく酸味を和らげたり、カロリーを抑えるといったメリットがあるのですが、デメリットもあります。
アセスルファムk は製造過程で溶媒として、塩化メチレンという発がん性物質が使用されることが多いのです。
また国内生産ではなく輸入されているので購入や残留の検査が行われていないという事実もあります。
ヨーグルトに使われている危険な添加物3・増粘多糖類
三つ目は増粘多糖類です。
増粘多糖類はヨーグルトに粘り気をつけるために、添加される増粘剤です。
増粘剤は2種類以上添加した際の表記が増粘多糖類と一括表示になってしまうため、実際には何が添加されてるのかわからないという危険性があります。
そして増粘多糖類の中には、発がん性があるものや遺伝子組み換えされた作物を原料に使用しているものもあるので注意が必要です。
ヨーグルトに使われている危険な添加物4・乳化剤
四つ目は乳化剤です。
乳化剤は水と油などのなりにくいものを均一に混ぜるために添加されます。
入荷させる目的で添加されたものは、全て乳化剤と一括表記になるので増粘多糖類と同じく、実際には何が使われているか分かりません。
乳化剤の中には、発がん性を有するものや多量に摂取すると内臓に障害をもたらすと言われているものがあるので注意が必要です。
ヨーグルトに使われている危険な添加物5・香料
五つ目は香料です。
香料はフルーツヨーグルトなどによく使われているのですが、これも表示見ただけでは実際に何が使われているのかが分かりません。
このようにヨーグルトには様々な添加物が使用されている可能性があります。
せっかく健康に良いからとヨーグルトを食べるのなら、安全性の高いヨーグルトを選んでみてはいかがでしょうか。
では安全なヨーグルトを選ぶにはどうしたらよいのでしょうか?
次にヨーグルトの添加物の避け方と見分け方をご紹介します
ヨーグルトの添加物の避け方見分け方

安全なヨーグルトとは、つまり添加物が使用されていないヨーグルトと言えると思います。
添加物が使用されているかどうかは、ヨーグルトの裏面に表示してある原材料名を見ることで確認することができます。
まずフルーツヨーグルトやバニラ風味などの味がついたもの、また加糖ヨーグルトなどは添加物が使用されている可能性が高いです。
なら、プレーンヨーグルトを選べば安心?
ただし、プレーンヨーグルトであっても風味のために香料が使用されているものや、食感のために増粘剤が使用されているものもあるので注意が必要です。
なんか選ぶだけでも疲れてしまいますね。
ですが原材料名に生乳や乳製品のみが記載されているものは、無添加なので安全だということになります。
また加糖であっても、蜂蜜や砂糖など人工甘味料ではない甘味料が記載されていれば安心と言えると思います。
また機能性表示食品や特定保健用食品という表示があっても、食品添加物がたくさん使用されている場合もあります。
健康やダイエットのために脂肪ゼロやカロリーゼロといった表示のある商品を手にとってしまいがちですが、人工甘味料が使用されている場合が多いので気をつけましょう。
次に選ぶ目安として、無添加で安心して食べられるヨーグルトをご紹介します。
無添加お勧めヨーグルト
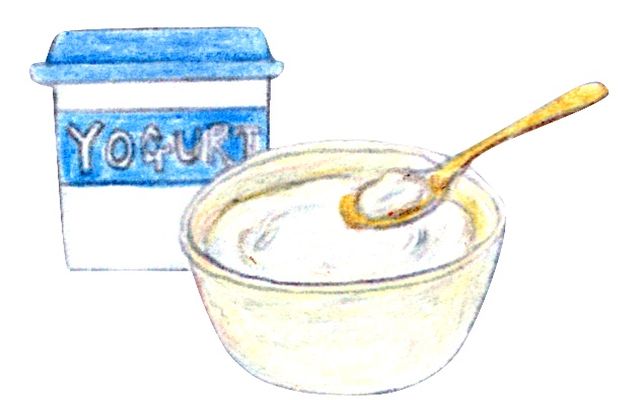
まずは通販で購入できる商品3選です。
少し割高になりますが商品を是非ご覧下さい。
無添加お勧めヨーグルト1・しあわせ乳業株式会社のプレミアムヨーグルトGY
通販のみおすすめ商品一つ目は、しあわせ乳業株式会社のプレミアムヨーグルトGYです。
完全自然放牧で、ストレスなく生活し、牧草を食べている牛からとれた牛乳のみでつくられた無添加ヨーグルトです。
水分を50%抜いて濃縮されているので、牛乳本来の味を楽しむことができると思います。
楽天や Amazon しあわせ牧場のホームページで購入できます。
無添加お勧めヨーグルト2・ATHENAギリシャヨーグルト
二つ目は、日本ギリシャヨーグルト株式会社のATHENAギリシャヨーグルトです。
原材料が生乳乳製品乳蛋白のみの無添加ヨーグルトで、まるでチーズのような濃厚でクリーミーな食感が特徴です。
無添加お勧めヨーグルト3・蒜山ジャージーヨーグルト プレミアムプレーン
三つ目は、蒜山酪農農業協同組合の蒜山ジャージーヨーグルト プレミアムプレーンです。
原材料は生乳のみ濃厚で、味わい深いと有名なジャージー牛乳で作られたヨーグルトです。
こだわりの製法で表面に滑らかなクリーム層があるのも特徴となっています。
次にスーパーなどで手軽に購入できる無添加ヨーグルトをご紹介します
無添加お勧めヨーグルト4・チチヤスの無添加ハニーヨーグルト
おすすめ商品四つ目は、チチヤスの無添加ハニーヨーグルトです。
なめらかでとろけるような口当たりで、酸味も少ないので食べやすくハチミツのほのかな甘みを感じます。
香料や安定剤が使用されていないので、安心して食べることができる無添加ヨーグルトです。
80g4個パックで値段も150円前後と手軽に食べられるおやつとしてもオススメです。
無添加お勧めヨーグルト5・ブルガリアヨーグルト LB 81プレーン
五つ目は、明治のブルガリアヨーグルト LB 81プレーンです。
王道といっても過言ではないとても有名な400gのヨーグルトです。
取り扱ってないスーパーはないと言っても過言ではないかも知れませんね。
原材料は国産生乳と乳製品のみ。
シンプルなヨーグルトながら酸味と生乳のあまみがほどよく、硬さやまろやかさのバランスも良い食べやすさが人気ですよね。
無添加お勧め6・小岩井の生乳100%ヨーグルト
三つ目は、小岩井の生乳100%ヨーグルト。
名前の通り、生乳100%で作られた安心して食べられる無添加ヨーグルトです。
柔らかくクリーミーな食感が特徴で、幅広い年代に好まれると思います。
国産生乳のやさしいコクがあり、甘みを加えなくても食べやすいと人気です。
以上ですが、気になる商品はありましたか?
ぜひ、通販やお近くのスーパーで探して試して下さいね。
最後
美容やダイエット目的でも注目され身近な食品であるヨーグルト。
腸活にも勧め、健康維持に毎日食べている方も多いと思います。
それならば、少しでも安心して食べられるヨーグルト選びの参考にして頂けると嬉しいです。