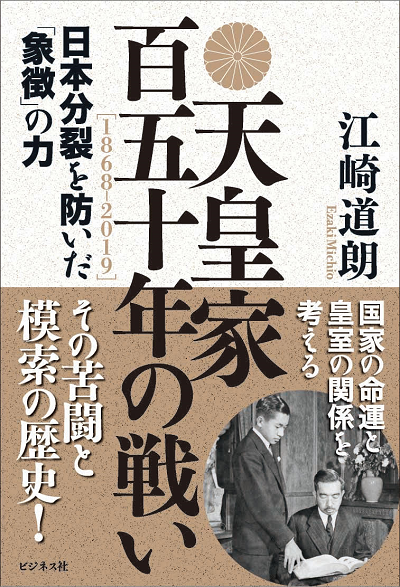閑院宮家は、1947年、皇室離脱した11宮家の中の一つです。
伏見宮
閑院宮
久邇宮
山階宮
北白川宮
梨本宮
賀陽宮
朝香宮
竹田宮
東久邇宮
東伏見宮
第百十四代中御門天皇の時代、宝永七年八月十一日(1710年9月4日)、旧暦では314年前の本日、東山天皇の第六皇子直仁(なおひと)親王を初代とする新宮家創設が決定されました。
その八年後、霊元法皇(前年崩御された東山天皇の父)より直仁親王に対して「閑院宮」の宮号と千石の新領が下賜されました。これは寛永二年の有栖川宮家が創設されて以来八五年ぶりの新宮家誕生です。
当時既にあった宮家(伏見宮・有栖川宮・桂宮)は何れも天皇とは遠縁となっており、皇統の断絶が危惧され、宮家からの即位となる場合に近親者が相応しいとの考えから、新井白石の建議により新宮家が創設されたのです。これにより、四宮家(四新王家)となりました。
新井白石は、徳川第五代将軍徳川綱吉の時代、儒学が重んじられ多くの学者を輩出し儒学(朱子学)が隆盛を極めた時、その学者の中にいました。徳川家は七代将軍家継の後宗家が断絶しましたが、徳川御三家の紀州家から吉宗が将軍になることで継続しました。そうした徳川家の後継問題がある中、新井白石は徳川将軍家に御三家があるように、朝廷にもそれを補完する新たな宮家が必要との建言を第六代将軍家宣に出したのです。
江戸時代は徳川家が権力を持っていた時代ですが、そうした時代に徳川家に仕えた新井白石出さえこうした提言をし、実現させたのです。それをなぜ、天皇と皇室を国家元首とする今実現できないのか?それは未だにGHQの呪縛から逃れることができていないからではないかと思わざるをえません。
閑院宮家創設後、直仁親王の孫である祐宮(さちのみや)師仁(もろひと)王が第百十八代後桃園天皇崩御に伴い践祚され、第百十九代光格天皇として即位され、今上陛下へと続く系統となりました。閑院宮家創設から69年後のことです。
その後、徳川家でも吉宗の子供から御三卿も創設し、幕末にはその中の一橋家に養子に入った水戸家の慶喜が最後の将軍となりました。
四宮家(伏見宮・有栖川宮・桂宮・閑院宮)は、宮家が皇室離脱した際の昭和二十二年(1947)、十一宮家の中(断絶により)既に二宮家しか残っていませんでした。有栖川宮家は大正十二年に断絶、桂宮家は明治十二年に断絶しています。
つまり皇室離脱した十一宮家の内、九宮家は閑院宮家創設以降に出来たさらに新しい宮家なのです。いかに家を継続することが難しいことかがわかるかと思います。
十一宮家はその後、その内四宮家が断絶しています。閑院宮家も断絶しています。↓
伏見宮家:北朝の第三第崇光天皇の第一皇子栄仁親王が初代。第二十六代博明王の時に皇室離脱。現在当主に男子がおらず、断絶見込み。
閑院宮家:江戸中期東山天皇の皇子、直仁親王が創設。第七代春仁王の時に皇室離脱。実子がなく断絶。
久邇宮(くにのみや)家:明治時代前期に伏見宮邦家親王の第四王子朝彦新王が創設。二代邦彦王の子女である良子女王が昭和天皇の皇后となる。三代朝融王の時に皇室離脱。妃との間に三男五女あり。
山階宮(やましなのみや)家:江戸時代末期に伏見宮邦家新王の皇子、晃新王が創設。三代武彦王の時に皇室離脱。実子がなく武彦王薨去により直系は断絶。
北白川宮家:明治初期、伏見宮邦家親王の第13王子、智成親王が創設。第三代宮成久王は明治天皇の第七皇女・房子内親王と結婚。一男三女があったが、長男の永久王は昭和15年陸軍の演習中に事故死。第五代道久王の時に皇室離脱。三女あり。道久王に男子がいなかったことから、2018年断絶。
梨本宮家:明治初期、伏見宮貞敬親王の第九王子守脩親王が創設。第三代守正王の時に皇室離脱。皇続とは関係のない血筋の養子により梨本家が継続しており、皇族としては断絶。
賀陽宮家:明治中期に久邇宮朝彦親王の第2王子邦憲王が創設。第二代恒憲王の時に皇室離脱。六男一女あり。
朝香宮家:明治後期久邇宮朝彦親王の第8皇子である鳩彦(やすひこ)王が創設。明治天皇第八皇女・允子内親王と結婚。二男二女あり。2代孚彦王の時に皇室離脱。一男二女あり。
竹田宮家:明治後期に北白川宮能久親王の第1王子(庶長子)、恒久(つねひさ)王が創設。明治天皇の皇女・昌子内親王と結婚。二代恒徳王の時に皇室離脱。三男次女あり。三男恒和の子が竹田恒泰氏である。
東久邇宮家:明治時代後期に久邇宮朝彦親王の第9子である稔彦王が創立。明治天皇の第九皇女・聡子内親王と結婚。一代限りで皇室離脱。四男あり。長男の盛厚王は昭和天皇の第一皇女・照宮成子内親王と結婚、三男二女あり。
東伏見宮家:伏見宮邦家親王の第17王子依仁(よりひと)親王が創立。一代限りで皇室離脱。継嗣がなく断絶。
現在、若い世代の皇統後継者が秋篠宮の悠仁親王殿下だけですから、二言目には女性天皇・女系天皇の話が出ますが、まず女系天皇の系統はありえません。万世一系で天皇は続いてきました。これは男系で続かれたからこそなのです。それが壊されたらもう天皇ではなくなります。
つまり女系天皇なんてものはないのです。女系となったら、それは天皇ではなくなるということだからです。
そして、古代からいた女性天皇はそのご負担が大きく大変だということが歴史をみるとわかります。天皇は宮中祭祀が本来の仕事ですが、その潔斎が女性にはとても厳しいものです。ですから、歴代の女性天皇は中継ぎとしてどうしようもない時のみ即位し、継承できるときになるとすぐ譲位をされてきました。例えば最後の女帝、後桜町天皇などは宮中祭祀ができないことが多かったことが記録から知られています。
日本では旧宮家が日本の意志ではなくGHQにより皇室離脱された過去がありますから、普通に考えればやはり旧宮家の復活がまず最初でしょう。現在の旧宮家の詳細な状況はわかりませんが、現在旧宮家の内、断絶見込みの一家を除き、五家が残っています。分家を加えるとさらにあるでしょう。しかし、そんなに沢山宮家復活は難しいとしても、明治天皇や昭和天皇の皇女が嫁ぎ男系が続いている宮家だけでも朝香宮家・竹田宮家・東久邇宮家だけでも四家あり、その分家を加えても十は超えません。現在の四宮家の状況(秋篠宮家以外全て子女は女性のみ)をみれば旧宮家から八宮家ほど戻しても多すぎることはないと思います。明治以降に次々に宮家が創設されたのも宮家が少なくなった(少なくなるのをみて)からでしょう。
以前竹田恒泰氏が、旧宮家の方々に確認したところ、もし宮家が戻ることになった場合その覚悟はできている、と言われたと竹田研究会で聞きました。一般人の自由を知ってから宮家に戻るのはとても大変なことだと思います。もし、天皇になったら自由がなくなり1日24時間365日天皇でいなければならないし、皇室のメンバーも自由がないものでしょう。しかし、今旧宮家が皇室復帰しておけば、宮家から次の天皇が出ることになる場合までの教育をしていくのに十分な期間ができます。
しかし皇籍復帰は難しいようで、旧宮家からの養子のお話が現実味をおびてきました。そうしたこともこれまで行われてきたわけですから、それもいいことだと思いますが、なにしろ早く決めていただきたいと思います。現在秋篠宮家へのバッシングが物凄い状態になっており、まだ若くこれからを担う期待を背負うことだけでも大変な悠仁親王までなにかと攻撃される始末であり、暗殺未遂事件や事故までも起きていることを考えるとその影響が懸念されています。
閑院宮家が創設されてから断絶(昭和63年:1988)するまで270年。
閑院宮家から光格天皇が即位されてから今上陛下の現在まで244年。
旧宮家が皇室離脱してから77年。
閑院宮家創設から天皇が即位するまで69年。
宮家でさえも存続するのは難しいのです。
旧宮家が復帰するも、旧宮家からの養子縁組も早ければ早いほど良いです。
旧宮家の復活や旧宮家からの養子縁組の話になると、皇室離脱してからこれだけ時間が経っているのに、という声があがりますが、それでも天皇と皇室との繋がりは変わりません。しかも、そのように言いながら全く関係のないところから女性宮家に入る人のほうが気になるのではないですか?現在も強く天皇と皇室と繋がっている旧宮家とは比較にならないのはいうまでもありません。
京都御苑に行くと、南西の位置に閑院宮邸跡があります。
以前、御所の中を少しだけ巡った時にこの閑院宮邸の中を見てきました。
(無料で見学することができます)
海外の王室を比較に上げる人がいますが、皇室と王室は違います。また比較するのであれば、どうして皇室がこれだけ続いてきたのかを、百年戦争から考えてみるのもいいかと思います。
GHQの政策により、何かあれば日本に反対する日本人を産み出すシステムができてしまっています。それは欧米が旧植民地などに行ってきた政策で、その政策を知ると戦後の日本がその構図に嵌っていることに驚愕します。
🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎