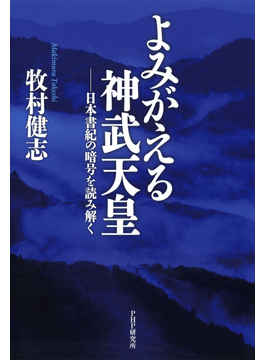東日本大震災の時、ネットで話題になっていたのが「民の竃」の話でした。
私は、子供の頃になにかで読んでいてこの話を知っていましたが、すっかり忘れていましたし、子供の頃の読解力ではこの話の凄さをわかっていませんでした。子供の頃はただ読んでいただけだったのです。東日本大震災の頃、私はちょうど古事記をちゃんと読もうとしたり歴史の学び直しをしようとしていた時でした。そんな時期に、ネットで民の竃が話題になっていたのです。古から伝えられる物語の力をこの時強く感じました。
というのも、民の竃の物語は、国民が一致協力して国難に立ち向かっていこうという物語だからです。だからこそ、国が困難な時には民の竃の話が出てくるのです。
現在、昨年来のコロナ禍他により、日本だけでなく世界中が大変な状態となっており、様々なことが変わってきており、経済活動も停滞しています。それでなくても消費税増税の影響で日本経済が停滞している中、大きな打撃です。しかもこれは日本だけでなく世界規模で起きていますから、今後への影響も大きい事が予想されます。
その経済の語源は、経国済民、または経世済民といわれています。これは中国の古典に登場する言葉で、「世を経(おさ)め、民を済(すく)う」という意味で、本来は政治・経済・行政全般についての言葉でした。ところが、明治の世に多くの翻訳語が出来た時に、この言葉から英語のEconomy(エコノミー)の翻訳語が創られ定着していったのには、江戸時代に経世済民という言葉が盛んに用いられ、経世済民論が流行したことが大きいようです。江戸時代といえば貨幣経済が浸透した時代でもあり、そうした時代の中で、経世済民という言葉に、次第に「生産・消費・売買などの活動が不可欠である」という現在使用されている経済という概念が組み込まれていったのです。明治になって、エコノミーを翻訳する時に、様々な言葉が使われましたがその中からだんだんに「経済」という言葉に定着していったのは、そうした下地があったことが大きいというわけです。
そしてその経世済民の見本として、古来から日本で手本とされてきたのが仁徳天皇の民の竈を代表とする善政です。
大阪市にある高津宮(こうづぐう)という神社には、こんな絵が奉納されています。これはここが仁徳天皇の宮である高津宮(たかつのみや)跡にできた神社であることから奉納されたもので(現在地は移転地であるため宮跡ではない)、民の竃の国見の様子を描いています。
高津宮には境内にかまどもあります。古代のかまどとは違うでしょうが、高津宮らしいと思ったものです。
「民の竃」とは、仁徳天皇四年二月六日、天皇が民の竈から煙が上がっていないのをご覧になり、民の窮乏を察し年貢の徴収を三年間禁止させる詔、「百姓(おおみたから)の窮乏を察し群臣に下し給える詔」を渙発されたことをいいます。民の竈の話にはこの詔についてまで語られることがありませんが詔が発せられて免税が始まりました。
今年の旧暦の2月6日は、新暦では昨日でした。改暦が何度もありますから、古来の日付との違いがあるかもしれませんが、それでも今のような時期であったことは確かでしょう。民の竃がこのまだ寒い乾燥した時期であったことを知るのは、例えば夏であったということよりもその窮乏さの加減が分かりやすいのではないかと思います。
歴史を繰り返しみるという事は、忘れない為という事が第一にありますが、繰り返しみることにより、以前は分からなかったことや理解できなかったことが分かるようになったり見えてくるという効果があるからだとも思います。私はこの日付を意識した時、その窮乏の加減や切実さがより一層強く感じられました。もしこの時が、夏であったなら仁徳天皇は竃の煙がなくても、そんなものと思ったかもしれません。夏であれば時期的にも生で食べられるものも多いと思われるからです。しかし、冬は保存食ばかりで生で食べられるものは少ない時期だったでしょう。また竃で暖をとるということもあったでしょう。そのような時期に煙が少なかったのです。当時の人々はどのように飢えや寒さをしのいでいたのか?と時を隔てた現代でも、季節を意識することで、仁徳天皇のご心痛が伝わってくるような気がします。
この3年間の免税の間、宮の屋根の葺き替えもされず宮殿はボロボロになりましたが、民の竈のその後は課税されて終わりかというとそうではありません。3年後もまだ課税を開始せず結局6年間免税されたのです。ですからその後、民はすすんで昼夜を問わず宮殿の材を運び宮を完成(再建か)させたといいます。
仁徳天皇は大土木事業を大々的に行ったことがその業績として知られていますが、その土木事業を行う下地には、この民を富ませたことも大きいのだといいます。確かに窮乏している状態で、大土木事業まで行うのは無理があります。そして民を富ませるとは経世済民そのものです。現在、古代の大阪と現在の大阪の地形の違いはあらゆるところで目にすることが出来ますので、検索等してみてください。大阪開発の始まりが仁徳天皇の頃であったこと、そしてその証が仁徳天皇陵を初めとする大規模古墳であることは間違いのないことでしょう。
そしてこの大土木事業を行ったことが、仁徳天皇陵という世界一の陵墓にも繋がっていきます。なぜなら沢山ある巨大な陵墓を比較すると、その土木工事の進歩までうかがい知ることができるからです。例えばその形だけを見れば、素人でもその技術の向上がわかります。そうした工事を繰り返すことで土木技術が進歩し、田畑が整備され民はより一層富んでいきました。だからこそ、そう励んだ天皇の陵墓が大きくなるのも不思議はありません。しかも、陵墓には土木工事で出た土の処理という一面もありました。このような大きな陵墓を造ったというのは民を使役したのではないかというような話が出た時期もあったようですが、この陵墓の造り方からそのように使役した造りではなかったという説も出てきました。宮殿も喜んで造られたといいますし、土木工事で川の氾濫も抑え、田畑が富んでいったわけですから人々、おおみたからは、宮を造るように喜んで陵墓も造ったというほうが筋が通っています。
土木事業を行われた仁徳天皇について書かれている本はいくつもありますが、この本はとても分かりやすい本の一つ。大土木工事の目的の一つには水田の整備もあります。天孫降臨の際の神勅に、「斎庭(ゆにわ)稲穂の神勅」があります。これは、高天原の稲穂をいただき、地上でも稲穂を育て民を養いなさい、というものです。稲を育てるためにも水田の整備は欠かせないものでした。水田が普及する前から稲作が行われていたことが最近では知られてきていますが、水田が普及することによってより一層収穫が増えたことから、水田が日本中にひろまっていっているからです。そもそも日本の始まりである神武天皇の東征とは、戦ではなく水田普及効果で人々を傘下にまとめていったものでもあるといいます。だからこそ、途中でとどまった時期が数年あるなど長い時期となっているのです。そうしたことを知ると、仁徳天皇が行われたとことは、「斎庭稲穂の神勅」に従い御歴代の天皇の業績を引き継がれたものであり、我が国の歴史に稲穂、つまり米が欠かせないことをあらためて示したものだと言えるかと思います。
仁徳天皇が聖の帝として歴代の天皇の範とされてきたのは、このような仁政を行ったことからであり、その漢風諡号もここから来ています。御歴代の天皇が仁徳天皇を模範とされてきたことは、日本の歴史をみると民が窮乏した時には何度も免税や減税が繰り返されていることからも伺いしれますし、平安時代には仁徳天皇が歌ったものとして(仁徳天皇の気持ちになって)和歌まで詠まれました。
高き屋に登りて見れば煙立つ.
民の竈(かまど)はにぎはひに けり
つまり、御歴代の天皇だけでなく貴族たちも仁徳天皇について学ばれていたということがこの和歌からわかるのです。
そして経世済民という言葉が盛んに使われた江戸時代に人々の頭に浮かんだのもやはり民の竈だったのだと思うのです。日本で経済という言葉を使う時、それは英語のエコノミーではなく経世済民であるということはとても重要なことではないかと思います。
聖の帝である仁徳天皇を見本としてきた皇室では、次第に皇子の名前には通字として「仁」の字が使われるようになりました。仁は不仁以外、悪い熟語のない素晴らしい言葉であり、それこそ天皇や皇室が理想としてきたものを体現する文字です。
御幼少の頃から、やはり仁徳天皇を理想とされた昭和天皇はその孫の皇子が生まれた時、仁徳天皇の諡号から漢字を選ばれ名前を贈られています。現在の天皇陛下です。この命名の説明には漢籍からとありますが、天皇陛下がご誕生された当時の人々は、仁徳天皇について誰でも知っていましたから、わざわざ説明するまでもなく多くの人が仁徳天皇のことを思い浮かべたことでしょう。
言葉の力を大切にする天皇というお立場を考えれば、昭和天皇は終戦後の日本の変化を鑑み、未来の天皇となるであろう皇孫に聖の帝のお名前で言祝ぎをされたということなのかもしれません。つまりは、その未来の天皇の時代を生きる私達への言祝ぎでもあります。
なんといってもそこに昭和天皇の想いが深く感じられるのは、昭和天皇が御幼少の頃から仁徳天皇の民の竈について深く考えていらっしゃったことを知るエピソードがあるからです。それは民の竈についての授業で先生がなぜ民は窮乏したのか?と質問をされた時、ご学友の誰もがお答えにならない中、幼い昭和天皇が(仁徳天皇の父や祖母の時代)長く続く戦のために民が疲弊したからだとお答えになったというのです。民の竈という物語にはその後の物語があるように、その前の物語もあります。
戦後昭和天皇は、日本が復興するには300年かかるとおっしゃっています。そこまで思し召していられた昭和天皇が、その後未来の天皇としてご誕生された皇孫に仁徳天皇の名前を託されたということには深い意味があるのだと思わざるをえません。
私はいつの頃からか、この民の竈の物語は聖の帝の物語だけでなく、古来からの日本人の民度も物語るお話だと考えるようになりました。天皇が窮乏していたら、その天皇になり替わろうとした人がいてもおかしくありませんが、そうした人はいませんし、免税の時期が終わると人々がこぞって君主の住まいを整えたなどという話が古今東西世界のどこにあるでしょう?君主が素晴らしければ民も素晴らしい。私達は素晴らしい先人達の子孫です。
見本とする多くの懸命な先人達がいる我が国はとても幸せだと思います。見本があれば見倣うことが出来るからです。しかし、それもきちんと知らなけらば見倣うこともできません。
現在の日本の姿をみれば、日本中が経世済民についてしっかり考えるべき時といえるかと思います。そのためにはこうした歴史を知ることです。多くの人がこうしたことを知るだけでも、意識や思考に影響を与え変わってくると思いますが、知らなければ始まらないからです。
御歴代の天皇も為政者であった武将や大名も、災害や飢饉の度に免税や減税を行ってきた国が我が国です。こうしたことは、現代の政治家や財務省などの官僚はきちんと知って勉強したほうがいいでしょう。東日本大震災の時のように、困難な時に増税するなど日本の歴史上異例事態であったことを考えてほしいと思います。
そして今こそ、悪税になると予想されていて実際その通りとなっている消費税をなくし、日本を活性化させるべき時でしょう。消費税をなくしても免税ではなく減税です。多くの人が税金を支払っています。消費税をなくすことで経済が活性化し日本が盛り返すとは経済の専門家がずっと言い続けていることです。
なお民の竈の話から、無税の話だと勘違いする人もいるようですが、その後の大土木工事を知れば天皇と民が一丸となって新しいことを始めるのに無税であったわけがないと理解できるかと思います。そもそも無税で成り立つ国家などないことは誰でもわかることだと思います。(当時、労働も税の一つとしてありました。)
それにしても古代の大土木工事を始めた当時、そのような前例がない時代でしたからそれは大冒険だったと思います。そのような冒険に、天皇と民が信頼しあって船出したことを知ると現在の私も頑張ろう!と思います。つまり、民のかまどと仁徳天皇についての物語は、自らを言祝ぎし、ひいては自分の未来、つまり日本の未来も言祝いでいるのだと最近考えています。日本の未来とは、そこに生きる自分の未来のことです。だからこそ、困難な時代に語られてきた物語なのだと。
竹田恒泰さんも、昨年こんな時期だからこそと民のかまどについて話をされています。
竹田さんが読まれているのはご自身で現代語訳にした「現代語古事記」
日本書紀にも記載があります。
300年先まで思召した昭和天皇と、戦後復興を行われた天智天皇についての本
仁徳天皇が行ったことは、それ以前からの皇室、天皇の伝統であるということ。
天皇と皇室は、古来から二つの家訓を守ってきたということを御製や和歌から紐解いた一冊
にこ姉@NikoNe_san_2525
元なでしこ澤穂希さん「みんな辞退するなら私が走るわ」五輪聖火リレー第1走者に いつも澤ちゃんにはキラッキラ✨のイメージしか浮かばない。こんなに眩しい女性、そうそういない。 https://t.co/yGLqUj61f3
2021年03月19日 00:34
西村幸祐@kohyu1952
個人情報保護法の欠陥は、本来守らればならない情報へ、アウトソーシングの回路で平気で誰もが簡単にアクセスできるシステムがユルユルに許容されているのに、学校や企業の名簿、同窓会の名簿も作らせないという、本末転倒した偽善がはびこる日本社会そのものにある。 @kohyu1952
2014年07月12日 11:38
アノニマス ポスト ニュースとネットの反応@anonymous_post2
LINEトーク画面の画像と動画はすべて韓国のサーバに保管されておりますのでご安心くださいw もちろんLINE Payの取引情報もw~ネットの反応「安心しました! アンインストールします」「芸能人の不倫会話画面のリークは、韓国からな… https://t.co/HWYpCaak3c
2021年03月18日 23:34
リフレ女子@antitaxhike
「国内メーカーが伸びないなら誘致するしかない」 いや、国内メーカーを伸ばすのが本当の国策でしょう。外資を誘致するより時間はかかるだろうが、その方が長期的な国益に必ず資する。そもそも国内基盤が弱体化してしまったことこそが政府のこの… https://t.co/gWrp8bHbb7
2021年03月19日 05:35
荒木健太郎@arakencloud
群青モーメント. https://t.co/RiAt6wx99V
2021年03月19日 05:22
映画「ブレイブ -群青戦記-」@brave_gunjo
☁┫#ブレイブ語録┣☁ 力を持つものには それに相応しい定めがある。 よ お く ぬ 考 し え が ろ 何 光 を 徳 と 信 川 な じ 家 る… https://t.co/rCQzjEaTCo
2021年03月18日 18:00
講談社ENT!@tokyo1week
/ HMV&BOOKS #日比谷コテージ 『映画ノベライズ 天外者』 🔥大 好 評 発 売 中🔥 \ #日比谷シャンテ 3階📣 エスカレーターを降りてすぐ右側の棚に✨ #天外者 #天外者ノベライズ本 #三浦春馬… https://t.co/v0v1rLrAYP
2021年03月17日 22:16
吉祥寺プラザ(公式)@kichi_plaza
3/19(金)より当館『森の学校』『天外者』再上映スタート となります。今回は4/15(木)までの4週間。 期間中には三浦春馬さん出演作のドリパス上映も予定しております。 若葉ゆれる季節にみなさまをまたお迎えできるうれしさ。 スタ… https://t.co/qOMYeelIet
2021年03月18日 21:48
高橋優@takahashiyu
https://t.co/u7EopA6XyJ
2021年03月18日 09:55
あらみたま 🇯🇵 君が代ー我らはひとつ We are One & We will win@aramitama9
「八卦良」 それって最初からおっしゃってましたっけ? 契約書をよくご覧下さいとか言って ここに来りゃ全部上手くいくと誘っといて 気がつきゃ崖っぷちの椅子取りゲーム すぐにシワがつく服みたい 最初だけいい顔したがり 男も女も… https://t.co/u9bEUYh90N
2020年10月26日 05:47
あらみたま 🇯🇵 君が代ー我らはひとつ We are One & We will win@aramitama9
君が代 〜我らはひとつ〜 KIMIGAYO 〜We are one〜 https://t.co/TrrZzVJ1la
2020年12月15日 05:18
🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎