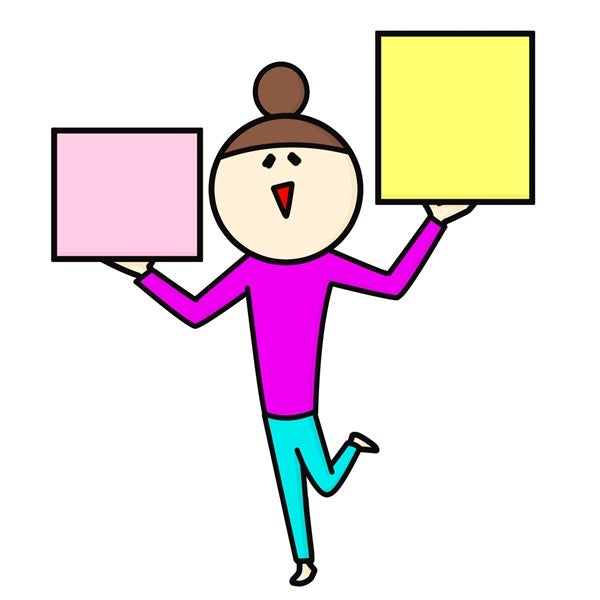前回、釈徹宗氏( 相愛大学学長。人文学部教授)の監修による「お経と仏像で分かる仏教入門」と、著書の「維摩経 空と慈悲の物語」について書いた。
今回は、著書「バカの壁」(2003年)がベストセラーになった(平成で一番売れた新書と言われている)養老先生と、スリランカのテーラワーダ仏教を日本で伝道するスマナサーラ長老の間の公開対談で、進行役と聞き手を釈先生が務めている。
養老先生の著書には「バカの壁」をはじめとして、「○○の壁」というタイトルの本が多い。
「無知の壁」というこのタイトルも、養老先生のそうした著作のシリーズを意識したものだろう。
本のタイトル:「無知の壁」の「無知」は、仏教の中ではどのような意味を持つのか、また養老先生が「バカ」と表現しているものと共通する部分があるのかというのが、この対談のテーマである。
その意味では、もしかすると「バカと無知」でもよかったのかもしれないが、ちょっと攻撃的な響きがする。まさしくこのタイトル名の本も出版されているが、書いているのは別の人(橘玲氏)で、もちろん内容もまったく別物である。
話をこの対談に戻すと、スマナサーラ長老と養老先生の間で、話があまり嚙み合わない部分が多い。
そもそもの発想や用語が異なる二人の「対談」を成立させるために、釈先生が、単に聞き手としてだけではなく、自らポジションをとって話をし、架け橋役となっているところもある。
それはこの場合にはどうしても必要で、欠かせないものであったとも思える。
養老先生の「バカの壁」を釈先生は次のように要約する:
釈 「つまり脳にある枠組みががっちりできてしまうと、脳はその枠の外のことをそもそも認識しようとしない、それをバカの壁と表現されたわけですね」
養老 「そうですね、自分で書いておいてなんですけど、「バカの壁」とは何か、一言で言うのは難しいですが、そういう「枠」ですよね」
釈 「どうでしょう、スマナサーラ長老。
仏道を「我々がついもってしまっている自分の枠組みを通してしか物事を認識していないことに、まず気づく。そしてその枠組みをはずすトレーニングを実践する」
というふうにとらえるならば、養老先生のお話をスマナサーラ長老が説いておられる領域はかなり共通しているんじゃないでしょうか」
スマナサーラ 「まったく共通していますね。
だから「バカの壁」っていうのはいい言葉ですよ。
先生は真理をすごくおもしろい単語を用いて世の中に広めたんですよね。
対談の中では話を合わせているけれども、養老先生自身の言葉では、「バカ」に込められた意味は、次のように説明されている。
細かく言えばいろいろあるのですが、まとめて言えば、結局は、「意識には限界がある」ということです
また、実際の「バカの壁」のまえがきでは、養老先生はこう言っている:
結局われわれは、自分の脳に入ることしか理解できない。
つまり学問が最終的に突き当たる壁は、自分の脳だ、そういうつもりで述べた。
釈先生は、「バカの壁」の意味を、自身の言葉で表現し、定義し直すことで、仏教の思想との接点を広げようという試みを行っていたのではないだろうか。
一方で、スマナサーラ長老が考えている「無知」とは何か。
スマナサーラ「無知の状態とは、どんな生命も本能的に持っている生存欲(存在欲)の状態です。
長老は、「本能・感情の衝動で生きること」を「無知」の状態と呼んでおり、知識・理性・智慧の働きで、「無知」の状態から脱していくことが、人間の正しい生き方であると説く。
順番で言えば、本能・感情の衝動で生きることは無知で、物事を学んで生きる能力を上げることが知識で、人格的によりよい人間になることは理性で、人格を向上して本能に打ち勝って、心の汚れをなくすことが智慧ということになります。
結論として、養老先生がもともと考えていた「バカ」と、スマナサーラ長老の言う「無知」は、同じ概念ではなかったと考えるべきだろう。
それでも、三人の間の対談の中には、示唆に富む話が多い。
そして、養老先生とスマナサーラ長老の考えが交錯し、共鳴していると思える言葉もある。
たとえば、スマナサーラ長老は、
「自我が実在しないとわかる人は、死を恐れません」
という。
一方、養老先生の対談での言葉:
死というものは、生きていないとないわけでしょう。
だいたい、(自分自身の)「死」について考えたって本当にダメなんです。
は、「バカの壁」の続編として書かれた「死の壁」では、もう少しわかりやすく、次のように説明されている:
そこで悩むのは、そもそも「一人称の死体」が存在していると思っているからでしょう。
死ぬのが怖いというのは、どこかでそれが存在していると思っている、一人称の死体を見ることが出来るのではという誤解に近いものがあります。
極端に言えば、自分にとって死は無いという言い方が出来るのです。
そうすると、「(自分の)死とは何か」というのは、理屈の上だけで発生した問題、悩みと言えるかもしれません。
こんなふうに、自分の死というものには実体がない。
それが極端だというのならば、少なくとも今の自分が考えても意味が無いと言ってもよい。
死んだらどうなるかは、死んでいないからわかりません。誰もがそうでしょう。
しかし意識が無くなる状態というのは毎晩経験しているはずです。
眠るようなものだと思うしかない。
そんなわけで私自身は、自分の死で悩んだことがありません。
死への恐怖というものも感じない。
養老先生にとって、「意識」や「心」は、脳の働きが生み出しているもの、脳という臓器の機能であって、それ自体に実体があるものではないという立場であり、それが「唯脳論」という本のテーマでもあった。
お二人が言おうとされていることは、表現方法やアプローチは違っていても、深い部分で相通じているように思える。
ところで、スマナサーラ長老は、先ほどの続きの語りの部分で、「理性」と「信仰」について、意外なことを言っている。
仏教は信仰を推薦していないのです
信仰と理性というものはお互い相反するもので、信仰が強くなってくると理性が死んでしまいます
信仰ではなく、理性で物事を考えて人生を歩むことが、お釈迦様の推薦なのです
生きる上で、ちょっとした安心感を得るために何かを信じてもいいのだけれど、お釈迦様が言うのは
「それだったら、ましなものを信じなさい」
ということですね
長老は、信仰をすべて否定するという立場ではないと最後に言っているのだが、ひとくくりに同じ仏教と言っても、例えばひたすら念仏を唱えることがが大事だとする日本のの阿弥陀仏信仰とはずいぶんと異なった思想である。
日本国内の仏教でも、さまざまな宗派が分かれて共存しているが、こうした多様性を許容できること自体が、仏教という宗教の一つの特徴なのだろう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
※当ブログ記事には、ミツキさんのイラスト素材がイラストACを通じて提供されています。