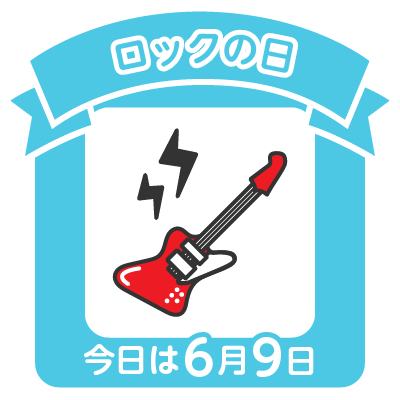好きなロックな曲教えて!
「な」って言われてもぉ![]()
▼本日限定!ブログスタンプ
埼玉大学の非常勤講師時代の講義やその当時興味があったロックについて書いた過去ログを並べて振り返ることにしました。
![]() カンボジア、ミャンマー、
カンボジア、ミャンマー、
ロックのイメージがないのですが、
東南アジア旧植民地のロックは政権の変化によって
社会風刺も伴った楽曲が愛好されていた半面、
社会習慣に馴染まない題材は批判の対象でした。
![]() 所謂「大衆音楽」21世紀に入り、グローバル化が進む。
所謂「大衆音楽」21世紀に入り、グローバル化が進む。
言語の違いが特徴として残るのですが、
感情表現なども民族・国特有のものが残っていました。
さらに何をロックと呼ぶのか。
また20世紀に分類されていた名称は意味をなさなくなりました。
![]() 講義で必ず取り上げていた香港のBeyond
講義で必ず取り上げていた香港のBeyond
好きだったのもあるのですが、
1900年代末期は、まだまだアジアの音楽に馴染みがなく、
「電波少年」も認知度が高かったので入口として。
その後、香港の芸能界は大陸化するか、
昔日を懐かしむかのようになってしまいました。
![]() この映画、すごく良かったです。
この映画、すごく良かったです。
途中、会場でチベット人の姿と国旗でテンションUPしました。
![]() ヴィジュアル系とかこういうパロディとか、
ヴィジュアル系とかこういうパロディとか、
あれから最終的に日本文化をいっぱい吸い込んでこのタイプは
アニメっぽいところに落とし込んでいって。
![]() どうでもいい。
どうでもいい。
音楽とかリスとか萌える自分ですね。
![]() 前にもまとめていました。
前にもまとめていました。
デジタル化・プロと素人の線引きの変化。
これは着目しなおしですかね。
令和の新しい音楽って何もしらない。
たぶん私のキャパをオーバーしたんでしょうね。一度、聴いたらすぐ再現できたり楽譜に書けたりという才能は不要だった??
これからは新しいものでなく、すでに身に付いている音楽を取り戻そう。
アメリカで黒人音楽風を白人がロックんロール、ロカビリー。英国でビートルズやローリングが旧植民地の音楽を取り入れ、インド人のフレディ・マーキュリーが西洋クラシックを取り入れ※「ラジオで聴いた曲を、その後ピアノで再現する、特異な能力を持っていた」(私と同じ。これ全然普通。トレーニングしていれば誰でもできる)
そして3コードのパンク。メロディーライン、実はイングランドの労働歌だったりもします。要するにロックと呼ばれる音楽は4度ベースでのコード進行と言語と自国のメロディーラインと「トリオ・ソナタ」(※ベース音+ソロ3の共演・バロック音楽の編成)
ところで、実母世代はプレスリーで、年の差婚配偶者はビートルズで、私の世代はヘビメタ。30代半ばの息子は台湾。それより若い子は「けいおん」かな?さらに若い子は把握できていません。