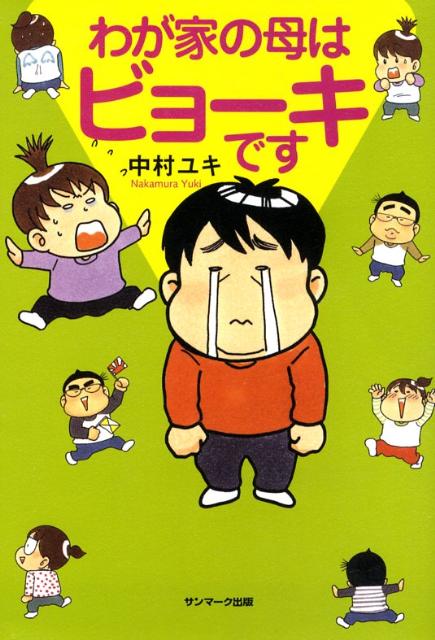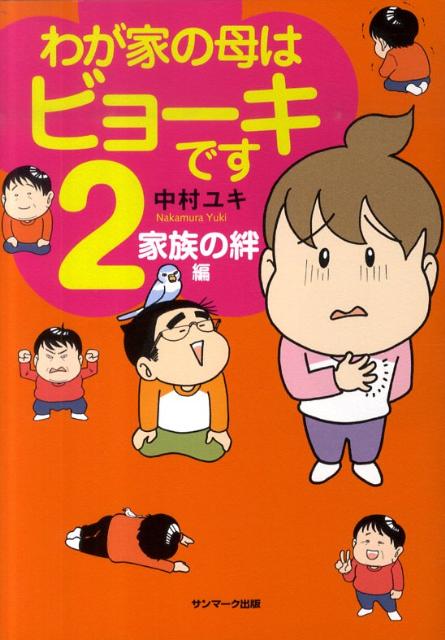精神保健福祉士の勉強を始めながら、精神疾患の当事者・家族が描いたエッセイや漫画などを読み進めています。
精神の病気は目に見えないから、実際どんな状態なのか、そのあたりは漫画などに表現されると、すごい伝わるんですよね。
うちら起立性調節障害(重度)とかコロナ後遺症とか慢性疲労症候群も、やはり「目に見えない」という点で精神疾患(統合失調症やうつ病)と同じような苦悩があります。
「脳機能障害」としては重なるエリアがあると感じます。
だから、うつ病や統合失調症の人たちの手記は、我が事のように伝わるんだと思います。
中村ユキさん著の「わが家の母はビョーキです1」「わが家の母はビョーキです2」「マンガでわかる!統合失調症」が素晴らしかったです。下にリンク貼ってます。
著者の中村ユキさんは、自分が物心つく前の幼少期からお母様が統合失調症という、大変な境遇からこの病気を理解していくのですが、その過程が見事に描かれていて圧巻でした。
これを読むと、ウチの息子は統合失調症ではないとは分かるんですが、以前の記事に書いたことがあるんですけど、もし統合失調症の「幻覚」「妄想」がなければ、そのほかの症状や悪化に向かう様子などは慢性疲労症候群に重なるので、息子のケースは「脳の機能障害」であると捉えると色々な改善方法が見いだせると感じました。
「マンガでわかる!統合失調症」中村ユキ著(日本評論社)のP172〜173に、「家族が病気になった時 悲嘆から回復までのプロセス」というのが、「1」〜「11」まで書かれています。
出典は「児童精神科医が語る〜響きあう心を育てたい」佐々木正美著、を一部抜粋加筆訂正したもの、とのことです。
これはまさに、私自身が息子の病気を受け止めてきた過程をなぞるもので、きっと多くの当事者家族の方も共感されるんじゃないかと思うので、抜粋してご紹介します。
詳細はぜひ、書籍を購入してお読みくださいませ。
※このたび、ブログ記事にするにあたり中村ユキさんご本人に連絡させていただき、記事と書籍一部写メの掲載についてご快諾いただきました。ありがとうございます。
「1」精神的打撃と麻痺の状態・・・強い衝撃を受け、何が起こっているのか分からない、本当のこととは思えない
「2」否認・・・家族が病気であるという事実を拒否する、そんなわけない、誤診だ
「3」パニック・・・家族の病気から目を背け続けることができなくなる時期がくる。病気なのかそうじゃないのか自分の中で収集がつかなくなり一種のパニックに陥る
「4」怒りと不当感・・・パニックが収まってくると問題が正確に見えてくる。同時に「なぜ自分たちだけがこんな思いをしなければならないのか」というやり場のない怒りや不当感が強まる
「5」敵意と恨み・・・病気の家族を持たない他者を嫉妬、羨望、敵意、恨みが生じる
「6」罪悪感・・・1〜5のような感情の中で気持ちが冷静さを取り戻す段階に入ると、自分を振り返り自責的な感情に支配されるようになる
「7」孤独感と抑うつ感情・・・周囲から離れて孤立した感覚
「8」精神的混乱と無欲無関心・・・孤独と抑うつの中で日常生活の目標を失った空虚な気持ちに支配され何をしたらよいかわからなくなる
「9」あきらめから受容へ・・・本格的な回復、再生の始まり。「あきらめ」とは自分の置かれた状態を「明らかにする」ことで決して消極的な態度ではなく、むしろ勇気をもって積極的に現実に向き合うようになる(病気についての勉強を熱心にはじめる、など)
「10」新しい希望、ユーモアと笑いの再発見・・・家族が病気になる前の希望、ではなく、今の生活の中で新たな希望に気づく。ユーモアと笑いが生まれてくる
「11」新しいアイデンティティの誕生・・・苦悩に満ちた困難な過程を経て、新しい価値観や、より成熟した人格をもつ者として生まれ変わる
以上。
これらは、必ず「1」から順に進むというわけではなく、「5」〜「8」を行ったり来たりとか、一瞬「9」になったのに、また「6」に戻ってメソメソ・・・とか、そういう感じにもなるようです。はい、なりました私も。
どす黒い思いも湧きました。
苛立ちや罪悪感をいったりきたり。
どうしようもない無気力に襲われたり。
皆さんは、いかがですか?
私は最初は必死でネット検索→同病の方のブログ閲覧→書込み交流→直接メッッセージ交流→当事者グループや、親の会への参加、そしてブログを通して出会った方との交流を通じて、「7」と「8」を越えてきたと感じます。
私は息子の病気の発症後8ヶ月目でブログを開始したのですが、その頃に「9」に入ったのだと思います。途中で何度も4,5,6,7,を彷徨ってはまた「9」になっていた頃です。
ブログを始めたことで仲間が出来て、ジワジワと自分の変化が起こり「10」に入っていったと思います。
書いて発信するというのは、ものすごいエネルギーが要りますが、リターンも莫大です。
ブログでは少数ですが「10」、まれに「11」の視点から描ける方がいらっしゃるんですよね。「11」は書籍出版されてたり、何らかの支援サイドの活動をされてる方が多いと感じます。
ブログを書く、という言語化する作業は一定の客観視が必要ですから、そういった方がいらっしゃるのだろうなぁ。
「7」「8」の段階で、最も支援が必要、と書かれていますが、まさに。
ブログを通して同病の方と交流したり(コメントしたりメッセージ送ったり)地域で開催される「起立性調節障害の親の会」みたいのに参加するなど、人と繋がることでしか癒やされない部分があるように思えます。
著者の中村ユキさんのHPでは、講演会配布リーフレットを読むことができます。
家族として、病者にどういった対応をすることが望ましいか、少し分かると思います。
病で苦しむ子に、家族としてどう接すると良いのか、どう接すると悪化するのか、詳細については書籍をぜひ!内容が統合失調症なのですが、あらゆる「脳機能障害」の方と共通するエッセンスが読み取れると思います。
統合失調症の症状とその対応の中から、うちら親子に共通するエッセンスを汲み取って読む必要があるので、我が子の病(慢性疲労症候群らしき病態)への一定の理解が深まってから読んだ方がいい場合があるかもしれないので、どうぞご自身のタイミングで選んでくださいね。
それにしても、中村ユキさんは、最初から親が病気の子ども、という立場であるから、それはもう甚大な努力をされたことでしょう・・・感服です!
現在、苦しい只中にいる方たち、繋がっていきましょうね。