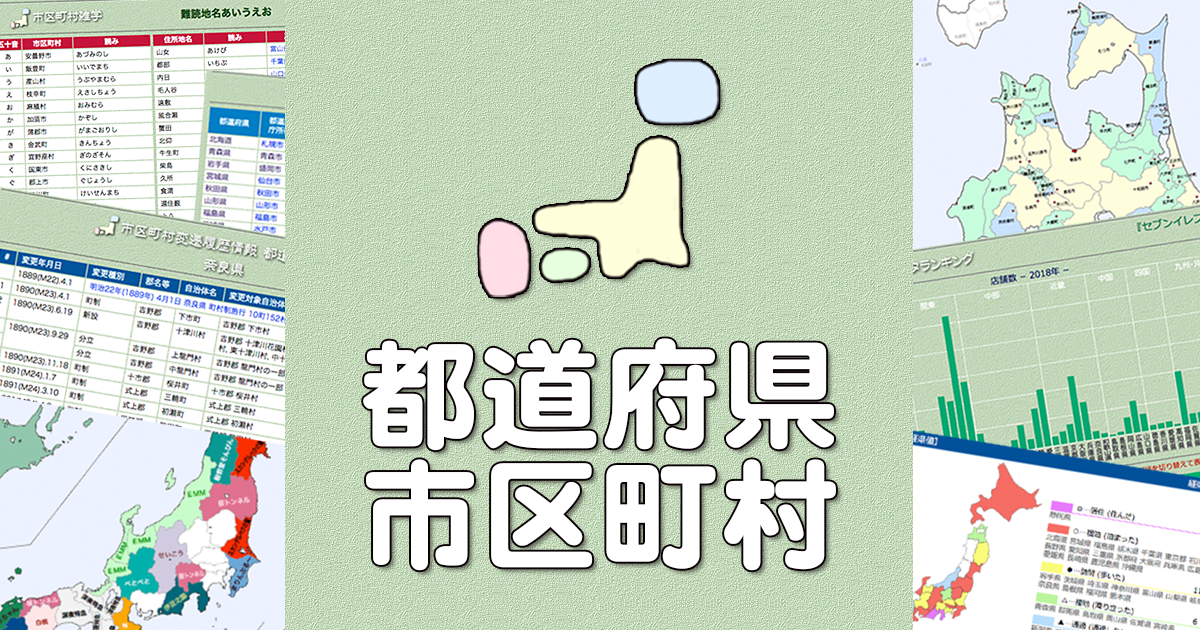消滅可能性と危機を煽るな】日本の人口減少って悪いこと?年金制度温存のために人に犠牲を強いるのはナンセンス
日本は2008年に総人口が1億2808万人に到達後2023年現在は1億2435万人にまで減少しこの減少傾向はしばらく継続することになる。2023年時点の日本全国の高齢化率は29.1%。
2021年の東京都の高齢化率は22.9%。
2021年の大阪府の高齢化率は27.7%。
東京都の1年あたり出生数は1989年から10万人前後。2020年は99661人。
日本全国の1年あたりの出生数は1989年は124万6000人。2015年には100万人。2020年には84万人。2023年には727万人。
東京都、首都圏在住の人々は、東京都内の1年あたりの出生数の減少速度が他地域と比較して非常に緩慢で全国の出生数の数字に対して東京都の出生数の数字の比率が高くなるから、少子化や日本全国の人口減少を実感しづらいのが困ったもの。
埼玉県の1年あたりの出生数の推移は1989年が6万3000人。2000年6万600人。2021年は4万5000人
沖縄県の1年あたりの出生数の推移は1989年が1万7000人くらい。そして2019年に1万5000人以下に低下して以降回復していない。
基本的にエネルギー効率の良い地域は人口が増えやすく、エネルギー効率の良くない地域は人口が増えにくい。こんな単純な事実に気づけない人が多い。
東京都は合計特殊出生率は低いがこれは、婚姻率の極めて低い大学生が多く居住しているからでもある。
15から49歳の女性のTFRの数字が低くなるのは当然。そして都内の25から49歳の女性のTFRの数字なら、相応に高くなるだろう。
日本全国の人手不足が語られることは多いが、人口が集中している首都圏で人手不足などまず発生し得ない。そして首都圏の平均所得はその他地方より一段高い。そして首都圏の外側の地方は平均所得が低いにもかかわらず恒常的な人手不足が何年も前から継続している。
つまり人手不足なら賃金が上がるかというなら、それは当てはまっていない場面が多い。私は何度も書いたようにエネルギーにも課税される消費税を減税しないことには所得、生産性が上昇しないのである。マクロ的には同じ国の内部であるなら、物価水準は人口の多い地域と少ない地域に対して作用しているのだから人手不足の地域の賃金が上がりにくいというのは不思議なことではない。
いま一つ気づいたこと。日本人は土地本位制的な価値観を持っているが、相続税制度を誰かがこの世を去った時に、その人の土地家屋を1年間国が預かって、その土地に相応しい値段を付け、相続権のある人のうち土地家屋を利用したいという意志を国に対して示し国が付けた値段分の支払いをするなら土地家屋を事実上の相続ができるが、しかし、相続する権利を持つ人が土地家屋を買い戻す意志及び支払い能力がなかったなら国が不動産屋向けのオークションをし不動産屋経由で市場に流通させられるというルールにしようとしたら、大抵の日本人は抵抗するだろう。
東京都内の土地家屋を以上のようなルールで市場に流通させようとしても、それでも宅地不足は発生しうるほどに東京都、首都圏内の他地区がもはやもはや枯渇寸前にまできている
東京都、首都圏内の人口も住宅戸数も飽和状態なのだから、人口を地方分散するように誘導するしかない。首都圏で人手不足など発生していないのに、どういう理由でか首都圏内の人々は人手不足という言葉を使いたがって、移民受け入れ促進もやりたがっている印象がある。
すぐにできる施策は私大も含めた大学の学費無償化。これをすれば高い学費の元を取るために首都圏にとどまらずに全国各地に人が分散しやすくなる。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/221522/r3_jindo_kakutei_2.pdf
エネルギー効率の良い地域の合計特殊出生率は高めになり、1年あたりの出生数も多くなる傾向がある。