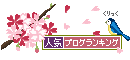緩い登りになってる小径。
結構な距離がある先の方は、薄暗くぼんやりとしていてよく見えない。
あの日、よく晴れていたはずなのに、道の先が霞んでいたのは、
何度も何度も擦って腫れてしまった瞼のせい。
おおちゃんが、女の子といた。
肩を抱いてた。
一緒にエレベーターに乗ろうとしてた。
すごく可愛い人だった。
迷惑そうな顔してた。
おおちゃんが、女の子と…
ぐるぐる、頭ん中でさっきのシーンがループして、なんか、吐きそうになって。
「はい、着いたよ」
「あ、はい」
ぐったり沈み込んでたシートから慌てて体を起こして、取り繕った笑顔の僕に、
「あれ? 君、よく見ると可愛いな。ジャニーズとかいけんじゃない?」
「…はは、とんでもないです」
お釣りくれながらそんなこと言う運転手さんに、
僕、もうジャニーズなんです、なんて言えるはずもなく。
まだ、全然世間に認知されてなくて、
その分、全然自由で。
そう、何やったって自由なんだ。
おおちゃんが、彼女作ったって。
………
…もう、いっかな。
ふらつく足で、ガイドブックで何度も見た美しい橋に向かう。
何がもういいのか、おおちゃんに彼女がいたからって、それがどうしたっていうのか。
自分でも分かんなくて踏み出す足がとても重くて向こう岸がとても遠くて、こんなよろけた足じゃ渡り切ることなんて到底無理そうで。
サラサラ頭上の葉擦れの音が、あの時の萎れたココロを呼び覚ます。
「オレ、あん時絶望のどん底でさ、橋歩きながらこのまま川ん中、飛び込もうかなって思った」
「ぅおい、そりゃ、ねぇだろ」
「そんだけショックだったっていうこと」
「自分で勝手に暴走しやがったくせに」
「ふふ、でもね、あまりにも観光客とかが多くてタイミング掴めなくてさ。そしたら、たまたまオレのこと知ってる子がいたんだ」
トボトボ歩いてたら、向こう側にいた家族連れみたいな集団の中から女の子が駆け寄ってきた。
「あっ、あのっ、二宮くんですよね?」
同じ年くらいの髪の長い可愛い子。
「…そうだけど、僕のこと、知ってるの?」
「はい! 私、ファンなんです!」
「え?うそ、なんで?」
「ドラマとか舞台とか見て、いいなーって思って」
ほら、って見せてくれたピンクの携帯、パカッと開いた待ち受けは精一杯のアイドルスマイルの自分。
「わ…、どうもありがと…」
「今日はお仕事なの?」
「う、ううん、休みで遊びに来たんだ」
「あ!もしかして大野智くんとこ?」
いきなりのビンゴで、心臓が飛び出しそうになった。
聞くところによると、その子は結構なジャニヲタで舞台とかも結構見に行ってるらしかった。そして、大野さんとは地元が一緒で小学校も近かったらしく、すっごく応援してるんだよって、熱く語った。
「今日、大野くん誕生日だもんね。お祝いに来たの?」
「…うん、まあ」
…そういえば、リュックどうしたっけ。
あん中にプレゼント、入れたままだ。
― 行くよー。
「はーい!」
向こうから母親らしき人に呼ばれて、女の子は焦って早口で続けた。
「ずっと応援してるから頑張ってね。大野くんにもおめでとうって伝えてね」
「…うん、ありがとね」
「そのうち二人、おんなじグループとかでデビューしてくれたら、最高なんだけどな」
「はは、それは無いよ」
「ざんねーん、あ、握手してもらっていいですか?」
「もちろん」
差し出された手を両手で包んで握手したげて、
きゃあ、って頬を真っ赤にして走ってく女の子にバイバイって手を振ったら、いつの間にか水に飛び込む気分はすっかり失せてた。
こんな、ジャニーズの最下層にいるような自分のこと、見てくれてる人もいるんだなあって胸が一杯になって、貴重なオレのファンのあの子の伝言、大野さんに絶対伝えなきゃって使命感に燃えて、僕は無事に橋を渡り終えた。
「すげぇな、その子、預言者だな」
「うん、まさか、その1年後にほんとにデビューするなんてね」
今でも覚えてる。古い型の携帯、小っちゃい画面の、今とは比べ物にならないほどの不鮮明な待ち受けの中のオレ。
得意げに見せてくれたあの子は、今頃どうしてんだろう。
きっと、結婚して子供とかいて、一緒にご飯食べながらテレビに映ったオレらを見て、そういえばあんなことあったな、なんて思い出してくれてんだろうか。
それとも、そんなことなんかすっかり忘れてて、テレビももちろん『プレバト』かなんかで。
ふふ、それとも嵐さんよりもジャンプくんとかに嵌ってたりして。
「何、笑ってんだよ」
「うん? すごいなって。人に歴史あり、オレらに歴史ありだなって」
「はぁ?」
あ、あの先のベンチ、あん時のじゃね?
どうしよう、戻ろうか、でも今戻ったらきっとあの女の子と一緒だろうし。
このまま帰ろうか、あ、でもリュック無きゃ困るし。
径の脇の休憩スペースのベンチで膝を抱えて、溜息をつく。
迷って、悩んで見上げた空。
凛と立つ竹の隙間から、眩しい秋の空が煌めいてる。
目に沁みるほどの緑と青と。
どうしてこんなにキリキリ胸が痛いんだろう。
どうしてこんなに泣きたくなるんだろう。
どうしてこんなにおおちゃんのこと、憎たらしいんだろう。
…なのに、どうしてこんなに逢いたいんだろう。
僕は、おおちゃんのこと…
「いた! かず、見つけた!」
「…え、ええっ? おおちゃ…ん?」
なんで、なんで…?
「こら、逃げんな!」
ベンチを降りて走り出そうとした僕に、おおちゃんは怖い声で怒鳴った。
固まった首をギシギシ回してそっと振り向けば、僕の重たいリュックを背負ったおおちゃんがゆっくりと近づいてくる。
「…?」
あと10mってとこで、体を追って膝に手を着いてハアハアと息を荒げてる。
「…どうしたの?」
「そ、そこに居ろ、逃げんなよ」
おおちゃんは、体を起こしてまたこっちに向かって歩き出した。
僕は足まで固まってしまって、前にも後にも動けずにゆっくりと歩いてくるおおちゃんを、ただ見ていた。
「ハアハア、なんで、おま…、逃げんだよ…」
ようやくベンチまで辿り着いて、ドサリと座りこむ。
キレイな顔を、ギュッとしかめて。
「おおちゃん、顔、真っ赤…」
「近づくな、感染るぞ…」
あ、って呟いておおちゃんはポケットからマスクを取り出して鼻と口を覆った。
「…風邪?」
「インフルエンザ…」
「え…」
思わず手を伸ばし、汗ばんでる額にそっと触れてみる。
アチ…
指先に感じた温度がびっくりするくらい熱くて、ハアハア、呼吸も浅くてすごく苦しそう…。
「…大、丈夫?」
「…大丈夫じゃねぇよ」
「なんで…」
「かずが逃げっから」
「…だって…」
「ヘンなこと想像してっだろ」
「…だって…」
「ばぁか…」
キツそうに閉じてた目が少しだけ開いて、いつもの優しいたれ目になった。
「…お、お、ちゃ…」
どうしてこんなに胸がキュッと縮むんだろう。
どうしてこんなに嬉しいんだろう。
どうしてこんなに嬉しいのに、涙が出るんだろう。
「う、うぅ…、ふっ…」
「泣くな。かず、おれの誕生日、祝ってくれんだろ?」
おおちゃんの開いた手の平の上、ゲームキャラクターのストラップ。
主人公よりも脇役が好きだから、僕がマリオでおおちゃんはヨッシー。
「リュックのポケットに入ってた。リボン付きの袋ン中」
「うん…、こんなのしか上げらんないけど」
嬉しいよ…っておおちゃんは僕をギュッと抱きしめた。
「でも、おれ、ほんとは他の、もらうつもりだった…」
「何を?」
「…んなこと、言えねぇ。こんなとこで」
「…?」
なんかよく分かんないけど、おおちゃんの顔がもっと赤くなって、背中に回った手がもっと熱くなったから、僕はマジで心配になって立ちあがった。
「帰ろ。おおちゃん、このままじゃ死んじゃう」
「…死にゃあしねえけど」
「だって、すごい体が熱いよ。さ、早く立って」
「こんままじゃ、心残りあり過ぎて死ねるワケねぇ」
「ゴチャゴチャ言ってないで、ほら、立てる? もぉ、フラフラじゃん」
「…一体誰のせいで…」
それからヨロヨロのおおちゃんを支えて、なんとか一般道まで歩いてタクシーを拾った。
おおちゃんは車の中でもずっと苦しそうに目を閉じたままで、時々、うわごとみたいに僕の名前を口にしてた。
神様、おおちゃんを助けて。
「かず、待て、行くな…」
行かない、どこにも行かないから、神様、お願い。
ようやくマンションに着いた。
「あ…」
エントランスに立っていたのは、さっきの女の子……? あれ?
女の子だと思ってたけど、よく見るともっと年上で、なんか、薄いピンクの上下、多分ナース服を着てる。
そして、ヨタヨタと入ってくる僕らを、腕組んでギッと睨み付けてる。
仁王立ちって、こういう感じ?
「智くん! あなた、死ぬ気?!」
「…るせぇ」
「とっとと部屋に戻んなさい!!」
怒鳴りながら、バンバンと音を立ててエレベーターの上昇ボタンを叩いている。
…なんか、状況が見えてきた。
押し黙ったまま、降りてきたエレベーターに乗り込む。
ほんとはすごくキレイなのに、鬼の形相の看護師さん。
ハアハアと、苦しそうな大ちゃんの浅い呼吸だけが、狭いハコの足元に溜まっていく。
そして、この最悪な状況の原因が僕だってことも。
続く。
ぽちっと押してね!