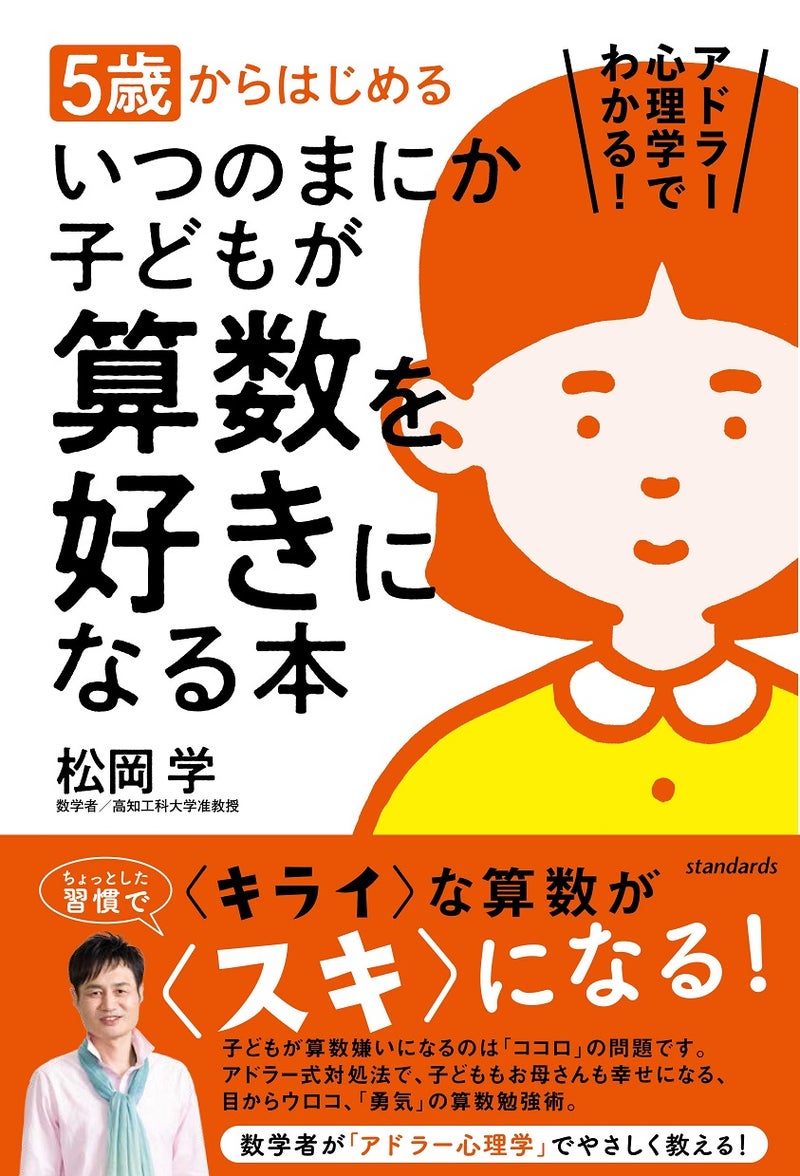算数・数学的な感覚を磨くにはどうすればよいのでしょうか?
難しく考えたり、身構えたりしなくても、
意外と身近なところにヒントが潜んでいるような気がします。
素朴に、
りんごが1つ、2つ、3つ、・・・
と数えますが、 これらの数は、
「偶数」 と 「奇数」 に分けることができます。
偶数:2,4,6,8,10,・・・
奇数:1,3,5,7,9,・・・
つまり、
2で割り切れる数が偶数で、
2で割ったとき、1余る数が奇数です。
ただ、そのような正確な用語を習う前から、
子どもたちは感覚的に理解していると思います。
小学生のとき、
「ニー、シー、ロー、ハー、トウ」
「イチ、サン、ゴウ、ナナ、キュウ」
などのように口ずさみ、親しみながら覚えるのです。
このような素朴なことが、
数学的な感性につながるのだと私は思っています。

口ずさみながら、無意識のうちに
整数が「偶数」と「奇数」に分けられることを覚えますが、
ちょっと意識することで、
さらに興味深いことが分かってきます。
たとえば、
3+4+5 を計算すると、12 となり偶数です。
でも、
なぜでしょうか?
当たり前のように思えますが、
ちょっと考えてみてください。
3+4+5 を計算すれば12になるので、
当然偶数になるのですが、
このことを偶数と奇数の性質から説明できますか?
そこが数学的な発想のポイントなのです。
どう考えればいいかというと、
3は奇数、4は偶数、5は奇数
であることに注目します。
そうすると、
3+4+5
は、どのように見えますか?
よく見てください。
そう、
3+4+5 は、
(奇数)+(偶数)+(奇数)
に見えてきましたか?
これは偶数か奇数かどちらでしょう?
ということを考えているのです。
計算をすると、
3+4=7 になり、
7+5=12 となるのですが、
これは、
(奇数)+(偶数)=(奇数)
(奇数)+(奇数)=(偶数)
と表されます。
まとめると、
3+4+5 が偶数になることの説明は、
(奇数)+(偶数)+(奇数)
⇒ (奇数)+(奇数)
⇒ (偶数)
となります。
いかがでしょうか?
偶数と奇数の言葉で理解できましたか?
ここでは、次の性質を使いました。
(偶数)+(偶数)=(偶数)
(偶数)+(偶数)=(奇数)
(奇数)+(奇数)=(偶数)
こうやって並べて書くと何気ない式のように思えますが、
これらは偶数、奇数の性質を表す大切な式なのです。
そしてこれは、
小学校の算数だけでなく、
中学、高校の数学にまでつながる重要な性質なのです。
高校生になると、偶数は2k、奇数は2k+1 のように
文字で表して式変形をします。
文字で書くと難しそうに思えますが、上に書いた性質が基本です。
また、先ほどの説明に 12 は出てきません。
つまり、3+4+5 を計算せずに、
答えが偶数であることを示したことになります。
これくらい小さい数だと、
計算した方が早い気もしますが、
大きい数を考えてみましょう。
38641+83962+28135
これはどうでしょうか?
計算するのはちょっと大変です。
でも、偶数になることが、計算せずに分かります。
なぜなら、これは
(奇数)+(偶数)+(奇数)
の形になっていて、先ほどの
3+4+5
と同じ構成になっているからです。
パッと見ただけでは、
3+4+5
38641+83962+28135
は同じ式に見えませんが、
偶数、奇数を意識すると、同じ種類の式に見えてきます。
このように数の仕組みを通して、
式の意味を考えることが数学的な発想なのです。
また、
「3+4+5」 を
「(奇数)+(偶数)+(奇数)」 と表現することを
抽象化といいます。
具体的なものの本質を見抜き、
抽象的に表現することは数学で大切な手法です。
ここでは、偶数、奇数に潜んでいる
数学的なエッセンスを書かせていただきましたが、いかがでしたか?
これまで見てきたように、偶数、奇数を通して、
数学で大切な考え方を理解することができます。
ですから、
小学生のうちから偶数、奇数の感覚をしっかり養いたいものです。
☆ 子どもの算数力アップを願う、お母さんのための本
子どもの算数力を育てる接し方を、
アドラー心理学にもとづいて書かれています。
実践しやすいように具体的に書かれています。
< 関連記事 >
◆ お母さんが読むだけで、子どもの算数や数学の成績が上がるコラム
◆ 不思議の国のアリスと算数・数学ファンタジー ~ まとめ記事 ~
◆ 0(零)の不思議