
ちょっと長いのですが、子どもの発達に関する記述をご紹介します。
人間はどうやって「社会的存在」になるのでしょうか?
端的に申し上げますと、物心がついた時に「安心」しているかどうかで全てが決まります。
この「安心」は昨今にメディア上で濫用されている「安心」という言葉が指すそれとは次元が違うものです。
自分がこれから申し上げようとしているのは「人間が生きる力の源」とでも表現すべきものです。
乳幼児期に両親もしくはそれに相当する養育者に適切に世話をされれば、子供は「安心」を持つことができます。
例えば子供が転んで泣いたとします。母親はすぐに子供に駆け寄って「痛いの痛いの飛んで行けーっ!」と言って子供を慰めながら、すりむいた膝の手当をしてあげます。
すると子供はその不快感が「痛い」と表現するものだと理解できます。
これが「感情の共有」です。子供は「痛い」という言葉の意味を理解できて初めて母親から「転んだら痛いから走らないようにしなさい」と注意された意味が理解できます。
そして「注意を守ろう」と考えるようになります。
これが「規範の共有」です。さらに注意を守れば実際に転びません。
「痛い」という不快感を回避できます。これで規範に従った対価に「安心」を得ることができます。
さらに「痛い」という不快感を母親が取り除いてくれたことにより、子供は被保護感を持ち「安心」をさらに得ることができます。
この「感情を共有しているから規範を共有でき、規範を共有でき、規範に従った対価として『安心』を得る」というリサイクルの積み重ねがしつけです。
このしつけを経て、子供の心の中に「社会的存在」となる基礎ができ上がります。
またこの過程で「保護者の内在化」という現象が起こります。子供の心の中に両親が常に存在するという現象です。
すると子供は両親がいなくても不安になりませんから、1人で学校にも行けるようになりますし、両親に見られているような気がして、両親が見てなくても規範を守るようになります。
このプロセスの基本になる親子の関係は「愛着関係」と呼ばれます。
この両親から与えられて来た感情と規範を「果たして正しかったのか?」と自問自答し、様々な心理的再検討を行うのが思春期です。
自己の定義づけや立ち位置に納得できた時にアイデンティティが確立され成人となり「社会的存在」として完成します。
端的に申し上げますと、物心がついた時に「安心」しているかどうかで全てが決まります。
この「安心」は昨今にメディア上で濫用されている「安心」という言葉が指すそれとは次元が違うものです。
自分がこれから申し上げようとしているのは「人間が生きる力の源」とでも表現すべきものです。
乳幼児期に両親もしくはそれに相当する養育者に適切に世話をされれば、子供は「安心」を持つことができます。
例えば子供が転んで泣いたとします。母親はすぐに子供に駆け寄って「痛いの痛いの飛んで行けーっ!」と言って子供を慰めながら、すりむいた膝の手当をしてあげます。
すると子供はその不快感が「痛い」と表現するものだと理解できます。
これが「感情の共有」です。子供は「痛い」という言葉の意味を理解できて初めて母親から「転んだら痛いから走らないようにしなさい」と注意された意味が理解できます。
そして「注意を守ろう」と考えるようになります。
これが「規範の共有」です。さらに注意を守れば実際に転びません。
「痛い」という不快感を回避できます。これで規範に従った対価に「安心」を得ることができます。
さらに「痛い」という不快感を母親が取り除いてくれたことにより、子供は被保護感を持ち「安心」をさらに得ることができます。
この「感情を共有しているから規範を共有でき、規範を共有でき、規範に従った対価として『安心』を得る」というリサイクルの積み重ねがしつけです。
このしつけを経て、子供の心の中に「社会的存在」となる基礎ができ上がります。
またこの過程で「保護者の内在化」という現象が起こります。子供の心の中に両親が常に存在するという現象です。
すると子供は両親がいなくても不安になりませんから、1人で学校にも行けるようになりますし、両親に見られているような気がして、両親が見てなくても規範を守るようになります。
このプロセスの基本になる親子の関係は「愛着関係」と呼ばれます。
この両親から与えられて来た感情と規範を「果たして正しかったのか?」と自問自答し、様々な心理的再検討を行うのが思春期です。
自己の定義づけや立ち位置に納得できた時にアイデンティティが確立され成人となり「社会的存在」として完成します。
大学時代の発達心理学の授業思い出しますが、そのとき聞いた話より、もっとわかりやすいです。
とてもロジカルですね。
これを書いたのは、昨日の記事にある「黒子のバスケ事件」の渡辺被告。
自分の生い立ちを分析した発言の一部です。
とても自分を遠くから見ている感じがします。
自分自身が 自分の傍観者のような感じ。
でも、愛着形成を的確にとらえた文章だと思います。
養育者との信頼関係をどのように育てていくか、はとても大切な課題なんですね。
この文には続きがありますが、長いのでこちらのサイトをご覧になってみてくださいね。
とても興味深い発言です。
さて。
上の文章では、生きる力の源を「安心」だと言っています。
私もそう感じます。
「こわい」という思いを押さえつけている人ほど、怒りっぽくて、不安で、心配性です。
そして、他人をコントロールしようとします。
安心できないから、いてもたってもいられないのです。
その安心の根源は「愛着」です。
もともとは自分を育ててくれた人との間にできる「きずな」。
世界を見るためのフィルターとも言えるかな。
養育者との間に「安心」があると、世の中は、安心であたたかい場所だと感じられれます。
でも「安心」が欠けていると、世の中は、こわくて不安で自分を責める人ばかり…と感じるようになります。
私が伝えていきたいのも、ここなんですよね。
子どもの心を安心感で満たしたい
「安心感」は、親が子どもに与えられる、最高の宝物だと感じます。
そのためには、
・子どもの話を聞く
・自分の話を聴く
・子どもに話を訊く
ことが、シンプルで簡単な方法です。
もっともっと伝えていきたいな。
今秋は、久しぶりに茨城でも講座をしようかなと思っています。
茨城以外では、ありがたいことにすぐに満席になる私の講座(笑)
なぜか地元では むずかしい…
勇気を出して、近々 お知らせしますね。
遠くて学びたくても学べない…という方には、メール講座がありますよ。
世界一の「大好きだよ!」を伝える10か月プログラム
こころのコーチング講座を受講された方の復習にも、とてもよいと思います。
あと、最近、再受講のお問い合わせも多いので、こちらに書いておきますね。
再受講は、4,980円で承っています。
初期に受講された方は、少し内容が増えていますのでお得です。
再受講のお申し込みはこちらからどうぞ(*^_^*)
たくさんの安心感に満たされた子供たちが増えますように。
これからも活動の幅を広げていきます。
叱るより聞くでうまくいく 子どもの心のコーチング/KADOKAWA/中経出版
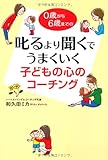
¥1,296
Amazon.co.jp
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング [ 和久田ミカ ]

¥1,296
楽天
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング 0歳から6歳までの[本/雑誌] / 和久田ミカ/著

¥1,296
楽天
