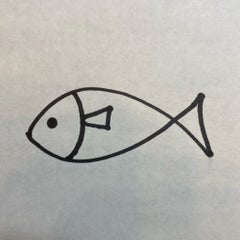DVは、個々の行為の集積ではなく、人間関係そのもの。構造を理解する必要があります。DVは、自分が絶対に正しいと考えている人が押し付けてくる上下関係に他ならず、自分が絶対に正しいというDV傾向が強い人ほど、自分のDV傾向と向き合うことができず、虚偽DV論と一体化した共同親権論や片親疎外論で自分を正当化していく傾向にあります。
現時点で、裁判所で共同親権推進論を持ち出す人は特異な方ですが、今の日本で安易に共同親権が導入されることになれば、DV加害者がこぞって共同養育を持ち出して離婚後の母子に対して干渉する未来が見えます。DVを原因として離婚した母子家庭の多くは精神的に追い詰められるでしょう。推進派は、この問題をどうやって克服するというのでしょう。
今でも共同養育がしたければ、それを阻む制度はなく、共同養育ができないのは制度のせいではありません。婚姻中に共同養育できていなかった者が、離婚後になると急に共同養育を持ち出して干渉をしてくるということが現実に起きています。
高校生の娘が、現代社会のテスト勉強をしていて、「1985年に雇用機会均等法ができてんのに、まだM字型雇用カーブとか言ってんの?35年もかけて何やってたの?」と言っていましたが、それが日本の現実です。ジェンダーに関する認識を社会ごと文化ごと変える政策を怠ってきたこの国で、共同親権制度を導入することが、むしろ女性の自立を阻み、女性に対する暴力を正当化する家父長制的な考えの方に利用されてしまうことの危険性を考えて欲しいのです。
今、ようやく、中高生に対してデートDV教育に関する講座を行う取り組みが増えてきました。DVの構造的理解が日本社会の共通認識にするためには、とてつもない努力が必要です。ジェンダーという点で対称性のない社会。日本のジェンダーギャップ指数が世界の153カ国中が121位と聞いても全く驚かなかった。スウェーデンに留学経験のある知人が、日本の政治家が何十年も前から男女平等とか福祉を視察にくるけれど、何回視察したら進歩できるのと言われると言っていました。
鬼滅の刃で、鬼には鬼にならざるを得なかった切ない理由があるのと同様に、DV加害者も遡れば不適切養育の被害者である場合も多く、激しい攻撃性の裏には、個人の尊重の意味が分からないという側面もあります。
DV被害者は、「貧困の海に放り出されてもここよりはマシ」と、家族という名の呪縛から避難しています。離婚後の面会交流が上手くいかないケースは、同居中の共同養育すら上手く行っていないケースであり、制度をかえれば共同養育できるという短絡的な考えでもって、DV被害者を追いつめないで欲しいというのが私の訴えです。