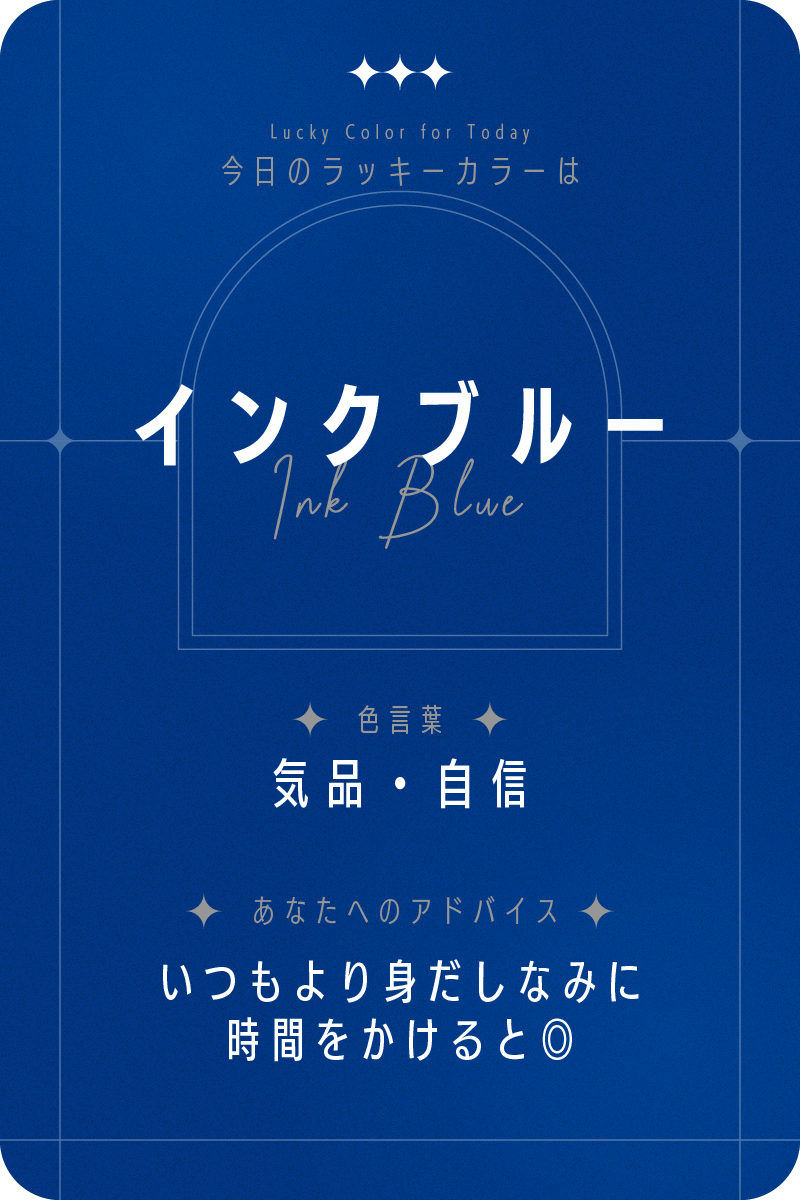お芝居を生で観たことある?
今日のブログスタンプ
歌舞伎の日の歌舞伎はありません―――
ですが
お芝居ならば少なからずはあります……
日本の政界では「 世襲制状態 」
が
大問題に浮上の最中―――
世襲制といえば………
現代社会では、その代表的典型例
が
歌舞伎の世界ではないでしょうか!?
昔々…その昔には
「 河原乞食(かわらこじき) 」
と
蔑まれていたと聞き及んでいるお仕事だったようです
が――
「 梨園 」
なんて
呼称をされるようになった
のは
いったい…いつ頃からだったのでしょうか……
この問題をズッと辿っていく
と
答の出ない
人間の原点にまで突き当たってしまいましょう……
なおチョッと変則的で余談なお話をします
と
金融関係、特に日本の金融機関
は
機械生産とかの形のない物は認めない―――
芸術、芸能関係など人間
の
「 感性 」
に
関するお仕事は決して認めない………
そんな性癖が強い!?
世襲も窮極のところは自分たちの身を守る
身の保身より生じた習性
で
テクニックだということになる…
そして
最終的に他の者をまったく顧みない…
自分独りだけの保身に陥った
時機(とき)――
組織であれ個体であれ調和の消失……
崩壊が待っている!!
残念ながら
その歴史の繰り返し
が
人間ということになる………
歌舞伎の日に因んでひと言
を―――
▼本日限定!ブログスタンプ
2024年2月20日(火)
こんにちは雪月 剛(ゆづきごう)です。
今日も今朝アメーバさんより
先日
2月14日(水)にも寄せられている
「 リブログ 」……
〈 原文に段落行間隔らの改定を施しています… 〉
どうか
よろしくお願いいたします~~~

2023年2月20日(月)
先回の繰り返しとなります
が……
この「 リブログ 」の方
が
適切??
以前より
も
ピッタリと当て嵌(は)まるのかも知れません
ので……
貴重な訓告をふたたび―――
この度も
ここに
やはり引用掲載をしておきたいと存じます―――
2022年6月15日(水) 付―――
──アーサー・ハーディー夫人のレシピ
(南オーストラリア・アデレード/1912年)
The Kookaburra Cookery Book, The Lady Victoria Buxton Girls’ Club
Jacqueline Newling
クーリエ・ジャポン。
タイトル―――
「 食べ物が『 生き物の死体である 』こと
を
私たちは忘れているのかもしれない 」
( 生き物を食べるという人間の行為を著わした文章、
偶然に見付けたもの…… )
一部分にはなりますけれど……
では~~~
食の現実を忘れた人間たち
現代の肉や魚は皮を剥がれ…
骨抜きや切り身にされ…
脂肪や筋を取り除かれ、取り分けられ…
あるいはマリネされ…
そのまま調理できるよう、
プラスチック包装されて売られることが多くなった。
面倒で血なまぐさい、
筋が多く、粘度が高く、ゼラチン質で滑りやすく、
ぬるぬるしていて、油っぽい──
こういった、
動物の部位が持つが持つ「 自然 」に対する人間の寛容さ
を、
水分補給用の小袋、体液や臭いを吸収する包装は失わせる。
消費者にとっては便利
だし、
時間の節約になるだろう。
だが
こうした調理のあり方
は
消費者を、素材となった動物から遠ざけ、切り離してしまう。
私たちは
実践的な技術だけでなく、
それらを扱うことで得られる
感覚的なつながりや感情的な感性も失いつつあるのだ。
現代の食肉に慣れている人の多く
は…
動物の生きていた痕跡
を
感じさせるような肉の断面に嫌悪感を抱く。
頭や舌、足、尾を嫌悪
し、
これらを恐らく野蛮にさえ感じるだろう。
逆に、
動物のすべての可食部を利用する
「 ノーズ・トゥ・テール・ダイニング(鼻から尾まで)」
は、
食肉生産が環境に与える影響を認識
し、
消費用に飼育された動物の命を尊重する方法であるとして称賛される。
食物は単に食べておいしいだけで
なく、
道徳的、倫理的に考えて
も
おいしいものでなければならない──
この格言を考慮するとすれば、どうだろう。
かつての
食物に抵抗したり、あるいは拒絶したりすること
は、
偏見だろうか。
それとも
洗練された味覚の表れなのだろうか。
過去の世代は、
その
嗜好や食習慣が粗野で野暮だったのだろうか。
それとも、
食の現実を直視した彼らの方
が、
実は高い倫理観を持っているのだろうか。
モックタートルスープのレシピ
できるだけ
新鮮な子牛の頭を手に入れた
ら、
割って脳を取り出
し…
よく洗って清潔に
し…
冷水に1時間浸けておく。
かぶるくらいの水と共
に
これを
2、3パイント分シチュー鍋に入れ…
火にかけて沸騰させ、1時間半煮る。
頭を取り出し…
冷めたら
1インチ四方の大きさに切り…
舌の皮をむいて小さく切り…
少量のリキュールと共に鍋に入れ…
翌日まで蓋をする。
鍋の中にリキュールを用意
し…
頭の骨全部と4ポンドの脛肉を入れる。
リキュールが沸騰したら、
レモンの皮1枚、
カブ1個、メース(スパイスの一種)とオールスパイス少々、
スイートハーブをひと束、
白胡椒、塩を加えて味を調えること。
これらを
5時間かけてゆっくり沸騰させ、濾す。
翌日に
これを肉、卵焼き、白ワイン
(シェリー酒が好ましい)
2~3杯と一緒に温める…………
……まだまだ本文は続いて行くのですが以上にします。
料理の素材を人間以外のモノでは
なく
人間自身の身体(肉体)に置き換えてみたら
一般の人たちは
どう受け取るのでしょうか?
作者が言いたいこと
は
人間は皆、
他の生命体を屠(ほふ)って生きている、
屠らなければ
活きてはいけないのが人間…
その
事実を決して忘れてはいけませんよ
と
話されているものと私雪月は受け取っているのです
が………
今日は
2022年2月14日(月)。
この度も、
アメーバさんより寄せられたリブログです。
とても恐縮です
が、
どうかよろしくお願いいたします。
- テーマ:
- ブログ
『 日本って不思議な国? 日本人って不可思議な人種!?』
新パート69
「雪月 剛のブログ216」パート147
2021年2月13 日付 タイトル:
生物たち------
より続く
「 雪月 剛のブログ 」です。
では―――
このような話し方を 何故? 私がするか--------
以前ブログで、
『 ボウフラを知らない子どもたち 』
で
衝撃の体験を描いています。
ですが、
その日に受けた衝撃
は、
その比ではなかったと言いたいのです。
大勢いた子どもたちの中
から
『 えぇー、お魚って、パックに入っているんじゃあなかったのぉー
てっきり僕は、
お魚ってパックに入ってスーパーに並んでいるの
が
お魚だとばかり思っていたよ。 』
『 ヘェー、動いているんだァ!
お魚って
こんな風にして動いているんだァー。』
『 うなぎって、こんな風になっているんだァ。』
『 ヒラメってこんな風になって動いているんだァー 』
という声が 一斉に挙がったのです。
聴いて私
は、
ほんとうに吃驚(びっくり)しか外(ほか)ありませんでした。
そうしたら、一緒にいた若いお母さん方
も
『 私も知らなかったわァーーー
こんな風に活きているのを見たの、いま初めてだよお母さん
もー――。
へェーこんな風に動いているんだァー 』
って…
開いた口が塞がりませんでした。
ひたすらに驚愕〈 衝撃 〉あるのみ-------
〖 母親になるような若い女性たちですら
も、
現実に、
こんな情況を迎えているような社会となっているんだなァ 〗
と
認知せざるを得ませんでした。
嘗て、
魚食世界だと称されていたような日本人
に、
最も馴染(なじ)み深い魚類でさえ
も
〈 観賞用の熱帯魚らは全く別物のようですね? 〉
一地方ではあっても、こんな情況を見せ付けるということ
は、
屠殺現場ら、
普通一般では決して眼にすることのない彼彼女ら
が、
ましてや、
牛や豚や鶏に対する処し方
が
なお更のこと
に、
スーパーのパックになっているのが当然だとしていることでしょう。
であれば、
キャピキャピのテレビタレントたち
が、
自分たちの口に放り込もうとしている、眼前に盛られている肉の塊
が、
ちょっと前には
自分たちと全く同じように生き、
そして、
活発に動き廻っていたことなど
そんな想い〈 想像 〉、
生まれてくる分けありませんよね!?
その現実
を、
私は
子どもたちから目の当たりに教えられてしまった
ということです。
私が嘗て視聴(鑑賞)した映画で、前述をしているところ
の
人間を食べるお話を、 もっともっと想像逞しくして、
人類の近未来世界を凄まじいまでに描写をしている!?-----
ハリイ・ハリスン氏
(アメリカ〈ロシア、ユダヤ系〉1925年~2012年)
という
人物の著作 『 人間がいっぱい 』 より取り挙げた映画、
監督は、嘗てSF映画
「 海底二万哩 」
〈 ジュール・ヴェルヌ(フランス、1828年~1905年)原作、
1954年、SFアメリカ映画 〉
や
「 ミクロの決死圏〈 1966年、SFアメリカ映画 〉 」 を手掛けた
リチャード・フライシャー氏(1916年~2006年)。
主演起用は、映画 『 ベンハ— 』 『 十戒 』 『 猿の惑星1,2 』
らと同じ
チャールトン・ヘストン氏
(1923年~2008年)。
未来人類の食糧難を描いた、1973年4月19日公開、
『 ソイレント・グリーン 』
という
アメリカで制作された、やはり同じSF映画があるのです
が、
ここでちょっとばかり、
あらすじだけを描いてみます-------
2022年…
アメリカ合衆国ニューヨークでは際限のない人口増加によって
あらゆる資源は枯渇。
社会は荒廃をしてしまっています。
人口爆発によって多くの人々が、食品や住居を満足に得ることが出来ず、
街はスラムと化
し…
「 本物の肉や野菜 」
は
一生のうち目にすること
が
出来るか否か、という超高級品に成り果てているのです。
代わりとなる食品
は
「 ソイレント社 」 という会社が供給する
クラッカー状の合成食糧 以外
には
殆ど口にする事ができない有様となっているのです。
一方では…
僅かな特権的階級が巨万の富を以て至上の価値を持つ
「 本物の肉や野菜 」
を
食する極度の二極化社会となっていたのです。
ある夜、
裕福な生活を送っていた弁護士のサイモンソン
( 演者、ジョゼフ・コットン、アメリカ 1905年~1994年、
〈 映画「 第三の男 」で有名俳優、〉 )
という人物
が
何者かによって殺害をされます。
殺人事件を担当する警察官 ソーン刑事
( 主演のチャールトン・ヘストン氏です )
は、
同居人で相棒であるソル
( エドワード・G・ロビンソン氏〈 ユダヤ系アメリカ人 〉
1893年~1973年 )
という老人
の
協力を得て捜査に乗り出します
が、
何度も妨害を受けた末に暗殺すらされかけます。
捜査を重ねた
末…
ゾーン刑事はある真実に辿り着きます。
事件の背景には、禁じられた大きな暗闇
が―――
と、続いて往く映画です。
結論は、タイトルの 『 ソイレント・グリーン 』 という
のは、
人間を原材料として生産をされた
食料品だった
という結末で終わる
凄惨な内容の映画でした。
ソイレント食料とは-------
原作「 人間がいっぱい 」は人口爆発後の世界
で、
小さな殺人事件を追いかけるだけの筋書
なので、
映画版の結末は映画オリジナルだということです。
「 ソイレント 」 という単語自体はソイビーン(大豆)
の
植物性タンパクから人工的に合成をされる食料という意味。
大豆を食料にする習慣がなかった時代の欧米SF小説
では
「 安価な家畜向け飼料を使って工場
で
大量生産されてる人工食料 」
といったニュアンス
で、
割とよく登場する未来食の一種
で、
ちなみに、
ソイビーンの語源はソイソース(醤油)。
ちょっとばかり意味が異なるのかも知れません
が、
既に前述をしているお話でもあるところの――――
隣国中国では、貴賓(きひん)、
もしくは
特別な客を接待する最高級のおもてなし
は、
【 生きたままの猿の脳みそ 】
を
その食卓に供する習慣があると聞きます――――
所変われば品変わる、という格言も世にはあります。
ではありましょうけれど
も、
そういう慣習のない日本人
では―――
身の毛もよだつ光景
の
悲惨な饗応だとしか
受け付けられない(呑み込めない)でありましょう--------
今回は以上です。
それでは、
「 雪月 剛のブログ217 」、パート148に続きます---------
2021年2月 20 日 (土)
雪月 剛
――以上がリブログ……
ありがとうございました。