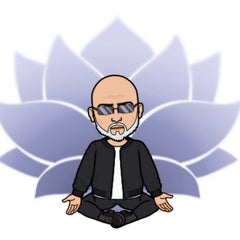❖大阿闍梨の道 比叡山に取り憑かれた三人の阿闍梨
三章 酒井雄哉 生々流転の行者 90
雄哉はいつも草鞋で歩いていた。二度の回峰行も、その後の巡礼、中山道を東京まで歩いたのも、東北恐山までの旅も、九州国東半島の六郷満山峯入行も、山陰・吉備路の旅も、中国の五台山に行ったときも、天台山に行ったときも、全部草鞋で歩いた。いまの人はみんな靴を履く。巡礼で一緒に歩くときに見ていても、底の厚いスニーカーを履いている、それと草鞋では、地べたを感じる感覚が全然違う。草鞋は足が地べたに吸いつく。地べたの感触がよく伝わってくる。固かったり、ぬかるんでぐちゃぐちゃだったり、でこぼこだったり。草鞋だと、地べたのぬくもりも冷たさも感じ取ることができた。草鞋で歩くと、大地の感触が実感として自分のなかに残るん。大げさに言うと足の裏で地球を感じているのである。自分は地球の上にいるんだな、ってことを肌で感じる。草鞋で歩くというのはね、雄哉にとって、そこの自然の一部になることでもあるのだ。それに、自分で歩くということは、ものに頼らないで自分のからだを使って前に進んでいく。ただの移動手段ではなくて、生きる手段だと。毎日、毎日、自分の力で前に進んでいく。それが自分の自信の源になっていくんじゃないのかと考えている。
恐山の菩提寺には、裏堂に慈覚大師さんが祀られている。恐山から見える宇曽利山湖を見た時、湖のほとりに硫黄が噴出していて、湖は一面ずーっとコバルト色で、本当に地獄だって感じがした。山を登って頂上から見える景色が、硫黄とコバルト色の湖だけだったら、地の果てのような印象を受ける。だから、昔は恐山が地の果てだって言われていたんだと思う。恐山には、当時、いたこたくさんいた。雄哉も坊さんだってことを隠して、一度だけいたこさんにみてもらったことがある。でも、全然当たってなかった。しかし、雄哉は不思議な経験をしている。昔、子どもの頃、大阪のおばさんが弁天さまがまつられているところへよく行っていた、雄哉もそこへよく遊びに行っていた。そしたら、そこへ来ていた一人に、「この子、おかしいよ。一生懸命、須弥壇の上に登ろうとして、爪を立ててるんだ。いずれは、須弥壇の上に登るんじゃないの?」って言われた。その時雄哉は、「この人、何言ってるんだ?」と思ったが、その人には、将来雄哉が寺に関係することをするのが、わかったのだろうと。