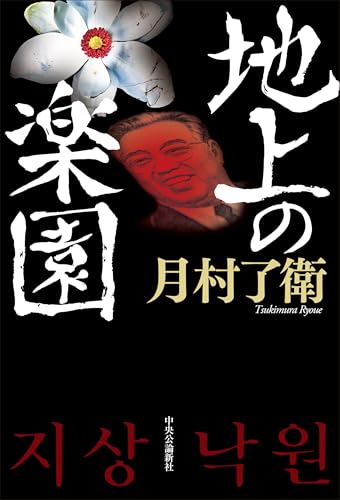いくつか雑な文を書いてみます。雑ですので。
キングクリムゾンのCDを車中で聴いて出勤していたりします。レッドという曲を、中1くらいのときに初めて聴いたのだとおもうのですが、なんかインドっぽい旋律が繰り返され続けるうるさい曲だなと思ったことを覚えています。
あれがインドとかアジアっぽいというのは、いったいなぜそう思ったのかわかりませんが、そんなふうに聴こえるひとは他にいるでしょうか? いわゆるインストゥルメンタルナンバーなんで、歌もないし、それに主旋律もあるようなないような曲です。後に、チープトリックが何枚目かのアルバムでオーボーイという曲をやっていて、それも歌無しのインストゥルメンタルなのですが、それを聴いた渋谷陽一がFMのヤングジョッキー(サウンドストリートだったか)で、
ーーー これは明らかにカラオケですよ
と言っていたのを思い出します。
たしかにオーボーイは、最初足音がして、口笛で旋律を吹き鳴らし、そのあとその旋律をそのままバンドが歌無しで演奏するのですが、それにロビンサンダーがなにかを歌ってしまえば、一曲できあがるはずを、端折ってそのまま売りに出した感じです。
しかしながら、レッドは違うのである。レッドをカラオケにジョンウェットンは歌えただろうか?あれの曲の構成はそのまんま、ロバートフリップがベネット師の学院でのグルジェフワーク修行を終えて出て来たあとのソロアルバム エクスポージャーの中の一曲、ブレスレス(邦題:呼吸困難)でも繰り返したのである。同じように奇妙な旋律をちょっと上げたり下げたりしてくりかえし、途中になんか精神がストップして変性意識に入りました的部分があって、ふたたびハードなエレキギターで上がったり下がったりの繰り返しをする。それで最後は未解決なコードで終わって、人を不安にさせ、
ーー どやねん。おれは病んでいるんじゃ。とりあえず心配しろ!!!
というフリップ師の個人的なメッセージに共感しなくてはならないという、なかなか鑑賞力を問う問題作となっている。
アルバム レッドの録音は難航を極めたらしい。後にビルブラフォードが、言っているようなのだが、フリップはそのときたぶん病んでいたでしょうと(言っていんですか、そんなこと)。だから、彼はずっと黙ってしゃべらなかったので、仕方ないから、ジョンウェットンが仕切ってエンジニアのみなさんとどうにか作ったのでしたと。(やっぱりジョンはいい人だ。)
しかし、病みながら作ったレッドのことを、フリップ師は、あれは傑作のひとつだと言っている。
フリップはたしか、”クリムゾンキングの宮殿”と”レッド”、そして”ディシプリン”を自分の中では傑作だと言っていたと思う。
この3つの共通点は、化学反応であって、たぶんフリップは自分がこうしよう思って作り上げるよりも、やってみたらこんなのできたじゃねえかすげえと言っているほうが面白い人なんでしょう。規模は違いますけれども、僕もそうです。共感できます。ビルブラフォードはイエスをやめてクリムゾンに来たのは、そこがよかったんだと言っているらしいです。
イエスの音楽はすごく技術が高いけれど、イエスの音、というものがずっと存在し続けたと思う。あの声じゃなきゃだめだったので、アンダーソンがいないときは、トレバーホーン(Video kill the redio star!!)まものまねしてアルバムを作ってみたほど、あの声でないとゆるされないのである。しかもトレバーの歌ったアルバム”ドラマ”はすこぶる出来がいい。そんなことは、クリムゾンではどうでもよくて、グレッグレイクの声とジョンウェットンの声はけっこう違う。しかし、それでもジョンウェットンがアル中で抜けたAsiaの日本ライブには、グレッグレイクが歌いに来た。ドラムをカールパーマーがたたいているので、もはやキーボードが変わったELPにイエスのguitarist(スティーブハウ)が参加したようなバンドである。
話がどんどん脱線している。宮殿とディシプリンは、新しい仲間を新しい音楽ジャンルを作ったということが、フリップ師の中の化学反応だとすれば、レッドは確実に、彼が自分のそのときまでの人生のありかたを、葬り去った作品だったんじゃないかと僕は思っています。
レッドの中の最後の曲、Starless and bible blackは、絶望に満ち満ちています。宮殿で、衝撃的にデビューしたかれらは、若者であったがゆえに、まだまだ遊びたい盛りで、分裂していったグレッグレイクが進んでいったELPや、イアンマクドナルドが進んでいったフォリナーは、離れ業の演奏とか、ポップなアメリカ路線に向かう歌謡であったりと、なかなかに若々しい活動に行ってしまったのです。気がふれたような歌詞を歌わされていたジョンウェットンでも、80年代にはなんかいい感じのお兄さんになって(30代だしまだ)イエスやELPを抜けて来たつわものたちと女子がキャーキャーいってくれそうな歌を歌っていたりもしたのでした。
しかしフリップさんだけは、狂気と正気のはざまで生きているかのように、なにか聞いたことのない音楽を作り続ける道をずんずんあるいていって、さらにアバンギャルドな歌い手トーヤさんとご結婚されたのでした。すごいです、あんなことをやって生きて食っていけて今にいたり、老人になってもなぜかかっこよすぎると言う離れ業をやってのけるのでした。