2014年
2冊目
「廃帝綺譚」
宇月原晴明
中公文庫
- 廃帝綺譚 (中公文庫)/中央公論新社

- ¥741
- Amazon.co.jp
時空をこえ、廃された帝王に残されたものとは―――
帝国の崩壊、栄華の終焉。
衰え、敗れ、滅び、流される時、
そこにはただ神の欠片だけがあった。
元末の順帝、明の二代建文帝、
明朝に幕を下ろせし崇禎帝、
承久の挙兵むなしく隠岐に流させし後鳥羽院・・・
廃され追われ流された4人の帝王たちをめぐる、
「安徳天皇漂海記」につらなる連作短篇集。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この短篇集はあくまでも1個の作品ではあるのですが、
作品世界にどっぷりとつかるためには、
あらすじにもある「安徳天皇漂海記」が必読です。
- 安徳天皇漂海記 (中公文庫)/中央公論新社
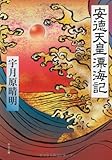
- ¥741
- Amazon.co.jp
できたら是非こっちを先に読んでいただきたい。
あらすじにある「神の欠片」というのが
「安徳天皇~」の物語内で生み出された物なので、
これを知らないと、
何か都合の良いオーバーテクノロジーな代物が
急に出てくるように思えてしまうかもしれませんので。
で、本編の話。
元から明へ、明から清へ
国が移り変わるということは、
滅んでいくものがあるということ。
城は落とされ、町は焼かれ、
兵や民は殺され、あるいは逃げ、
栄華を誇ったすべてのものが、
がらがらと崩壊していきます。
遥かに強い外敵。
修復不能なほど腐敗した政治。
滅びは必定。
全てが失われるのも亦、必定。
しかし、それでも、
守りたいものがある。
一縷の望みを託し、神の欠片に懇願するものとは・・・
というのが、
「北帰范范」
「南海彷徨」
「禁城落陽」
の3篇です。
まとめてざっくり書いたので、
少々違う趣の話もありますが、
だいたいこんな感じです。(適当。というか、記憶が遠い)
軍記物とか読んでても、
最後の城が落城するというのはクライマックスで、
悲喜こもごものカタルシスがあるものですが、
その「悲」を全面に出したような感じ、といえばいいのでしょうか。
大きな諦観と、その中にある小さな切望、
というのが印象的で、
そのために使われているのが
「安徳天皇~」のあの「神の欠片」だというのが、
さらに悲しさと切なさをあおります。
だから「安徳~」は読んでおいた方がいいです!(2回目)
最後の「大海絶歌」は
隠岐に流罪になった後鳥羽上皇の話。
隠岐の海近くの住まいに身をやつした
後鳥羽院の心に去来するのは、
源実朝という男のこと。
実朝というと源家3代目将軍で、
政治には無頓着で和歌を嗜んでばかり。
挙句の果てに、こっそり中国(宋)に渡ろうとして大問題になったりする、
いわゆるボンクラのボンボンとして有名ですが、
「安徳~」では、その辺のエピソードを全部包括して、
鎌倉を、もっと大きく言えば日本を、守ろうとしていた
キーパーソンなのです。
それが分からないと、この時の後鳥羽院の実朝に対する畏れや
実朝の本意が分かりづらいので、
やはり「安徳~」を先に(3回目)
「大海の 磯もとどろに 寄する波
割れて砕けて 裂けて散るかも」
この実朝の歌を、
海を遠景としてしか歌に盛り込めない都の公家たちにはない、
海を間近に見たものの歌だと評するところがかっこいいです。
公家じみた武士だと囁かれていた実朝は、
しかし公家とは違う距離で、目線で海を見ていた。
その理由は、「安徳~」(4回目)
とまあ、どうしても「安徳天皇漂海記」ありきの表現になってしまいます。
「安徳~」未読で読めばそれはそれで面白いとは思うんですが、
あいにく私は既読だったのでこんな紹介の仕方で申し訳ない。
こんなこと書いてるとまた「安徳~」を再読したくなります。
というか、この本を読んだ時も再読したくてたまらなくなったんですが、
積読のせいでそれもままならず。
いずれ、両方まとめて再読したい作品です。