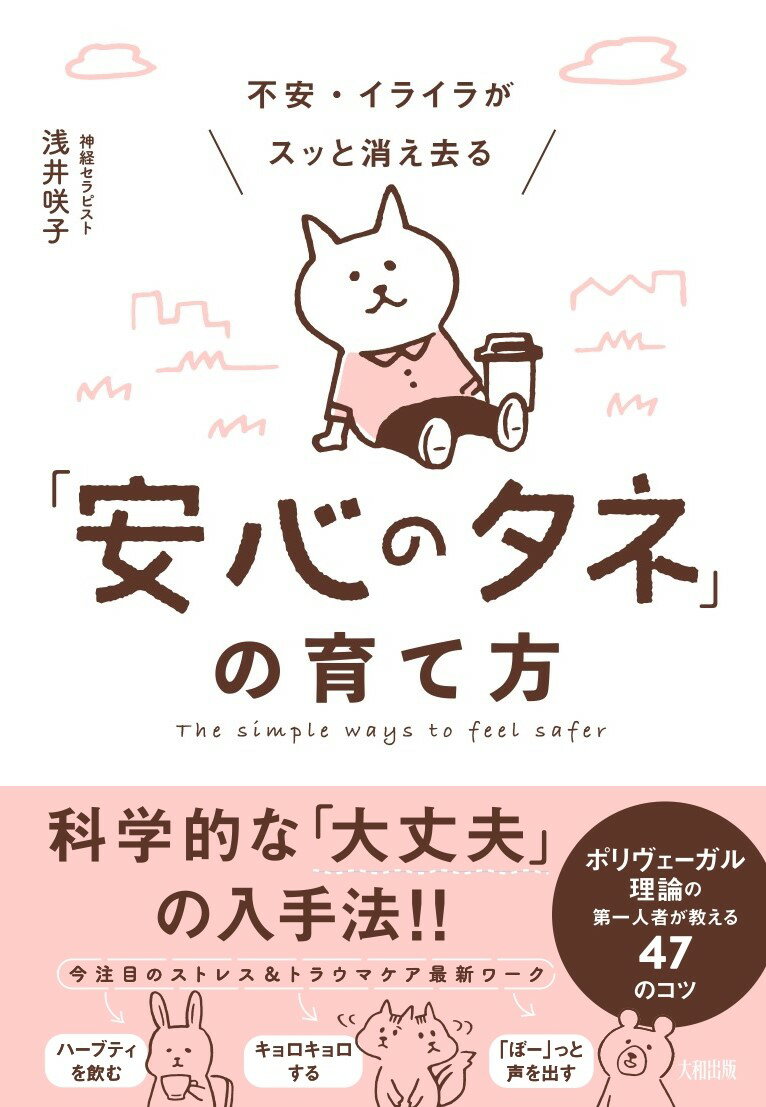認知行動療法的な視点でマネジメントについて書いてみたいと思います。
人間の様々な行動は結果によってその増減、維持が決まってきます。
ある行動を取った結果が本人にとって望ましいものであればその行動は増えますし、結果が嫌なものであればその行動は減少します。
さらに行動と結果の時間差が少ないほど効果的です。
部下の育成・関わりで悩んでいる上司の方などはこれを活用しましょう。
つまり部下が望ましい行動を取ったときは
「すぐに」
「褒める」
「安定的に」
を結果として随伴させることでそういった行動を増加させることができると思います。
増えない場合は「褒める」が部下にとって望ましい結果ではないのかもしれません。
部下一人ひとりにとって価値観が違いますので、そういうときは何がその部下にとってモチベーションになるのか観察してみるといいかと思います。
また、部署やチームなどの集団としての成長も上司にとって重要な任務です。
そういう点では「集団」⇒「個人」の順番で褒める方が無難でしょう。
集団の成長に部下間の競争心を煽る手法を用いている上司も見かけますがあまり得策ではありません。
部下は上司の動悸をよく観察しています。
そういった上司のもとではメンバー間の関係性が悪くなり、集団としての成績を出すことは難しくなります。
あと部下とのコミュニケーションをどうしたらいいか分からない上司もいるかと思います。
あまり「内容」に拘らないことが肝だと思います。
認知行動療法では行動を「数」に置き換えます。
複数の部下がいるなら部下それぞれと
・何回挨拶をしたか
・何回褒めたか
・何回電話したか
・何回食事に行ったか
等を記録してみましょう。
結構偏りがあるものです。
できるだけ均等になるようにしましょう。