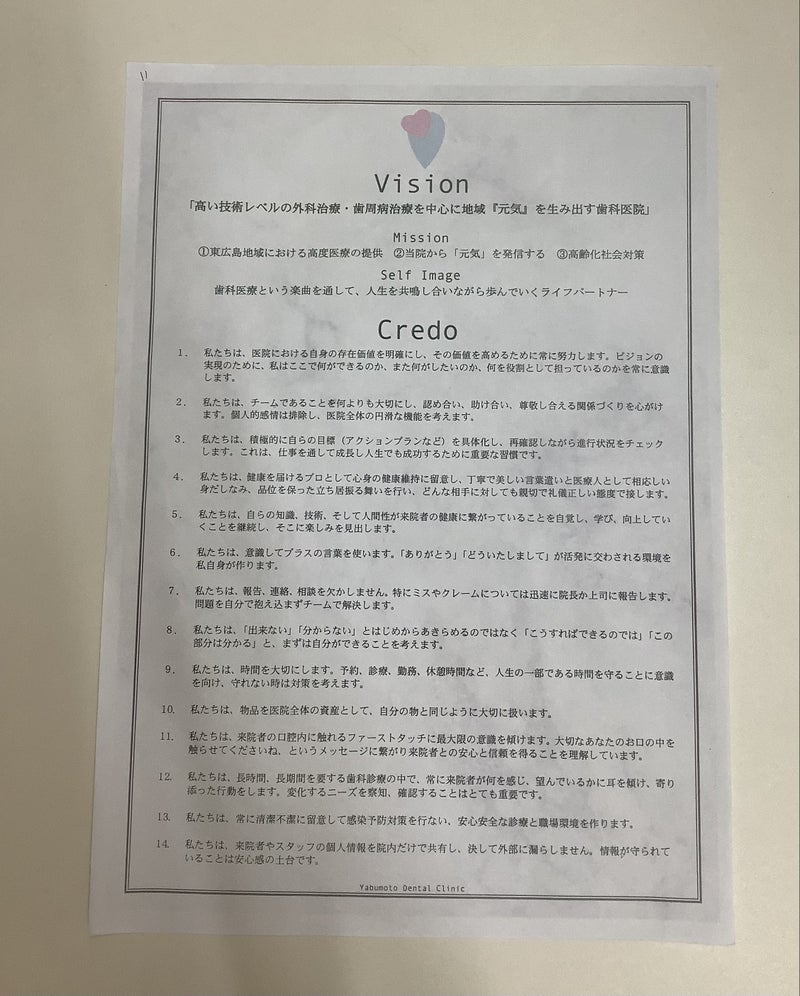こんにちは。歯科助手・受付の内木です。
4月になると、春の訪れとともに、新しい季節に身を清めるような気持ちになります。
そして健康や美容に関するケアも忘れてはいけません。特に、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアは、健康に関わる重要な習慣です。そこで今回はプロフェッショナルケアの意義や効果について、ご紹介したいと思います。
1.バイオフィルム(歯垢)と歯石の除去
バイオフィルム(歯垢)は、口の中で常に形成される薄いフイルム状の細菌の集まりです。放置されると硬化して歯石となります。歯石は歯ブラシやフロスでは取り除けず、専門的な道具を使用した器械的除去が必要となります。定期的なプロフェッショナルケアによって、歯科衛生士が歯石やバイオフィルムを適切に除去し、歯周病やむし歯のリスクを軽減します。
2.歯の白さと輝きの維持
食事や飲み物によって歯に付着する着色物やシミは、ブラッシングだけでは完全に取り除けません。歯科医院での専門的なプロフェッショナルケアによって、歯の表面の汚れを除去し、歯の白さと輝きを保ちます、これにより自信を持って明るい笑顔を維持することができます。
3.口腔内疾患の早期発見と定期管理
口腔内疾患の代表でもある歯周病は、歯茎の炎症や歯周ポケットの深さなどの徴候から早期に発見することが重要です。定期的なプロフェッショナルケアの際に歯科医師や歯科衛生士が口腔内を詳細にチェックすることで、歯周病の早期発見や適切な治療が可能となります。これによって、歯周病が進行する前に予防措置を講じることもできます。
4.口臭の予防
口臭は、口腔内の細菌の増殖によって引き起こされることがあります。定期的なプロフェッショナルケアによってこれらの原因を除去することで、口臭の予防に効果的です。
5.全身の健康と関連性
口腔の健康状態は、全身の健康と密接に関連しています。歯周病などの口腔疾患は、心臓病や糖尿病などの全身疾患のリスクを増加させる可能性があります。定期的なプロフェッショナルケアや歯科検診によって口腔健康を維持することは、全身の健康を保つための重要な手段の一つです。
これらのことから、定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケアは、口腔健康を維持し、美しい笑顔と全身の健康を保つために不可欠なプロセスなのです。
当院では患者さんごとのリスク状態に合わせたプロフェッショナルケアの内容、期間をご提案させていただいております。
患者さんのご希望も出来るだけ取り入れさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。