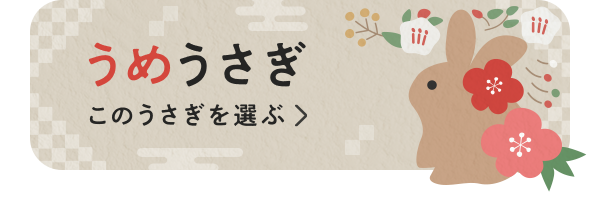- 前ページ
- 次ページ
三島由紀夫を読み返そうかと考え中。没後50年だという。
学生時代に一度ほとんどの作品を読んでいるけれど、今、三島由紀夫の生きた歳を超えて、違う感想を持つに違いない。
三島由紀夫を知ったのは梶原一騎の漫画『夕やけ番長』(荘司としお・画)で、主人公の赤城忠治は三島由紀夫の自決に衝撃を受ける。子どもの漫画にそんなエピソードをぶち込んで来るところはいかにも梶原一騎。
最後の小説『豊饒の海』を読んだ時、本当に三島由紀夫の書いた小説なのか、と思うくらい平凡でつまらない作品でがっかりした。
おそらく、三島由紀夫自身も自分の才能の枯渇した事を悟っただろう。死にたくなったのもわかるように思う。
自分の才能は終わった。しかし、そんな理由で三島由紀夫は自殺しない。それは三島由紀夫の美学の問題なのである。三島由紀夫は国を憂いて死ぬ、という演出を考え、実行した。
よく考えたら、そんなことで死ぬ理由など全くないのに。
なんで今更二十五年以上も前の、佐川道場に通っていた話を書き始めたのかというと、最近になって、いろいろ分かって来たような気もするからなんですよ。
それは合気とかそんな大仰な事ではなくて、技を掛けられる、とか、投げ飛ばされるという事の大切さというか、学びとる姿勢についてです。
自分は体も固いし、柔道をやってた時の癖なのか相手に技を掛けられると、反射的に力を入れて萎縮するんですね。こうすると、相手はやりづらいわけです。
それはね、柔道ならよかったかも知れない。しかし、佐川道場では、やりづらい相手というのは面白くないんですよ。
あの時は分かっていなかったけど、投げられてるだけとはいえ、教えてもらってるのだから、もっと体を繊細にして、神経を研ぎ澄まして、上段者の技を受けなければならなかった。そういう教えてもらう姿勢みたいなものを、きちんと出来てなかったんですね。
やりづらい相手というのは、上段者にしてみれば面白くないわけです。こっちに悪気は無いんですけどね。
で、ある時上段者のひとりに思い切り肩関節を極められる。周りで見てた人は外れたと思ったらしい。自分はそれほどでもなかったんですよ、その時はね。
しかし、翌日の朝起きると肩動かせないんですよ。ポケットに手を入れようとするだけで、痛い。近所の接骨院に行ったら「ああ、これは治らないよ。よくはなるけど、元には戻らない。一生違和感残るよ」って、あっさり言われる始末。
それでも、稽古に行くんですけど、痛くて痛くてどうにもならない。仕方ないので、ちょっと休んである程度良くなってから出直そうと思うているうちに、何年も経ち、佐川幸義先生もお亡くなりになって、自分の中で、なんだか、人を倒す、って事に興味を失ってしまいました。
リハビリと、体力維持のためにジム通いを始め、肩もだいぶよくなってから、空手の道場に戻ってみたものの、以前のようにはのめり込めず、二年も続きませんでした。
ただね、なんだか最近佐川道場の事をよく思い出すんですよ。あの時習った技の事なんかをね。あれはこういう事だったんじゃないか、あの時佐川幸義先生の仰った事はこんな事だったんじゃないか、って。
まぁ、もう確かめようもないわけですけどね。
おしまい。