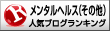それでは今回は
の続きをお届け致します。
ちなみに前回の記事でもお伝えした様に、感じ方にはそれぞれ個人差がありますので、あくまでも「私の個人的な感想」として、私らしく"歯に衣着せぬスタイル"で書かせて頂く事をご了承頂けますと幸いです。
☆_(_☆_)_☆
ではここから感想に参ります。
(^^✿
日本最古のバレエ団である谷桃子バレエ団のSWAN LAKE(白鳥の湖)」を今回初めて拝見させて頂いて、まず私が全体から受けた印象としては、踊っていない時の細かい演技等含めて、全幕物には不可欠な「調和」が隅々まで行き届いていたという事です。
そしてそれは何から来るかと言うと、それぞれのダンサーの方々が持っている誠実さ・気品・愛らしさ・健気さ・素朴さといった「人間らしい温もり」から生まれているという事が分かります。
その雰囲気は、私に取っては「古き良き時代のバレエ」という、何処か懐かしさを感じるレトロ感だったかもしれません。私がバレエが大好きになった「小学生の頃の自分を思い出す」様な、そんな感覚がありました。
だから私は今回3回全ての公演をハシゴさせて頂いても、全く「飽きる」という事がありませんでした。
そしてそこから日本のレジェンドバレリーナとして、今も語り継がれている故・谷桃子さんの「心で踊る」というバレエに対する美学と精神が、しっかりと今の谷バレエ団にも受け継がれているという事を私は感じました。
ちなみに「他ではあまり見られなくなった」と私が思えたそのレトロ感というのは、今時のバレエに有りがちな「皆が主役」という様な、皆がテクニックのみに囚われ過ぎて、何か大事なものが失われている様な、技術は凄いけど何処か殺伐とした"自己主張の強い雰囲気"と言うか、
まるで「ダンサーがオリンピック競技をしている」かの様な、全体の調和を欠く「アーティストと言うよりアスリート」といった様な感じが、このバレエ団のダンサー達からは一切感じられなかったという事です。
ちなみに私が若かりし頃に憧れたバレエには、ちゃんとものの作りにも「適材適所」というものがベースに有って、それは振り付けに於いても「主役が際立つ様な全体のバランス=ドラマのクライマックスを盛り上げる為の全体的な工夫」というものがキチンと計算して考えられており、演出されていた様に思います。
そういう一見目立たない所から、実は「情緒」というものが生まれるのですが、最近の方達は生活に追われて心に余裕が無かったり、アナログだった時代とは違い、何でも簡単にスピーディーに安易に手に入れられる「忙しない機械の時代」のせいなのか、
そういう「情緒」というものを繊細に感じ取れたり、理解出来る人間は、極僅かになってしまった今の世の中の様に私は感じます。そしてそれはクラシックバレエの世界にも、随分前から反映されている様に思います。
勿論いつの時代も「成長と発展」というものが大事であり、常に「進化し続ける」という事は、人間の営みには不可欠なものでもありますが、
何でも行き過ぎてしまうと「進歩と思っていたものが、いつの間にか気付かず後退している」という現象に転じてしまうという事も起こります。
今の時代のバレエは、そんな事を感じてしまう事が私には増えてしまい、そしてそれが私が引退後に「バレエの世界から離れた大きな理由」だと自分で思います。
ですので、今回観させて頂いた谷バレエ団の舞台は、逆に「そのレトロ感から生まれる情緒感が、私にはとても新鮮に感じられた」という事をお伝えしたいと思います。
そしてそこから、団員の皆様を日々指導されておられる方々の「バレエに対する造詣の深さ」というものを感じ取る事が出来たという事も、私が今回お伝えしたい事の一つでしょうか。
( ・・) ~ ☆彡☆彡☆彡
ではここからは"歯に衣着せぬ"の、少々細かい感想になります♪
(^^✿
一幕と三幕に登場する重要な役の一つである、高度なテクニックが要求される道化ですが、13日の昼の公演で拝見した清水豊弘さんに感じたのは、緊張感からなのか「少し踊りと表情が固かった」という事でしょうか。
ドラマを盛り上げる狂言師としての役割を持つ道化の役には、奥深い知性というものが要求されますが、それと共にもっと「陽気な明るさと遊び心」が有った方が、より魅力的になると私は思いました。
13日の夜に踊られた松尾力滝さんと、14日に踊られた児玉光希さんのそれぞれにチャーミングな道化には、その点も含めて私は大変魅了されました。
そして3回公演ともヴォルフガング(王子の家庭教師)役を演じられた、ゲスト出演の井上浩二さんからは、人間味のある温かさが伝わって参りました。
同じく3回公演とも王妃(王子の母親)役を演じられた、このバレエ団の元プリマバレリーナで在られた尾本安代さんですが、多分「尾本さんのお人柄が自然に滲み出ているのだ」と感じましたが、私的には非常に「日本的な王妃様=温か過ぎる」様に感じられたかもしれません。
何故ならヨーロッパの王族・貴族というものは、実際の歴史から見た生い立ちというものを見ても「冷徹で尊大でクールなキャラクター」である事が多いからです。(※これはロシアのバレエスタイルが好きな私の好みという事でご了承願います)
あと王妃様の少々縦長過ぎる王冠に、全体のバランスの悪さというものを感じました。そのアンバランスさは「王妃の威厳」というものを逆に削いでしまった様に個人的には感じました。(※正直過ぎてすみません)
ではここからは、第一幕の最大の華であるパ・ド・トロワに付いてですが、13日の昼に拝見した前原愛里佳さん・石川真悠さん・吉田邑那さんには初々しさを、夜に拝見した馳麻弥さん・北浦児依さん・田村幸弘さんにはソリストらしい力強さを感じました。
そして14日に拝見した、多分今回の公演で一番注目されたであろう永倉凜さん・大塚アリスさん・昴氏吏功さんですが、とてもチャーミングな印象を受けました。
ただ今回YouTubeでもかなり話題になっておられた、私が応援したいバレリーナのお一人であるアリスさんに感じた事は「とても品格があって美しいけれど、思ったよりも弱かった」という事でしょうか。
やはり「本番の舞台でしか見えて来ないものがあるなぁ」と、今回の舞台から私は改めて感じましたが、
彼女にはロシアのバレエ団に入団出来るほどの「バレリーナに必要な恵まれた条件を持たれた方」なので、私は「更にこれから場数を踏まれて、成長されて行く彼女」に期待したいと思いました。
その点、やはり私が好きなダンサーのお一人でもある凜さんは、今回非常に安定感がありソリストとしての見応えを感じました。凜さんの様に「本番に強い」というのも、ソリストやプリマに成るには必須条件だという事を、今回の舞台から私は思いました。
そして全幕を通してのアンサンブル(※三幕のキャラクターダンス含む)に感じた事は「調和が有りとても良く揃っていて、谷バレエ団らしさを感じる誠実さ、真摯さ、ひたむきさと愛らしさ、そして丁寧さというものが感じられましたが、
時にそれは「幼さ」や「子供っぽさ」として目に映る様な事にも繋がる感じも正直致しました。
その要因として「日本人の小柄な体形から来ている印象」というものもあるかもしれませんが、でもそれは「もっと厚みの出る上体の使い方」というものをマスターすれば、改善出来る様に私は思いました。
私の記憶に間違いが無ければ、14日にスペインを踊られた今西由記さんと川名佑芽さんの、スペインらしいダイナミックな上体の使い方とアクセントが大人っぽくて素敵でしたし、
そして13日の昼・夜にロシア(ルスカヤ)の真ん中を踊られた山口緋奈子さんの繊細で表現豊かな上体の使い方に、私はとても「バレエ」を感じて非常に好感を持ちました。
昔と違い、今はバレエを習い始めると同時に。猫も杓子も「子供の頃から人と競う事を要求されるコンクール漬け」という、未だバレエ後進国と言われる日本バレエ界の、子供を育てるというより、非常にビジネス色が色濃い、バレエを習う子供達に歪さを生じさせる事も多い「コンクール三昧な環境」からの影響があるのだと思いますが、
今では多くの「コンクールダンサー」とも揶揄される様な芸達者なバレエダンサーの方達も増えてしまい、まるでアスリートの様に「派手なテクニックに拘る事に夢中」な状況が色濃いバレエ界で、
今回のルスカヤの様に、一見地味に見える様な静かな動きの中に、洗練されたバレエ芸術が持つ「情緒的で優美な魅力」というものを感じられる繊細な感性を持たれた方は「今時一体どのくらいいらっしゃるでしょうか?」という事を、今回の優雅でチャーミングな彼女の踊りを拝見しながら同時に思った私でしょうか。
そしてこの様な深みのある繊細な上体の使い方を、テンポが速くても使える様になると、踊り全体にドラマティックな奥行きが生まれますので、日本人特有の「子供っぽさ」をカバー出来ると私は感じました。
それはクラシックバレエの神髄と言われる「バレエ・ブラン(白いバレエ)」と呼ばれる情緒溢れる2幕と4幕のアンサンブルにも生かされると良いなと私は感じました。
又2幕・4幕では、特に走る時の足さばきに、もう少しつま先が使えると良いなと私は感じました。何故なら白を浮き立たせる為の暗い照明は、同時にバレリーナのつま先のラインというものを、良くも悪くも非常に目立たせてしまうからです。
谷バレエ団は、もしかして昔のスタイルのまま「ドゥミ・ポアントで走る」というのが継承されたスタイルの一つなのかなとも私は思いましたが、
つま先から降りる様に走る繊細な足さばきの感覚を生かした方が、よりバレエ・ブランの幻想性や神秘性や幽玄の世界を表現出来る様に私的には感じました。
ではここからは、いよいよ主役3組と悪魔ロットバルトを演じられたお三方の感想に参ります・・・と行きたい所ですが、長くなり過ぎますので次回に続きます。
☆_(_☆_)_☆
世界中で「バレエと言えば白鳥の湖」と言われるほどの大作を生んだ芸術大国のロシアでは、この「白鳥の湖」の主役を踊る女性は「プリマの中でも選ばれた人しか踊る事を許されない」とされるほど、
非常に大事に丁寧に伝統が受け継がれている事で有名です。
( ・・) ~ ☆彡☆彡☆彡
★私のXポスト(旧Twitter)はこちらから
(※記事に載せていない社会的なコアな情報も、結構ポストしています)
↓ ↓ ↓
E-brand
https://twitter.com/Ebrand30179826
【参考コラム】
宜しかったら、こちらも是非ご覧下さい♪
↓ ↓ ↓
★今回何故この世界的コロナパンデミックが起こされたのかが分かるコラムはこちら♪
↓ ↓ ↓
世界的コロナパンデミックが何故引き起こされたのかが分かる【参考コラム】特集 Ⅰ
★そして、コロナウィルスをやみくもに怖がる必要はないという事が分かるコラムはこちらデス♪
↓ ↓ ↓
世界的コロナパンデミックが何故引き起こされたのかが分かる【参考コラム】特集 Ⅱ
世界的コロナパンデミックが何故引き起こされたのかが分かる【参考コラム】特集 Ⅲ
世界的コロナパンデミックが何故引き起こされたのかが分かる【参考コラム】特集 Ⅳ
世界的コロナパンデミックが何故引き起こされたのかが分かる【参考コラム】特集 Ⅴ
世界的コロナパンデミックが何故引き起こされたのかが分かる【参考コラム】特集 Ⅵ
★noteさんにも記事を書いています♡
(※こちらにしか書かないショートメッセージをいつも添えています♪)
以下のランキングに参加しております♪
応援して下さると嬉しいです♡ (*^^*)