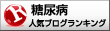こんにちわ。
実は昨夜、Mastering Diabetes (今後は
省略してMDと書きます。)の無料トレーニング
ってのにちょっと参加してきました!
省略してMDと書きます。)の無料トレーニング
ってのにちょっと参加してきました!
ライブでサイラスとボビーの話を聞き
参加者はチャット形式で発言できます。
昨夜のイベントは300人くらいの参加
があったようです。
参加者はチャット形式で発言できます。
昨夜のイベントは300人くらいの参加
があったようです。
アメリカだけでなく世界中から!
私も一応「こんにちわ!日本からです!」
ってだけ言いました。
「私は韓国から!」「ドイツからです!」
とか、すごいインターナショナル。
私も一応「こんにちわ!日本からです!」
ってだけ言いました。
「私は韓国から!」「ドイツからです!」
とか、すごいインターナショナル。
最初は、ヘモグロビンA1cについての話。
なにしろ私はヒアリングが中学生レベル
で、全然ついていけないんだけど、
画像を使って話してくれてたのでなんとなく
わかりました。
なにしろ私はヒアリングが中学生レベル
で、全然ついていけないんだけど、
画像を使って話してくれてたのでなんとなく
わかりました。
「みなさんは、A1cが何を意味するか
知ってますかー?」とサイラスが
呼び掛けると、参加者がチャットで
「血糖値だよ!」「三か月の平均値だよ!」
とか次々に発言。世界中から。
インターネットってすげー!と実感しました。
知ってますかー?」とサイラスが
呼び掛けると、参加者がチャットで
「血糖値だよ!」「三か月の平均値だよ!」
とか次々に発言。世界中から。
インターネットってすげー!と実感しました。
昨日のレクチャーはA1cとは何か
糖質制限するとA1cは下がるが
実はインスリン抵抗性は上がっている、
運動がなぜ大切か、PBWFの基本
などでした。
糖質制限するとA1cは下がるが
実はインスリン抵抗性は上がっている、
運動がなぜ大切か、PBWFの基本
などでした。
運動は週に6日、一日30分を勧められて
ました。(結構きびしいw)
そのうち3日を有酸素運動、3日を
無酸素運動にするのがいい、と。
しかし高強度でなくていいそうです。
ました。(結構きびしいw)
そのうち3日を有酸素運動、3日を
無酸素運動にするのがいい、と。
しかし高強度でなくていいそうです。
運動をすると、運動後も筋肉がグルコース
を吸収し続ける、ってことも言ってました。
を吸収し続ける、ってことも言ってました。
チャットコーナーでは「とにかく
早く良くなりたい」「痩せたい」
「糖質制限やめたいんだけど
どうしていいかわからない」
「PBWF始めてみたけど、体重が減らない!」
とか切実な声がたくさん。
(糖尿病には国境がない!)
早く良くなりたい」「痩せたい」
「糖質制限やめたいんだけど
どうしていいかわからない」
「PBWF始めてみたけど、体重が減らない!」
とか切実な声がたくさん。
(糖尿病には国境がない!)
それに対してどうやらスタッフらしい人が
「インスリン抵抗性の改善には
普通は6か月から1年かかりますよ」
と答えてて、私もなんだか安心できました。
「インスリン抵抗性の改善には
普通は6か月から1年かかりますよ」
と答えてて、私もなんだか安心できました。
さて、今日はそのMDのサイエンス系記事から
「インスリン抵抗性を改善する食事」
ってのを翻訳します。
「インスリン抵抗性を改善する食事」
ってのを翻訳します。
この、インスリン抵抗性の機序の話
前に紹介した徳島大の舟木先生の
英語論文とほぼ同じことを言ってて
まったく矛盾はないです。
前に紹介した徳島大の舟木先生の
英語論文とほぼ同じことを言ってて
まったく矛盾はないです。
すごくわかりやすく説明してくれてます。
私も読みやすく翻訳することをがんばった
つもり。それほど重要ではないところ
は中略してます。
私も読みやすく翻訳することをがんばった
つもり。それほど重要ではないところ
は中略してます。
インスリン抵抗性って糖尿病だけの
問題ではなくあらゆる慢性疾患の
基本の病態になってるみたいです。
問題ではなくあらゆる慢性疾患の
基本の病態になってるみたいです。
*************************************
インスリン抵抗性改善ダイエットガイド
何を食べればよいのか、それはなぜなのか。
インスリン抵抗性が境界型糖尿病と
2型糖尿病の原因であることはご存知
かもしれません。
そしてアメリカで蔓延している慢性疾患
にも大きくかかわっている要因である
ことも。
2型糖尿病の原因であることはご存知
かもしれません。
そしてアメリカで蔓延している慢性疾患
にも大きくかかわっている要因である
ことも。
(中略)
私たちが「インスリン抵抗性ダイエット」
と呼ぶものは、85年以上に渡るエビデンス
に基づく研究による、インスリン抵抗性を
逆転させる科学的に証明されたライフスタイル
です。
と呼ぶものは、85年以上に渡るエビデンス
に基づく研究による、インスリン抵抗性を
逆転させる科学的に証明されたライフスタイル
です。
(ちなみに、サイラスは栄養生理学の博士)
インスリン抵抗性はすべてのタイプの
糖尿病の根底要因ですから、血糖値を
コントロールするために、これについて
理解することはとても大切です。
糖尿病の根底要因ですから、血糖値を
コントロールするために、これについて
理解することはとても大切です。
インスリン抵抗性について簡潔に説明
してください、と言われたらどう答えますか?
してください、と言われたらどう答えますか?
食事のどの要素が一番インスリン抵抗性の
原因となりうるか、明確にご存知ですか?
原因となりうるか、明確にご存知ですか?
インスリン抵抗性改善のための食事
についてあなたの主治医に聞いてみたいと
思われるかもしれませんが、医療界の人たち
はインスリン抵抗性と糖尿病を逆転させる
食事方法を理解していません。
についてあなたの主治医に聞いてみたいと
思われるかもしれませんが、医療界の人たち
はインスリン抵抗性と糖尿病を逆転させる
食事方法を理解していません。
なぜ?それは簡単なことです。
医学部では栄養学を教えられていないからです。
それゆえ多くの患者は、慢性病を食事で逆転
させることに関して間違った情報を与えられて
います。
医学部では栄養学を教えられていないからです。
それゆえ多くの患者は、慢性病を食事で逆転
させることに関して間違った情報を与えられて
います。
(中略)
では質問の答えです、
インスリン抵抗性は、たくさんの脂肪を
貯蔵するようにデザインされていない器官に
余分な蓄えられたことが原因です。
貯蔵するようにデザインされていない器官に
余分な蓄えられたことが原因です。
インスリン抵抗性は砂糖を食べ過ぎたことが
原因だと思われるかもしれませんが
過剰な食事中の脂肪は、精製砂糖よりも強力に
インスリン抵抗性を生じさせます。
原因だと思われるかもしれませんが
過剰な食事中の脂肪は、精製砂糖よりも強力に
インスリン抵抗性を生じさせます。
インスリン抵抗性は今日広く見られる健康
問題です。
それは多くの慢性疾患のリスクを増やします。
問題です。
それは多くの慢性疾患のリスクを増やします。
ここではインスリン抵抗性と糖尿病、β細胞の
死滅について論じますが、実際は、ガン、冠状動脈
疾患、高血圧、動脈硬化、肥満、高コレステロール、
脂肪肝、アルツハイマー、腎不全、網膜症、などの
多くの病気に関係しているのです。
死滅について論じますが、実際は、ガン、冠状動脈
疾患、高血圧、動脈硬化、肥満、高コレステロール、
脂肪肝、アルツハイマー、腎不全、網膜症、などの
多くの病気に関係しているのです。
(中略)
インスリン抵抗性はすべてのタイプの
糖尿病と関連しています。
糖尿病と関連しています。
糖尿病におけるクラッシュコース
インスリン抵抗性の基本を理解するために
まずは膵臓の生理学を理解しましょう。
まずは膵臓の生理学を理解しましょう。
膵臓の機能には外分泌と内分泌があり、
膵臓の機能の99%は外分泌(消化酵素
の小腸への分泌)です。
膵臓の機能の99%は外分泌(消化酵素
の小腸への分泌)です。
(中略)
残りの1%が内分泌機能です。
残りの1%が内分泌機能です。
(ランゲルハンス島の細胞からの血液中
へのホルモン分泌)
へのホルモン分泌)
(中略)
ランゲルハンス島には何千ものα細胞とβ細胞
があり、全部で1000から4000の細胞です。
α細胞は血糖値を上げるグルカゴンを分泌します。
β細胞は血糖値を下げるインスリンを分泌します。
デルタ細胞はインスリン分泌を阻止する
ソマトスタチンを分泌します。
β細胞は血糖値を下げるインスリンを分泌します。
デルタ細胞はインスリン分泌を阻止する
ソマトスタチンを分泌します。
β細胞はインスリンを分泌する唯一の細胞
だという点が重要です。
だという点が重要です。
膵臓内のβ細胞の数はとても少ないので
それらが十分なインスリンを分泌でき
なくなったら、あらゆる器官に障害が
生じ、治療しなければ死に至りかねません。
それらが十分なインスリンを分泌でき
なくなったら、あらゆる器官に障害が
生じ、治療しなければ死に至りかねません。
(中略)
1型糖尿病とは違って、2型糖尿病は
筋肉と肝臓から始まって、その後膵臓に
至ります。
その一連の出来事は以下のようなパターン
です。
至ります。
その一連の出来事は以下のようなパターン
です。
**********************
ステップ1:高脂肪食を食べる
ステップ2:グルコースより先に脂肪酸が血中に入る
ステップ3:脂肪酸が脂肪組織に入る
ステップ4:脂肪組織が機能不全になる
ステップ5:筋肉と肝臓に脂肪が蓄積し
インスリンの作用を拒絶する
インスリンの作用を拒絶する
ステップ6:β細胞は過分泌となる。
ステップ7:β細胞の自死
***********************
ステップ1:高脂肪食を食べる
血糖値のコントロールのために、炭水化物を
制限した低炭水化物・高脂肪・高蛋白質の
食べるとします。
それは、乳製品、卵、赤肉、白肉、魚、貝類、
植物油、ナッツ、種子、アボガド、ココナッツ
などを含みます。
制限した低炭水化物・高脂肪・高蛋白質の
食べるとします。
それは、乳製品、卵、赤肉、白肉、魚、貝類、
植物油、ナッツ、種子、アボガド、ココナッツ
などを含みます。
ステップ2:グルコースより先に脂肪酸が
血中に入る
血中に入る
脂肪が小腸に入ると、それらは直接リンパ管に
入り、それからすぐに血中に移動します。
入り、それからすぐに血中に移動します。
すると消化管と脳の間の一連の複数の
ホルモンシグナルによって、胃の蠕動が減り、
胃から食物が腸に移動する速度が遅く
なります。
ホルモンシグナルによって、胃の蠕動が減り、
胃から食物が腸に移動する速度が遅く
なります。
胃の蠕動が減る結果、炭水化物の吸収も
ゆっくりになり、グルコースが血液中に
入るのもゆっくりになります。
ゆっくりになり、グルコースが血液中に
入るのもゆっくりになります。
ステップ3:脂肪酸が脂肪組織に入る
循環血液中の脂肪酸は全身の組織に
入ります。まず脂肪組織に、そして
筋肉と肝臓です。
入ります。まず脂肪組織に、そして
筋肉と肝臓です。
脂肪組織は、余分な脂肪酸があるとき
はそれを吸収し、足りないときは放出
するようデザインされている、体を守る
組織なのです。
はそれを吸収し、足りないときは放出
するようデザインされている、体を守る
組織なのです。
脂肪組織は、筋肉や肝臓が過剰な脂肪酸
を吸収しないよう守ってるのです。
を吸収しないよう守ってるのです。
ステップ4:脂肪組織が機能不全になる
高脂肪なものを常に食べ続けていると
脂肪組織が故障します。
これは取り込むべき脂肪酸が多すぎて
脂肪組織の限界を超えたときに生じます。
脂肪組織が故障します。
これは取り込むべき脂肪酸が多すぎて
脂肪組織の限界を超えたときに生じます。
脂肪酸が血中に常に高濃度で存在していると
脂肪細胞はできるだけ多くの脂肪酸を
取り込もうとベストを尽くします。
脂肪細胞はできるだけ多くの脂肪酸を
取り込もうとベストを尽くします。
しかし、脂肪の多い食べ物を食べ続けて
いると、脂肪細胞の中の脂肪滴は大きく
なり、ついには許容量を超えます。
いると、脂肪細胞の中の脂肪滴は大きく
なり、ついには許容量を超えます。
脂肪細胞は容量過多となりサイズが大きく
なり、ついには綻び、その中身を細胞外液
の中に漏れ出させます。
なり、ついには綻び、その中身を細胞外液
の中に漏れ出させます。
すると周囲の細胞はサイトカインと呼ばれる
ホルモンを分泌し、細胞の破片を掃除する
ためにマクロファージを誘導します。
ホルモンを分泌し、細胞の破片を掃除する
ためにマクロファージを誘導します。
このプロセスは「脂肪組織へのマクロファ
ージ侵入」と呼ばれ、低グレードの慢性炎症を
生じさせ、それが脂肪細胞とインスリンとの
コミニュケーションを妨害するのです。
ージ侵入」と呼ばれ、低グレードの慢性炎症を
生じさせ、それが脂肪細胞とインスリンとの
コミニュケーションを妨害するのです。
つまり、脂肪組織へのマクロファージ侵入は
脂肪組織のインスリン抵抗性の原因なのです。
脂肪組織のインスリン抵抗性の原因なのです。
ステップ5:筋肉と肝臓に脂肪が蓄積し
インスリンの作用を拒絶する
インスリンの作用を拒絶する
筋肉と肝臓の細胞は脂肪酸が入ってくる
のをうまく阻止できません。
高脂肪食をたべるとすぐに、何時間もしない
うちに脂肪酸は筋肉と肝臓の中に入ってきます。
のをうまく阻止できません。
高脂肪食をたべるとすぐに、何時間もしない
うちに脂肪酸は筋肉と肝臓の中に入ってきます。
残念なことに、筋肉と肝臓は脂肪酸の侵入を
自ら防ぐことはほとんどできないのです。
自ら防ぐことはほとんどできないのです。
組織内に入った脂肪酸は集まって、脂肪滴
というものになります。
というものになります。
これは脂肪の量が少ないなら、問題では
ありません。
ありません。
しかし筋肉も肝臓も、大きな脂肪滴を蓄える
ようにはデザインされていないのです。
ようにはデザインされていないのです。
高脂肪食を食べ続けるとやがて各細胞
の中の脂肪滴は大きくなっていき、深刻
な問題を引き起こします。
それがインスリンシグナルの障害です。
の中の脂肪滴は大きくなっていき、深刻
な問題を引き起こします。
それがインスリンシグナルの障害です。
脂肪滴が大きくなると、さまざまな脂肪分子
がインスリン受容体に直接働きかけ、その
正常な働きを阻害します。
がインスリン受容体に直接働きかけ、その
正常な働きを阻害します。
筋肉と肝臓の細胞は、まずは余分な脂肪滴を
燃やすために、インスリン受容体の
働きを止めることを選択します。
燃やすために、インスリン受容体の
働きを止めることを選択します。
筋肉と肝臓の細胞はこう言うのです。
「僕たちはエネルギーを吸収する前に
まずこの脂肪滴を燃やさないといけないんだ。
たとえそのエネルギーがグルコースでもね。」
まずこの脂肪滴を燃やさないといけないんだ。
たとえそのエネルギーがグルコースでもね。」
ステップ6:β細胞は過分泌となる。
そして、炭水化物の多い食べ物を食べるとします。
バナナ、ポテト、パンなど。
炭水化物の分子は体内でグルコースとなります。
バナナ、ポテト、パンなど。
炭水化物の分子は体内でグルコースとなります。
血液中にグルコースが循環すると、それを
インスリンによって細胞内に取り込ませない
といけません。
インスリンによって細胞内に取り込ませない
といけません。
1型糖尿病では、筋肉と肝臓のインスリン受容体
からグルコースが取り込まれるよう、インスリン
の注射を打つわけです。
からグルコースが取り込まれるよう、インスリン
の注射を打つわけです。
しかしそこの大きな脂肪滴が蓄積されていると
筋肉も肝臓もインスリンの作用を拒否します。
ですから血糖値を下げるために、インスリン
注射の量を増やしていくことになります。
筋肉も肝臓もインスリンの作用を拒否します。
ですから血糖値を下げるために、インスリン
注射の量を増やしていくことになります。
2型糖尿病や境界型の場合、膵臓内のβ細胞は
筋肉と肝臓の細胞を反応させるために
過分泌(たくさん分泌する)しなくては
いけなくなります。
筋肉と肝臓の細胞を反応させるために
過分泌(たくさん分泌する)しなくては
いけなくなります。
インスリンの仕事というのは、細胞の
ドアをノックしてこう言うのです。
ドアをノックしてこう言うのです。
「ヘイ!グルコースありますよ!欲しいですか?」
インスリン受容体が過剰な脂肪蓄積によって
阻害されていると、筋肉と肝臓の細胞は
こう返事します。
阻害されていると、筋肉と肝臓の細胞は
こう返事します。
「ごめん、今はグルコース受け取れないよ。
この脂肪を先に燃やさなくちゃいけないんだ。」
この脂肪を先に燃やさなくちゃいけないんだ。」
結果としてインスリンは組織とうまく
コミニュケーションが取れなくなり
血液中にとどまって「高インスリン血症」
を引き起こします。
コミニュケーションが取れなくなり
血液中にとどまって「高インスリン血症」
を引き起こします。
それに加えて、グルコースが組織内に入って
いけないので、グルコースも血液中に取り残され
「高血糖」を引き起こします。
いけないので、グルコースも血液中に取り残され
「高血糖」を引き起こします。
それで、炭水化物の多い食事をして2時間ほど
すると血糖値が上がっているのを見て、
ショックを受けることになります。
すると血糖値が上がっているのを見て、
ショックを受けることになります。
ステップ7:β細胞の自死
その後、大量のインスリンを分泌させられた
β細胞はアポトーシス(プログラムされている
細胞の死)となります。
β細胞はアポトーシス(プログラムされている
細胞の死)となります。
この理由はシンプルです。
筋肉や肝臓の細胞と同様に、β細胞も
絶えず脂肪酸を吸収しているからです。
筋肉や肝臓の細胞と同様に、β細胞も
絶えず脂肪酸を吸収しているからです。
残念なことに、β細胞は大量の脂肪酸に
耐えれるようにはデザインされていない
壊れやすい細胞なのです。
耐えれるようにはデザインされていない
壊れやすい細胞なのです。
脂肪を食べ続けると、β細胞はインスリンの
分泌を増やすだけでなく、フリーラジカルを
生じさせ、それが細胞の自死をもたらします。
分泌を増やすだけでなく、フリーラジカルを
生じさせ、それが細胞の自死をもたらします。
β細胞が脂肪酸の蓄積に堪えられる時間は
きわめて短いので、高脂肪の食事はβ細胞
の脂肪吸収能力を超えさせてしまい、
「脂肪によるβ細胞の死」のリスクを増やします。
きわめて短いので、高脂肪の食事はβ細胞
の脂肪吸収能力を超えさせてしまい、
「脂肪によるβ細胞の死」のリスクを増やします。
では今日はここまで。
次はインスリン抵抗性を改善する食事
についてです。
についてです。
***************************************
訳してて思ったのは、きっと日本人の
多くは脂肪組織の能力が低い(たくさん
貯めることができず簡単に破綻する)
し、インスリン分泌量も少ないから
太らないうちに2型糖尿病になる人
が多いのかな、と。
多くは脂肪組織の能力が低い(たくさん
貯めることができず簡単に破綻する)
し、インスリン分泌量も少ないから
太らないうちに2型糖尿病になる人
が多いのかな、と。
そういう人でも良くみるとお腹が
ちょっと出てるし、そして筋肉が
細い気がします。
ちょっと出てるし、そして筋肉が
細い気がします。
今日も午前中ジムに行きました。
今日はペーズリーお兄さんと二人っきりww
今日はペーズリーお兄さんと二人っきりww
適当に筋トレやりました。
王城さんのブログで紹介されてた
片手にダンベル持って上げ下げする
運動もやってみました。
50肩の腕でもできました。(負荷5キロ)
なんとなく50肩が楽になってきた
気もします。
王城さんのブログで紹介されてた
片手にダンベル持って上げ下げする
運動もやってみました。
50肩の腕でもできました。(負荷5キロ)
なんとなく50肩が楽になってきた
気もします。
その後、トレッドミルできっちり3㎞
走りました。汗だく。
走りました。汗だく。
運動前はリブレで250ほど(笑)
バナナ2本と干し芋一本食べて
30分後くらい。
運動後は羊羹食べたけど100くらいまで
下がり、その後上昇しました。
昨日より上下幅が小さいです。
家に帰って、お昼は炊き立てご飯で
ベジカレーがっつり。
でもそれほど上がってないわ。
ベジカレーがっつり。
でもそれほど上がってないわ。
ブログお友達が、実は焼き芋は高GI
ってことを教えてくれました。
ってことを教えてくれました。
ガーン!
だから昨日、特大紅天使(たぶん糖度を上げる
品種改良を重ねてできた逸品です)
がアホほど血糖値上げたのねw
品種改良を重ねてできた逸品です)
がアホほど血糖値上げたのねw
しばらく封印するか、小分けして
凍らせてシャーベットにしてみるかw
凍らせてシャーベットにしてみるかw
あ、私有名ブロガーなんかじゃない
ですので~。
ですので~。
気軽にからんでくださいねっ!
もずくさんってブロガーさんも
PBWFで糖尿病治療にチャレンジ
されてて、仲間ができてすごく
うれしくって、勝手にお友達に
させてもらってます!
PBWFで糖尿病治療にチャレンジ
されてて、仲間ができてすごく
うれしくって、勝手にお友達に
させてもらってます!
ジムでもネットでも「一人じゃない!」
っていうのは励みになりますねー。
っていうのは励みになりますねー。