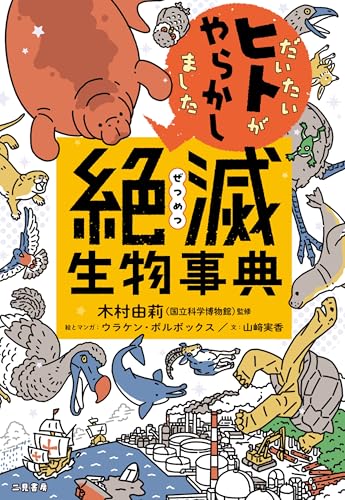愛新覚羅家に嫁いだ日本人女性
清朝最後の皇帝として知られる愛新覚羅溥儀(あいしんかくら ふぎ)
その数奇な生涯は映画「ラストエンペラー」を通じて世界的に広く知られ、今なお強い印象を残している
幼くして皇帝となり、退位、満洲国での再即位、終戦後の収容生活、そして釈放後は新たな中国で静かに暮らしながら生涯を終えた人物である
その溥儀には、実弟の溥傑(ふけつ)がいた
そして彼には、日本から一人の女性が嫁いでいる
華族の家に生まれ、のちに激動の時代を夫とともに歩むことになる、嵯峨浩(さが ひろ)である
嵯峨浩がどのように愛新覚羅家と結びつき、どのような日々を送ったのかを、当時の背景とともにたどっていきたい
ラストエンペラーの弟・溥傑の出自
愛新覚羅 溥傑(あいしんかくら ふけつ、1907年生)は、清朝の有力皇族である醇親(じゅんしん)王家の一員として生まれた
父は醇親王・載灃(さいほう)、母は正白旗出身の瓜爾佳氏(グワルギャし)・幼蘭(ようらん)
祖父は道光帝の第七子の醇賢親王・奕譞(いけん)、兄はのちに清朝最後の皇帝・宣統帝となる溥儀(ふぎ)である
兄が幼くして帝位に就いたため、溥傑は醇親王家の継嗣とみなされ、幼少期から兄の側近くで学び、伴読(共に書物を読み、学問を補佐する役目)として仕えた
1924年、溥傑は満洲旗人の名門出身である唐石霞(とう せきか)と結婚する
しかし夫婦関係は早くからぎくしゃくし、やがて別居となって婚姻は事実上破綻した
その背景には唐石霞が、その美貌から多くの男性と浮き名を流したことがあった
1927年、北京飯店の舞踏会で出会った軍閥の実力者、張学良と不倫関係に陥り、他にも複数の男性との関係が噂されるようになる
さらに溥傑が日本に留学していた時期には、醇親王府から多数の財宝を持ち出したことが発覚し、これらの出来事が重なって夫婦仲は完全に冷え切り、長い争いの末に別居・離婚へと至ったと伝えられている
一方、中国本土では辛亥革命後の混乱が続き、1924年の北京政変では馮玉祥(ふうぎょくしょう)と孫岳(そんがく)らが軍事クーデターを起こし、清室優待条件を一方的に破棄した
これにより、皇帝を退位していた溥儀一族は紫禁城を追われ、日本公使館へと避難することになる
溥傑もこの流れの中で日本政府の庇護を受けるようになり、日本との距離は一気に近づいていった
1929年、溥傑は婉容(えんよう)皇后の実弟・郭布羅潤麒(かくぶら じゅんき)とともに来日し、日本語などの基礎教育を受けたのち、学習院高等科に進む
その後、陸軍士官学校に入学して軍事教育を受け、日本の軍隊生活を通して日本社会や文化にも深く触れていった
この日本での経験が、のちに彼の人生を決定づける大きな要素となる
嵯峨浩の出自
嵯峨浩(さが ひろ)は1914年、東京で生まれた
父は侯爵・嵯峨実勝(さが さねかつ)
嵯峨家は、正親町三条家の流れをくむ公家華族であり、藤原北家閑院流に属する由緒ある家柄である
さらに昭和天皇とは父方を通じて母系の遠縁にあたり、皇室とも血縁で結ばれた家系であった
浩は女子学習院に学び、宮中行事にも出入りしながら、礼儀作法や和歌、ピアノ、フランス語などを身につけた
いわば「華族社会の教養を体現した若い女性」であり、その家柄と人柄は、当時の日本社会においても特別な存在感を放っていた
満洲国皇帝となっていた溥儀は、当初、弟の溥傑を日本の皇族女子と結婚させたいと考えていた
しかし、日本の皇室典範および皇室典範増補では、皇族女子の結婚相手は皇族や王公族、もしくは特に認められた華族に限られており、満洲国の皇弟であっても外国人男性である溥傑は、その条件から外れていた
このため、皇族との縁組は制度上認められず、代わりに皇室と血縁のある華族女子から候補が探されることになった
そこで候補として白羽の矢が立ったのが、侯爵嵯峨家の長女・浩であった
こうして関東軍の主導のもと、日満関係強化の象徴ともいえる縁談が進められていった。
1937年(昭和12年)2月6日、溥傑と浩の婚約内定が満洲国駐日大使館から発表され、同年4月3日には東京・軍人会館(旧九段会館、現・九段会館テラスの復原部分)で結婚式が挙げられた
媒酌人は陸軍大将の本庄繁、司祭は靖国神社宮司が務め、当日は号外が配られるほど話題になったという
満洲で始まった二人の新生活
1937年、東京で結婚式を挙げた溥傑と嵯峨浩は、その年の秋に満洲国の首都・新京へと向かった
夫婦として歩み始める場所は、異国の地でありながらも、皇帝溥儀の存在を中心とした特殊な宮廷社会が広がる場所だった
満洲国での生活は、一見すると華やかに思われがちだが、実際には日本と満洲の政治的事情に左右される、緊張感を伴う日々であった
浩は嫁いだ直後から新しい環境に馴染もうと努め、宮中行事への出席、外国使節との応対、公式行事での礼節など、多くの場面で華族としての教養と品位を求められた
夫婦は新京で静かに暮らしながら、周囲の人々とも良好な関係を築いていったという
そうした日々の中、1938年には新京で長女の慧生(えいせい)が誕生した
1940年には、浩が一時帰国していた際に、東京で次女の嫮生(こせい)が誕生する
夫婦にとっては幸福な時期であり、浩は育児にも熱心に取り組んだとされる
しかし満洲国を取り巻く情勢は、次第に緊迫の度を増していく
表向きの平穏とは裏腹に、国際情勢の変化は新京にも確実に影を落とし、夫婦の生活はいつ戦火に巻き込まれてもおかしくない状態であった
戦争と離別
1930年代末から世界情勢は急速に不安定化し、満洲国もまたその渦中に巻き込まれていった
日中戦争が拡大するにつれ、日本の軍事方針は満洲国にも強く影響を及ぼし、皇弟であった溥傑にもさまざまな政治的役割が求められるようになった
新京の宮廷は表向きこそ整然と保たれていたが、その内側では日本の意向が絶えず反映され、皇族である溥傑の行動にも制限が加わるようになっていく
そして時代の大きな波は、ついに夫婦生活にも大きな影を落とすこととなる
1944年、満洲国の情勢が悪化する中、溥傑には「満洲国の象徴としての役務」や「皇弟としての外交的存在感」などを理由に、日本本土への出向が命じられた
これは実質的には日本側の要請によるもので、新京を離れ、単身で日本へ向かうことを余儀なくされたのである
浩は次女の嫮生とともに満洲に残り、夫婦は初めて長期の別離となった
一方、長女の慧生は学業のため日本に滞在していた
浩は後年、夫が日本へ旅立った日のことを「生涯でもっとも胸の締めつけられる思いだった」と振り返っている
溥傑との再会と、浩の最期
1945年8月、ソ連軍が突如満洲へ侵攻すると、満洲国は急速に崩壊へ向かった
首都・新京は混乱に包まれ、溥儀をはじめとする皇族や政府高官たちは南方へ退避し、日本への脱出を図ろうとしたが、情勢は一刻ごとに悪化していった
溥傑は1944年に日本へ渡っていたが、戦局の悪化に伴い、翌1945年には再び新京へ戻るよう命じられていた
このため満洲国崩壊の際には、溥儀やその側近たちと行動を共にし、退避の一行に加わっていた
混乱の中で溥傑は、溥儀や満洲国の要人たちとともにソ連軍に拘束された
その後、一行はシベリア方面の収容所へ送られ、長い抑留生活を強いられることになる
そのころ、浩は満洲に残り、次女の嫮生を抱えて混乱の続く大陸を転々とすることを余儀なくされた
食糧も乏しく、移動の安全も保証されない過酷な状況の中で、浩は幼い嫮生を守ることだけを心の支えに、幾度もの危険を乗り越えていった
戦後の混乱が落ち着き始めた1947年、ようやく引き揚げが実現し、浩と嫮生は長い流転の末に日本へ戻り、慧生と再会することになる
しかし、戦後の生活は決して穏やかではなかった
日本社会は敗戦のショックに揺れ、華族制度も廃止されたことで、浩の生活基盤は一気に失われた
その中で、浩が最も心を痛めたのは、長女・慧生(えいせい)の死である
1957年、慧生は学習院大学に通う中で、交際していた青年・大久保武道とともに、伊豆天城山でピストル心中を遂げた
「天城山心中」と呼ばれるこの事件は、浩の人生に深い傷を残した
一方、溥傑はソ連の収容所を経て、1950年に中国へ送還され、撫順戦犯管理所に収容された
中国での「再教育」は約10年におよび、長い年月のあいだ家族と会うことは叶わなかった
しかし1960年、模範囚として釈放され、翌1961年にようやく浩との再会が実現する
10数年ぶりの再会は、言葉では表せないほど感慨深いものであったという
その後、浩は溥傑と北京で再び夫婦としての生活を始めたが、嫮生(こせい)は日本に戻り、のちに日本へ帰化して結婚した
浩は皇族でも華族でもなく、一人の日本人女性として、夫のそばで穏やかな時間を大切にしたと伝えられる
そして1987年、浩は北京の病院で静かに息を引き取った
享年73
溥傑はその後も、日中友好の象徴として活動しながら余生を過ごし、1994年に北京で亡くなった
享年86
夫妻と慧生の遺骨は本人たちの希望により、日中双方に分骨され、今も静かに祀られている
激動の時代に押し流されながらも、夫婦は離れても離れず、最後には再び共に歩む道を取り戻した
嵯峨浩の生涯は、一人の女性の人生を越え、戦争と国家の運命に翻弄された「歴史の証人」として、今も静かな余韻を残している
参考 : 愛新覚羅溥傑『溥傑自伝「満州国」皇弟を生きて』愛新覚羅浩『流転の王妃の昭和史』他
文 / 草の実堂編集部
(この記事は草の実堂の記事で作りました)
愛新覚羅家に嫁いだ日本人女性
清朝最後の皇帝として知られる愛新覚羅溥儀(あいしんかくら ふぎ)
その数奇な生涯は映画「ラストエンペラー」を通じて世界的に広く知られ、今なお強い印象を残している
幼くして皇帝となり、退位、満洲国での再即位、終戦後の収容生活、そして釈放後は新たな中国で静かに暮らしながら生涯を終えた人物である
その溥儀には、実弟の溥傑(ふけつ)がいた
そして彼には、日本から一人の女性が嫁いでいる
華族の家に生まれ、のちに激動の時代を夫とともに歩むことになる、嵯峨浩(さが ひろ)である
ラストエンペラーの弟に嫁いだ日本人女性・嵯峨浩の激動の生涯・・・
夫婦は戦争の混乱などで離れることも・・・
溥傑との再会と、浩の最期
1945年8月、ソ連軍が突如満洲へ侵攻すると、満洲国は急速に崩壊へ向かった
首都・新京は混乱に包まれ、溥儀をはじめとする皇族や政府高官たちは南方へ退避し、日本への脱出を図ろうとしたが、情勢は一刻ごとに悪化していった
溥傑は1944年に日本へ渡っていたが、戦局の悪化に伴い、翌1945年には再び新京へ戻るよう命じられていた
このため満洲国崩壊の際には、溥儀やその側近たちと行動を共にし、退避の一行に加わっていた
混乱の中で溥傑は、溥儀や満洲国の要人たちとともにソ連軍に拘束された
その後、一行はシベリア方面の収容所へ送られ、長い抑留生活を強いられることになる
そのころ、浩は満洲に残り、次女の嫮生を抱えて混乱の続く大陸を転々とすることを余儀なくされた
食糧も乏しく、移動の安全も保証されない過酷な状況の中で、浩は幼い嫮生を守ることだけを心の支えに、幾度もの危険を乗り越えていった
戦後の混乱が落ち着き始めた1947年、ようやく引き揚げが実現し、浩と嫮生は長い流転の末に日本へ戻り、慧生と再会することになる
しかし、戦後の生活は決して穏やかではなかった
日本社会は敗戦のショックに揺れ、華族制度も廃止されたことで、浩の生活基盤は一気に失われた
その中で、浩が最も心を痛めたのは、長女・慧生(えいせい)の死である
1957年、慧生は学習院大学に通う中で、交際していた青年・大久保武道とともに、伊豆天城山でピストル心中を遂げた
「天城山心中」と呼ばれるこの事件は、浩の人生に深い傷を残した
一方、溥傑はソ連の収容所を経て、1950年に中国へ送還され、撫順戦犯管理所に収容された
中国での「再教育」は約10年におよび、長い年月のあいだ家族と会うことは叶わなかった
しかし1960年、模範囚として釈放され、翌1961年にようやく浩との再会が実現する
10数年ぶりの再会は、言葉では表せないほど感慨深いものであったという
その後、浩は溥傑と北京で再び夫婦としての生活を始めたが、嫮生(こせい)は日本に戻り、のちに日本へ帰化して結婚した
浩は皇族でも華族でもなく、一人の日本人女性として、夫のそばで穏やかな時間を大切にしたと伝えられる
そして1987年、浩は北京の病院で静かに息を引き取った
享年73
溥傑はその後も、日中友好の象徴として活動しながら余生を過ごし、1994年に北京で亡くなった
享年86
夫妻と慧生の遺骨は本人たちの希望により、日中双方に分骨され、今も静かに祀られている
激動の時代に押し流されながらも、夫婦は離れても離れず、最後には再び共に歩む道を取り戻した
嵯峨浩の生涯は、一人の女性の人生を越え、戦争と国家の運命に翻弄された「歴史の証人」として、今も静かな余韻を残している
満洲帝国皇帝弟に嫁ぐも、終戦後は夫と離れ次女を連れて大陸を流浪、帰国後の苦しい生活と長女の死・・・激動の人生を綴る自伝的昭和史