再掲 高麗神社。
関東に関しては細かく隈なく神社仏閣を巡ったが、埼玉と群馬県境周辺は興味深い寺社や地名が多く、何も無い田舎町の中にそれらはある。高麗神社もその一つなのだが_ここはある意味、関東一のパワースポットかもしれない。まず天皇陛下は定期的に訪れているし…歴代の総理大臣になる人は任命される前に必ずここで祈願してること。支配、昇進、子孫繁栄の御利益は間違いない。また伺いたいが横須賀からは厳しいな。
高麗神社と言えば「天下大将軍、地下女将軍」と書かれたトーテムだが…実は僕が小さい頃、母がこの2対の大将軍の小型の像を持っていて不思議に思っていた、また意味が分からなかった。「地下に棲む女の将軍ってなんだ?」。というか今は僕が持っていてちゃんと飾ってある。実はこれは関東大震災までは普通に多く置いてあった 장군표(チョングヒョ)「除魔将軍標」と呼ばれていたもので、八坂神社の由来に書いた朝鮮における 장싱이、御神木である。関東大震災までと書いたが、大正時代は朝鮮半島は日本国だった。そして当然のように先進国だった日本へ朝鮮半島から大量の民族大移動があった。言ってみれば国内移動である。現在でも東京から九州へ行くより韓国へ、あるいは韓国経由の方が早かったり安かったりするのと同じ理由だ。母がこの像を持っていたのは母方の親族にこのとき朝鮮人と結婚した者が居たからだった。そして関東大震災が起こり…朝鮮人は迫害の一途を辿ることになる。なので現在はこの埼玉県日高市にある高麗神社と聖天院、そして西多摩郡日の出町の東光院妙見宮の3ヶ所にしか現存してない。当然ながらこの3ヶ所にある祭殿や奉納祭はチマチョゴリである。


高麗神社 : 埼玉県日高市大字新堀833
狛犬は言うまでもないが、例えば茅葺屋根や尺貫法なども朝鮮由来である。およそ600年前頃まで日本も朝鮮半島も文化や生活にはほとんど違いが無い。日本独自発祥の文化とは武士、侍が登場して以降と考えていい。明治維新でおこなわれた廃仏毀釈は先に朝鮮半島で起こったもので、シン政府が神道国教のためにそれをパクった政策だ。
西暦716年5月16日、高句麗人の1,799人を現在の静岡~関東地方7県(静岡,山梨,神奈川,千葉,茨城,栃木)に移住させ開拓を任せ高麗郡を創った、と続日本書紀巻第7巻に書かれている。埼玉と群馬が入ってないのは現在の飯能から川越辺りを中心に既に高句麗人の国だったからだ。ある意味、天皇家より正当に1400年以上の血統、60代に渡る系譜のあるのが「高麗氏」でもある。猿田彦、宿祢や妙見の系譜も同じく高句麗の人間だと分かってくる。
※ 毎日、寺社いずれかしつこく繰り返し掲載しますが無意味な規則のためご了承ください
さて。
一年分の経費精算、伝票入力は終わりました。まぁ後は大した作業量は無く書類を記入するだけ、税務には慣れているので残りは1日で終わるのだが… 手元に無く記入できずに困ってるのが銀行の通帳。都内にしか無い銀行(信金)も仕事に使っているので記帳が見れず面倒くさい。そこでストップしてる。というか決算報告には何も問題は無いが_昨年秋から始まった「インボイス制度」に当然ながら対応してないこと。取引先大手企業からも特に何も言われてないのでスルーしたが_制度に申請してないことに国税局もスルーしてくれるのか?
ここんとこ礼儀作法の話しを書いていましたが…これもお茶、着物、香、武道、熨斗、風呂敷…とキリが無いのでそろそろ終わりにしたい。生活の全てに渡って奴隷作法が敷かれているので終わりゃしない。言葉、文書、歩いて座って食事して、何もかも呪われてる。手紙だって元は呪術であって、個人間で紙なんて貴重で高価なものを使えたわけじゃないし、読み書き出来る者も限られていた時代。呪術といえばその名残が年賀状でもあるが、年賀状や書初めはイランからもたらされたもの。あ"先日は大阪だけ様々な決まりを逆にしてると書いた(上座、通路の右側に立つなど)が、もう一つ思い出した。配膳の位置_普通は全国どこでも左にご飯、右に汁椀が当たり前だが「ご飯の上(奥)」に汁椀を置く。大阪人以外にはめっちゃ不自然だ。
食事で言えば「箸使い」も奥が深くタブーが多いのはご存知だろう。原則として「挟んで口に運ぶ」以外の動作は禁止と言っていい。なので食べ物を刺したり潰したり、手の代わりに使ってはいけないし、膳の上で迷ったりしてもいけない。ご存知のように神事でも箸は使われるし、古事記なんかにも登場する_のだが、東アジアでモノを使って食べるようになった最初は形でいえばトングである。それがいつしか2本の棒の形になったわけで、現在の箸の形状になったのは古事記の捏造がおこなわれた時代ということ。魚膳の場合「尾頭付き」なんてのもある。魚の頭は左向き、これは注連縄と同じで「一」の文字の書き方と同じで「左から始める」もの。ただし注連縄も一部では左右を逆にしてる場合があるのはご承知の通り。これは大阪と違って「反アブラハム(天照)」でもあってユダヤ・カルトと一線を画す意思の表れでもある(国に逆らえず違う伝承が書かれているかもしれない)。
ここら飲食だけで一旦終わりにしよう。すべては規則を設けた茶道、その元となる禅に始まる。こうした面倒な作法にうるさい高級店といえば「懐石」だが、なぜ懐石と言われるか。禅宗は読経ではなく座禅を重んじた宗派だが_年中いつでも座禅といっても真夏以外は寒くて座禅どころじゃない。なので禅僧は温めた石を懐に入れていたから「懐石」と言われる。しかし…懐石と精進料理はまったく別物で注意が必要。精進料理はビーガン、ベジタリアンのようだが一粒残らずありがたくいただくもの、また葬式や法事の後には参加者がいただく。これは死者が永遠の修行に入ったことと残された者の功徳のため。しかし懐石の場合は「茶のもてなし」であり一期一会、こちらの場合は「少し残す」ことが「また会いましょう」の掟であって「一粒残らず」とは「縁を切る」という意味になる。また懐石では良くて精進料理ではダメな野菜がある。想像すれば分かると思うが…ニンニク、ニラ、ネギだ。
酒は仏教ではダメだが神社では問題無い。三々九度をされた方は意味を知っているだろうが…何度もやった人も居るのか?別に悪いことじゃない、昔は寿命が短かったし戦死も多かったはずだし。三々九度は大中小の盃を新郎新婦が交互に同じ盃で3回3度飲むことだが_小さい盃を新郎、新婦、新郎の順で吞んでいく。次は新婦から、三度目は新郎から。小さい杯は2人の過去であり中は現在、大は未来を指し、それぞれ3度の順は神サマへの誓い、、新郎新婦の誓い、両家家族への誓いである。えっと、結婚ではなく義兄弟固めの儀、襲名披露で見たことある…なんてこともあるかもしれないが(汗) そう、この三々九度は神事から始まったものではない。これもサムライの登場からで、椀飯振舞("大判振るまい"は誤字である)が発祥の元で主従の固めの杯として将軍を筆頭に下々全員に同じ盃で酒を回して忠誠を誓わせたことに始まる。他人が口にする物を共有することで血族以上の絆を得る…という主従契約儀式。ちなみにこの酒宴を開くことを「御成」といい、「○○殿の、おな~り~」であって、そこから神事へ移った作法。なので雛祭りの三人官女がこの三献の儀に受け継がれた。太古から続く神事かのように云われるが歴史と同じく宮中行事の多くもせいぜい千年、ほぼ捏造でしかない。

ちなみに_昭和時代では宴会に遅れて来た奴には「駆けつけ3杯」という掟があった(笑)
結婚にしてもすべてのこうした儀式、作法はユダヤの「奴隷契約」の教えに過ぎない。

朝だけはしっかり起きるんですけどね… 毎日眠い、ヤル気が出にくい…
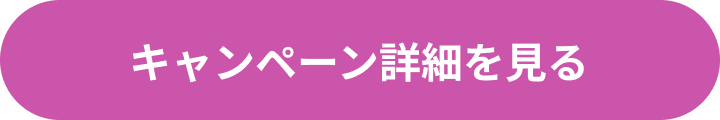
お腹空いた…朝、サンドイッチ2枚食べただけで、また食事忘れてた。
夜中に食べるの良くない?お蕎麦茹でようかな。