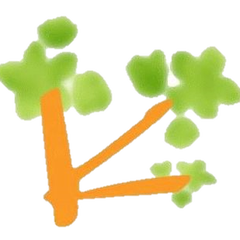Word文書でも“表”はよく使われますね。
表の挿入や基本的な編集については「Word 表の作成」記事でご紹介し、表を構成するセルのサイズの調整については「Word 表のスタイル/レイアウト」でご紹介しました。
簡単そうに見えて、多くの方が手間取っているのが、今回の表題「表の列幅・行高の変更」ではないでしょうか。
簡単な例題を作ってみました。(下図)

単に [挿入]-[表の挿入]で 3列×5行の表を挿入し、各セルに文字を入力しました。
ここで、意識していただきたいのが、列の幅です。
[挿入]-[表の挿入]をクリックして「表の挿入」ダイアログを表示させてみると、既定では「自動調整のオプション」項で「列の幅を固定する」が選択されており、その右側が「自動」となっています。(下図)

つまり、既定の状態では、左側の余白と右側の余白の間(ウィンドウサイズ)の幅に合わせて表が作成され、列数で等分割した幅で各セルが設定されます。
この「列の幅を固定する」が「自動」であることと、その下「ウィンドウサイズに合わせる」を選択したときは、実質的に同じ表が作成されます。
つまり、これらのモードのときは、1つのセル幅で収まらない長い文字列を入力したときでも、列幅は固定されているので、収まらない分の文字列は折り返されて表示されます。
それでは、「表の挿入」ダイアログで「文字列の幅に合わせる」を選択して、同じ内容で表を作成してみます。(下図)

文字通り、同じ列の中で文字列が一番大きいセルに合わせて各列幅が決定されています。
また、この表を作成後に、この幅以上に文字を加えていくと、自動的に列幅が広げられていきます。
文字列の幅に合わせて列幅を決めたいときは、最初から「文字列の幅に合わせる」を選択して作成したほうが手間が省けるということです。
ところが、「文字列の幅に合わせる」とすると、なんとなく列幅に余裕がない気がして、もう少し広げたくなります。
最初に試す方法は、列と列の境界線をマウスでドラッグする方法ではないでしょうか。
もちろん、それでよいのですが、お薦めは一番左の列から順番にしましょう。
1列めと2列めの境界線、つまり1列めの右側の境界線をドラッグして移動させます。
1列めの幅が程よく調整出来たら、続いて 2列めの右側の境界線をドラッグし、最後に 3列めの右側の境界線をドラッグします。
この順番を変えると、何度も調整することになりますので、左の列から順番にやってみてください。
さて、列幅については、もうひとつ自動調整する方法があります。
調整したい列の右側の境界線上でダブルクリックします。
下図は、2列めの右側の境界線上でダブルクリックした結果の列幅です。

もちろん、1列めでも 3列めでも同様に自動調整できます。
以上、列幅について見てきましたが、行の高さはどうでしょう。
表内の行の高さは、表外と同じく既定では「1行」になっています。
そのため、[段落]-[行と段落の間隔]などで設定することにより、セル内の行の高さも変更できます。
手動で行高を変更するには、セルの下側の境界線をドラッグして広げることができます。
ただし、「1行」より狭くすることはできません。
また、先ほどのダブルクリックによる自動調整は機能しません。
その他の自動調整などは、冒頭に掲げた先の記事などをご参照ください。