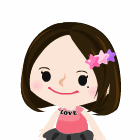復学支援で不登校を終わらせた、
中2の息子と私の記録です。
1年間の完全不登校から 中1の3月復学![]()
2022年12月-【見守るアプローチ 編】
2023年2月-【復学支援の葛藤-再登校】
2023年4月- 【復学支援/家庭教育 編】
“居心地のいいおうち”
それは不登校のあるなしに関わらず、
子どもにも大人にも、とても大事・・・
ですが、
お母さんのお世話や口出しによる、
保護も解決も全てしてくれる![]()
が強すぎると、
子どもはお母さんの居ない学校で、
問題や困難に対処しきれず・・・
学校に適応できなくなる![]()
こと。
私は思い知りました・・・![]()
大ごとになって 気がつきました。
『家庭の居心地を良くすること』と、
『家庭で子の自立スキルを育むこと』
分けて考えるべきこの二つ。
私は、
後者をすっかり忘れていたのです![]()
・ ・ ・
おうちの居心地はいいけれど、
子どもの自立は促せていなかった私。
息子の学校復帰をめざすにあたり、
「思い通りになるお家」と
「思い通りにはならない学校」との
ギャップを縮めるべく、
自力で困難に対応する力をつける![]()
ことが急務でした![]()
家庭のなかでも、
・自分のことは自分でやる
・困ったことは自分でなんとかする
・解決方法を自分で考える
・共同生活での ‘思い通りにならない’ を知る
息子がこれらの力をつけられるよう、
親の対応を変えました。
(命令,指示,提案 をやめる)
・ ・ ・
学校という社会。
それは100%快適な お家 とは違う。
あたり前のことでした。
そのギャップが大きいほど、
外の世界がより厳しいものになる・・・
まずは家庭で、家庭教育をもって、
子どもの自立や解決能力を養いたい。
“ 安心のできる家、安らげる家、
充電のできる家。
子どもの自立を促せる親。
子の解決能力を育む親の対応 ”
これらは全て、
同居 (両立) できました。
たとえ不登校の充電中であっても。
いえ充電中にこそ、
子の自立を促せたほうがいいです![]()
学校にお母さんは居ないもんで・・・
自力でがんばれ!↓
ママのサービスや保護が過ぎると、
家の外がキケンレベルになる恐れが・・・↓
給食と家庭の食事とのギャップで・・・↓
学校と家庭。双方で解決を目指せるといい↓