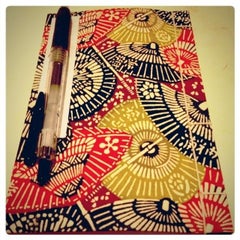気づけば日付が変わっておりました…
週休2日のしが無い会社員の為、金曜の夜はついつい何かしらやってしまい、気づくと結構な時間に。
特に何をしてる訳でも無いのですが。いやはや、落語でも聴けば良かったといつも後悔。
本日は出囃子について。そういえば書いてなかったと思い出しました。ネタは気づかない所に溢れて居るものなのですね。
で、出囃子ってなんだ?そもそも、何て読むの?!
ええ、私も手書きで書けと言われたら書けません。スマフォの変換機能万歳。
読み方は「でばやし」です。
出てくる時のお囃子。音楽の事です。
どこから何が出て来る時かと言うと。
「寄席などで芸人さんが舞台に出てくる時」です。
落語家さんや色物の方(こちらの詳細は過去の記事をペラっと書き綴らせて頂いてます。)の出番が終わり、前座さんが出てきて高座を返したり、捲りを返したりして、次の方が舞台に出てきます。
ここです。ここで流れる音楽の事を出囃子と言います。
ちなみにこの出囃子は寄席では三味線や太鼓、銅鑼などの鳴り物と呼ばれる楽器で…
生演奏です。
太鼓などの鳴り物は前座さんが叩きます。テンツクテンツク。
勿論、練習されてるそうです。落語家さんはリズム感も要求されるのです。
苦手な方も居るそうですが…
そして、三味線は通称「下座さん」と呼ばれる出囃子を弾く専門の方が弾かれます。高座に出ないから下座。お囃子のお師匠さんです。舞台の脇の客席から見えない所でひっそりと弾かれてます。
こちらの方々も協会に所属されています。
で、この出囃子。
落語家さん、色物の方、全員に専用の曲があるのです。
あっ、前座さんは無いです。修行の身の上。
で、オリジナルで誰かが作曲した訳ではないですよ。
基本は昔からある長唄や小唄などの曲を使うようです。
が、落語家さん、色物の方々、一つの協会に何百人も居るわけです。
…何百人も居るんです。笑点だけが全てじゃないのが痛いほどよく分かる…
となると、何百曲も使われる事になります。
古くからある長唄や小唄とはいえ、そんなに曲は無い…しかも、なんとなく早い者勝ち。
ですので、最近二つ目になった方は童謡やら下手したら洋楽を使っている方も。寄席という空間で三味線で聴くディープ・パープルの「スモーク・オン・ザ・ウォーター」は何とも言えません。
寄席の通の方は出囃子を聴いただけで「あー、次はあの人か」となるのでしょう。
私も少しずつ覚えて「あっ、次はきっとあの人だ!」となりつつあります。
分かるとテンションが上がります。ワクワク感増量。
曲が変われば太鼓などの鳴り物のリズムも叩き方も変わります。
下座さんも大変です。前座さんも曲毎に覚えなくてはならないです。間違えたら…きっと確実に怒られるんでしょうね…本当に大変。
テーマソングとあって、その落語家さんらしい曲が流れます。
渋い方は渋い曲。明るい方には賑やかな曲。
ちなみに…亡くなった方の曲はどうなるかと言うと。
基本的には使われなくなるそうです。やはり、テーマソング。その方のイメージが染み付くのですね。
例えば、「名跡」(みょうせき)という~代目◯◯と呼ばれる古くは江戸時代から伝わる昔ながらの名前を継いだりすると前の方の出囃子も継ぐ事があるそうです。
また、名跡を継いでも出囃子は継がない事もあるそうです。
イメージが染み付き過ぎてしまっているのでしょうね。
名前は同じでも別の方。その方の個性を魅せる為です。
と言う事で。
寄席に行くともれなく生の三味線の音色が聴けるのです。何と言うお得感。
本日は寄席の魅力の一つでありながら、うっかり書き忘れてた出囃子について書き綴らせて頂きました。
明日(正確にはもう今日ですね…気づけば1時。恐ろしい。)は何を書き綴らせて頂こうかと、やや魘されながら眠りに就こうと思います。
ここまで読んで頂き、有難う御座いました。
また、読んで頂けたら幸いです。
雨華
iPhoneからの投稿
週休2日のしが無い会社員の為、金曜の夜はついつい何かしらやってしまい、気づくと結構な時間に。
特に何をしてる訳でも無いのですが。いやはや、落語でも聴けば良かったといつも後悔。
本日は出囃子について。そういえば書いてなかったと思い出しました。ネタは気づかない所に溢れて居るものなのですね。
で、出囃子ってなんだ?そもそも、何て読むの?!
ええ、私も手書きで書けと言われたら書けません。スマフォの変換機能万歳。
読み方は「でばやし」です。
出てくる時のお囃子。音楽の事です。
どこから何が出て来る時かと言うと。
「寄席などで芸人さんが舞台に出てくる時」です。
落語家さんや色物の方(こちらの詳細は過去の記事をペラっと書き綴らせて頂いてます。)の出番が終わり、前座さんが出てきて高座を返したり、捲りを返したりして、次の方が舞台に出てきます。
ここです。ここで流れる音楽の事を出囃子と言います。
ちなみにこの出囃子は寄席では三味線や太鼓、銅鑼などの鳴り物と呼ばれる楽器で…
生演奏です。
太鼓などの鳴り物は前座さんが叩きます。テンツクテンツク。
勿論、練習されてるそうです。落語家さんはリズム感も要求されるのです。
苦手な方も居るそうですが…
そして、三味線は通称「下座さん」と呼ばれる出囃子を弾く専門の方が弾かれます。高座に出ないから下座。お囃子のお師匠さんです。舞台の脇の客席から見えない所でひっそりと弾かれてます。
こちらの方々も協会に所属されています。
で、この出囃子。
落語家さん、色物の方、全員に専用の曲があるのです。
あっ、前座さんは無いです。修行の身の上。
で、オリジナルで誰かが作曲した訳ではないですよ。
基本は昔からある長唄や小唄などの曲を使うようです。
が、落語家さん、色物の方々、一つの協会に何百人も居るわけです。
…何百人も居るんです。笑点だけが全てじゃないのが痛いほどよく分かる…
となると、何百曲も使われる事になります。
古くからある長唄や小唄とはいえ、そんなに曲は無い…しかも、なんとなく早い者勝ち。
ですので、最近二つ目になった方は童謡やら下手したら洋楽を使っている方も。寄席という空間で三味線で聴くディープ・パープルの「スモーク・オン・ザ・ウォーター」は何とも言えません。
寄席の通の方は出囃子を聴いただけで「あー、次はあの人か」となるのでしょう。
私も少しずつ覚えて「あっ、次はきっとあの人だ!」となりつつあります。
分かるとテンションが上がります。ワクワク感増量。
曲が変われば太鼓などの鳴り物のリズムも叩き方も変わります。
下座さんも大変です。前座さんも曲毎に覚えなくてはならないです。間違えたら…きっと確実に怒られるんでしょうね…本当に大変。
テーマソングとあって、その落語家さんらしい曲が流れます。
渋い方は渋い曲。明るい方には賑やかな曲。
ちなみに…亡くなった方の曲はどうなるかと言うと。
基本的には使われなくなるそうです。やはり、テーマソング。その方のイメージが染み付くのですね。
例えば、「名跡」(みょうせき)という~代目◯◯と呼ばれる古くは江戸時代から伝わる昔ながらの名前を継いだりすると前の方の出囃子も継ぐ事があるそうです。
また、名跡を継いでも出囃子は継がない事もあるそうです。
イメージが染み付き過ぎてしまっているのでしょうね。
名前は同じでも別の方。その方の個性を魅せる為です。
と言う事で。
寄席に行くともれなく生の三味線の音色が聴けるのです。何と言うお得感。
本日は寄席の魅力の一つでありながら、うっかり書き忘れてた出囃子について書き綴らせて頂きました。
明日(正確にはもう今日ですね…気づけば1時。恐ろしい。)は何を書き綴らせて頂こうかと、やや魘されながら眠りに就こうと思います。
ここまで読んで頂き、有難う御座いました。
また、読んで頂けたら幸いです。
雨華
iPhoneからの投稿