爆笑モノだったので紹介します。
---引用ここから---
黒田日銀が起こす国債市場の死
小幡 績 | 経済学者 2013年4月15日 6時37分
三つの想定内と三つのサプライズ
黒田日銀が、新しい政策を発表した。日経平均は発表時の12200前後から一時は先物で13000をつけ、800円の上昇、祭りとフェスティバルとが一緒にやってきたような騒ぎとなった。
黒田氏は徹底してやるし、相当やる、というのは想定内。そして、打ち出された内容は、今可能性のあるモノとして挙げられた政策すべて。黒田氏は、とことんやるが、まともなので、オーソドックスなものしかやらないと思われていたので、これも想定内(その2)。日銀当座預金に対する付利の撤廃はないと個人的には思っていたので、これも想定内。質的も量的にも異次元のもの、ということだったが、質的には異次元では無く、非常にまともな想定内(その3)。
一方、想定外だったのは、量。量的には異次元だ。デュレーションも市場に存在する国債の平均そのものということで一気に7年。これは驚いた。3年以下を5年以下あるいは10年以下として、次に超長期国債の可能性も、と思っていたから、大きなサプライズだ。また、当然だが、額も異次元。今の2倍はともかく、今後、新発国債発行額の7割を日銀が買うことになる。新発債を直接買うわけではないが、市場に出てきたものの7割を日銀が買ってしまうのだから、民間金融機関で満期が来た国債をロールオーバーする金融機関もあるから、そうなると、新しい国債は新しい買い手にはまったく出回らないことになる。ロールオーバーも難しくなるだろう。
二つ目のサプライズは、一気に一発で玉を打ち尽くしたところだ。逐次投入はしない。現在やるべきと思われるものはすべてやった、という黒田総裁の言葉通りのものだった。これがマーケットインパクトを与えた。
しかし、何より、一番驚いたのが、5人の審議委員だ。これまで、ずっとやらなかったものを、総裁が変わったらあっさり賛成するというのはどういうことなのだろうか。木内委員以外は説明がつかないのではないか。審議委員は要らない、総裁一人いればいい、ということなのだろうか。
さらに驚いたのが、黒田氏のパネルの多様だ。準備万端。普通は準備万端ではいけない。なぜなら、直前まで、議論を尽くした上で、すぐに採決、発表するから、パネルを準備するヒマが普通はないはずなのだ。ということは、実質昨日の時点で、今日発表するモノは決まっていたということだ。もちろん、根回しもいろいろあるだろうが、この建前は守らないと、政策決定会合の意味がなくなる。ウォールストリートジャーナルで、初会合で全員を説得した黒田総裁という記事が出ているが、間違いだ。彼らは、会合の前に説得された。しかも、黒田氏にではなく、事務方にだ。更に言えば、説得など必要ない。総裁と世論の言いなりになる委員だから、いかなる場合でも説得する必要は無いのだ。これが、三番目の最大のサプライズだ。
株価は、今日に続き、明日(4月5日)は上がるかもしれないが、来週以降はどうだろうか。材料出尽くしで下がるよりは、大きなサプライズであったために、そう簡単には失速しないだろうが、それでも金曜日の米国雇用統計などに引きずられるようであれば、かなりヤバい。
黒田日銀は、もはや次の玉がない。今後、株価、景気が低迷した場合にはどうするのだろうか。市場が調子に乗って、さらなる催促相場を展開してきたら、どうするのだろうか。
実際には深刻な問題が2つある。1つは、単純に、消費税引き上げの影響、駆け込み需要の反動減だ。このとき、景気は短期にかなり落ち込むと思われるが、このとき、サプライズを演出する金融緩和はほとんど存在しない。ゼロ金利にしてしまって、後がなくなったのが、これまでの日銀の失敗だったとすると、金融緩和の余地をサプライズをもたらしてまで、自ら放棄した黒田日銀は、今後、追い込まれたらどうするのか。
もう一つは、中小の金融機関である。今日の異次元の量的金融緩和により、彼らが破綻に追い込まれる期日が早まった。日銀がデュレーション7年としてしまうと、今日10年ものが0.425%まで下がったように、利回りが確保できなくなるから、超長期国債ばかりを買うしかない。大幅に値上がったものは、天井に達すれば、後は下落するしか無い。黒田日銀バブルとなった国債は、今後はあるタイミングから下落する以外無くなる。つまり、必ず、下落するタイミングが来ることになったのだ。
そのとき、必ず、中小の金融機関はどこかが破綻する。預貸率20%、デュレーション8年という中小の金融機関が存在する以上、どこかは、金利上昇が始まれば、まもなく破綻する。しかし、景気が回復するにせよ、回復を金融政策でもたらすことが出来ず、金融政策が失敗に終わり、名目金利が上がるにせよ、必ず、国債は値下がりし、彼らのどこかは破綻する。
いよいよ、国債は、黒田日銀によりバブル、バブル崩壊へのレールを敷かれてしまったのだ。
---引用ここまで---
国債の価格と金利は負の相関関係があります。
①金利が下がれば、価格が上がる (相対的に買い手が多い)
②金利が上がれば、価格が下がる (相対的に買い手が少ない)
という絶対の関係があります。
金利が下がり、価格も下がるということは原理的にあり得ません。
もちろん、価格が上がり、価格が下ることも同時に起こり得ません。w
前半部分では、金融機関が国債を買いたくても買えないことを問題視①しながら、後半部分では、国債金利が上昇する②と完全に矛盾することを書いてます。
さらに、前半部分で株価高騰は「祭だ」というようなことを書きつつ、後半部分では来週(4月22日)以降の株価低迷を心配している。てゆうか、実際には13700円なので、残念ながら、さらに700円くらい上っちゃってるんですけどね。w
もう、この人、滅茶苦茶です。こんなことをインターネット記事で出しちゃって大丈夫なんでしょうか。完全に学者として終わってますね。
かつてのマルクス経済学者のように、大学の中でだけでしか通用しない無駄な人生を送るんでしょうね。
↓クリックお願いします
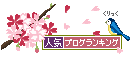
人気ブログランキングへ