岩田規久男氏「デフレの経済学」より
デフレの経済学/東洋経済新報社

¥1,995
Amazon.co.jp
---引用ここから---
<昭和恐慌前夜>
井上蔵相は金輸出解禁と同時に、国際収支の悪化を止めようとして、財政支出を大幅に削減するという超緊縮財政政策を実施した。貨幣供給量と超緊縮財政による需要の大幅な減少により、消費者物価の下落率は30年が10%、31年が11.5%に達した。(p148) 井上蔵相が右のような政策を取ったのは、「大戦中の好況で水ぶくれした経済が、その後10年経っても整理されずに、停滞が続いているのは金の輸出を禁止しているからである」と考えたからである。そこで、彼は相当の不況を覚悟して、不良な企業を整理し、経済を活性化させ、国際競争力の強い経済を作ろうとした。しかし、タイミングの悪いことに世界恐慌と重なってしまい、経済成長は急落し、雇用が1割も減少した。 昭和恐慌によって、最も打撃を受けたのは農村であった。先にも書いたように30年と31年(略)、農産物価格だけを見れば、30年の下落率は34%に達していた。(p148-149)
<政治家暗殺事件>
このような農村の窮乏を、青年将校たちは、農村出身の新兵を教育するうちに知ることになる。31年の3月事件に始まる青年将校のクーデター参加、その後の政治家暗殺事件発生は、こうした青年将校たちの農村・農民への同情と、正義感に基づくものが多かったのである。旧平価による金輸出解禁に踏み切り、財政を引き締めることによって不況をいっそう激化させた井上蔵相も、32年2月に暗殺された。
---引用ここまで---
※強調・文字色追加
デフレ下において、財政収支を黒字化するという暴挙は、井上準之助の緊縮財政と同じことです。しかも、消費増税という消費を減らすのが明らかなことをデフレ期に行うことは、恐慌への道です。
ちなみに、金本位制というのは、各国通貨をGOLDに連動させるものであり、各国で独自の金融政策をとれないので共通通貨ユーロに似ている気がします。
ヨーロッパはすでに恐慌に足を突っ込んでいる状態だと思います。
ヨーロッパの金融危機を解決するには、ECBが大量に国債を購入するか、ユーロの解消しかないでしょうね。
中央銀行が国債を買うというのは、金利上昇を招き、民間を圧迫することであり、インフレ期においてはタブーです。
しかし、インフレにおいてのタブー、それが「デフレ」という状況においてもタブーでありつづけるのが間違いの原因であり、その間違いの結果おきたのが、昭和恐慌であり、世界大恐慌なのです。
↓クリックお願いします
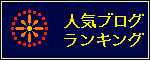
人気ブログランキングへ